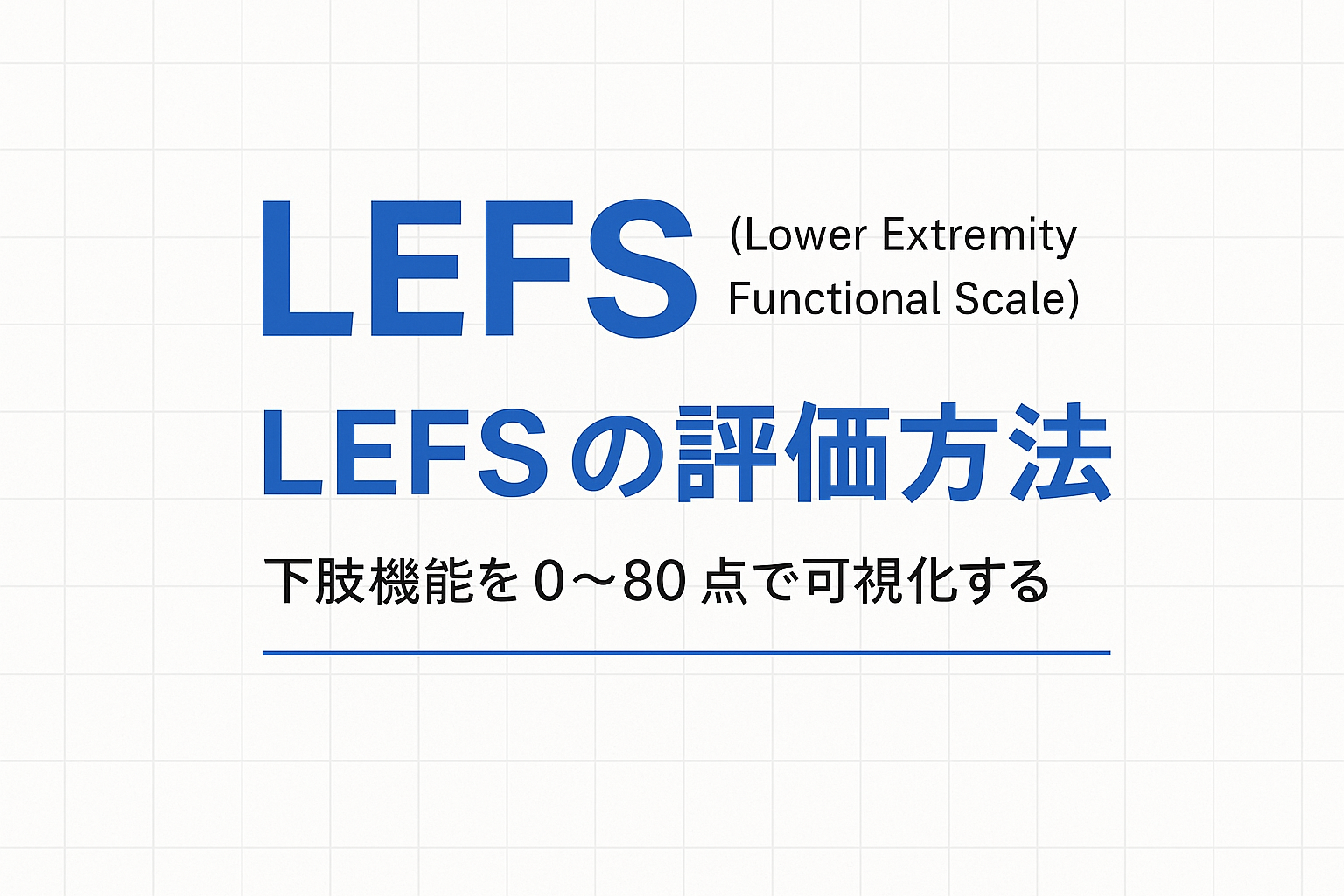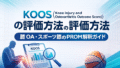LEFS(Lower Extremity Functional Scale)とは?
LEFS(Lower Extremity Functional Scale)は、下肢全般の機能を 20 項目で評価する患者立脚型アウトカム指標(PROM)です。膝・股関節 OA や人工関節置換術後だけでなく、足関節捻挫や骨折、アキレス腱断裂、神経筋疾患など、さまざまな下肢疾患・外傷に横断的に用いられる点が特徴です。各項目を 0〜4 点で評価し、合計 0〜80 点で機能レベルをスコア化します。1–4,8
疾患特異的な WOMAC・KOOS と異なり、LEFS は「下肢機能そのもの」を俯瞰できる汎用スケールです。歩行・階段・しゃがみ込み・走行など、実際の日常生活や活動場面に即した項目が並んでおり、術前後の経時変化や保存療法のフォロー、脳卒中や末梢神経障害での歩行再建の一側面としても活用しやすい指標です。1–4,8
下肢評価を「強み」にしたい理学療法士へ|学び方とキャリアの整え方を見る
LEFS の構成項目とカバーする下肢機能
LEFS の 20 項目は、「日常の移動・移乗」から「高負荷の活動」まで、下肢の使用場面を難易度順にカバーするよう設計されています。原文の設問はここでは示しませんが、おおまかに以下のような層構造として捉えると、点数変化と臨床像を結びつけて理解しやすくなります。1–3,8
図のように、安定期の膝・股 OA や TKA・THA 術後では「歩行・階段・しゃがみ」のレベル、高齢者の転倒リスク評価では「屋外歩行・不整地」のレベル、スポーツ復帰期では「走行・ジャンプ」のレベルの項目が鍵になりやすく、症例の活動レベルに応じてどのゾーンに課題が集中しているかを俯瞰できます。当ブログの 評価ハブ では、LEFS と歩行テスト・筋力評価を組み合わせた評価フローも順次整理していきます。
評価手順とスコアリング|0〜4 点から 0〜80 点・%機能へ
LEFS は、各項目を 0〜4 点の 5 件法で評価します。原版では「0=まったくできない/1=かなり困難/2=中等度に困難/3=少し困難/4=まったく問題なくできる」と定義されており、全 20 項目の合計が 0〜80 点となります。1–3,8 点数が高いほど下肢機能が良好で、0 点に近いほど重度の障害を示します。
臨床では、合計点に加えて 「%機能」=(LEFS スコア ÷ 80)×100 と換算しておくと、患者さんへの説明や他指標との比較がしやすくなります。多くの解説では、最小検出可能変化(MDC)および最小限臨床的重要差(MCID)がともにおおよそ 9 点とされており、9 点以上の変化があれば測定誤差を超えた改善とみなせる目安になります。2,4,8,9 カルテには「LEFS 40/80(50%)」のように分数と%を併記しておくと、経時比較が直感的になります。
スコアの解釈と MCID・回復の目安
LEFS の MCID は、開発論文や解説資料で 9 点前後 とされることが多く、「9 点以上の変化」が患者が自覚する意味のある改善と対応すると報告されています。1–4,8,9 例えば、40→50 点(+10 点)であれば「MDC・MCID を超える改善」、40→45 点(+5 点)であれば「測定誤差の範囲内であり、まだ大きな変化とは言い難い」といった解釈が目安になります。
一方で、ベースラインの低さや併存疾患、活動レベルによって、同じ点数変化でも臨床的な意味は変わります。また、“%機能”で見たときに 20%→40%、60%→70%といった変化では、患者さんの受け止め方が大きく異なることもあります。実地では、LEFS の変化量だけで白黒をつけるのではなく、6 分間歩行や TUG、痛みスケール、本人の主観的回復感と合わせて、「介入の方向性は妥当か」「ゴール設定を修正すべきか」を総合的に判断することが重要です。
臨床での活用例|保存療法・術後・神経筋疾患
整形外科外来では、膝・股 OA、足関節捻挫、下肢骨折後などの保存療法で、初回・3 ヶ月・6 ヶ月といったタイミングで LEFS を実施し、痛みスケールや歩行テストとともに経時変化を追う使い方が一般的です。3,5,8 「痛みは減っているが LEFS はあまり伸びていない」「LEFS は改善しているが 6MWT が頭打ち」など、主観と客観のズレは介入内容やゴールの見直しに直結します。
術後(TKA/THA/骨切り術/下肢再建術など)では、術前→退院時→外来フォローで LEFS を記録し、患者さんとも共有しながら活動レベルの回復を可視化します。3,6,8 また、脳卒中や末梢神経障害の症例でも、歩行能力が一定レベルに達した段階から「下肢機能の患者立脚評価」として LEFS を併用し、BBS や FIM 歩行項目などとの関係を見ていく応用もあります。
WOMAC・KOOS・NDI/ODI など他指標との使い分け
下肢の PROM には、膝・股 OA に特化した WOMAC や KOOS、股関節 OA・THA 向けの HOOS など、多数の疾患特異的指標があります。LEFS はそれらと異なり、下肢全般の機能レベルを 1 本で横断的に見られる汎用スケールという位置づけです。1,2,8 そのため、膝 OA であれば WOMAC/KOOS+LEFS、股 OA・THA であれば HOOS+LEFS といった組み合わせが選択肢になります。
脊椎疾患では、頚椎に NDI、腰椎に ODI や RDQ を用いつつ、歩行・下肢機能の側面を補完する目的で LEFS を併用することも考えられます。同一症例で複数 PROM を用いる場合は、「主訴に最も近い疾患特異的スケール+汎用スケール(LEFS)+客観評価(歩行・筋力・バランス)」という構成にしておくと、評価負担を増やしすぎずに情報を整理しやすくなります。
記録とチーム共有のコツ
カルテには、「合計点」「%機能」「併用した歩行・ADL 評価」の 3 点セットで記載しておくと、経時比較がスムーズです。例えば「LEFS 40/80(50%)→ 55/80(69%)、TUG 14→10 秒、6MWT 280→360 m(入院時→退院時)」といった書き方にすると、主観・客観の変化を一目で共有できます。3,5,8,10
カンファレンスや退院サマリーでは、「LEFS のどのレベルの項目が改善したか」「どこに課題が残るか」を、実際の動作(階段・不整地・しゃがみ・スポーツなど)と結びつけて説明するのがポイントです。患者さんや家族に対しては、「今は 80 点満点中 50 点くらいで、日常生活はおおむね自立だが、階段や長距離歩行に課題が残る」といったように、点数を具体的な生活像に翻訳して伝えるとイメージしやすくなります。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
LEFS は何点くらい変化したら「リハビリの効果あり」と考えてよいですか?
LEFS の最小限臨床的重要差(MCID)は、多くの資料で 9 点前後と紹介されています。1–4,8,9 これは、9 点以上の変化であれば測定誤差を超え、患者が意味のある変化として認識しやすいレンジと解釈できます。例えば、40→50 点(+10 点)は「MCID 超え」、40→45 点(+5 点)は「変化はあるが、まだ小さい」といったイメージです。
とはいえ、ベースラインが低い症例や併存疾患が多い高齢者では、5〜8 点程度の変化でも本人には大きな進歩に感じられることもありますし、その逆もあります。LEFS の点数だけで介入の良し悪しを決めるのではなく、「本人の主観的回復感」「歩行・筋力・バランスなど客観評価」「仕事や趣味への復帰状況」と合わせて総合的に判断することが重要です。それでも、「評価やエビデンスを追いかけているのに、そもそも今の職場の体制では十分な時間やリソースをかけられない」と感じる場面が続くなら、働き方そのものを見直すタイミングかもしれません。そうした“危険サイン”を整理するには、理学療法士の転職・職場選びガイドも参考になります。
おわりに
下肢疾患のリハビリでは、「レッドフラッグの除外 → ROM・筋力・疼痛評価 → 歩行・バランス評価 → PROM(LEFS や WOMAC/KOOS)による患者視点の把握 → ゴール設定と介入計画 → 再評価」というリズムを押さえておくと、評価結果を治療戦略に結びつけやすくなります。LEFS は疾患を問わず下肢機能を横断的に捉えられるため、保存療法・術後・神経筋疾患をまたいだ“共通言語”として使いやすいスケールです。
一方で、「本当は PROM や歩行評価をもっと丁寧に回したいのに、外来や病棟の時間配分の中で十分に活かし切れていない」と感じる場面も少なくありません。働き方を見直すときの抜け漏れ防止に。見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック( A4・5 分)と職場評価シート( A4 )を無料公開しています。印刷してそのまま使えますので、転職に限らず情報収集や見学の場面でもダウンロードページを活用してみてください。
参考文献
- Binkley JM, Stratford PW, Lott SA, Riddle DL; North American Orthopaedic Rehabilitation Research Network. The Lower Extremity Functional Scale (LEFS): scale development, measurement properties, and clinical application. Phys Ther. 1999;79(4):371–383. doi:10.1093/ptj/79.4.371. PubMed
- Binkley JM, Stratford PW, et al. The Lower Extremity Functional Scale (LEFS). Reprinted scoring sheet and instructions. Phys Ther. 1999;79:371–383. (各種医療機関配布版 PDF 参照)
- Abbott JH, Schmitt J. Minimum clinically important difference for the Lower Extremity Functional Scale in individuals with lower extremity musculoskeletal conditions. Arch Phys Med Rehabil. 2014;95(1):194–201. doi:10.1016/j.apmr.2013.07.024.
- McCormack J, et al. The minimum clinically important difference and patient acceptable symptom state for the LEFS: a systematic review. (抄録・二次資料より MCID ≒9 点を引用)
- Pan SL, et al. Responsiveness of SF-36 and Lower Extremity Functional Scale in hip and knee osteoarthritis. Clin Rehabil. 2014;28(6):604–612. doi:10.1177/0269215513512219.
- Lin CW, et al. Responsiveness and validity of the Lower Extremity Functional Scale for ankle fractures. J Orthop Sports Phys Ther. 2009;39(6):468–475. doi:10.2519/jospt.2009.3022.
- Pua YH, et al. The Lower Extremity Functional Scale for hip osteoarthritis: reliability, validity, and responsiveness. Arch Phys Med Rehabil. 2009;90(6):955–962. doi:10.1016/j.apmr.2008.12.017.
- Shirley Ryan AbilityLab. Lower Extremity Functional Scale (LEFS). Rehabilitation Measures Database. (2025 年アクセス)Web サイト
- 中丸宏二ほか. 下肢疾患外来患者における日本語版 Lower Extremity Functional Scale の信頼性と妥当性. 理学療法学. 2014;41(7):433–440. J-STAGE
- Emory Healthcare. Lower Extremity Functional Scale (LEFS) form and scoring instructions. (院内配布用 PDF 資料)
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下