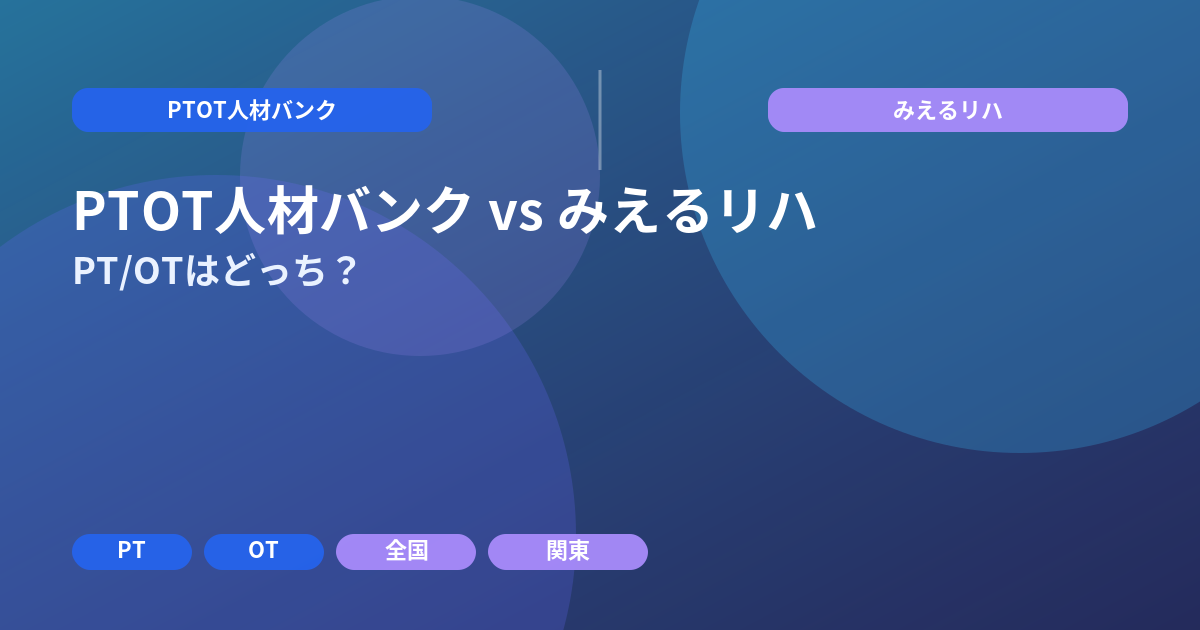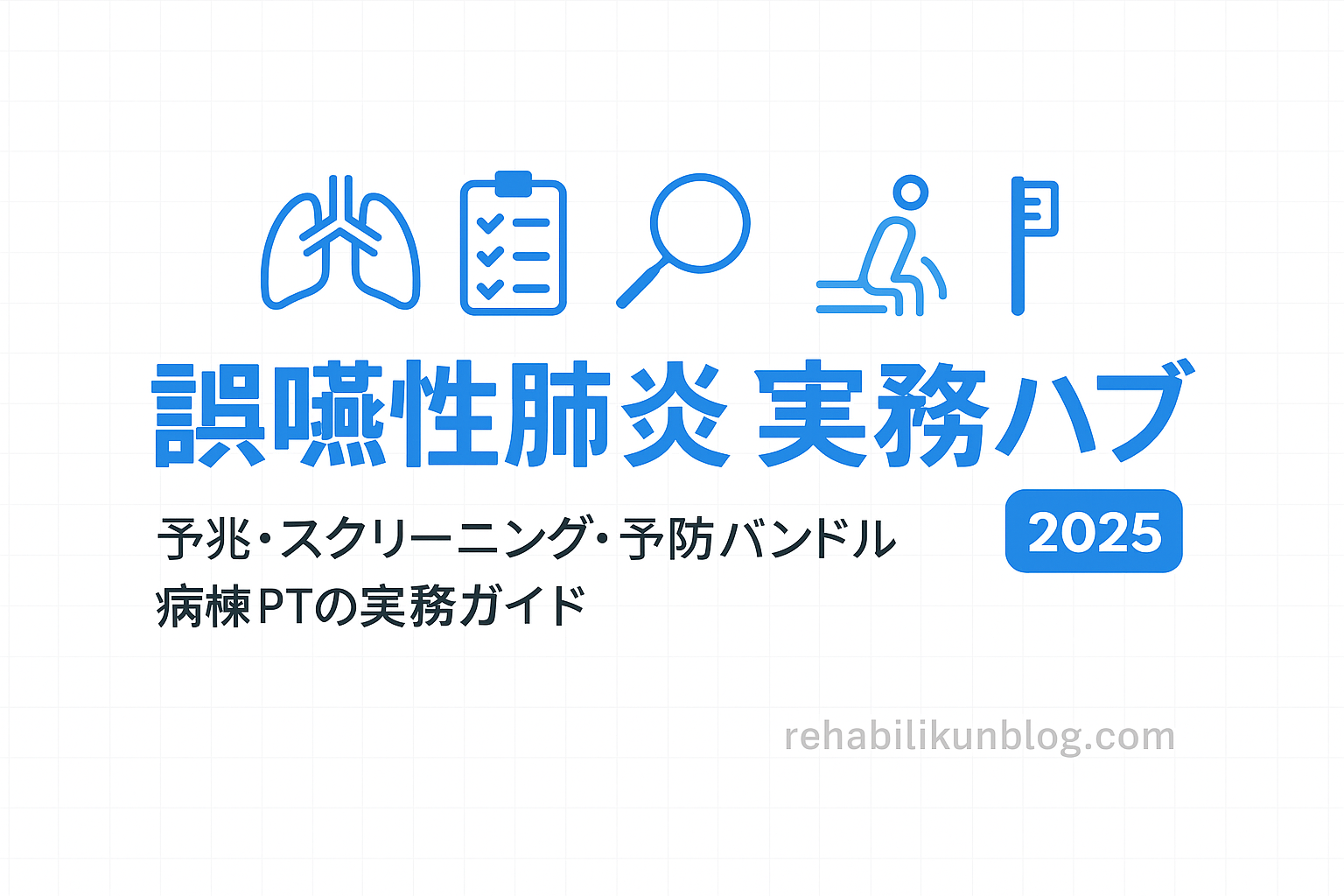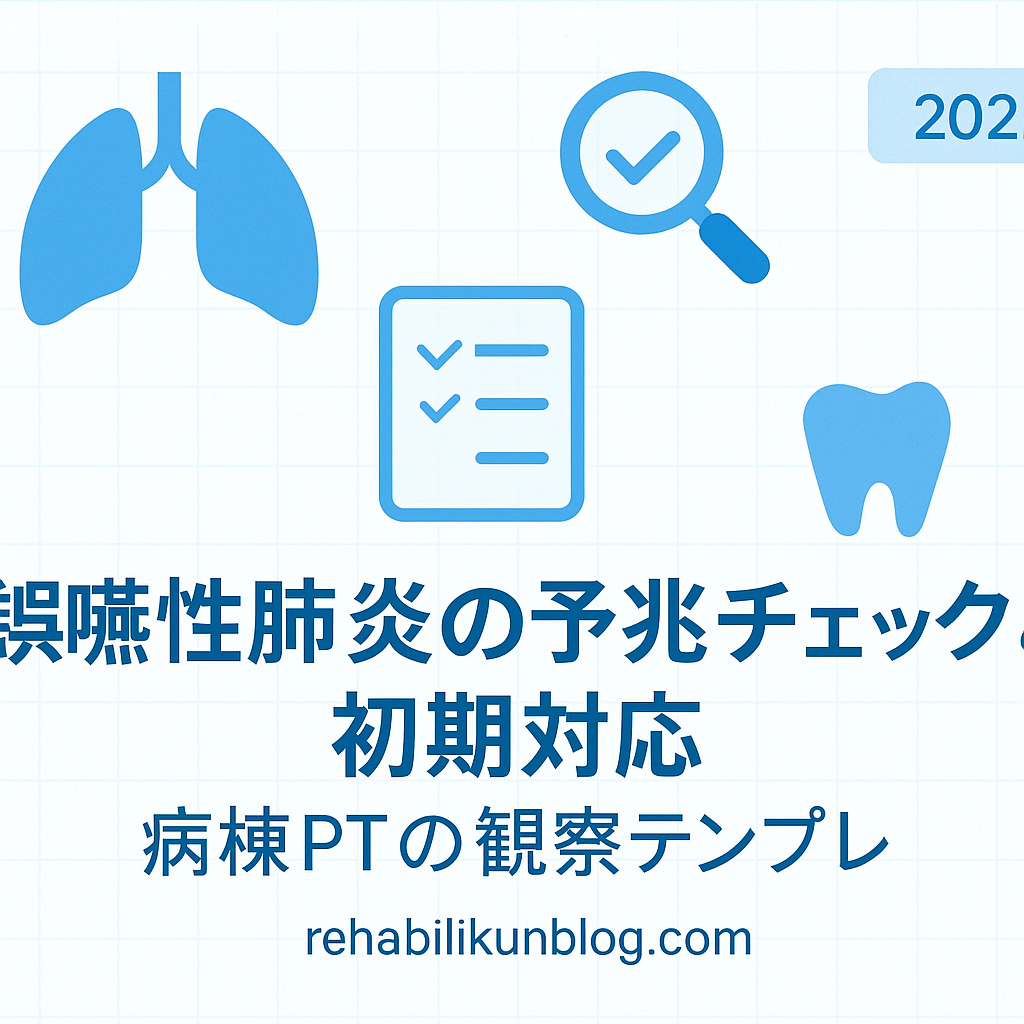PTOT人材バンクとみえるリハの違い【どっちを選ぶ?ケース別使い分け・2025】
結論:短期決定・交渉のテンポ重視ならPTOT人材バンク、提案の「見える化」で比較しやすさ重視ならみえるリハ。地方やニッチ領域は併用で母数確保が安全策です。この記事は「要点→ケース別→比較表→チェックリスト→断り方テンプレ」で最短意思決定を支援します。
最終更新:2025年10月24日
要点サマリー(まずはここだけ)
- PTOT人材バンク:非公開求人の厚み+面接調整〜交渉のテンポが強み。短期決定と相性◎。
- みえるリハ:提案の見える化で比較しやすい。訪問・介護領域も並列比較しやすい。
- 共通の注意:担当との相性差/地域偏りはあるため、希望の優先順位Top3を先に共有。地方・ニッチは併用前提。
ケース別の使い分け
| ケース | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 短期で決めたい/複数内定を比較したい | PTOT人材バンク | 調整と交渉のテンポが速い。提案の母数が確保しやすい。 |
| 提案を可視化して丁寧に比較したい | みえるリハ | 見える化で判断材料を並べやすい。 |
| 訪問・介護領域も含めて広く見たい | 併用 | 両社の強みを使い分けると取りこぼしが少ない。 |
| 地方・ニッチ領域 | 併用 | 地域偏りを補完し、案件の母数・比較軸を確保。 |
メリット・デメリット比較
| 観点 | PTOT人材バンク | みえるリハ |
|---|---|---|
| 求人の母数・非公開 | 医療〜介護横断の非公開が厚い傾向 | 案件の“見える化”で比較がしやすい |
| 面接調整・交渉のテンポ | 速い(短期決定と相性◎) | 速いが、比較観点の可視化重視 |
| 情報の粒度 | 求人票の要点が揃いやすい | 提案面での可視化が強み |
| 地域バランス | 都市圏は安定/地方は併用で補完 | 地域により母数の偏り→併用推奨 |
| 注意点 | 担当との相性差/提案ペースが速いと感じること | 担当との相性差/見える化の粒度は担当次第 |
求人票チェックリスト(コピペ可)
比較の観点詳細はエージェント比較のコツを参照(同一タブ)。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 給与レンジ | 基本給/手当内訳/賞与◯ヶ月/昇給幅/インセン有無 |
| 勤務形態 | 週労働時間/残業実績/オンコール/土日祝の扱い |
| 教育体制 | OJT/症例カンファ/学会支援/外部研修費補助 |
| 症例・病期 | 急性期/回復期/維持期/訪問の割合と担当件数 |
| 配置基準 | セラピスト数・職種構成/1人あたり負担 |
| 通勤・立地 | 最寄り駅・通勤時間/マイカー可否/住宅手当 |
連絡が多い時の“丁寧な断り方”(テンプレ)
ペース調整の要望は遠慮なく。関係維持を前提に伝えるのがコツです。
メール例(週1・メール中心に調整)
件名:ご提案ペースのご相談
いつもご提案ありがとうございます。現在、検討中案件の整理を優先したく、
新規のご提案は週1回・メール中心でお願いできれば幸いです。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)で開閉できます。
どっちを先に登録すべき?
短期決定重視→PTOT人材バンク先、見える化で比較重視→みえるリハ先。地方・ニッチは両方同時でOK。
同時登録は問題ない?
問題ありません。提案が重なる場合は担当同士の調整を依頼。面接日程のバッティングだけ注意。
連絡が多いと感じたら?
連絡手段(メール中心)・頻度(週1回)・時間帯を先に指定し、検討中案件の整理を優先したい旨を伝えればコントロールできます。
PTOT人材バンクとみえるリハの次に考えたい「転職の進め方」
ここまで見てきたように、PT・OT の転職では PTOT人材バンク と みえるリハ のどちらか一方に絞るよりも、「短期決定に強いサービス」と「提案の見える化に強いサービス」を組み合わせて使うほうが、情報の取り逃しを減らせます。まずは自分の優先順位に近い方を軸に登録しつつ、もう 1 社は「条件の比較用」として併用するとバランスがとりやすいです。
一方で、そもそもの 転職の進め方やキャリアの考え方 に不安がある場合は、先に「どんな現場でどんな経験を積みたいか」を整理しておくと、担当者との面談がスムーズになります。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止には、見学や情報収集の段階でも使える 面談準備チェック(A4・5 分)と職場評価シート(A4) も用意しています。印刷してそのまま使えるので、「今回の転職で何を優先したいか」「今の職場のどこに違和感があるか」を整理するのに役立ててみてください。
次のアクション
- 希望条件の優先順位Top3を決めてメモ(給与/病期/教育など)。
- 上の求人票チェックリストで情報を揃える。
- 比較の観点はエージェント比較のコツを参照。
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下