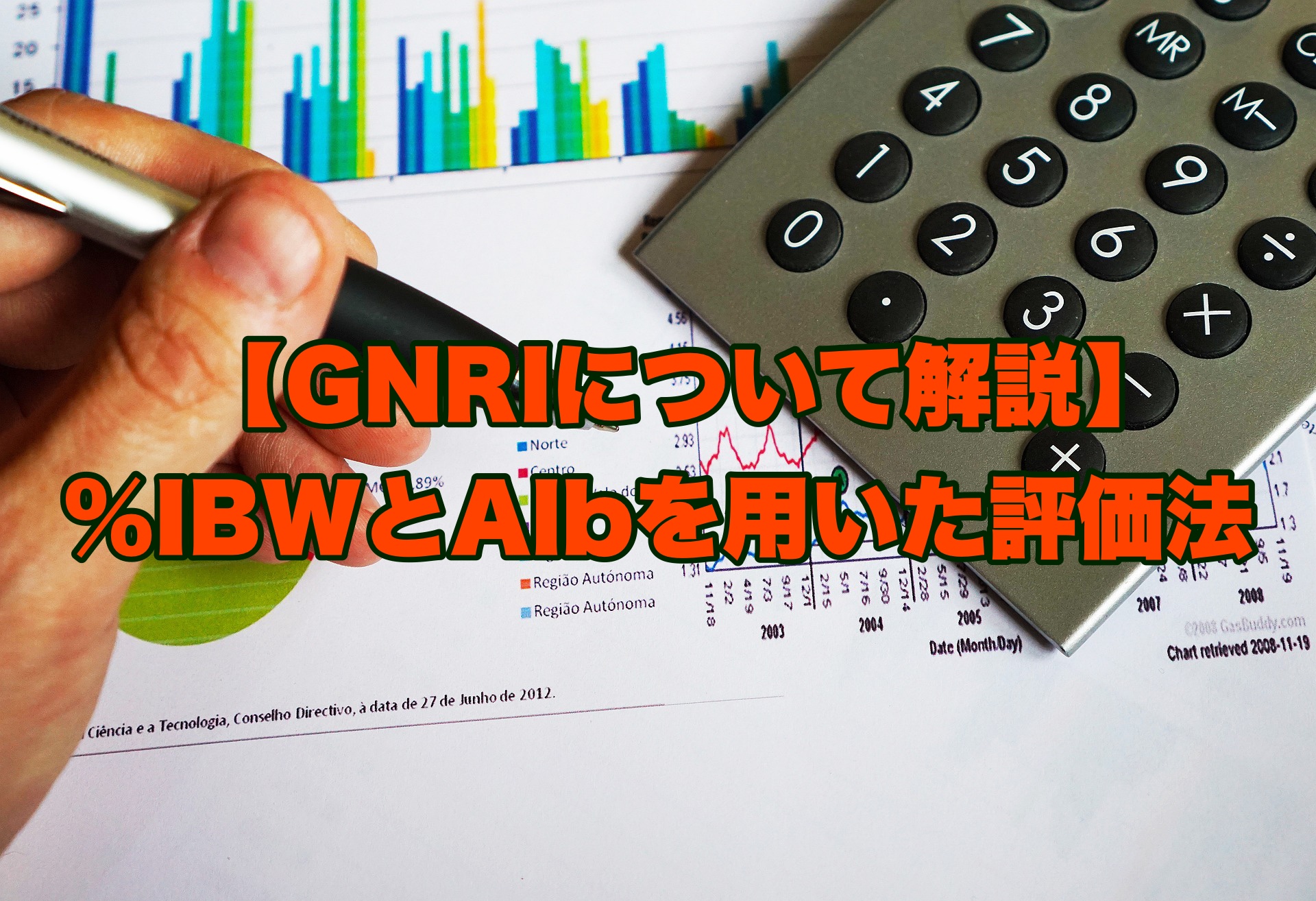- GNRI(栄養評価)とは?(目的と読み方・使いどころ)
- GNRI の計算式と、まず迷わない手順(必要な入力・ 3 分で計算)
- GNRI のカットオフと、栄養関連リスクの解釈(まずは 4 区分)
- 透析患者における GNRI の使い方(実務で迷わない目安)
- 心不全での GNRI の位置づけ(体液変動を踏まえた読み方)
- GNRI を起点にした栄養評価フロー(スクリーニング → 診断 → 介入 → 再評価)
- GNRI 解釈のよくある落とし穴(詰まりどころを表で回避)
- GNRI の計算例( 2 パターンでイメージを固定)
- GNRI を測定するタイミングと、記録のコツ(経時変化で価値が出る)
- おわりに:GNRI を「入口」として使い倒す
- よくある質問
- 著者情報
- 参考文献
GNRI(栄養評価)とは?(目的と読み方・使いどころ)
結論:GNRI( Geriatric Nutritional Risk Index )は、高齢者の低栄養リスクを簡便に数値化する栄養評価(栄養スクリーニング)指標です。読み方は一般に「ジー・エヌ・アール・アイ(ジーエヌアールアイ)」とされ、血清アルブミン( Alb )と現体重 ÷ 理想体重( %IBW )から算出します。入院高齢者や心不全・ CKD などの慢性疾患で、予後や合併症リスクの層別化に利用されます。
GNRI は低栄養の「診断」そのものではなく、リスクを拾い上げる入口です。リスクありの場合は、体重減少・筋量低下・摂取量・炎症などを含めた栄養診断( GLIM など )と介入設計へ進みます( Alb は炎症や体液バランスの影響を受けやすく、単独で栄養状態を断定できません)。
GNRI の計算式と、まず迷わない手順(必要な入力・ 3 分で計算)
GNRI の基本計算式は次の通りです。ポイントは現体重 ÷ 理想体重を 1 を上限として扱うことです( 1 を超える場合は 1 として代入)。これにより、過体重の人を「リスクなし」と過小評価しにくくなります。
GNRI = 14.89 × Alb( g/dL )+ 41.7 ×(現体重 ÷ 理想体重)
| 項目 | 単位 | 現場のコツ |
|---|---|---|
| 血清アルブミン( Alb ) | g/dL | 炎症( CRP など )や体液バランス(浮腫/脱水)を同時にメモします。 |
| 身長 | m(または cm ) | IBW の計算式に合わせて単位を統一します。 |
| 体重(現体重) | kg | 心不全や透析では体液変動の影響を受けやすいので測定条件をそろえます。 |
| 理想体重( IBW )の方式 | — | 院内で統一し、評価表/カルテに「方式名」を明記します。 |
理想体重( IBW )の定義にはいくつか選択肢があり、代表的なのが原著で用いられた Lorentz 式と、日本でなじみの深いBMI 22 法です。どちらを採用するかを院内で統一し、評価表やカルテに方式を明記しておくことが重要です。
| 方式 | 計算 | 運用の注意 |
|---|---|---|
| Lorentz 式(身長 cm ) | 男性:身長 − 100 −(身長 − 150)/ 4 女性:身長 − 100 −(身長 − 150)/ 2 |
原著の再現性を意識する場合に選ばれます。身長は cm で統一します。 |
| BMI 22 法(身長 m ) | 身長 × 身長 × 22 | 日本の実務で扱いやすい方式です。身長は m で統一します。 |
| 手順 | やること | つまずきポイント |
|---|---|---|
| 1 | Alb( g/dL )・身長・体重をそろえる | 浮腫/脱水/炎症の有無を同時に記録します。 |
| 2 | IBW を計算( Lorentz 式 または BMI 22 法 ) | 方式が混在すると、同じ患者でも時系列比較が崩れます。 |
| 3 | 体重 ÷ IBW を計算し、 1 を上限で扱う | 1.00 を超えたら 1.00 として代入します。 |
| 4 | GNRI = 14.89 × Alb + 41.7 ×(体重 ÷ IBW ) | Alb の単位( g/dL )が違うとスコアが崩れます。 |
| 5 | 区分( 4 段階 )に当てはめ、次アクションを決める | GNRI は入口です。診断/介入へ確実につなげます。 |
GNRI 計算をルーチン化するには、電子カルテの計算式登録や、病棟で使える簡易シートの整備が有効です。評価だけで終わらない「次アクション」の作り方は、栄養スクリーニング運用フローに沿って院内の標準手順へ落とし込むと安定します。
GNRI のカットオフと、栄養関連リスクの解釈(まずは 4 区分)
高齢者入院患者を対象とした多くの研究では、GNRI はおおよそ次の 4 区分で評価されます。施設で使用する用語や具体的な対応方針をあらかじめ整理し、クリニカルパスや看護計画に落とし込んでおくと運用がスムーズです。
| GNRI スコア | 栄養関連リスク | 臨床上の目安 |
|---|---|---|
| > 98 | なし | 定期モニタ(食事量・体重・活動量の維持確認) |
| 92–98 | 低 | 食事支援+経過観察(摂取記録と体重推移のチェック) |
| 82–< 92 | 中等度 | 栄養介入を検討(経口強化・補助食品・食形態調整など) |
| < 82 | 高度 | 多職種で積極的介入(経腸/静脈栄養やリハ強化も含め検討) |
GNRI のカットオフは研究ごとに若干の違いがありますが、「 98 を境にリスクなし」「 82 未満は高度リスク」という枠組みは多くの報告で共通しやすい整理です。病棟での「栄養関連リスク可視化ツール」として、他の栄養評価や身体機能評価とセットで運用するのがおすすめです。
透析患者における GNRI の使い方(実務で迷わない目安)
透析領域では、GNRI は死亡リスクや入院リスクと関連する栄養評価指標として用いられています。実務上はシンプルに、GNRI ≥ 92(≒ 91–92 以上)=栄養リスクなし/未満=栄養リスクありというカットオフで整理されることがあります。
| GNRI | 評価 | 対応のイメージ |
|---|---|---|
| ≥ 92 | 栄養リスクなし | 維持方針(食事・透析条件・運動療法の継続) |
| < 92 | 栄養リスクあり | 摂取量・炎症・体液量の評価を拡張し、必要に応じ栄養診断へ |
GNRI は Alb 値に強く依存するため、感染症・炎症・浮腫・脱水などの影響を必ず考慮する必要があります。特に腹膜透析や感染合併時は、CRP や体液バランス、身体機能・ ADL の変化と組み合わせて総合判断することが前提になります。
心不全での GNRI の位置づけ(体液変動を踏まえた読み方)
慢性心不全では、サルコペニアやフレイルを伴った心臓悪液質が予後不良因子として知られており、GNRI はそのリスクを簡便に捉えるツールの 1 つです。GNRI 低値は死亡・再入院・ ADL 低下と関連しうるため、チーム内の共通指標として使う価値があります。
- 心不全では、体液貯留や利尿薬により体重・ Alb が変動しやすい点に注意が必要です。
- GNRI 単独ではなく、病態指標と運動耐容能・身体機能の変化を合わせて評価します。
- PT の立場では、GNRI を手掛かりに運動療法と栄養療法の両輪を意識し、チームと目標(体重・ Alb ・機能)を共有することがポイントです。
「GNRI 低値だから歩かせてはいけない」のではなく、「GNRI 低値だからこそ安全性に配慮しながら運動+栄養介入を早期から始める」という発想が重要です。
GNRI を起点にした栄養評価フロー(スクリーニング → 診断 → 介入 → 再評価)
GNRI はあくまでスクリーニング(ふるい分け)です。GNRI でリスクを拾ったあとは、診断と介入に確実につなぐフローをチームで共有しておく必要があります。病棟・在宅いずれにも応用しやすい標準的な流れの一例です。
- スクリーニング( GNRI 計算 ):Alb( g/dL )、身長、体重を取得し、浮腫・脱水・炎症所見も記録します。
- IBW の統一:Lorentz 式または BMI 22 法のどちらを使うか院内で決定し、評価表に明記します。
- 栄養診断( GLIM など ):GNRI でリスクありなら、体重減少・筋量・摂取量・炎症など「表現型+原因」の両軸を確認します。
- 栄養介入の設計:食事量の確保、経口栄養補助食品、食形態調整、必要に応じ経腸/静脈栄養を検討します。
- 身体機能の設計:耐久性・下肢筋力・活動量を評価し、運動プログラムの強度と頻度を調整します。
- モニタリング:GNRI・体重・ Alb ・身体機能を定期的に追跡し、介入内容をアップデートします。
このように GNRI は「栄養評価の入口」として位置づけ、スクリーニング → 診断 → 介入 → モニタリングをワンセットで運用することが大切です。
GNRI 解釈のよくある落とし穴(詰まりどころを表で回避)
GNRI は計算自体はシンプルですが、解釈を誤ると栄養評価を見誤ります。院内マニュアルに入れておくと役立つポイントをまとめます。
| 落とし穴 | なぜ起こる? | 対策/記録ポイント |
|---|---|---|
| Alb は栄養だけを反映しない | 炎症・感染症・肝機能・体液バランスの影響を強く受けます。 | CRP など炎症所見と、浮腫/脱水の有無を同時に残します。 |
| 現体重 ÷ IBW は 1 を上限で扱う | 比が 1 を超えると、過体重が「安全」に見えてしまいます。 | 比が 1.00 を超えたら 1.00 として代入します(方式を統一)。 |
| IBW の定義が混在して比較不能 | Lorentz と BMI 22 が混在すると、時系列比較が崩れます。 | 院内で方式を決め、評価表/カルテに方式名を明記します。 |
| GNRI 単独で結論を出す | GNRI は入口であり、診断と介入の情報が不足します。 | 体重減少・筋量・摂取量・炎症を追加確認し、介入設計へつなげます。 |
GNRI の計算例( 2 パターンでイメージを固定)
よくある 2 パターンを例に、GNRI 計算とカットオフのイメージを掴んでおきましょう(四捨五入あり)。
- Alb 3.0 g/dL、現体重 ÷ IBW = 0.90 の場合:
GNRI = 14.89 × 3.0 + 41.7 × 0.90 = 44.7 + 37.5 = 82.2(中等度リスク) - Alb 3.8 g/dL、現体重 ÷ IBW = 1.00 の場合:
GNRI = 14.89 × 3.8 + 41.7 × 1.00 = 56.6 + 41.7 = 98.3(リスクなし)
実務では、電子カルテの自動計算やシート化を進めて、毎回の電卓作業を減らしておくと運用が安定します。
GNRI を測定するタイミングと、記録のコツ(経時変化で価値が出る)
GNRI は「一度きり」ではなく、経時的に追うことで真価を発揮する栄養評価指標です。タイミングを標準化しておくと変化を捉えやすくなります。
| 場面 | 頻度の目安 | セットで残すと良い情報 |
|---|---|---|
| 入院時/入所時 | ベースライン | Alb・体重・ IBW 方式・浮腫/脱水・炎症所見 |
| 急性期〜回復期 | 週 1 回程度 | 摂取量・体重推移・活動量・機能変化 |
| 安定期(外来/通所/在宅) | 月 1 回程度 | 体重・食事量・フレイル/活動性の変化 |
記録には、GNRI スコアだけでなく「計算に用いた Alb・体重・ IBW(方式名)」も併記するのがポイントです。GNRI が変化したときに「どの要素が動いたのか」が分かり、介入の修正につながりやすくなります。
おわりに:GNRI を「入口」として使い倒す
GNRI は、Alb と体重( IBW )から低栄養リスクを素早く可視化できる栄養スクリーニング指標です。一方で、GNRI だけで栄養状態を診断することはできません。臨床のリズムとしては、入院時 GNRI → 栄養診断 → 栄養+運動介入 → GNRI と機能の再評価という流れをチームで共有し、「評価して終わり」を避ける設計が重要です。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に。見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック( A4 ・ 5 分)と職場評価シート( A4 )を無料公開しています。印刷してそのまま使えます。マイナビコメディカルの活用ポイントとダウンロードはこちらを参考にしてください。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
GNRI の読み方と、ほかの栄養評価( MNA-SF ・ MUST など )との違いは?
GNRI の読み方は一般に「ジー・エヌ・アール・アイ(ジーエヌアールアイ)」です。GNRI は Alb と体重( IBW )から算出する数値指標で、栄養関連リスクや予後の層別化に使われます。一方、質問票形式のスクリーニングは、食事量や体重減少、 BMI などを含めて総合的に評価します。実務では、施設のフローを決めて「入口(スクリーニング)→ 診断 → 介入 → 再評価」までつなげることが大切です。
GNRI の理想体重( IBW )は Lorentz 式と BMI 22 法、どちらを使うべき?
どちらが「正解」というより、院内で方式を統一しておくことが最重要です。原著の再現性を重視するなら Lorentz 式、日本人高齢者の実務に合わせるなら BMI 22 法を採用する施設もあります。途中で方式が混在すると、同じ患者でも GNRI の時系列比較が崩れるため、評価表やカルテに「方式名」を明記して運用します。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下
運営者について/編集・引用ポリシー/お問い合わせフォーム:サイト内の各固定ページをご参照ください。
参考文献
- Bouillanne O, et al. Geriatric nutritional risk index: a new index for evaluating at-risk elderly medical patients. Am J Clin Nutr. 2005;82(4):777–783. doi: 10.1093/ajcn/82.4.777
- Cereda E, et al. Geriatric Nutritional Risk Index and overall-cause mortality prediction in institutionalised elderly: a 3-year survival analysis. Clin Nutr. 2008;27(5):717–723. doi: 10.1016/j.clnu.2008.07.005
- Jensen GL, et al. GLIM consensus approach to diagnosis of malnutrition: A 5-year update. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2025;49(4):414–427. doi: 10.1002/jpen.2756
- 加藤 明彦ほか(日本透析医学会学術委員会 栄養問題検討ワーキンググループ). 慢性透析患者における低栄養の評価法. 日本透析医学会雑誌. 2019;52(6):319–325. J-STAGE