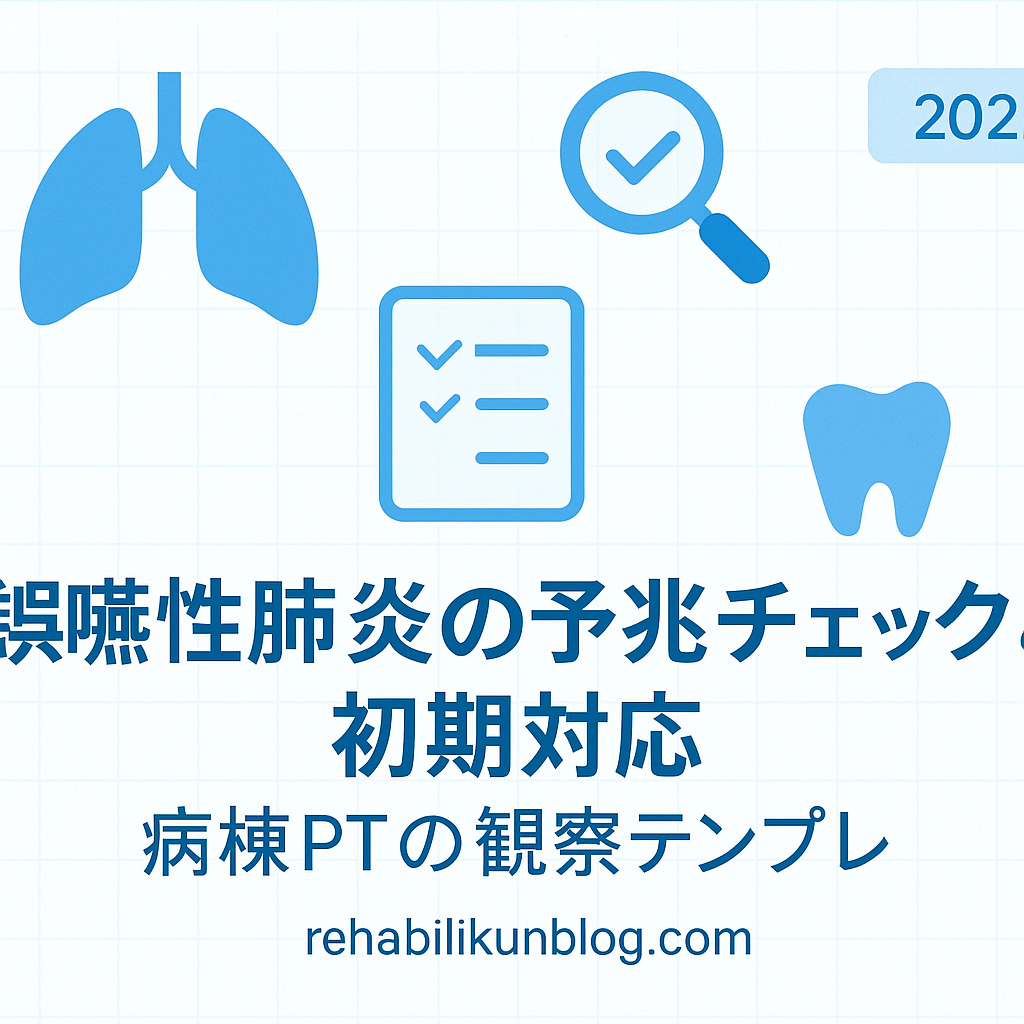誤嚥性肺炎 PT 実務ハブ 2025:予兆・スクリーニング・予防
本ページは、病棟・老健・在宅で誤嚥性肺炎に直面する理学療法士のための実務ハブです。総論よりも「予兆の拾い方」「スクリーニングの選び方」「何から手を打つか」を 1 ページで俯瞰し、詳細は各プロトコル記事へつなげます。
嚥下・呼吸・活動量は“単発”だと抜けやすいので、本ハブではバンドル(束ねて回す)前提で整理します。まずは下の「最短の使い方」だけ押さえれば、現場で迷いにくくなります。
はじめに:最短の使い方
結論として、誤嚥性肺炎の実務は「疑う」より先に観察の型を固定すると、見逃しと対応遅れが減ります。まずは予兆を定型化し、次に薄く広いスクリーニングを回し、最後に予防バンドルを毎日チェックで回します。
このハブは、①予兆の拾い方 ②スクリーニングの選び方 ③予防の 7 要素を、そのまま病棟の運用に落とせる順番でまとめています。必要に応じて、嚥下プロトコルの全体像は 栄養・嚥下ハブ も参照してください。
予兆 → 初期対応の流れ( 3 ステップ )
最初の一手は「検査を増やす」ではなく、体位・口腔・呼吸負荷・活動量の条件を整えつつ、多職種に早めに共有することです。以下の 3 ステップを院内の共通言語にすると、対応が揃いやすくなります。
- 予兆を言語化:「いつもと違う」を観察項目で拾い、時間軸(いつから)を添える
- 条件を整える:頭部挙上・口腔内状態・呼吸数 / SpO2・水分環境を調整する
- 薄く広くスクリーニング:反復で追い、変化があれば医師・看護・ ST と共有する
予兆チェック(観察テンプレ)
高齢者は発熱が目立たず、非特異症状が先行しやすいです。まずは「観察 → 解釈 → 次アクション」が 1 行で書ける形にします。※スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 観察ポイント | どう問題になるか(例) | PT の初期対応(例) | 共有の目安(例) |
|---|---|---|---|
| 湿性嗄声・湿った咳・痰量増加 | 気道クリアランス低下で不顕性誤嚥が持続しやすい | 座位で呼吸リズム調整、咳嗽誘導、体位で排痰を助ける | 声質変化・痰性状の変化が続く |
| 食思不振・脱水傾向 | 唾液粘稠化 → 嚥下負担増 → 誤嚥リスク上昇 | 水分環境の調整(タイミング・姿勢)、口腔内乾燥の確認 | 摂取量低下が数日続く / 口腔乾燥が強い |
| 日中傾眠・せん妄様 | 覚醒低下は嚥下反射・咳嗽反応の低下と連動 | 日中活動量の微増、座位時間の確保、睡眠覚醒リズムの支援 | 食事場面で覚醒が保てない |
| 呼吸数微増・SpO2 低下 | 微小吸引の集積 / 換気低下を示唆 | 頭部挙上 30–45°、胸郭可動性の介入、負荷量の調整 | 安静でも SpO2 が低下 / 呼吸数が増える |
| 体温・炎症反応が軽微でも「いつもと違う」 | 肺炎の典型像が出にくいことがある | 変化の出た項目を固定して再評価(同条件) | 観察項目が複数同時に悪化 |
スクリーニング 5 点セット(最短ルート)
スクリーニングは「 1 回で決める」より、薄く広く反復で追うのがコツです。下の 5 点を基本セットとして、数値+所見+体位条件をセットで記録します。
| 項目 | 見たいもの | 実務のコツ | 注意点 |
|---|---|---|---|
| RSST | 反復嚥下の可否(嚥下の持久性・覚醒) | 同じ姿勢・同じ時間帯で反復し「変化」を拾う | 実施前に覚醒・口腔乾燥を確認 |
| MWST / WST | 水分での嚥下の安全性(むせ・声質・呼吸) | 「むせなし」でも声質・呼吸の変化を必ず観察する | 安全配慮は施設手順に従う |
| 咳(随意 / 誘発の観察) | 咳嗽力・痰の出しやすさ | 座位での咳の質(弱い / 途切れる)を言語化する | 疲労・呼吸苦が強い日は負荷を下げる |
| 口腔衛生の観察 | 口腔内負荷(乾燥・舌苔・義歯など) | 看護・歯科衛生と「観察ポイント」を揃える | 口腔ケアは “量” より “質とタイミング” |
| 呼吸数 / SpO2 / 声質 | 呼吸負荷・微小吸引の示唆 | 体位(頭部挙上角度)を固定して比較する | 酸素設定は医師指示・施設基準に従う |
スクリーニングを「やった」で終わらせないコツは、同条件再評価です。体位(角度)・補助具・介助量・実施時間帯を揃えて、変化の解釈精度を上げます。
予防は “バンドル” で: 7 要素
誤嚥性肺炎の予防は、単発介入だと抜け漏れが出やすいです。そこで毎日チェックで回す 7 要素として束ねます。口腔ケアと姿勢、日中活動量の底上げが土台です。
| 要素 | ポイント | PT の関わり(例) | 記録の一言(例) |
|---|---|---|---|
| ① 体位 | 頭部挙上 30–45°、摂食時は軽度前屈など | 角度を揃えて環境調整、座位耐久の確保 | 「頭部挙上 30° で安定」 |
| ② 口腔ケア | タイミングと質(食前後・就寝前など) | 観察所見を看護と共有し、介入の方向性を揃える | 「口腔乾燥強く介入依頼」 |
| ③ 早期離床・活動量 | 日中の覚醒と換気を底上げ | 座位・立位の機会を増やし “微増” で継続 | 「座位 20 分 × 2 回」 |
| ④ 呼吸の再調整 | 呼吸リズム、胸郭可動性、咳の質 | 呼吸介入+休息設計で呼吸仕事量を調整 | 「呼吸数 22 → 18」 |
| ⑤ 水分・栄養 | 乾燥・栄養低下は嚥下負担を増やす | 摂取環境の調整、栄養職・ ST と連携 | 「摂取姿勢を統一」 |
| ⑥ 眠気・口渇に影響する要因 | 覚醒低下は誤嚥リスクと連動 | 日中の活動設計、観察所見を共有 | 「傾眠あり食事前要配慮」 |
| ⑦ 排痰・気道クリアランス | 痰が出せるかが重要 | 体位・動作・呼吸のセットで “習慣化” | 「湿性嗄声 ↓、痰排出可」 |
家族説明用: NHCAP を短く
NHCAP は、医療・介護と継続的に関わる方に起きやすい肺炎で、市中肺炎と院内肺炎の中間のイメージです。高齢や要介護、最近の入退院などが背景にあることが多く、むせや咳が目立たない “サイレント誤嚥” が関与する場合があります。予防のカギは、口腔内を清潔に保つこと、食事や内服の体位を整えること、日中に身体を動かすこと、そして早めの気づきと共有です。
関連プロトコル・評価
- RSST(反復唾液嚥下テスト):カットオフと読み方
- MWST・WST:比較と使い分け
- 息切れスケール: mMRC × Borg(運用)
- 6 MWT:プロトコルと中止基準
- 呼吸評価の実務ガイド( PT 向け )
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. むせがなくても誤嚥を疑うべきですか?
A. はい。むせは分かりやすいサインですが、むせが目立たないケースもあります。声質(湿性嗄声)、呼吸数 / SpO2、痰の増加、食後の疲労・傾眠などをセットで見て「いつもと違う」を言語化し、同条件で反復して変化を拾うのが実務的です。
Q2. スクリーニングは何から始めると迷いませんか?
A. 迷ったら「呼吸数 / SpO2 / 声質(体位条件つき)」+「口腔観察」から始め、次に RSST、必要に応じて水嚥下系( MWST / WST )を施設手順の範囲で実施します。ポイントは、 1 回で決めずに “薄く広く反復” することです。
Q3. 予防で一番抜けやすいのはどこですか?
A. 体位と口腔ケア、日中の活動量(離床)の 3 点が、忙しい現場ほど抜けやすいです。予防は単発ではなく、 7 要素をチェックで回す「バンドル」にすると抜け漏れが減ります。
Q4. PT として “いま” できる初期対応は何ですか?
A. ①頭部挙上と摂食時姿勢の調整、②口腔内状態の確認と共有、③呼吸負荷の調整(休息設計を含む)、④離床の微増、⑤観察所見を定型化して多職種に早めに共有、の順で動くと迷いにくいです。
おわりに
誤嚥性肺炎の実務は、予兆を拾う → 薄く広くスクリーニング → 体位と口腔を整える → 離床と呼吸で土台を作る → 同条件で再評価のリズムで回すと、対応が揃いやすくなります。面談前に準備を整えたい方は、面談準備チェック&職場評価シートもあわせて活用してみてください。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下