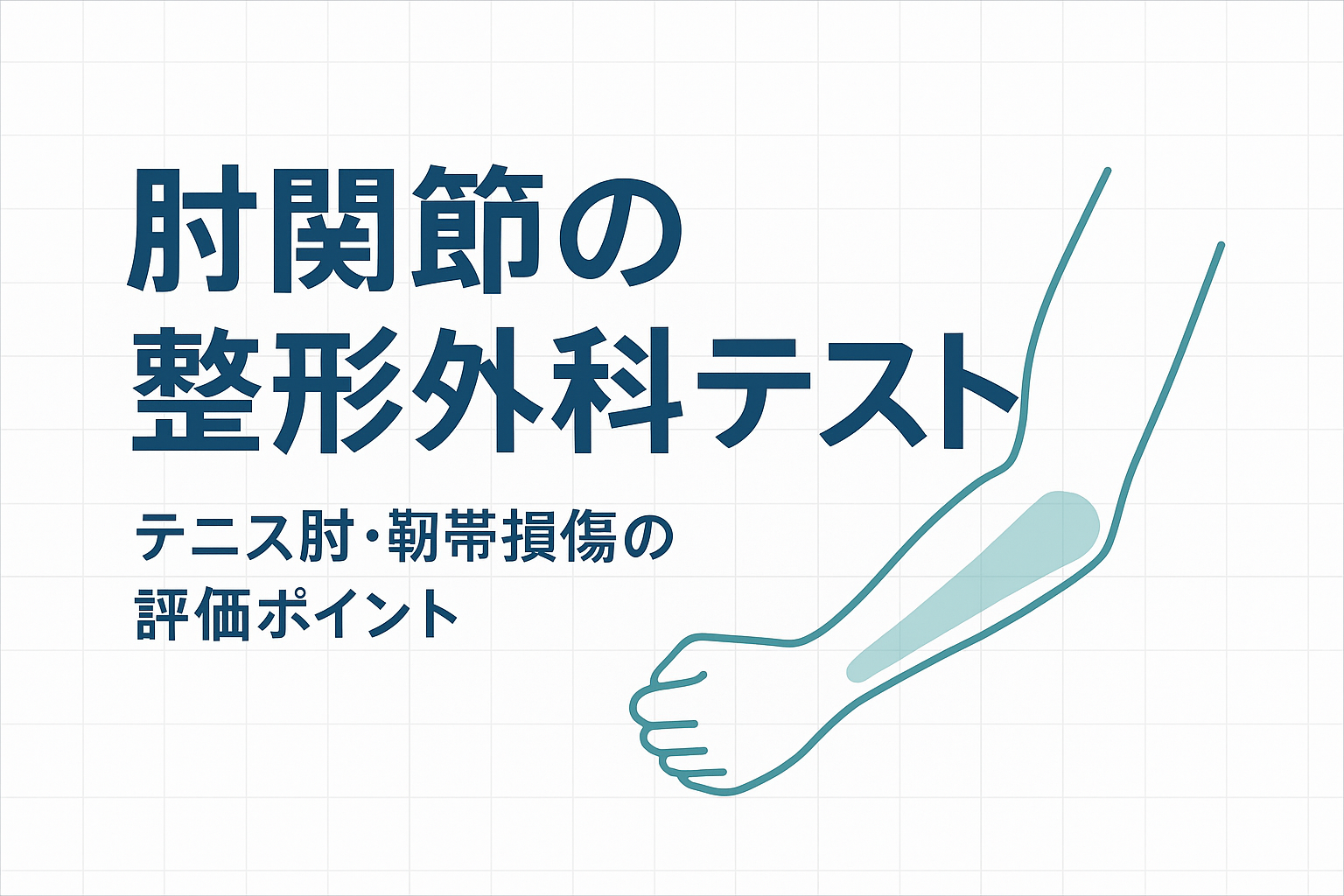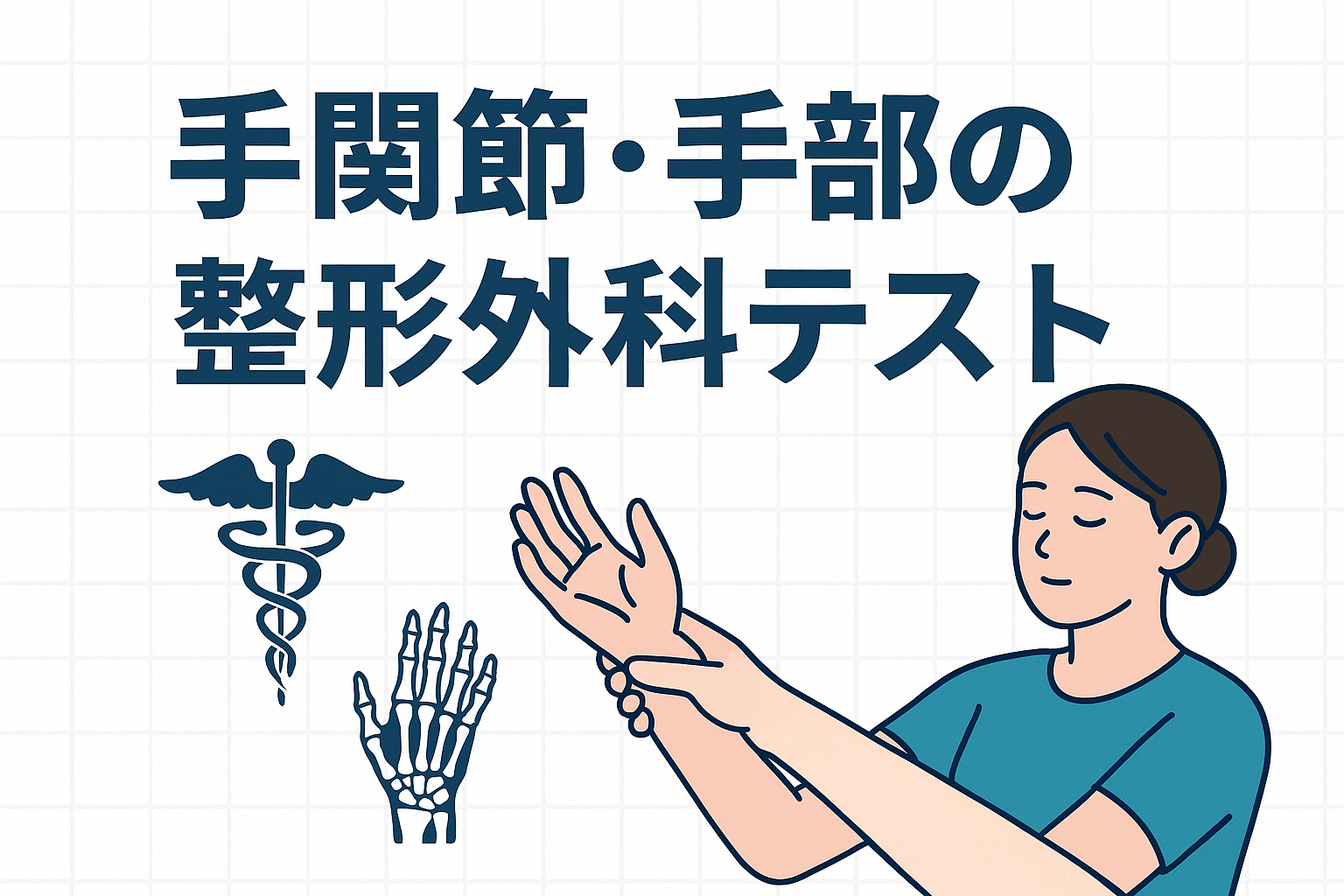肘関節の整形外科テストとは
肘の整形外科テストは、テニス肘・ゴルフ肘などの上顆炎から、側副靱帯損傷、肘部管症候群などの末梢神経障害まで、いわゆる「使いすぎ痛」を整理するうえで役立つツールです。ただし、レントゲンやエコーが正常でも外側上顆炎はあり得ますし、テスト単独で診断を確定できるわけではありません。あくまで 疼痛の主座と、負荷が集中する動作パターンを可視化するための道具 として位置づけるのが現実的です。
本記事では、外側上顆炎(テニス肘)、内側上顆炎(ゴルフ肘)、側副靱帯損傷、肘部管症候群を想定した代表的なテストを整理し、理学療法士が押さえておきたいポイントと禁忌、リハビリテーションへの展開の仕方をまとめます。レッドフラッグや頸椎・手関節の病態も念頭に置きながら、「どこまでが PT の守備範囲で、どこからは医師に評価を委ねるべきか」を意識して読み進めてください。
外側上顆炎(テニス肘)を疑うテスト群
タオルを絞る、やかんを持ち上げる、PC マウス操作などで肘の外側から前腕にかけて痛みが走る場合には、まず外側上顆炎(テニス肘)を想定します。代表的なテストとして、テニス肘テスト(Cozen)、チェアテスト、中指伸展テストなどがあり、いずれも手関節背屈筋群や総指伸筋に負荷をかけ、外側上顆部での疼痛再現を狙います。
| テスト名 | 主な操作 | 狙う構造・病態 |
|---|---|---|
| テニス肘テスト | 手関節背屈+橈屈に抵抗を加える | 短橈側手根伸筋を中心とした伸筋群の overuse |
| チェアテスト | 肘伸展位で椅子の背をつかみ持ち上げる | 日常動作に近い負荷での外側上顆痛の再現 |
| 中指伸展テスト | 中指伸展に抵抗を加える | 総指伸筋起始部への集中的ストレス |
評価のポイントは、「どのテストで」「どの部位に」「どのような痛みが出るか」を圧痛とセットで整理することです。典型的な外側上顆炎では、外側上顆〜やや遠位の圧痛点と、抵抗性手関節背屈や握り動作での鋭い局所痛が一致します。一方、前腕全体のだるさやしびれが主体であれば、頸椎症性神経根症や橈骨神経領域の神経障害も視野に入れる必要があります。
リハビリテーションの立場では、「局所の overuse」だけでなく、肩・肩甲帯や体幹を十分に使えているか、作業環境(机の高さ、マウス位置など)に問題がないかも含めて評価することが重要です。テストの陽性・陰性を記録して終わりにするのではなく、「どの動作で痛みを再現できるか」を患者さんと共有し、負荷調整とフォーム修正のターゲットを明確にしていきます。
内側上顆炎(ゴルフ肘)を疑うテスト
肘の内側から前腕屈側にかけて痛みが出る場合には、内側上顆炎(ゴルフ肘)を考えます。代表的な Golf Elbow テストでは、前腕回内+手関節掌屈位で抵抗に抗させ、内側上顆部の疼痛再現を狙います。前腕屈筋群・円回内筋の overuse と関連しやすく、投球動作や職業的な握り作業、PC キーボード入力などとも関係します。
| 項目 | 外側上顆炎 | 内側上顆炎 |
|---|---|---|
| 主な圧痛部位 | 上腕骨外側上顆〜伸筋腱付着部 | 上腕骨内側上顆〜屈筋腱付着部 |
| 誘発動作の例 | 手関節背屈・前腕回外・握り込み | 手関節掌屈・前腕回内・グリップ動作 |
| 関連スポーツ | テニス・バドミントン・ラケットスポーツ | ゴルフ・投球・投てきなど |
実際の臨床では、「テニスをしていないのにテニス肘」「ゴルフをしていないのにゴルフ肘」ということも多く、スポーツ歴よりも日常や仕事で繰り返している動作パターンが重要です。疼痛の部位と誘発動作が外側/内側どちらに近いかを整理しながら、頸椎・肩・手関節など他部位からの関連痛の可能性も含めて評価します。
リハビリでは、急性期には疼痛誘発肢位や負荷を抑えつつ、作業姿勢の調整や一時的な動作制限を検討します。慢性期には、前腕屈筋群・伸筋群の筋持久力を高めるエクササイズや、肩・体幹の関与を増やすフォーム修正を組み合わせ、同じ負荷でも肘への偏ったストレスがかからないようにしていきます。
側副靱帯損傷・不安定性を疑うテスト群
転倒での手伸展位着地や、投球動作での肘ストレス後に「ぐらつき感」や局所痛を訴える場合には、側副靱帯損傷・不安定性を疑います。代表的なテストとして、肘関節の内反ストレステスト(外側側副靱帯)、外反ストレステスト(内側側副靱帯)があり、軽度屈曲位でストレスをかけて疼痛や不安定性を評価します。
ポイントは、「痛みがあるかどうか」に加えて「健側と比べて明らかなゆるみがあるか」を慎重に観察することです。疼痛のみで不安定性が乏しいケースでは炎症や軽微な損傷にとどまる可能性もありますが、グラつきが明らかであれば高グレード損傷の可能性が高まり、早期に整形外科での精査や装具・手術の検討が必要になります。
理学療法の立場では、急性期にはストレステストを繰り返し行うことは避け、必要最低限の評価にとどめます。固定や装具の有無、医師の指示を踏まえつつ、痛みを増悪させない範囲で関節周囲筋の軽い収縮や肩・体幹のエクササイズを導入し、全体としての運動量低下を防ぎます。スポーツ復帰期には、痛み・腫脹・不安定性の有無を確認しながら、投球・キャッチボールなどの段階的復帰プログラムに整形外科と連携して取り組みます。
肘部管症候群など末梢神経障害を疑うテスト
小指〜環指尺側のしびれや感覚低下、把持力の低下などがある場合には、肘部管症候群など尺骨神経障害を念頭に置きます。肘部の Tinel 徴候は、尺骨神経走行上を軽く叩打し、末梢側への放散痛やしびれ感を確認するテストです。慢性的な神経刺激がある場合には、叩打によって電撃痛やジンジンするようなしびれが誘発されることがあります。
ただし、単に「ぶつけて痛い」急性の打撲と、慢性的な神経障害による Tinel 陽性は性質が異なります。しびれの分布が典型的な尺骨神経領域に一致するか、夜間や肘屈曲位で症状が増悪しないか、頸椎や手根管など上流に病変がないかなどを併せて確認することが重要です。頸椎症性神経根症や胸郭出口症候群、手根管症候群などでも類似の訴えが出るため、「どのレベルで神経が絞扼されているのか」をイメージしながら評価します。
リハビリテーションでは、肘過屈曲位での長時間保持(スマホ操作、うつ伏せでの肘立てなど)を避ける工夫や、職場での肘支持の位置調整が重要です。必要に応じて夜間の肘伸展位保持装具や、神経の滑走を促す軽いエクササイズを導入し、症状の変化を追います。進行例や筋萎縮を伴う場合には、手術やより専門的な治療の適応も含めて、早期に主治医と相談することが推奨されます。
評価結果をリハビリテーションにどう落とし込むか
肘関節の整形外科テストは、「外側か内側か」「靱帯か筋腱か」「神経が絡んでいないか」を整理するための入口に過ぎません。本当に重要なのは、テスト結果をもとに 原因動作と負荷のかかり方を具体的な場面に落とし込むこと です。たとえばテニス肘テストや中指伸展テストで外側上顆痛が強く再現される場合、ラケットや荷物の持ち方、キーボード・マウス操作の姿勢など具体的な場面に引き寄せて対策を考える必要があります。
側副靱帯損傷が疑われる症例では、ストレステストの結果だけでなく、肘伸展位での荷重や荷物の持ち上げ動作、投球フォームにおける肘角度と体幹の使い方を評価します。肘部管症候群など神経障害が疑われる場合には、症状が出やすい肢位と時間帯、仕事や生活での肘の使い方を詳しく聞き取り、姿勢指導や環境調整とセットで介入していきます。
再評価では、毎回すべてのテストを繰り返すのではなく、診断仮説と治療ターゲットに関係する 1〜3 個のテストに絞り、疼痛・しびれ・機能の変化を追うと効率的です。疼痛スケールや握力、簡単な機能テスト(ペットボトル把持、タオル絞りなど)と組み合わせることで、患者さんにも変化を実感してもらいやすくなります。
配布物・チェックシートの活用(働き方の整理にも)
肘の「使いすぎ痛」は、スポーツや作業環境だけでなく、勤務体制や人員配置など、職場や働き方そのものとも密接に関係します。症例ごとの評価・治療フローを整理することに加えて、自分自身がどのような環境であれば学びを継続しやすいか、患者さんとじっくり向き合いやすいかを考えることも、長期的な臨床力の維持には欠かせません。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に。見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック(A4・5 分)と職場評価シート(A4)を無料公開しています。印刷してそのまま使えます。ダウンロードページを見る。
おわりに
肘関節の整形外科テストは、外側上顆炎・内側上顆炎・側副靱帯損傷・神経障害など、「使いすぎ痛」の背景にある病態を整理するうえで有用ですが、テスト名と手順だけを暗記しても臨床ではなかなか使いこなせません。どのテストがどの筋・靱帯・神経にストレスをかけているのか、どの動作場面と結びついているのかをイメージしながら、評価→介入→再評価のリズムを作ることで、症例ごとの方針が立てやすくなります。
上で紹介したチェックシートも活用しつつ、日々の症例を通じて「肘の痛みをどう整理し、どう説明し、どう動作に落とし込むか」という自分なりの型を少しずつ磨いていきましょう。そのプロセス自体が、将来のキャリア選択や働き方を考えるうえでも大きな財産になっていきます。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
テニスをしていなくても「テニス肘」になり得ますか?
はい、テニスをしていなくても外側上顆炎(いわゆるテニス肘)になることはよくあります。重要なのはスポーツの種類ではなく、手関節背屈や握り込みを繰り返す作業・趣味・家事があるかどうかです。パソコン作業、調理、介護場面での移乗介助、工具の使用なども原因になり得ます。問診では「どんな場面で痛みが出るか」を具体的に聞き出すことが大切です。
レントゲンが正常でもテニス肘やゴルフ肘は疑ってよいですか?
上顆炎は主に筋腱付着部の微細損傷や変性が中心であり、レントゲンでは明らかな異常が写らないことが多いです。圧痛点や誘発テストで典型的なパターンがみられれば、レントゲンが正常でも上顆炎を疑うことは十分にあり得ます。必要に応じてエコーや MRI などで筋腱の状態を確認しつつ、負荷調整やフォーム修正を軸にリハビリを進めていきます。
ストレステストは痛みが強くても最後までやるべきですか?
いいえ、痛みが強い場合や患者さんが不安を訴える場合に、無理にストレスをかけ続ける必要はありません。目的は「どの範囲で痛みや不安定感が出るか」を知ることであり、「最大限ストレスをかけること」ではありません。痛みや不安感が出た時点で負荷を緩め、その角度や感覚を記録すれば十分な情報が得られます。疑わしい所見があれば、早めに医師と連携して評価方針を相談しましょう。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下