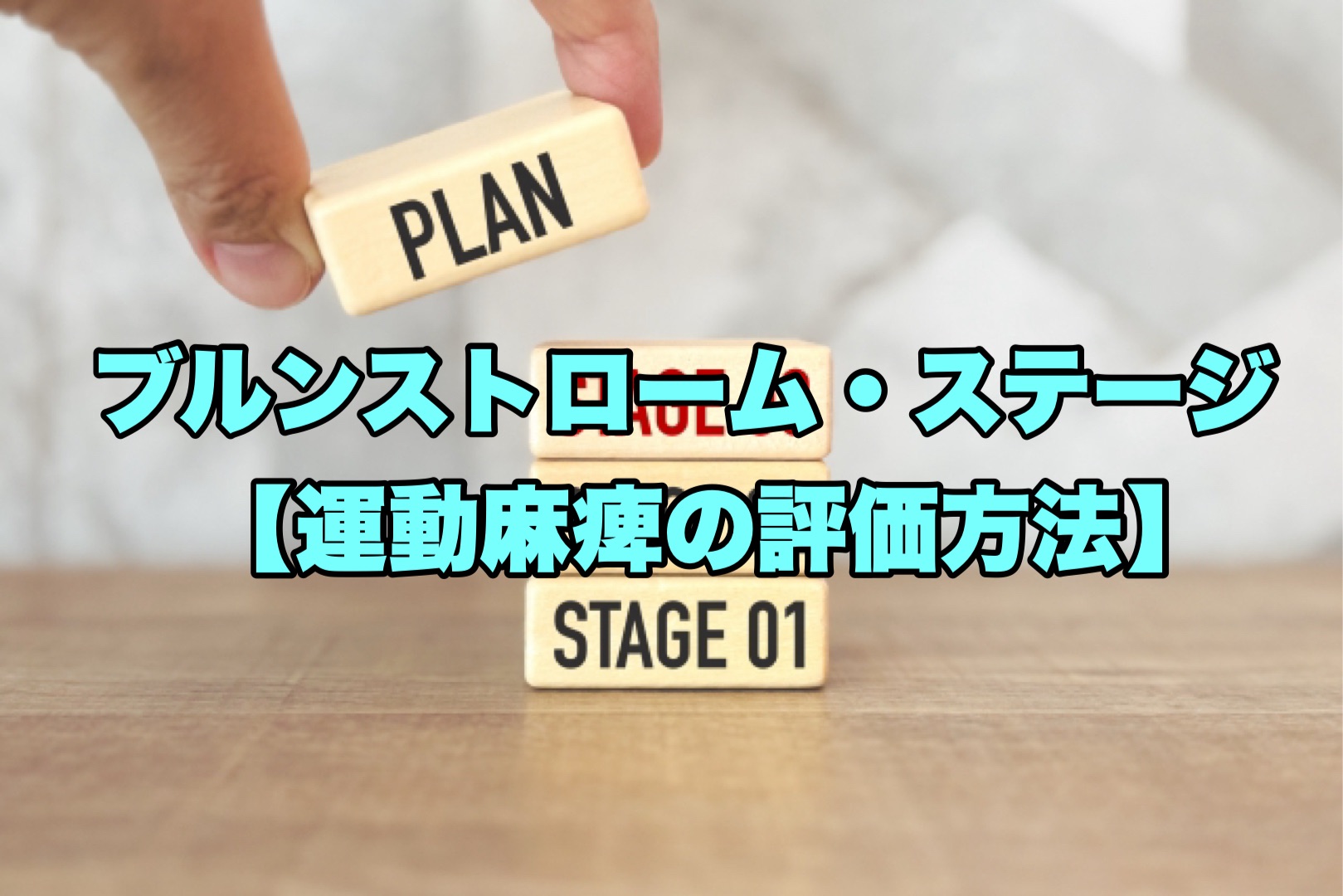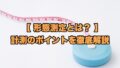- ブルンストロームステージ( BRS )の評価方法| 6 段階の特徴と判定のコツ
- ステージ目安(早見表)|まずは 30 秒で全体像
- ブルンストロームステージ( BRS )の要点
- 評価方法(やり方)|段取りを固定すると再現性が上がる
- 上肢( A )の判定ポイント|まず Stage III を見て分岐
- 手指( H )の判定ポイント|“手だけ遅れる”は珍しくない
- 下肢( L )の判定ポイント|座位→立位で課題が変わる
- 記録方法|段階だけでなく「条件」を 1 行添える
- 判定のコツとよくある誤り|“最良再現性”で丸める
- 臨床での使い方|共有言語として“速く”使い、詳細は併用で補う
- 安全の目安(中止・再評価)|強い誘発で悪化させない
- よくある質問(FAQ)
- 参考文献
- おわりに
- 関連記事
- 著者情報
ブルンストロームステージ( BRS )の評価方法| 6 段階の特徴と判定のコツ
BRS は「姿位」と「課題」を固定すると、判定と経時比較が一気に安定します。 評価 → 介入 → 再評価の流れを 3 分で復習する( #flow )
ブルンストロームステージ( Brunnstrom Recovery Stages: BRS )は、脳卒中後の片麻痺を回復過程(共同運動 → 分離運動)の視点から段階づける評価です。筋力テスト( MMT )のように単関節・単筋をみるのではなく、全体の動き(パターン)と分離の出現を捉えるため、チーム内の共通言語として使いやすいのが特徴です。
臨床の結論:上肢( A )・手( H )・下肢( L )を別々に Stage I–VI で判定し、シナジー内 → シナジー外(分離)の順に確認して、最も再現性の高い段階に丸めて記録します(例:BRS-A IV / H III / L V)。
ステージ目安(早見表)|まずは 30 秒で全体像
最初に「何が変わると段階が上がるのか」を掴むと、評価が速くなります。BRS は痙縮の強さそのものではなく、共同運動への依存度と分離運動の広がりで捉えるとブレにくいです。
下の早見表は、臨床で使いやすいように「特徴」と「まず見るポイント」を最小セットで整理しています。
| Stage | 特徴(ざっくり) | まず見るポイント | 代表的に見やすい動き(例) |
|---|---|---|---|
| I | 弛緩、随意ほぼなし | 連合反応や筋収縮の兆しがあるか | 触診での収縮、努力時の反応 |
| II | 痙縮出現、共同運動の兆し | わずかな随意/痙縮の出現 | 連合反応、わずかな随意収縮 |
| III | 痙縮最強、シナジー内で随意可 | 共同運動(屈曲/伸展)で明確に動くか | 上肢:屈曲/伸展シナジー、下肢:屈曲シナジー |
| IV | 痙縮減退、一部の分離が出る | シナジー外の“芽”が同条件で再現するか | 肘単独伸展、前腕回内外、足背屈 など |
| V | 分離が拡大、複合運動が概ね可能 | 分離課題が複数で安定するか | 肩挙上の拡大、より難しい分離課題 |
| VI | 分離・協調が良好、痙縮ほぼ消退 | 協調性・反復の質(ぎこちなさが少ない) | 反復課題の協調、スピードの安定 |
ブルンストロームステージ( BRS )の要点
BRS は上肢( A )・手( H )・下肢( L )をそれぞれ Stage I–VI で独立判定します。上肢が先に上がって手指が遅れる、下肢だけ改善が先行する、といったズレは珍しくありません。
判定が揺れるときは、「段階」より先に姿位・開始肢位・口頭指示・促通の有無を固定し、同条件で再現する段階に丸めて記録すると、経時比較が一気に読みやすくなります。
評価方法(やり方)|段取りを固定すると再現性が上がる
評価は「 I から順番」ではなく、臨床ではまず Stage III 相当(共同運動が明確か)を見て、そこから上下に分岐するとスムーズです。無理に誘発して痙縮や疼痛を増やさないよう、安全確認 → 課題 → 観察 → 記録の順で進めます。
ポイントは、シナジー内の随意を確認したあとに、シナジー外の分離を同じ条件で確認することです。
- 姿位と準備:背臥位または端座位(下肢の高難度は立位)。疼痛・拘縮・注意・バイタルを確認し、無理な誘発は避けます。
- 誘発課題:まず上肢/下肢の屈曲・伸展シナジーを確認し、次にシナジー外の分離(例:肘単独伸展、手指伸展、膝屈曲、足背屈)を確認します。
- 観察ポイント:痙縮の出現タイミング、随意の質、分離の可否と協調性、疲労や疼痛での変動を見ます。
- 判定と記録:最も再現性の高い段階に丸め、上肢/手/下肢を別々に記録します(例:
BRS-A IV / H III / L V)。姿位・誘発課題・促通の有無も併記します。
上肢( A )の判定ポイント|まず Stage III を見て分岐
上肢は「共同運動が明確か( Stage III )」を入口にし、分離課題が成立すれば Stage IV–VI へ進みます。代償(体幹の回旋・側屈)で“できた”に見えるケースがあるため、開始肢位と指示を固定して確認します。
Stage III:共同運動(屈曲/伸展)の明確な出現
- 見ること:屈曲または伸展シナジーで、明確に関節運動が出るか
- 注意:代償(体幹)と促通の強さを揃える
Stage IV:共同運動からの分離が“一部”可能
- 見ること:シナジー外の課題が 1 つでも同条件で再現するか
- 例:肘単独伸展、前腕回内・回外、肘伸展位での肩屈曲の一部 など
Stage V:より難しい分離が可能(分離が拡大)
- 見ること:分離課題が複数で安定するか( 1 回だけは採用しない)
- 例:肩の挙上範囲の拡大、肢位保持下での分離 など
Stage VI:分離・協調が良好(反復でも崩れにくい)
- 見ること:反復で協調が保てるか、ぎこちなさが少ないか
- 注意:明確な回数基準より、協調性・再現性を重視して判定
Stage I–II:連合反応/わずかな収縮の確認
共同運動が明確でない場合は、連合反応や触診での収縮の有無を確認し、Stage I–II を判定します。ここは「強く誘発する」より「安全に反応を拾う」方が臨床的です。
手指( H )の判定ポイント|“手だけ遅れる”は珍しくない
手指は上肢よりも難しく、回復が遅れたり段階が揺れたりしやすい部位です。上肢( A )と同じ段階で決め打ちせず、手指としての分離(伸展やつまみ)が同条件で再現するかで判定します。
評価は短時間で疲労が出やすいので、必要なら休息を挟み、再現性が高い段階に丸めて記録します。
- Stage III の目安:集団屈曲や鍵握りで明確に動く
- Stage IV の目安:横つまみ、わずかな手指伸展など“分離の芽”が出る
- Stage V の目安:より難しいつかみや集団伸展が成立する
- Stage VI の目安:全可動域での伸展や各指の分離が比較的良好
下肢( L )の判定ポイント|座位→立位で課題が変わる
下肢は Stage III–IV を座位で確認し、Stage V–VI の一部は立位課題が入ります。転倒リスクがあるため、立位課題は支持を確保して安全に実施します。
「足背屈が出る/出ない」だけで段階を決めるより、共同運動への依存度と分離の再現性で判定するとブレにくいです。
- Stage III の目安:屈曲シナジー(股・膝屈曲+足背屈)が明確
- Stage IV の目安:足底をつけた膝屈曲、踵接地での足背屈など“分離の芽”
- Stage V の目安:立位で分離課題が成立(支持下で確認)
- Stage VI の目安:協調性や反復でも崩れにくい分離が確認できる
記録方法|段階だけでなく「条件」を 1 行添える
段階だけを書くと、次の評価者が同条件を再現できず、結果が揺れやすくなります。BRS は条件固定と相性が良いので、最小限でよいので「条件」を併記します。
おすすめは段階+条件です(姿位、誘発課題、促通の有無、疼痛・疲労)。これだけで経時比較の質が上がります。
例) BRS-A IV / H III / L V(端座位、促通なし、疼痛 NRS 2、疲労あり) BRS-A III / H II / L IV(背臥位、誘発課題=屈曲シナジー、促通あり)
判定のコツとよくある誤り|“最良再現性”で丸める
判定がブレる理由の多くは、患者の変動よりも評価条件の差です。とくに促通の強さ、開始肢位、口頭指示、疲労・疼痛は境界で結果を動かしやすい要素です。
一度だけ偶然できた動作で段階を上げず、休息後も同条件で再現する段階に丸めると、チーム内の合意が取りやすくなります。
| よくある誤り | なぜ起きる? | 対策(固定する項目) | 記録の一言例 |
|---|---|---|---|
| 上肢( A )と手指( H )を同じ段階で決め打ち | 近位と遠位で回復がズレる | A/H/L を独立判定し、別々に目標を立てる | 「A 先行、H は別課題で追跡」 |
| 一度だけできた分離で段階を上げる | 疲労・注意・促通の影響 | 休息後に再確認し、最良再現性で丸める | 「再現性優先で IV に丸め」 |
| 痙縮の強さ=筋力と解釈する | Stage III は力強く見えやすい | 分離運動の可否を最優先に見る | 「力感より分離の再現性を採用」 |
| 評価条件が毎回違う | 姿位・指示・促通が変わる | 姿位、開始肢位、指示文、促通の有無を固定 | 「端座位、促通なし、指示文固定」 |
評価の全体像(他の指標を含む整理)は、評価ハブにまとめています。
臨床での使い方|共有言語として“速く”使い、詳細は併用で補う
BRS は回復の大枠を共有するのに強く、家族説明やゴール設定の足場になります。一方で微細な変化の感度は尺度によって差があるため、必要に応じて上肢機能の詳細評価などを併用し、目的に合わせて情報量を調整します。
III → IV の移行期は、共同運動に寄りすぎないようにシナジー外課題を“同条件で”繰り返し確認し、再評価で差が出るように設計すると臨床の手応えが出やすいです。
安全の目安(中止・再評価)|強い誘発で悪化させない
評価は介入ではありません。疼痛や強い痙縮を誘発してしまうと、その後の練習や ADL に影響します。中止基準を先に決め、必要なら課題を下げて再評価します。
経時比較は同条件(姿位・課題・促通の有無)で行い、段階が揺れる場合は休息後に再確認します。
- 疼痛増悪、著明な痙縮誘発、強い疲労、 SpO2 低下などがあれば中断し、姿位や課題を調整
- 評価後に筋緊張が上がり続ける場合は、誘発の強さ・課題選択を見直す
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. 判定が日によって揺れます。どう扱えばいいですか?
A. まずは評価条件(姿位、開始肢位、口頭指示、促通の有無、疼痛・疲労)を固定し、同条件で再確認します。それでも揺れる場合は「揺れ」自体が重要な情報なので、段階だけでなく条件を 1 行添えて記録すると、次の介入設計がしやすくなります。
Q2. III と IV の境界は何を優先して決めますか?
A. 「共同運動が主か/分離の芽が同条件で再現するか」を優先します。促通や代償が強い状態で 1 回だけ出た分離は採用せず、休息後も同条件で再現するレベルに丸めるのが安全です。
Q3. 上肢が IV で手指が II のようにズレても大丈夫?
A. あり得ます。A/H/L は独立判定なので、近位が先行し手指が遅れるのは珍しくありません。ズレを“異常”と捉えるより、課題と目標を分けて運用すると臨床が進みます。
Q4. BRS だけで経過を追っていいですか?
A. チーム共有の共通語としては有用です。一方で「微細な変化」を目的にするなら、上肢機能の詳細評価などを併用し、目的に応じて感度を補うと再評価がラクになります。
参考文献
- Brunnstrom S. Motor testing procedures in hemiplegia: based on sequential recovery stages. Physical Therapy. 1966;46(4):357-375. DOI:10.1093/ptj/46.4.357
- Naghdi S, Ansari NN, Mansouri K, Hasson S. A neurophysiological and clinical study of Brunnstrom recovery stages in the upper limb following stroke. Brain Injury. 2010;24(11):1372-1378. DOI:10.3109/02699052.2010.506860 / PubMed
- Twitchell TE. The restoration of motor function following hemiplegia in man. Brain. 1951;74(4):443-480. DOI:10.1093/brain/74.4.443 / PubMed
- Huang C-Y, Lin G-H, Huang Y-J, et al. Improving the utility of the Brunnstrom recovery stages in patients with stroke. Medicine. 2016;95(31):e4508. DOI:10.1097/MD.0000000000004508
おわりに
BRS は、安全の確保 → 条件固定 → 段階づけ( A/H/L )→ 課題設定 → 再評価のリズムで回すと、チーム内のズレが減って介入が前に進みます。まずは「姿位」と「課題」を 1 つずつ固定し、同条件での再評価から始めてみてください。
あわせて、面談準備の抜け漏れ防止に使えるチェックシートもまとめています。面談準備チェック&職場評価シート( MyNavi )を必要に応じて活用してください。
関連記事
上田式 12 段階との違い
境界で迷う人向け
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下