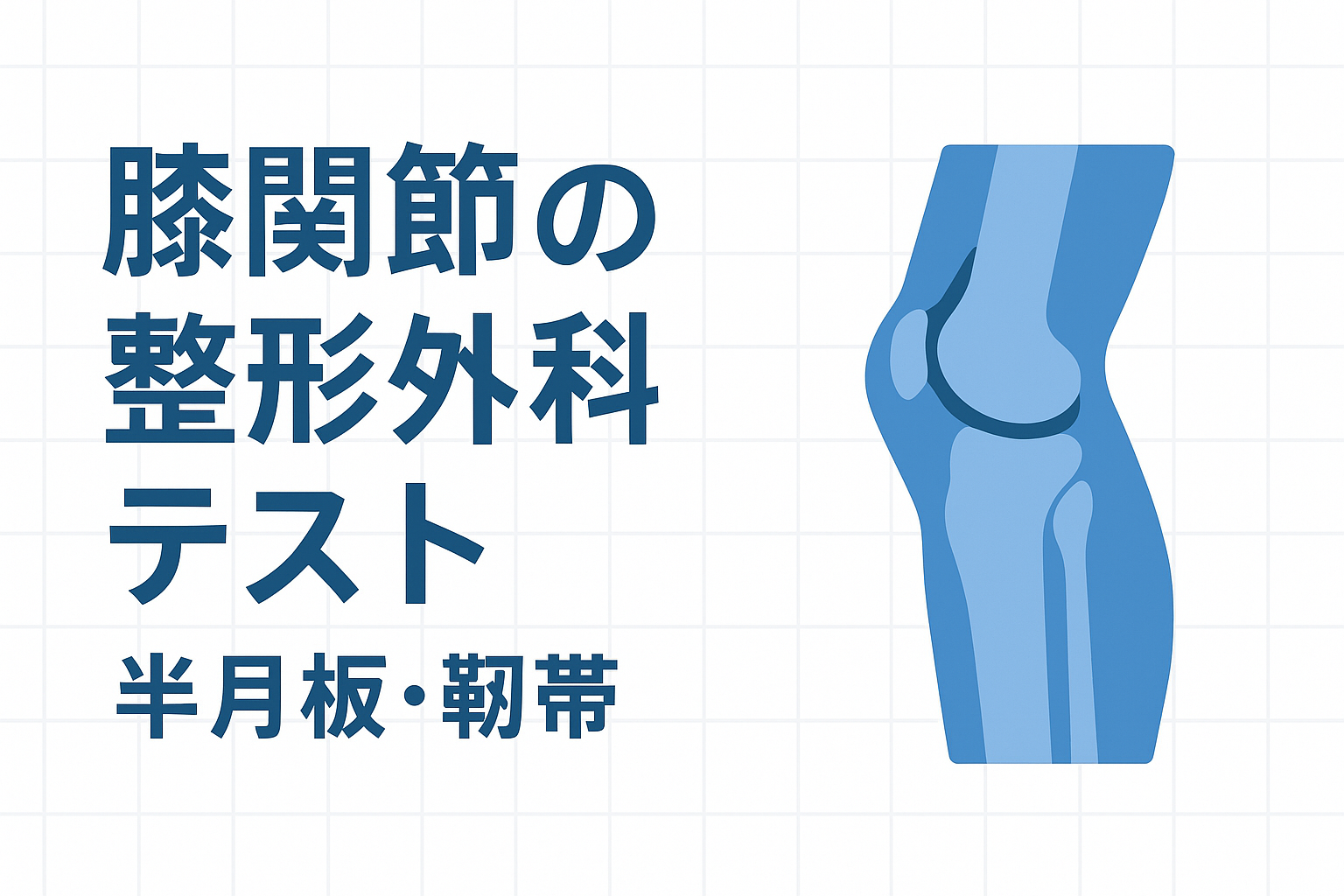- 膝の整形外科テスト一覧|半月板・靱帯を “最小セット” で回す
- 5 分フロー|水腫 → 半月板 → 靱帯 → 膝蓋大腿を “1 周” で確認
- 最小セット早見表| “増やす” 前に、まず 2〜4 個で回す
- 関節水腫・血腫|まず “いま刺激を増やして良いか” を決める
- 半月板( McMurray / Apley )| “裂隙痛+引っかかり” の整合で読む
- ACL / PCL| “前後移動+終末感” を左右差で固定する
- MCL / LCL(外反・内反)| “ 30° → 0° ” を固定して迷いを消す
- 膝蓋大腿関節(前面膝痛)|階段・しゃがみ込みと一致するか
- よくある失敗|テストを増やしすぎて所見が壊れる
- 現場の詰まりどころ|迷ったら “アンカー → チェック → 共通指標” に戻る
- 回避の手順チェック|10 秒で “条件” を揃える
- 記録の型| “角度・方向・左右差・終末感” を 1 行で固定
- よくある質問( FAQ )
- 次の一手|運用を整える → 共有の型 → 環境の詰まりも点検
- 参考文献
- 著者情報
膝の整形外科テスト一覧|半月板・靱帯を “最小セット” で回す
膝の整形外科テストは、病名を当てるためではなく、外してはいけない病態(骨折・重度靱帯損傷など)を先に除外しながら、半月板/十字靱帯/側副靱帯/膝蓋大腿関節のどこに負荷が集まっているかを絞るための道具です。現場でブレるのは「テスト名は知っているのに、順番と量が決められない」こと。本記事では、① 5 分フロー→② 最小セット早見表→③ 病態別の使い分け→④ 失敗回避と記録までを 1 ページに固定します。
特に膝は、痛み・水腫・防御収縮があると徒手所見が崩れやすい部位です。だからこそ、まずは水腫の評価→侵襲の低い確認→必要最小限のストレスの順で、再現性を優先します。
同ジャンルで回遊して、判断を速くする:まずはハブ → 標準手順 → 代表記事の順に辿ると、膝の評価がブレにくくなります。
- サブ導線(総論/標準手順):関節可動域( ROM )検査のやり方|記録と中止基準【運用】
- サブ導線(子記事/各論):Lachman テスト( ACL )のやり方とコツ
5 分フロー|水腫 → 半月板 → 靱帯 → 膝蓋大腿を “1 周” で確認
結論はシンプルで、① 水腫(いまストレスをかけて良いか)→② 半月板(ロッキング/裂隙痛の整合)→③ 十字靱帯(前後不安定)→④ 側副靱帯(内外側不安定)→⑤ 膝蓋大腿(前面膝痛)の順に回すと、過剰にテストを増やさずに仮説が立ちます。
- 水腫:膝蓋跳動などで腫脹の程度を把握(高度ならストレスを増やさない)
- 半月板:裂隙痛・クリック・ロッキングの整合 → 必要最小限で再現
- ACL / PCL:前後引き出し(必要なら Lachman を軽く)+他所見(腫脹/恐怖/終末感)
- MCL / LCL:外反・内反ストレスは “30° → 0°” の順で左右差を確認
- 膝蓋大腿:階段・しゃがみ込みの痛みパターンと一致するかを確認
最小セット早見表| “増やす” 前に、まず 2〜4 個で回す
テストは増やすほど痛みと防御収縮が混ざり、所見が崩れます。ここでは「まずこれだけ」を固定します。
※表は横スクロールできます(スマホ OK)。
| 疑う領域 | まずやる(最小) | 追加(必要時) | 所見の残し方(1 行) |
|---|---|---|---|
| 水腫/血腫 | 膝蓋跳動(膝蓋浮遊) | 周径・熱感・皮膚緊張 | 水腫:±/+/++、痛み/熱感、他テストは控えた |
| 半月板 | 関節裂隙圧痛+ McMurray | Apley 圧迫(必要最小限) | 内側裂隙痛+クリック(角度)/ロッキング有無 |
| ACL | Lachman(軽く) | 前方引き出し/Pivot 系(状況次第) | 前方移動:健側比+終末感(firm/soft)+恐怖 |
| PCL | Sagging 徴候+後方引き出し | Quadriceps active test | 脛骨後方落ち込み(左右差)+後方移動の終末感 |
| MCL/LCL | 外反/内反(30° → 0°) | 痛み部位の一点化 | 角度(30/0)+方向(外反/内反)+開大/終末感 |
| 膝蓋大腿 | 圧迫(グラインド)+不安感 | Q 角/足部/股関節回旋の観察 | 前面膝痛:階段/しゃがみ込み一致+不安感の有無 |
関節水腫・血腫|まず “いま刺激を増やして良いか” を決める
外傷直後や強い腫脹がある場合は、徒手で所見を取りに行くほど悪化することがあります。膝蓋跳動などで水腫の程度を確認し、高度ならストレステストを増やさず、荷重・装具・痛みのコントロールを優先します。
- 高度の腫脹+強い痛み:深追いせず共有(医師評価・画像/穿刺が優先になることがある)
- 慢性的な反復水腫:負荷量・炎症・体重・活動量の関係を見直し、トレーニング量を調整
半月板( McMurray / Apley )| “裂隙痛+引っかかり” の整合で読む
半月板を疑うときは、テストの陽性/陰性より、関節裂隙部痛と動作中の引っかかり(クリック/ロッキング)が整合するかが重要です。裂隙の圧痛や変形性変化が強いと偽陽性も増えるため、所見は “一点化” して残します。
- 各論は別記事で固定:McMurray テストのやり方と注意点
※表は横スクロールできます(スマホ OK)。
| テスト | 狙い | 陽性の目安 | まず残す記録 |
|---|---|---|---|
| McMurray | 屈伸+回旋で症状再現 | 裂隙痛/クリック | 内側/外側、出た角度、ロッキング有無 |
| Apley 圧迫 | 圧縮ストレスで裂隙痛 | 鋭い裂隙痛 | 圧の強さは増やさない(最小再現) |
ACL / PCL| “前後移動+終末感” を左右差で固定する
十字靱帯の評価は、前後方向の移動量(健側比)と終末感(止まる/ふわっと)を 1 行で残すと、介入と再評価に繋がります。急性期は痛みと防御収縮で所見が崩れるため、必要最小限に留める判断も含めて運用します。
- 各論は別記事で固定:Lachman テスト( ACL )のやり方とコツ
※表は横スクロールできます(スマホ OK)。
| 疑う | まずやる | コツ | 記録(型) |
|---|---|---|---|
| ACL | Lachman(軽く) | 痛みが強いときは “強く引かない”。左右差と終末感を優先 | 前方移動:健側比、終末感、恐怖/防御 |
| PCL | Sagging+後方引き出し | まず “後方落ち込み” の左右差を確認してから | 後方落ち込み:±、後方移動と終末感 |
MCL / LCL(外反・内反)| “ 30° → 0° ” を固定して迷いを消す
側副靱帯は、30°(単独が見えやすい)→ 0°(複合要素が混ざりやすい)の順で実施すると、判断と共有が安定します。伸展位( 0° )で明確な不安定性があれば、関節包などを含む複合要素を疑いやすく、扱い(負荷量・再評価・共有)が変わります。
- 各論は別記事で固定:外反・内反ストレステストを迷わず運用する
膝蓋大腿関節(前面膝痛)|階段・しゃがみ込みと一致するか
前面膝痛(PFJ)を疑うときは、局所テストだけでなく、階段・しゃがみ込み・長座位後の立ち上がりでの痛みパターンと一致するかが重要です。膝蓋骨の圧迫や不安感の所見は、股関節・足部アライメントや大腿四頭筋のタイトネスに影響されるため、下肢全体の見立てに繋げます。
- 不安感が強い症例は禁忌寄り:軽い力から開始し、恐怖や防御収縮が出たら深追いしない
- 記録は “動作一致” を主語に:階段で痛い角度/しゃがみ込みでの再現性
よくある失敗|テストを増やしすぎて所見が壊れる
膝は、痛みと防御収縮が強いほど “テストを増やすほど読めなくなる” 典型部位です。失敗は 3 つに集約できます。
※表は横スクロールできます(スマホ OK)。
| 失敗 | 起きること | まず直す 1 点 | OK 記録(型) |
|---|---|---|---|
| 水腫を無視してストレスを増やす | 痛み増悪、防御収縮で所見が崩れる | 先に水腫を評価し “最小再現” に留める | 水腫:++なのでストレスは最小、左右差のみ確認 |
| 角度・順番がその場で変わる | 再評価で比較できない | 外反/内反は “30° → 0°” を固定 | 角度(30/0)+方向+終末感+痛み部位(一点) |
| 陽性/陰性だけ残して次が決まらない | 介入と再評価に繋がらない | “どの角度で・どこが・どう痛いか” を 1 行で残す | 裂隙痛(内側)+クリック(伸展終盤)→負荷調整へ |
現場の詰まりどころ|迷ったら “アンカー → チェック → 共通指標” に戻る
詰まりやすいのは「所見が曖昧で、次の打ち手が決まらない」ことです。ここは読ませるゾーンなので、まずはページ内に戻れるように 3 段で置きます。
- ページ内アンカー:よくある失敗へ戻る(条件が崩れていないか確認)
- ページ内アンカー:回避の手順チェックへ(10 秒で整える)
- 同ジャンルの内部リンク(共有の型):KOOS(膝 PROM )の評価と使い方
回避の手順チェック|10 秒で “条件” を揃える
- 水腫(腫脹)が強いときは “ストレスを増やさない” 判断をした
- 半月板は “裂隙痛+引っかかり” の整合で読んだ(テストを増やしすぎない)
- ACL は “前方移動+終末感” を左右差で残した(強く引かない)
- 外反/内反は “30° → 0°” を固定し、角度を記録した
- 最終的に 1 行で説明できる形にした(角度・方向・部位・終末感)
記録の型| “角度・方向・左右差・終末感” を 1 行で固定
膝の徒手所見は、書き方が固定されると再評価が回るようになります。陽性/陰性よりも、条件と左右差を残します。
- 水腫:±/+/++、熱感、他テストは控えた(理由)
- 半月板:内/外側裂隙、出た角度、クリック/ロッキング有無
- ACL:前方移動(健側比)、終末感(firm/soft)、恐怖/防御
- MCL/LCL:角度(30/0)+方向(外反/内反)+開大+終末感+痛み部位
- PFJ:動作一致(階段/しゃがみ込み)+不安感の有無
よくある質問( FAQ )
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. 痛みや腫れが強い急性期は、どこまでテストしてよい?
急性期に優先するのは「所見を取り切る」より悪化させないことです。まず水腫・熱感・恐怖(防御収縮)を確認し、強い場合はストレスを増やさず、左右差の “最小確認” に留めます。深追いはせず、荷重・装具・共有(必要なら医師評価)を優先して、再評価で条件を整える方が結果として早く進みます。
Q2. 半月板テストが陽性なら、手術が必要と考えてよい?
テスト陽性=手術適応ではありません。年齢・活動量・変形性変化・ロッキング頻度・他靱帯損傷の合併などで方針は変わります。実務では、裂隙痛の一点化と動作一致(引っかかり)の整合を取り、負荷調整と経過で再評価します。ロッキングが頻発し日常生活に支障が大きい場合は、精査ルートを含めて共有します。
Q3. Lachman と前方引き出しは、どちらを優先すべき?
優先は「条件を揃えやすい方」です。Lachman は軽度屈曲位で前方移動と終末感を捉えやすい一方、痛みや筋緊張で実施しにくいこともあります。どちらでも、左右差と終末感を固定して記録できれば実務上は十分に役立ちます。迷ったら、まず “軽く確認して悪化させない” を優先します。
Q4. 外反・内反ストレスは、0° と 30° の両方が必要?
実務では“30° → 0°”で固定すると迷いが減ります。30° 付近は側副靱帯の単独所見が見えやすく、0°(伸展位)で明確な開大がある場合は複合要素を疑いやすく、共有や負荷量の判断が変わります。両方を行う目的が違うため、角度ごとに所見を分けて残します。
Q5. テストが陰性でも痛みが残るとき、何を優先すべき?
徒手テストは “仮説を絞る道具” であり、陰性でも症状が続くことはあります。動作一致(階段・しゃがみ込み・方向転換など)、疼痛部位、腫脹、可動域、筋機能(痛み抑制か真の低下か)を統合し、負荷調整と再評価が回る設計にします。経過共有には KOOS など共通指標を併用すると、説明と意思決定が揃います。
次の一手|運用を整える → 共有の型 → 環境の詰まりも点検
評価が回り始めると、次に必要なのは「条件を揃えて、チームで再現する運用」です。膝のテストも、測る → 記録 → 介入 → 再評価までを 1 セットにすると、同じ時間でもアウトプットが増えます。
- 運用を整える:関節可動域( ROM )検査のやり方|記録と中止基準【運用】
- 共有の型を作る:KOOS(膝 PROM )の評価と使い方
教育体制・人員・記録文化など“環境要因”を一度見える化すると、次の打ち手が決めやすくなります。
チェック後に『続ける/変える』の選択肢も整理したい方は、PT キャリアナビで進め方を確認しておくと迷いが減ります。
参考文献
- Benjaminse A, et al. Clinical diagnosis of an anterior cruciate ligament rupture: a meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2006;36(5):267-288. DOI: 10.2519/jospt.2006.2011 / PubMed: 16715837
- Hegedus EJ, et al. Physical examination tests of the knee: a systematic review with meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2007;37(9):541-550. DOI: 10.2519/jospt.2007.2544 / PubMed: 17877272
- LaPrade RF, et al. Correlation of valgus stress radiographs with medial knee ligament injuries: an in vitro biomechanical study. Am J Sports Med. 2010;38(2):330-338. DOI: 10.1177/0363546509349347 / PubMed: 19966093
- Kane PW, et al. Fibular Collateral Ligament: Varus Stress Radiographic Analysis Using 3 Different Clinical Techniques. Orthop J Sports Med. 2018;6(5):2325967118770170. DOI: 10.1177/2325967118770170 / PubMed: 29770342
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下