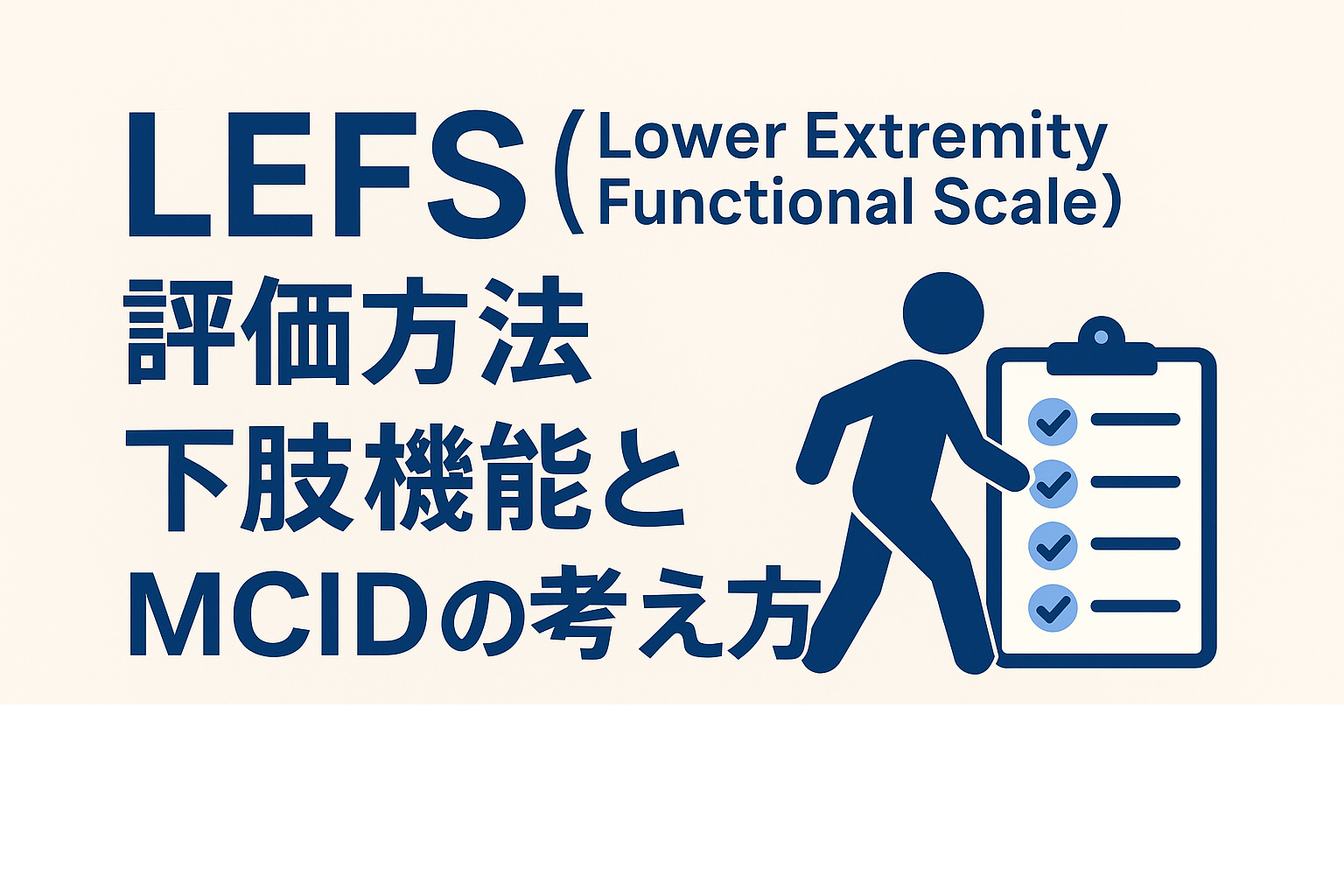LEFS による下肢機能評価の実務ガイド|採点・解釈( MCID / MDC )まで 1 ページ
LEFS( Lower Extremity Functional Scale )は、下肢の「生活動作の困りごと」を 0〜80 点で追える代表的な PROM です。結論としては、採点( 0〜80 点 )を固定し、変化量は「 9 点前後」を 1 つの目安にしながら、痛みや歩行テストと束ねて読むと、説明と再評価が一気にラクになります。
評価は「選ぶ → 条件固定 → 再評価」までセットにすると、チーム共有が崩れません。 評価 → 記録 → 再評価の流れを 3 分で確認する ※ 忙しい現場ほど「順番」と「条件」を先に固定するだけで、再評価の質が上がります。
本ページは 小記事(単体スケール)として、LEFS を「実施 → 採点 → 解釈 → 記録」まで最短で回すことに特化します。どの PROM を選ぶか迷う場合は、運動器 PROM の使い分け(ハブ)側で全体像を確認してから戻ってくる運用が回りやすいです。
LEFS とは?何を測れる PROM か
LEFS は、下肢の筋骨格系症状(股関節・膝・足関節など)により「日常生活や活動がどの程度やりにくいか」を、患者の主観で数値化する質問紙です。画像所見や可動域だけでは拾いにくい、生活動作レベルの変化を追えるのが強みになります。
注意点として、PROM は 痛み・不安・抑うつ・補償などの影響を受けます。スコアが説明しにくいときは「データが間違い」と決めつけず、生活背景とセットで解釈するのが安全です。
いつ・誰に使う?|適応の目安(臨床で迷わない)
LEFS は、部位特異的(膝だけ・股だけ)に寄せすぎず、下肢機能を広く押さえたいときに相性が良いです。外来の保存療法、術前後の経過、回復期の歩行獲得期などで「生活動作の戻り」を追う場面で使いやすくなります。
- 向く場面:下肢の活動制限を横断的に追う(複数部位・複合要因でも運用しやすい)
- 迷いやすい場面:膝 OA / 股 OA など疾患特異的評価が必要( KOOS / HOOS / WOMAC も候補)
- 運用のコツ:初回で「説明」と「条件(靴・装具・杖など)」を固定し、再評価でも同条件で回す
LEFS の評価方法(実施手順)と採点ルール
LEFS は自己記入式が基本です。評価時点における「典型的な状態」を想定して回答してもらい、迷う場合は「一番近い選択肢」を選ぶように説明します。読み書きに制限がある場合は代読・代筆も可能ですが、選択は本人が行う形に統一するとブレにくくなります。
採点は各項目 0〜4 点の合計で、0〜80 点で表記します。%表示にしたい場合は(合計点 ÷ 80 )× 100 で換算できます。未回答が出ると比較が難しくなるため、原則として全項目に回答が得られるように実施手順を整えるのがおすすめです。
横スクロールで全体を確認してください。
| 要素 | 結論 | 運用で詰まりやすい点 | 対策(固定する条件) |
|---|---|---|---|
| 尺度 | 各項目 0〜4 点( 5 段階 ) | 説明が毎回変わる | 教示文を 1 パターンに固定する |
| 総得点 | 0〜80 点(高いほど良い) | %表記と混在 | 院内は 80 点満点で統一(必要時のみ換算) |
| 再評価 | 絶対値+変化量で読む | 靴・装具・杖の条件が不明 | 靴/装具/杖/時間帯をカルテに固定で残す |
| 欠損 | 原則は欠損ゼロを目標 | 未回答が増えて比較不能 | 代読・代筆を許可し、選択は本人に統一 |
スコアの解釈| MCID ・ MDC(変化量の目安)
LEFS はスコアが高いほど機能が良好です。臨床で一番大事なのは「点数そのもの」より、変化量が説明できるかです。よく引用される目安として、 9 点前後が「意味のある変化( MCID )」や「誤差を超える変化( MDC )」の参照値として扱われることがあります。ただし、対象疾患や評価時期で幅が出るため、痛み( NRS など)や歩行テスト、患者の主観的な変化と束ねて判断します。
横スクロールで全体を確認してください。
| 見るポイント | 目安 | 臨床での解釈 | 書き残すと強い情報 |
|---|---|---|---|
| 絶対値 | 0〜80 点 | 高いほど機能が良い | 「どの活動レベルが残るか」を言語化 |
| 変化量 | おおむね 9〜10 点以上を 1 つの目安 | 「変化あり」の候補として扱う | 痛み、歩行、主観(患者コメント)と一緒に残す |
| 注意 | 疾患・時期で変動 | 数字だけで効果判定しない | 評価条件(靴・装具・杖・環境)を固定 |
LEFS と WOMAC / HOOS / KOOS の使い分け( 1 表で整理)
下肢 PROM は「対象のズレ」がそのまま解釈のズレになります。迷うときは、疾患特異性が必要か( OA・術前後など )と、活動レベル( ADL までか、スポーツまでか )で決めるとブレにくいです。
横スクロールで全体を確認してください。
| 尺度 | 得意な対象 | 強み | 注意点 | 迷ったら |
|---|---|---|---|---|
| LEFS | 下肢の活動制限を横断的に | 運用が軽く、経過を追いやすい | 心理社会的要因の影響を受ける | 下肢全体の「生活動作」をまず押さえる |
| WOMAC | 膝 / 股 OA の痛み・ ADL | OA 領域で研究が多い | 高機能レベルの天井効果に注意 | 変形性関節症の「痛み+ ADL 」中心なら |
| KOOS | 膝(損傷〜 OA ) | 症状・スポーツ・ QOL まで多面的 | 項目数が多く運用が重い | 膝の症状とスポーツ要素も追うなら |
| HOOS | 股関節( OA / THA など) | 股関節の症状・ ADL ・ QOL に強い | 項目数が多く運用が重い | 股 OA / THA 前後を疾患特異的に追うなら |
記録とチーム共有のコツ(カルテに残す最小形)
カルテに残すときは、① LEFS の絶対値 ② 変化量 ③ 生活像(どのレベルが改善/残存か)を 1 セットにすると共有が速くなります。下のテンプレは、そのままコピペで使える形にしてあります。
【LEFS】○○年○月○日 合計:___ / 80(前回:___ / 80) 変化:___ 点 条件:靴( )装具( )杖( )時間帯( )環境(病棟/外来/自宅想定) 主観:患者コメント「 」 生活像:できる/困る(例:階段、長距離歩行、買い物、通院) 併用指標:痛み NRS ___/10 歩行(TUG/10m/6MWT など):____________ 次回:再評価日( ) 介入の焦点:____________________
現場の詰まりどころ/よくある失敗(運用で差がつく)
- 説明が人によって違う:教示文を 1 パターンに固定し、代読・代筆時のルールも統一します。
- 条件が固定されていない:靴・装具・杖・時間帯がズレると「点数の比較」が不安定になります。
- 点数だけで判断してしまう: 9 点前後は便利な目安ですが、痛み・歩行・主観と束ねて読みます。
- 運用が回らない:評価そのものより、教育体制や記録文化が未整備で崩れることが多いです。面談準備チェック(印刷して使える)を置いておくと、職場環境の整理がしやすくなります:/mynavi-medical/#download
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
LEFS は何点くらい良くなれば「効果あり」と考えてよいですか?
臨床では、変化量を読むのが基本です。目安として 9〜10 点前後を「変化あり」の候補として扱い、痛み( NRS など)や歩行テスト、患者の主観的な変化とあわせて総合判断します。
%(パーセント)表記にした方がいいですか?
院内運用は 80 点満点のまま統一する方がブレにくいです。報告書で必要な場合のみ(合計点 ÷ 80 )× 100 で換算すると混乱が減ります。
代読・代筆はしてもいいですか?
可能です。読み上げや記入の補助をしても、選択自体は本人が行う形に統一し、説明文も固定すると再評価の信頼性が上がります。
LEFS と WOMAC はどう使い分けますか?
OA を疾患特異的に追う(痛みと ADL )なら WOMAC が便利な場面があります。一方で、下肢機能を横断的に軽く回したいなら LEFS が扱いやすいです。迷ったら「対象が OA か」「スポーツ要素を追うか」で決めるとブレにくいです。
LEFS の点数が画像所見や可動域と一致しません
PROM は心理社会的要因や生活背景の影響を受けます。まずは「生活上の困りごと」と「痛み」「不安」「活動量」を聴取し、必要なら他指標(痛み、歩行、活動量)とセットで解釈します。
次の一手(運用を整えて、再評価を強くする)
LEFS は「測る」だけでなく、条件を固定して比較できる状態にして初めて価値が出ます。まずは運用の型を小さく作って、説明と再評価のコストを下げましょう。
次にやることは、①想起期間と再評価間隔の固定、②欠損対応の統一、③合計点だけ保存しない、の 3 点です。ここが揃うと「伸びない/読めない」が一気に減ります。
- 運用を整える:想起期間/欠損の扱い/再評価間隔をチームで固定する
- 共有の型を作る:合計点+困りごと上位(生活・仕事)をセットで残す
- 環境の詰まりも点検:教育体制や記録文化の抜け漏れ確認に 無料のチェックシートを見る
続けて読む:評価ハブ
評価の全体像と、関連スケールの使い分けをまとめています。評価ハブへ
迷ったとき:PT キャリアガイド
教育体制や働き方の選択肢まで含めて整理できます。PT キャリアガイドへ
参考文献
- Binkley JM, Stratford PW, Lott SA, Riddle DL. The Lower Extremity Functional Scale (LEFS): scale development, measurement properties, and clinical application. Phys Ther. 1999;79(4):371–383. doi: 10.1093/ptj/79.4.371
- Mehta SP, Fulton A, Quach C, Thistle M, Toledo C, Evans NA. Measurement properties of the Lower Extremity Functional Scale: a systematic review. J Orthop Sports Phys Ther. 2016;46(3):200–216. doi: 10.2519/jospt.2016.6165
- 中丸 宏二. 下肢疾患患者における日本語版 Lower Extremity Functional Scale の計量心理学的特性. 理学療法科学( J-STAGE ). 2013. J-STAGE
- 中丸 宏二. 下肢疾患外来患者における日本語版 LEFS の信頼性・妥当性・反応性. 理学療法科学( J-STAGE PDF ). 2014. PDF
- Shirley Ryan AbilityLab. Lower Extremity Functional Scale (LEFS). SRALab
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下