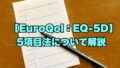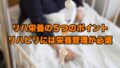摂食嚥下障害のスクリーニング検査とは?(妥当性と “使い分け” の結論)
摂食嚥下障害のスクリーニング検査は、「誤嚥の疑いを短時間で拾い上げ、次の一手(食形態調整/訓練/ ST 相談/ VE・ VF などの精査)につなぐ」ためのベッドサイド評価です。ポイントは “1 つの検査で確定させない” こと。妥当性(感度・特異度)を理解しつつ、患者背景(意識、呼吸、口腔環境、協力度)に合わせて段階的に選ぶと、事故と迷いが減ります。
本記事では、 RSST / MWST /水飲みテスト( WST 系)/ EAT-10 /(補助的に) GUSS / V-VST を、目的・リスク・妥当性の考え方で整理します。まずは「やってよいか」「どこで止めるか」「次に何へつなぐか」を決められる状態を目標にします。
妥当性(感度・特異度)を “現場の判断” に落とすコツ
妥当性は、ざっくり言うと「拾いやすさ(感度)」と「間違いにくさ(特異度)」です。感度が高いほど “見逃しにくい” 一方、陽性が増えやすく(過剰に止めてしまうこともある)、特異度が高いほど “陽性なら本当に怪しい” 反面、陰性で安心しすぎると見逃しが起こり得ます。
嚥下スクリーニングでは、検査単体の数値よりも「前提条件(姿勢・一口量・指示理解)を揃えたか」「危険サインが出た瞬間に止められたか」「陽性後に精査へつなげたか」が実務上の再現性を左右します。数字は “比較の物差し” として持ちつつ、運用はフローで固定すると安定します。
最短 5 分フロー|どれから始めて、どこで止める?
- 実施前チェック:意識・呼吸(呼吸数、努力呼吸、 SpO2 )、咳嗽力、口腔乾燥、姿勢保持、指示理解。
- まず “安全側” のスクリーニング:湿性嗄声、唾液処理、随意咳、必要なら RSST で嚥下惹起と連続性を確認。
- 液体の安全域を段階確認: MWST(少量)→(条件が良ければ) WST 系へ。所見が出たら無理に反復しない。
- 主観症状の整理: EAT-10 は “点数” より “推移” が武器。説明条件を揃えて再評価に使う。
- 陽性なら次:食形態調整・姿勢/代償手技・ ST 相談。必要に応じて VE / VF へ。
使い分け早見表|目的・リスク・次アクション
※表は横にスクロールできます。
| 検査 | 主な目的 | 強み | 限界/注意 | 陽性時の次 |
|---|---|---|---|---|
| RSST | 嚥下惹起と連続性(唾液処理)の確認 | 超低侵襲・短時間。水を使わず開始しやすい | 口腔乾燥・理解度の影響。誤嚥の有無は確定できない | MWST へ進めるか、 ST 相談/精査へ |
| MWST( 3 mL ) | 少量液体の安全性(むせ・湿性嗄声・呼吸変化) | 段階づけしやすい。 “止めどころ” を作れる | silent aspiration を拾い切れない可能性 | 食形態・姿勢調整、必要なら VE / VF |
| WST 系( 30 mL/ 3 oz 等) | 連続嚥下の耐性とリスク抽出 | 負荷が高く、陽性が出やすい場面がある | 高リスク例には不適。実施条件の厳格化が必要 | 中止→精査( VE / VF )または ST 評価へ |
| EAT-10 | 自覚症状の定量化(経時変化の把握) | 外来・在宅で追いやすい。 “変化” が見える | 認知・理解の影響。項目の丸写しは避ける | 客観評価(ベッドサイド)と組み合わせる |
| GUSS | 脳卒中など急性期での段階的スクリーニング | 多段階で食形態へ落とし込みやすい | 運用手順が必要。施設で統一しないとブレる | 推奨食形態の設定→必要なら精査 |
| V-VST | 量×粘度で安全性/効率を系統的に確認 | “どの粘度なら安全か” を決めやすい | 準備(粘度調整)と観察スキルが要る | 粘度・一口量の処方→必要なら VF へ |
各検査の実施ポイント(要点のみ)
RSST(反復唾液嚥下テスト)
説明は短く「今から 30 秒で唾を何回飲み込めるか」を 1 文で統一します。喉頭挙上を触知し、回数だけでなく “湿性嗄声・呼吸の乱れ・途中で止まる” をセットで記録します。口腔乾燥が強いときは、口腔環境を整えた上での再試行や、別手段(観察中心)へ切り替えます。関連:RSST 評価方法( 30 秒スクリーニング)
MWST(改訂水飲みテスト:少量)
体位(座位・頸部角度)と一口量を固定し、嚥下直後〜後嚥下の “声・呼吸・ SpO2 ” を観察します。嚥下誘発が遅い人は待機時間を十分に取り、焦って次の指示へ移らないことが事故予防になります。所見が出たら同条件での反復は避け、段階を戻すか中止して次へつなぎます。
水飲みテスト( WST 系:連続嚥下)
一気飲みを強要せず、少量→連続へ段階化して耐性を確認します。むせの有無だけで判断せず、飲水後の再呼吸(息が戻るか、呼吸が乱れるか)と湿性嗄声の出現を必ず記録します。実施できない背景(意識・呼吸不安定・姿勢保持困難)がある場合は “やらない” 判断が正解です。
EAT-10(自覚症状のスクリーニング)
EAT-10 は、主観症状を点数化して “推移” を追えるのが強みです。初回評価の点数だけで結論づけず、「いつ・どの場面で・どの程度困るか」を具体化し、客観所見(声・呼吸・むせ・体重変化など)と合わせます。再評価する場合は、説明・タイミング・支援の有無を揃えて比較します。
安全配慮・中止目安(ベッドサイド)
※表は横にスクロールできます。
| 危険サイン | その場の対応 | 次の一手 | 記録ポイント |
|---|---|---|---|
| 強いむせ/咳が止まらない | 直ちに中止、呼吸が落ち着くまで待機 | 姿勢・食形態の再検討、 ST 相談 | 一口量、体位、出現タイミング(嚥下前後) |
| 湿性嗄声の出現・増悪 | 中止、発声・咳払いで変化を確認 | 精査( VE / VF )の検討 | 声質の変化、咳払い後の改善有無 |
| 呼吸苦/努力呼吸/呼吸数増加 | 中止、安静、必要に応じて医療者へ共有 | 呼吸状態の安定化が優先 | 呼吸数、 SpO2 、チアノーゼの有無 |
| SpO2 の低下(例: 3% 以上など) | 中止、酸素化と呼吸を優先 | 他所見と合わせて解釈し精査へ | ベースライン、低下量、回復までの時間 |
| 意識低下・指示理解不良 | 無理に実施しない | 観察中心+チームで評価方針を決める | どの指示が困難だったか |
現場の詰まりどころ|よくある失敗と対策
嚥下スクリーニングで多いのは「検査の当たり外れ」ではなく、前提条件のブレです。下の “失敗パターン” を潰すだけで、記録の再現性が上がり、チーム内の意思決定が速くなります。
※表は横にスクロールできます。
| よくある失敗 | 起こる理由 | 対策 | 記録の型 |
|---|---|---|---|
| “むせ” だけで陰性・陽性を決める | silent aspiration を想定していない | 声・呼吸・ SpO2 ・再呼吸をセット観察 | 嚥下直後〜後嚥下 10 秒の変化を記載 |
| 体位・一口量が毎回違う | 手順が固定されていない | 座位角度/頸部角度/ 3 mL 固定など “条件” を先に書く | 条件→所見→判断の順で記録 |
| 陽性でも次が決まらず止まる | “つなぎ先” が曖昧 | 陽性=食形態調整/ ST 相談/精査のいずれかを必ず選ぶ | 「次アクション」欄を作る |
| EAT-10 を単発点で評価する | 再評価条件が揃っていない | 説明・タイミング・支援の有無を揃えて “推移” を見る | 評価条件(誰が・いつ・どう)を残す |
嚥下スクリーニング記録シート(最小セット)
チーム共有を前提に「条件→所見→判断→次」を 1 枚で残せる形式にします(項目の丸写しはせず、運用に必要な枠だけ用意します)。
※表は横にスクロールできます。
| 日付 | 場面 | 体位/頸部 | 事前チェック(意識・呼吸・口腔) | 実施検査 | 所見(声・呼吸・むせ・ SpO2 ) | 判断 | 次アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. 1 つだけ選ぶなら、どの検査から始めるのが安全ですか?
A. 「まず水を使わずに情報が取れる」観察と RSST(可能なら)から入るのが安全側です。そのうえで、条件が整えば MWST(少量)で液体の安全域を確認し、必要があれば段階的に負荷を上げます。実施可否(意識・呼吸・姿勢)が怪しいときは “やらない判断” が最優先です。
Q2. 陰性なら “誤嚥なし” と考えてよいですか?
A. いいえ。スクリーニングは確定診断ではなく、 silent aspiration を拾い切れないことがあります。陰性でも「湿性嗄声」「反復する微熱」「食後の呼吸苦」「痰の増加」「栄養・体重低下」などがあれば、精査( VE / VF )を含めて再検討します。
Q3. EAT-10 は点数が高いほど危険ですか?
A. 点数は症状負荷の目安になりますが、 “その人の変化(推移)” が特に重要です。再評価するなら、評価条件(説明・タイミング・支援)を揃え、客観所見(声・呼吸・むせ・食事形態)とセットで解釈します。
Q4. 陽性が出たら、次は何を優先すべきですか?
A. ①その場の安全確保(中止・呼吸の安定)→ ②食形態・姿勢・一口量の調整 → ③ ST 相談(必要なら VE / VF )の順に “つなぎ先” を決めます。陽性のまま曖昧に継続するのが最も危険です。
おわりに
嚥下スクリーニングは、「実施前チェック → 低侵襲から段階的に確認 → 危険サインで中止 → 次アクションを固定 → 再評価」というリズムで回すと、現場の迷いと事故が減ります。評価と記録の型を整えたうえで、面談準備チェックと職場評価シートも合わせて揃えておくと、臨床の意思決定がさらにスムーズです:/mynavi-medical/#download
参考文献
- Oguchi K, Saitoh E, Mizuno M, et al. The Repetitive Saliva Swallowing Test (RSST) as a Screening Test of Functional Dysphagia. Jpn J Rehabil Med. 2000;37(6):383-388. DOI: 10.2325/jjrm.37.383
- Belafsky PC, Mouadeb DA, Rees CJ, et al. Validity and reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10). Ann Otol Rhinol Laryngol. 2008;117(12):919-924. DOI: 10.1177/000348940811701210 / PubMed: 19140539
- Trapl M, Enderle P, Nowotny M, et al. Dysphagia bedside screening for acute-stroke patients: the Gugging Swallowing Screen. Stroke. 2007;38(11):2948-2952. DOI: 10.1161/STROKEAHA.107.483933 / PubMed: 17885261
- Clavé P, Arreola V, Romea M, et al. Accuracy of the volume-viscosity swallow test for clinical screening of oropharyngeal dysphagia and aspiration. Clin Nutr. 2008;27(6):806-815. DOI: 10.1016/j.clnu.2008.06.011 / PubMed: 18789561
- Oguchi N, Yamamoto S, Terashima S, et al. The modified water swallowing test score is the best predictor of postoperative pneumonia following extubation in cardiovascular surgery: A retrospective cohort study. Medicine (Baltimore). 2021;100:e24478. DOI: 10.1097/MD.0000000000024478 / PubMed: 33530263
- Lee B, et al. A Pilot Study of a Modified Swallowing Screening Tool for Bedridden Older Adults. (GUSS を参照した運用の背景). 2024. PubMed Central: PMC12328495
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下