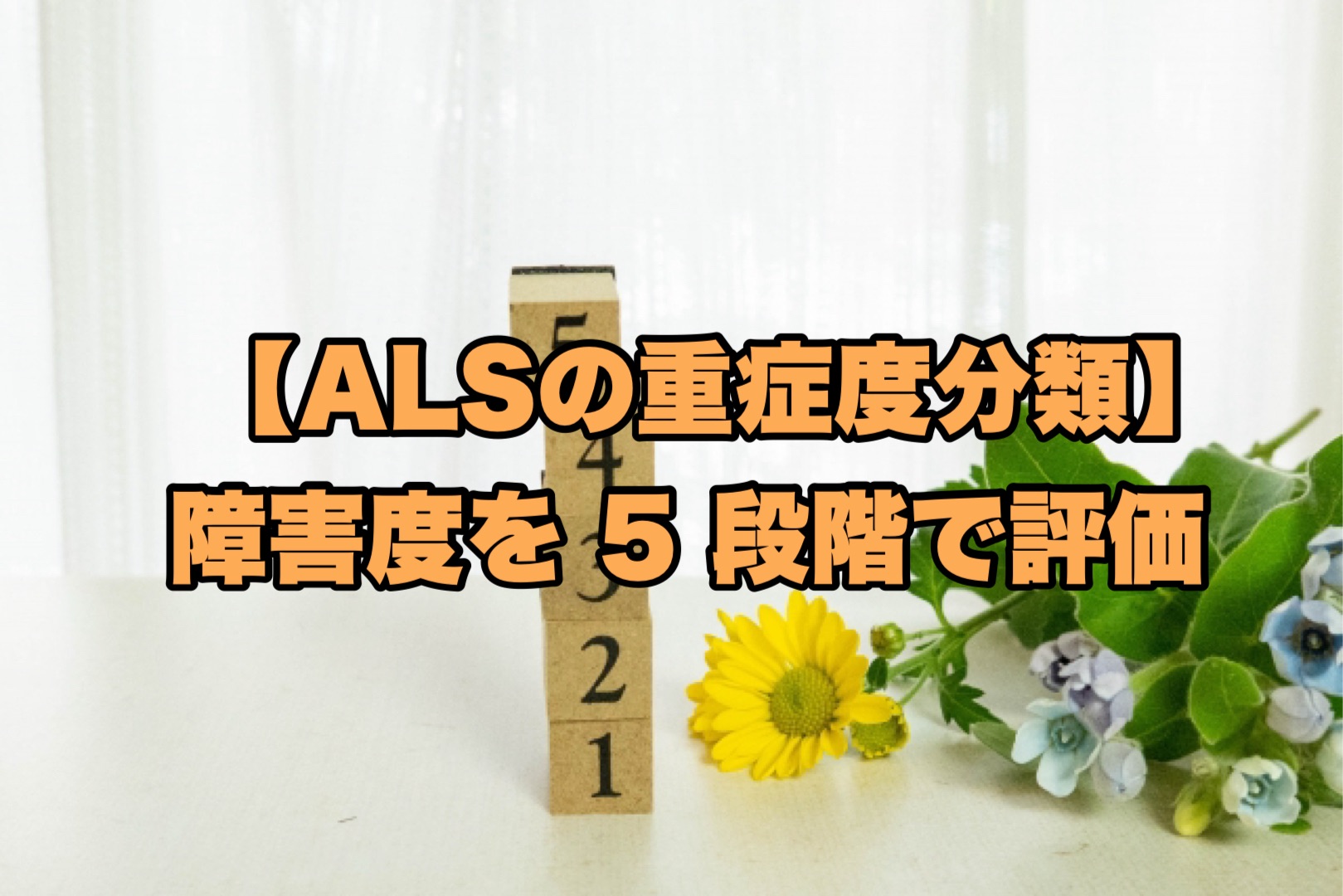ALS 重症度分類( 1〜5 )とは?(この記事の結論)
ALS は “段階を言語化” できると、準備が前倒しになります。 臨床の整理に役立つロードマップを見る ※進行性疾患ほど「評価→共有→先回り」の “型” が効きます。
ALS 重症度分類( 1〜5 )は、指定難病(医療費助成)の判定で用いられる公的な段階分類です。数字が大きいほど重くなり、治療中は直近 6 か月で最も悪い状態を医師が判断して評価します(自治体の運用も確認)。
このページでは、分類の定義の要点を早見表で整理し、リハ・ケアで何を先回りして準備するかまで落とし込みます。評価全体(呼吸・嚥下・ AAC ・姿勢)をまとめて把握したい場合は、ALS リハの評価まとめも合わせて使ってください。
公的な重症度分類(指定難病・医療費助成)
重症度は 1 → 5 の順で重くなります。助成の対象は原則「重症度 2 以上」とされますが、軽症高額や高額かつ長期など、例外的に対象となる枠もあります(自治体や要綱で確認)。
臨床では、定義を “暗記” するより、各段階で増えやすいイベント(呼吸・嚥下・意思伝達・介助量)を見越して、準備を前倒しするのがコツです。
| 重症度 | 定義(要点) | リハ・ケアの着眼点(例) | 先回りの準備(例) |
|---|---|---|---|
| 1 | 家事・就労はおおむね可能 | 省エネ動作/安全な運動、 ADL/IADL の “崩れ方” を把握 | 呼吸・嚥下のスクリーニング導入、教育(疲労・転倒・誤嚥) |
| 2 | 家事・就労は困難だが、日常生活はおおむね自立 | 自助具・装具、姿勢・体位管理、摂食姿勢の最適化 | 福祉用具の “試す→合う物に絞る”、家族へ介助の型を共有 |
| 3 | 食事・排泄・移動のいずれか 1 つ以上ができず、介助を要する | 移乗・体位変換の省力化、座位保持、介助量の急増に備える | 車いす/座位保持具、ベッド周り動線、介助者負担の評価 |
| 4 | 呼吸困難・喀痰喀出困難、または嚥下障害がある | 呼吸・嚥下イベントが増えやすい “要注意期” | NIV/機械排痰の検討、吸引体制、食形態・摂食姿勢の見直し |
| 5 | 気管切開、人工呼吸器、非経口的栄養(経管/中心静脈)を使用 | 褥瘡・拘縮・意思伝達・家族支援が中核 | 呼吸ケア体制の標準化、意思伝達の二重化、在宅支援の再設計 |
臨床での使い方(進行予測と “先回り” のコツ)
公的重症度分類は「助成の判定」のための枠組みですが、リハの現場では“次に起こりやすい変化” を先読みする地図として使えます。とくに 3 → 4 期の移行では、呼吸・嚥下のイベントが増えやすく、介助量も一気に変わることがあります。
実務では、①重症度(段階) ②困っている場面(生活) ③次アクション(準備)を 1 セットで書くと、チーム共有が早くなります。具体的な評価の回し方は、呼吸は ALS の呼吸評価、嚥下は ALS の嚥下スクリーニングも参照してください。
研究・評価で用いる病期モデル( King’s / MiToS )
公的重症度分類は “助成判定” に寄った段階分類で、研究や経過把握では、別の病期モデルが用いられます。代表的なのがKing’sとMiToSです。目的が違うため、同じ患者さんでも “見え方” が変わります。
現場では、ALSFRS-R の推移(点数の変化)と合わせて、病期モデルを “補助線” にすると、説明の筋が通りやすくなります。
| モデル | ステージ構成 | 基準の要点 | 臨床での読み方(例) |
|---|---|---|---|
| King’s | 1 → 4A/4B | 罹患領域の広がり+ 4A(経腸栄養)/ 4B(呼吸補助) | 部位進展と “栄養・呼吸のマイルストーン” を把握 |
| MiToS | 0 → 4 | ALSFRS-R の 4 ドメインで “機能喪失数” を数える | 中期(数か月〜)のイベント予測の補助線 |
ALSFRS-R と重症度分類の違い
ALSFRS-R は 12 項目( 0〜48 点)の機能評価スケールで、重症度分類( 1〜5 )の “段階そのもの” ではありません。ALSFRS-R は経時変化を追うのに強く、重症度分類は助成判定に使われる、という役割分担です。
ALSFRS-R を実務でどう回すか( 5 分運用の型/点数の読み方/よくある失敗)は、ALSFRS-R の評価まとめで整理しています。
申請・運用の実務メモ(見落としやすい点)
実務で詰まりやすいのは、①治療中の評価条件(直近 6 か月で最も悪い状態) ②例外枠(軽症高額など) ③更新時期と書類の “抜け” です。ここは施設内で共有メモを作っておくと、手戻りが減ります。
最終的な判定は医師の医学的判断に基づきます。現場側は、観察(生活・呼吸・嚥下・介助量)を “同じ言葉” で届けるのが役割です。
| ポイント | 要点 | 現場の動き(例) | メモの残し方 |
|---|---|---|---|
| 対象の目安 | 原則 重症度 2 以上(例外枠あり) | 自治体の要件を確認し、説明資料を一本化 | 自治体名/更新時期/必要書類を 1 行で |
| 治療中の評価 | 直近 6 か月で最も悪い状態 | 状態が揺れる時期ほど “最悪値” の根拠を整理 | いつ/どの場面で悪化したかを簡潔に |
| 段階移行 | 3 → 4 期でイベントが増えやすい | 呼吸・嚥下・介助体制を前倒し | 夜間・食事時・移乗時の変化を記録 |
ダウンロード( A4 ・印刷可)
ベッドサイドやカンファで使いやすいよう、 A4 で印刷できる “早見” と “ログ” を用意しています。運用は、早見で全体像 → ログで判定根拠と次アクションの順にするとブレにくいです。
必要に応じて、呼吸・嚥下・意思伝達は個別に掘り下げていくと、評価と準備がつながります(下の「次に読む」も参照)。
次に読む( ALS の評価を “分解” して迷わない)
重症度分類は “段階” を揃える道具です。次は、臨床で詰まりやすい領域(呼吸・嚥下・意思伝達・姿勢)を分解して、評価と準備を具体化します。
- ALS の呼吸評価: SpO2 だけにしない観察ポイント
- ALS の嚥下スクリーニング:誤嚥リスクを早めに拾う
- ALS の意思伝達( AAC ):早期から “二重化” を作る
- ALS のシーティング/ポジショニング:呼吸と疲労を守る
よくある質問(ミニ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
治療中の重症度は、いつの状態で判定しますか?
治療開始後は、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態で、直近 6 か月で最も悪い状態を医師が判断して評価します。現場側は、悪化した “場面” と “影響(生活・介助・呼吸・嚥下)” を簡潔に整理して届けると判定がスムーズです。
重症度 2 でも助成の対象になりますか?
原則として、重症度分類で 2 以上が対象とされています。加えて、軽症でも医療費負担が大きい場合など、例外枠が設定されることがあります。自治体の要件や更新時期は必ず確認してください。
重症度 3 から 4 に上がる前に、何を準備しておくべきですか?
臨床では、 3 → 4 期で呼吸・嚥下イベントが増えやすいので、呼吸(排痰・ NIV の検討)と嚥下(食形態・姿勢・栄養経路)、そして吸引体制を前倒しで整えるのが定石です。準備の優先順位を付けるために、呼吸・嚥下の評価記事も併用してください。
公的重症度分類と ALSFRS-R は、どちらを優先して見ますか?
目的が違います。公的重症度分類は “助成判定” の枠組みで、 ALSFRS-R は “機能の変化” を追うスケールです。現場では、重症度(段階)で共有 → ALSFRS-R(推移)で変化を追うと、説明と意思決定が噛み合いやすくなります。
参考文献
- 難病情報センター. 筋萎縮性側索硬化症( ALS )(指定難病 2 ). 掲載ページ
- 日本神経学会(筋萎縮性側索硬化症診療ガイドライン作成委員会). 筋萎縮性側索硬化症( ALS )診療ガイドライン 2023. PDF
- Roche JC, Rojas-Garcia R, Scott KM, et al. A proposed staging system for amyotrophic lateral sclerosis. Brain. 2012;135(3):847-852. DOI:10.1093/brain/awr351 / PubMed
- Chiò A, Hammond ER, Mora G, et al. Development and evaluation of a clinical staging system for amyotrophic lateral sclerosis. Ann Neurol. 2015;77(3):384-394. DOI:10.1002/ana.24326 / PubMed
- Cedarbaum JM, Stambler N, Malta E, et al. The ALSFRS-R: a revised ALS functional rating scale that incorporates assessments of respiratory function. J Neurol Sci. 1999;169(1-2):13-21. DOI:10.1016/S0022-510X(99)00210-5 / PubMed
- Tramacere I, Dalla Bella E, Chiò A, et al. The MITOS system predicts long-term survival in amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015;86:1180-1185. DOI:10.1136/jnnp-2014-310176 / PubMed
- Urushitani M. The clinical practice guideline for the management of amyotrophic lateral sclerosis in Japan. Clin Neurol. 2024;64(4). J-STAGE
- ALS STATION. ALSFRS-R の概要とスコアリング(日本語). 解説ページ
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下
おわりに
ALS の重症度分類は、安全線の確認→段階の言語化→先回り準備→多職種共有→再評価のリズムに乗せると、説明も支援もブレにくくなります。面談準備の抜け漏れを減らしたいときは、印刷して使える面談準備チェックと職場評価シートを こちら(ダウンロード)にまとめています。