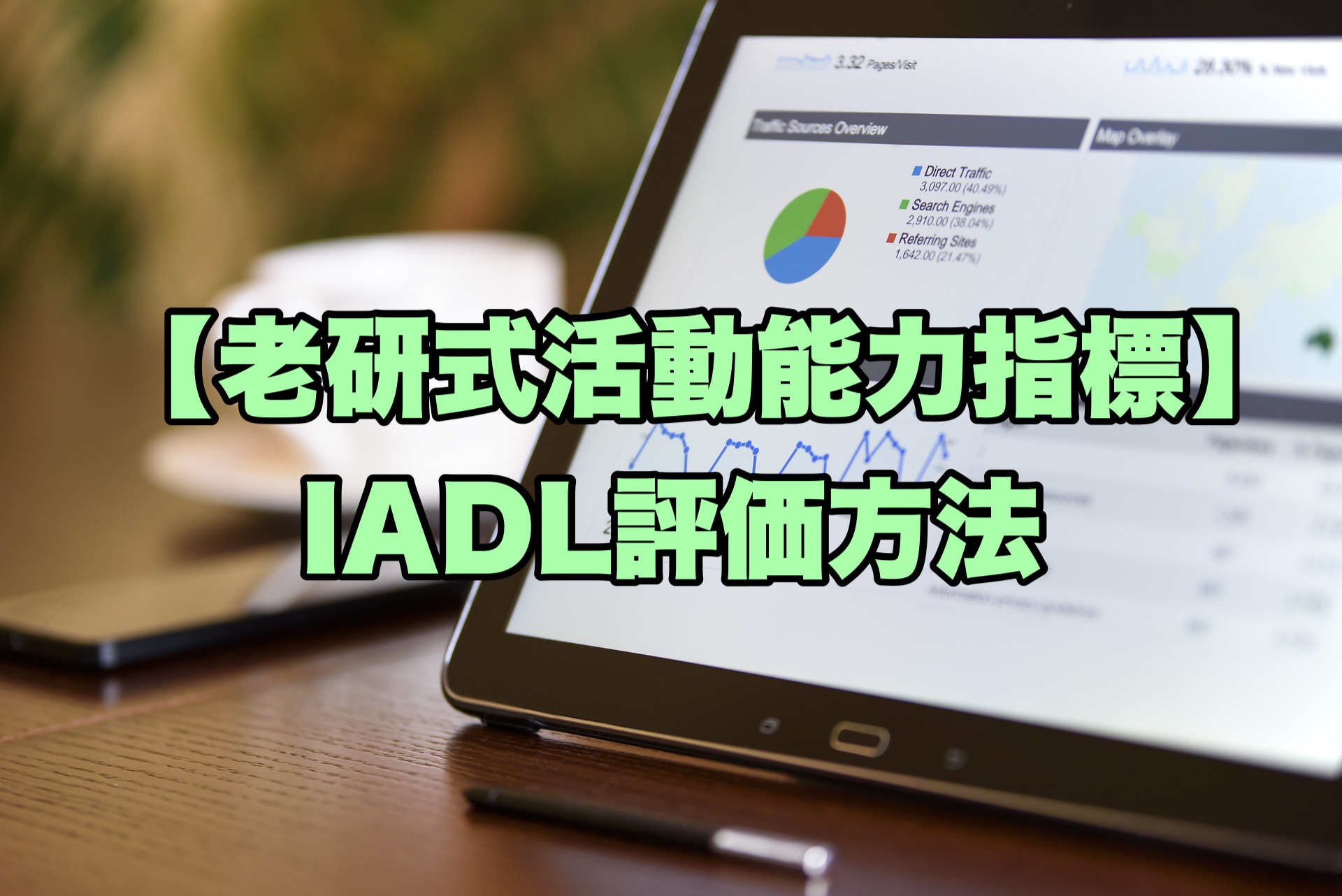老研式活動能力指標(TMIG-IC)の評価方法(やり方)|何を・何分で・どう採点する?
結論:老研式活動能力指標( TMIG-IC )は、高齢者の「高次生活機能」を IADL(手段的自立)/知的能動性/社会的役割の 3 領域・計 13 項目で 0/1 採点し、合計 0–13 点で全体像を把握するスクリーニングです。
所要は 自記 2–3 分(面接 5–10 分)が目安。評価のコツは、各設問を「できるか」ではなく 直近 1–2 週間の通常生活で “実際にやっているか”で判定し、支援条件(配食・送迎など)を短くメモして解釈のズレを防ぐことです。なお JST-IC(新・老研式:16 項目)とは別尺度であり、混同しないようにしてください。
5 分でできる:評価のやり方(結論だけ)
①説明(目的と判定期間)→ ②自記 or 面接 → ③ 0/1 採点 → ④サブスコア(IADL/知的能動性/社会的役割)→ ⑤共有(課題→対応→再評価)の順で進めると、記録が崩れにくいです。
評価のやり方(5 ステップ)
- 説明:「今の暮らしぶりを 13 の質問で確認します。普段どおりの生活で当てはまるなら ‘はい’ です。」
- 判定期間を統一:直近 1–2 週間の通常生活を基準にします(入院中は「入院前」か「退院後想定」かをチームで統一)。
- 自記 or 面接:本人自記が基本。視力・書字・理解が難しければ読み上げで面接し、誘導せず本人の表現をそのまま記録します。
- 採点:「はい=1/いいえ=0」。合計( 0–13 )に加えて サブスコア(IADL 0–5・知的能動性 0–4・社会的役割 0–4)を併記します。
- 共有:下位尺度ごとに 課題→対応案(代償/環境/教育)→担当→再評価時期を決め、申し送りの粒度をそろえます。
質問票の入手先(公式)
設問の確認と実施は、配布元が公開している質問票に沿って運用してください。
0/1 判定で迷いやすいポイント(早見表)
| 迷いどころ | よくあるズレ | そろえる基準(おすすめ) | 記録の一言例 |
|---|---|---|---|
| 「できる」vs「やっている」 | 能力はあるが、実際はやらない(配食・送迎・家族代行など) | 実施実態で判定し、代行の有無をコメント | 「配食利用のため調理は未実施(支援条件あり)」 |
| 支援ありでの実施 | 見守り/一部介助を “自立” と混同 | 施設ルールを 1 枚に統一(見守り・介助の扱い) | 「買物:家族同伴。会計は本人」 |
| 入院中の回答 | 病棟の生活で答えてしまう | 入院前か退院後想定かを冒頭で明示して統一 | 「入院前(直近 2 週)の生活で回答」 |
| 感覚・媒体の影響 | 難聴・視力低下で “やっていない” に見える | 補助具・媒体(拡大文字・音声等)を確認して解釈 | 「新聞は読まず、音声ニュースで情報収集」 |
| 社会的役割の頻度 | 「たまに」を “あり” として過大評価 | 頻度を具体化(週◯回・月◯回) | 「近所交流:月 1 回」 |
領域別:何を見ているかと採点の実務(要点)
TMIG-IC は 3 領域の “全体像” を短時間で捉える設計です。合計点だけで終わらせず、どの領域が落ちているかで次アクションを決めると実装に乗ります。
| 領域 | 代表テーマ | 1 点(はい)の目安 | 0 点(いいえ)の目安 | 評価のコツ |
|---|---|---|---|---|
| IADL(0–5) | 外出手段/買物/食事準備/支払/金銭管理 | 直近 1–2 週間の通常生活で自立実施が確認できる | 実施していない、または支援が必要で自立が担保されない | 実施実態で判定。支援(配食・送迎等)は短くメモ |
| 知的能動性(0–4) | 情報アクセス/学習/健康への関心/手続き | 継続的に取り組み、必要な情報にアクセスできる | ほとんど行動がない/機会がない | 媒体(紙/スマホ/音声)を確認し、代替手段も含めて解釈 |
| 社会的役割(0–4) | 交流/相談される/訪問・見舞い/役割 | 役割があり、交流が継続(頻度が具体化できる) | 交流が乏しい/役割が途絶 | 「週◯回」など頻度の具体化でブレを減らす |
| 合計(0–13) | 3 サブスコアの合算 | — | — | 合計よりサブスコアの組み合わせ+前回比を優先 |
結果の読み方と次アクション(領域別)
| 下位尺度 | 読み方 | 次アクション例 | 再評価の目安 |
|---|---|---|---|
| IADL(0–5) | 生活マネジメントの核。低下は要介護化リスクの早期サインになりやすい | 外出導線、買物手段、配食・送迎の検討、移動能力の底上げ | 退院前後、介入開始 2–4 週 |
| 知的能動性(0–4) | 情報アクセス・新規学習の力。遂行機能の “生活側” 指標 | 媒体調整(拡大・音声)、手順カード化、家族同席説明 | 環境調整後 2–4 週 |
| 社会的役割(0–4) | 交流と役割保持。フレイル予防と直結しやすい | 短時間参加から導入、役割の再設計(家族・地域)、外出機会づくり | 導入後 4–8 週 |
よくある失敗(現場で詰まるところ)
- 判定期間が人によって違う:入院後の生活と入院前の生活が混ざる → 冒頭で「どの生活で答えるか」を統一してから開始。
- “できる” を 1 点にしてしまう:実際は代行されている → 実施実態で判定し、支援条件を短くメモ。
- 社会的役割の “たまに” を過大評価:頻度が曖昧 → 週◯回/月◯回に具体化して点の一貫性を作る。
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q. 自記が難しいとき、面接で代替しても良いですか?
A. 可能です。読み上げで面接し、誘導せず本人の表現をそのまま記録します。入院中は「入院前」か「退院後想定」かの統一を先に行うと、回答のブレが減ります。
Q. 合計点だけ見れば良いですか?
A. 合計だけでなく、IADL/知的能動性/社会的役割のどこが落ちているか(組み合わせ)で次アクションを決めると実装に乗ります。変化を追うなら前回比(経時変化)も併記します。
Q. TMIG-IC と JST-IC(新・老研式)は同じですか?
A. 別尺度です。TMIG-IC は 13 項目で 3 領域の全体像を捉えます。JST-IC は別枠の指標なので、名称と項目数を確認して混同を避けてください。
参考文献
- Koyano W, Shibata H, Nakazato K, Haga H, Suyama Y. Measurement of competence: reliability and validity of the TMIG Index of Competence. Arch Gerontol Geriatr. 1991;13(2):103–116. DOI
- Koyano W, et al. TMIG Index of Competence(13 項目・分布). Jpn J Public Health. 1993. PubMed
- Tomioka K, et al. Social participation and IADL using the 5-item TMIG-IC subscale. PLoS One. 2016;11(10):e0165103. PMC
- Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist. 1969;9(3):179–186. PubMed
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下