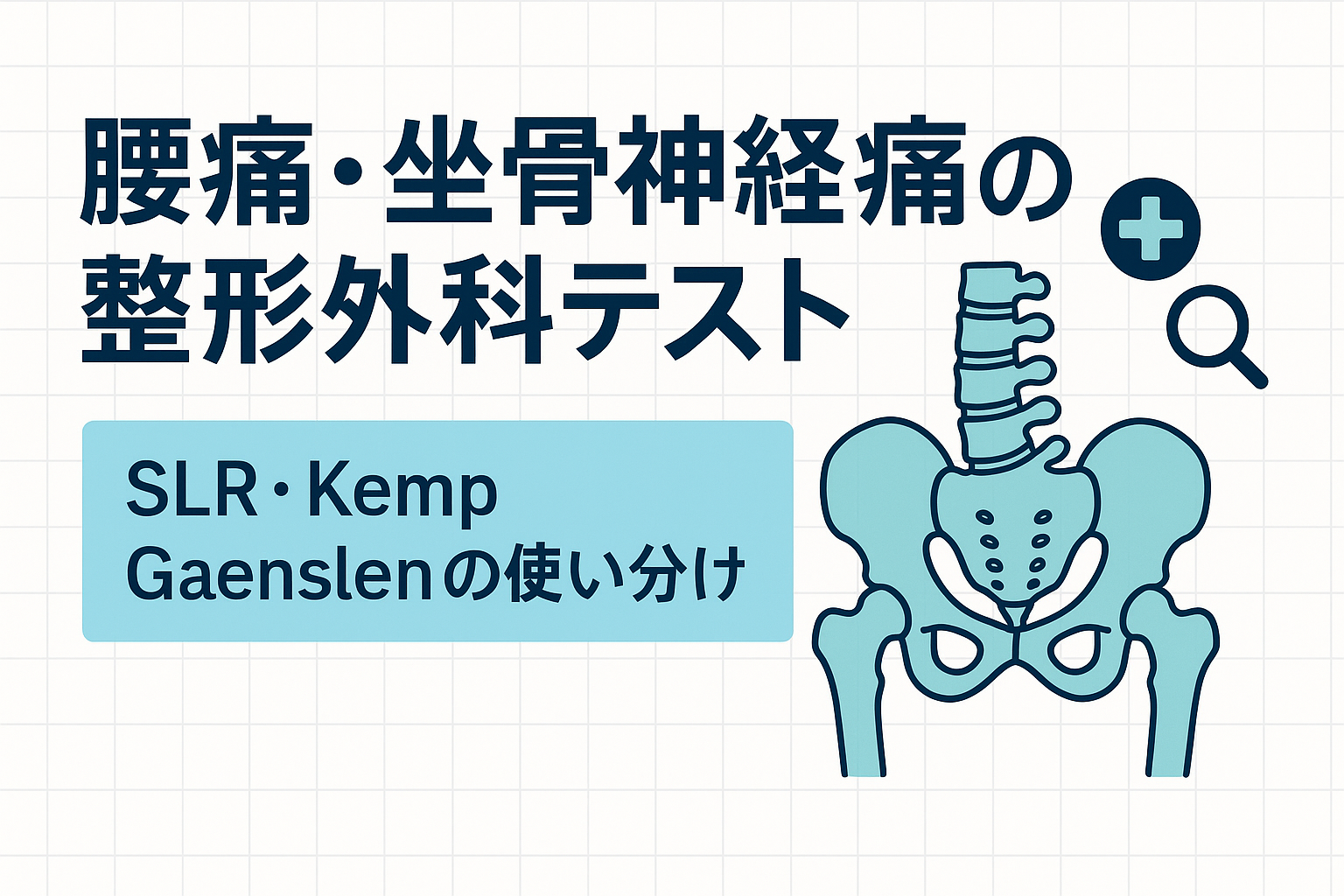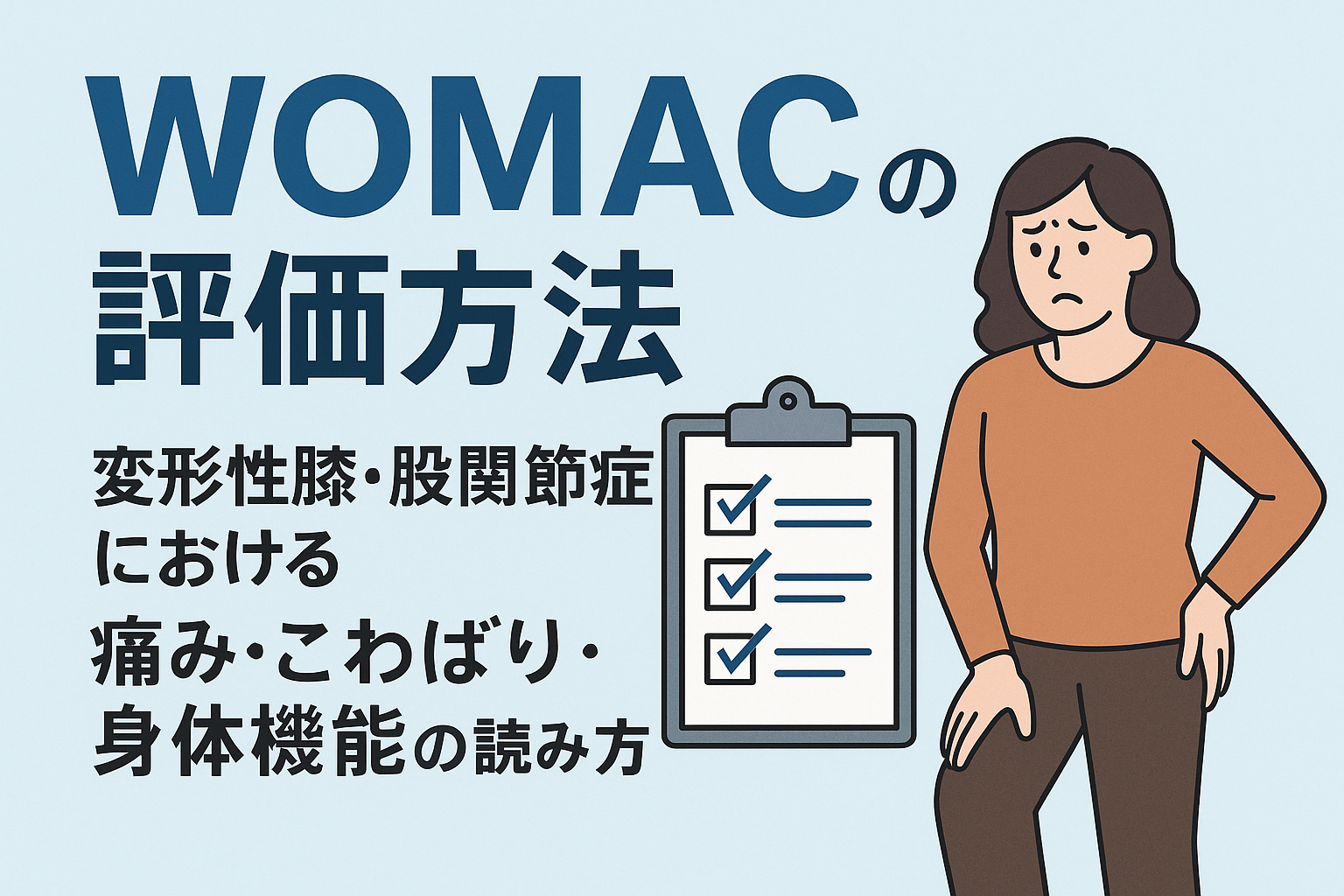腰椎・骨盤まわりの整形外科テストとは
腰痛や坐骨神経痛の評価では、画像検査や触診に加えて、「どの整形外科テストをどう組み合わせるか」が悩みどころです。ただし、テスト単体で診断が「確定」するわけではなく、あくまで 病態仮説を絞り込むための道具 です。本記事では、日常的によく使うテストを「症状パターン別」に整理し、理学療法での実務的な使い方に焦点を当てて解説します。
レッドフラッグ(骨折・感染・腫瘍・急性の神経障害)を見逃さないことを前提に、腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄症・仙腸関節障害・骨盤不安定性などを段階的に考えられる視点をまとめました。痛みの強さだけでなく、動作や生活への影響を把握するには、疼痛スケールや歩行・バランス評価などの併用も意識しましょう。
下肢伸展で悪化する坐骨神経痛パターンをみるテスト
片側の殿部〜大腿後面に放散する痛みやしびれを訴える症例では、まず 下肢伸展で症状がどう変化するか を押さえると、腰椎椎間板ヘルニアや神経根障害のイメージがつきやすくなります。その際、「何度で」「どの部位に」「どのような痛み・しびれが出たか」を具体的に記録することが重要です。
代表的なテストには、下肢伸展挙上テスト(SLR テスト)、Bragard 徴候、Lasègue 徴候、Bowstring 徴候、Flip テスト、大腿神経伸展テスト(FNS テスト)などがあります。個々の名前を単独で覚えるのではなく、「仰臥位でのパッシブ伸展」「座位での神経伸張」「大腿神経優位」など、狙っている神経伸張パターンごとにグループ化すると整理しやすくなります。
| テスト名 | 主な肢位・動き | 想定する主な病態 |
|---|---|---|
| SLR テスト | 仰臥位で下肢を伸展挙上 | L4–S1 神経根障害、椎間板ヘルニアなど |
| Bragard 徴候 | SLR で症状が出た角度から足関節背屈 | 坐骨神経への伸張刺激による症状増悪の確認 |
| Lasègue 徴候 | 殿部〜大腿後面の放散痛を再現 | 坐骨神経痛の再現性の確認 |
| Bowstring 徴候 | 膝窩部の神経を押圧 | 神経伸張での疼痛再現 |
| Flip テスト | 座位での膝伸展(SLR 相当) | 仰臥位困難時の代替評価 |
| FNS テスト | 腹臥位で膝屈曲+股関節伸展 | L2–4 大腿神経根障害 |
実施時のポイントは、痛みが出る角度・部位・性状 を丁寧に確認することです。10〜30 度の早期から殿部より近位の強い腰痛が出るのか、30〜70 度で下腿遠位にしびれが出るのかで、同じ「陽性」でも背景となる病態が異なります。また、恐怖回避が強い症例では、痛みが出る前から防御的に股関節屈曲や骨盤後傾が入りやすく、偽陽性が増える点にも注意が必要です。
禁忌・注意点として、明らかな骨粗鬆症で急な体動が危険な症例、急性椎体骨折が疑われる症例、安静時も痛みが増悪し続ける場合などがあります。そのような状況では、テストを「やり切る」ことよりも、「痛みを増悪させない範囲での観察」にとどめ、画像検査や主治医への報告を優先します。
体幹伸展で増悪する腰痛をみるテスト
前屈よりも伸展や立位保持で腰痛が増悪するパターンでは、椎間関節障害や腰部脊柱管狭窄症の関与を想定します。ここでは、体幹伸展と回旋を組み合わせる Kemp テスト や、棘突起叩打テストなどを用いて、「どのレベルで」「どのような痛みが」誘発されるかを整理していきます。
Kemp テストで一側の腰痛と同側下肢への放散痛が再現される場合と、両側伸展で腰部中央の鈍い痛みが増悪する場合とでは、同じ陽性所見でもニュアンスが異なります。さらに、棘突起叩打テストで局所の鋭い疼痛や異常な叩打痛がある場合には、椎体骨折や腫瘍などレッドフラッグの可能性も想起する必要があります。
理学療法の立場では、Kemp テストを「危ない動き」として一律に避けるのではなく、「どの方向・角度で症状がどう変化するか」を把握し、エクササイズや ADL 指導に反映させることが重要です。軽度の伸展で症状が軽減する症例では伸展系エクササイズが有効となることもあれば、伸展で悪化・屈曲で軽減する症例では、屈曲優位の姿勢戦略や座位中心の活動提案が優先されます。
一方で、安静時も増悪し続ける強い腰痛、夜間痛、原因不明の体重減少、発熱などが併存する場合には、運動療法よりも原因精査が優先されます。テストで痛みを「引き出す」前に、問診や既往歴からレッドフラッグをスクリーニングしておく習慣をつけましょう。
仙腸関節障害・骨盤不安定性をみるテスト
仙腸関節や骨盤帯の問題では、殿部〜鼠径部の鈍痛や「片側の腰の奥の痛み」として症状が出てくることが多く、典型的な神経放散痛とは異なるため、股関節・腰椎由来の痛みと混同しやすい点が難所です。その結果、テスト所見をどう解釈するか迷う場面が少なくありません。
代表的なテストには、Gaenslen テスト、骨盤不安定性テスト(Pelvic Rock Test)、FADIRF テストなどがあります。いずれも、仙腸関節への剪断ストレスや圧縮ストレス、股関節屈曲・内転・内旋でのインピンジメントを利用して、痛みが再現される部位とパターンを確認するテストです。
ここでのポイントは、単一のテスト結果のみで「仙腸関節障害」と決めつけない ことです。複数のテストで同じ側の仙腸関節近傍に痛みが再現されるか、股関節可動域制限やクリック感はないか、腰椎伸展で症状がどう変化するかなど、複数の所見を組み合わせて判断します。妊娠後期や産後、外傷後の症例では骨盤帯の靱帯性支持が一時的に低下しており、同じストレスでも痛みの出方が変わりやすい点にも留意が必要です。
リハビリテーションへの展開としては、痛みが出やすい肢位や荷重方向を把握したうえで、荷重位での骨盤安定化トレーニング や、起立・歩行動作の指導に結びつけることが重要です。とくに片脚立位や階段昇降で痛みが強い場合には、股関節外転筋・殿筋群の機能と体幹の側方安定性を評価し、必要に応じて上肢支持や段差の高さ調整などを組み合わせていきます。
末梢循環・レッドフラッグを疑うときの補助テスト
腰痛や下肢痛を訴える患者の中には、運動器ではなく末梢動脈疾患や血栓症など、循環器・血管系の問題が背景にあるケースも含まれます。安静時痛や夜間痛、下肢の冷感・蒼白、間欠性跛行などが目立つ場合には、整形外科テストだけに頼らず、循環評価を視野に入れる必要があります。
Buerger テストは、下肢挙上時の皮膚色の変化や挙上角度による循環不全のサインをみるテストです。理学療法士が比較的簡便に実施できますが、「異常があるからすぐ運動療法で改善を図る」というよりは、末梢循環の問題を疑い、主治医に共有・相談するためのスクリーニング として位置づける方が安全です。
深部静脈血栓症を疑うホーマンズ徴候などは、評価そのものがリスクとなる場合もあり、慎重な判断が求められます。強いふくらはぎ痛や腫脹、発赤、呼吸苦を伴う場合には、テストで疼痛を「引き出す」前に、医師への即時報告と安静保持を優先します。整形外科テストで循環器系の問題まで確定しようとせず、「危険なサインを見逃さないこと」を第一に考えましょう。
評価で終わらせないためのリハ介入へのつなぎ方
整形外科テストは、「陽性/陰性」を記録して終わりではなく、その結果を 運動療法・動作指導・生活指導の設計にどう活用するか が本番です。たとえば SLR テストで早期から強い下肢放散痛が出る症例では、神経伸張ストレスを避けたポジショニングや、体幹・骨盤の安定化を優先した段階的アプローチが必要になります。
一方、Kemp テストで体幹伸展・回旋方向の局所痛が中心で下肢症状が乏しい症例では、椎間関節由来の痛みを念頭に、伸展方向の負荷コントロールや姿勢調整が有効な場合があります。Gaenslen テストなどで仙腸関節近傍の痛みが再現される症例では、片脚荷重動作や歩行時の骨盤制御に着目し、日常生活動作を通して負担軽減を図っていきます。
再評価のタイミングは、「すべてのテストを毎回繰り返す」のではなく、治療ターゲットとなっている病態に関連するテストを数個に絞って追いかける と、患者の負担が少なく経時変化も追いやすくなります。主観的な痛みや機能の評価には NRS・VAS・PDAS などの疼痛評価スケールや、歩行・バランスの評価を組み合わせて、記録と共有の質を高めていきましょう。
配布物・チェックシートの活用(働き方の整理にも)
整形外科テストの使い分けを学びながら、自分の判断プロセスを言語化しておくと、症例検討やカンファレンスでの共有がぐっとやりやすくなります。同時に、「どのような職場環境なら学び続けやすいか」を整理しておくことも、長期的な臨床力の維持には欠かせません。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に、見学や情報収集中から使える面談準備チェック(A4・5 分)と職場評価シート(A4)を無料公開しています。印刷してそのまま使えます。ダウンロードページを見る。
おわりに
腰椎・骨盤まわりの整形外科テストは、「どの病態を想定しているのか」「陽性・陰性をどう運動療法に落とし込むのか」を意識して使うことで、評価→介入→再評価のリズムが整ってきます。レッドフラッグを見逃さず、必要に応じて画像検査や専門医への紹介につなぎながら、リハビリテーションでできることを最大化していきましょう。
上で紹介した面談準備チェックと職場評価シートも活用しつつ、自分の学び方や働き方を定期的に振り返ることで、「整形外科テスト 腰痛」「整形外科テスト 坐骨神経痛」「仙腸関節障害・骨盤不安定性」といったテーマに強い臨床スキルとキャリア形成を並行して進めていける環境づくりを意識してみてください。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
SLR テストは何度まで挙上できれば「正常」と考えてよいですか?
一般的には 70 度前後まで痛みなく挙上できると「正常範囲」とされることが多いですが、年齢や柔軟性、職業歴などで大きく変わります。重要なのは角度そのものよりも、痛みが出る角度・部位・性状と、日常生活で困っている動作とのつながり を押さえることです。たとえば 50 度で下肢放散痛が出ても、座位や立位では症状がほとんど出ない場合と、数分の立位で強い症状が出る場合では、評価の意味合いが異なります。
整形外科テストがすべて陰性なら、運動器由来の痛みではないと考えてよいですか?
いいえ、すべて陰性でも運動器由来の痛みが否定できるわけではありません。テストはあくまで「その肢位・その負荷条件」での反応をみているだけであり、実際の日常生活動作や長時間負荷とは条件が異なります。テスト結果だけで完結させず、問診・動作分析・疼痛評価を組み合わせて総合的に判断することが大切です。
腰痛患者さんにどこまで整形外科テストを行ってよいか不安です。
まずはレッドフラッグ(骨折・感染・腫瘍・急性神経障害など)を問診と視診でチェックし、「少しでも危険な可能性があれば無理なストレスをかけない」という方針を徹底することが前提です。そのうえで、痛みの強さや恐怖回避の程度に応じてテストを選び、再現したい症状と負荷の大きさを意識しながら段階的に実施すると安全性が高まります。迷う場合は、主治医に評価方針を相談しておくと安心です。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下