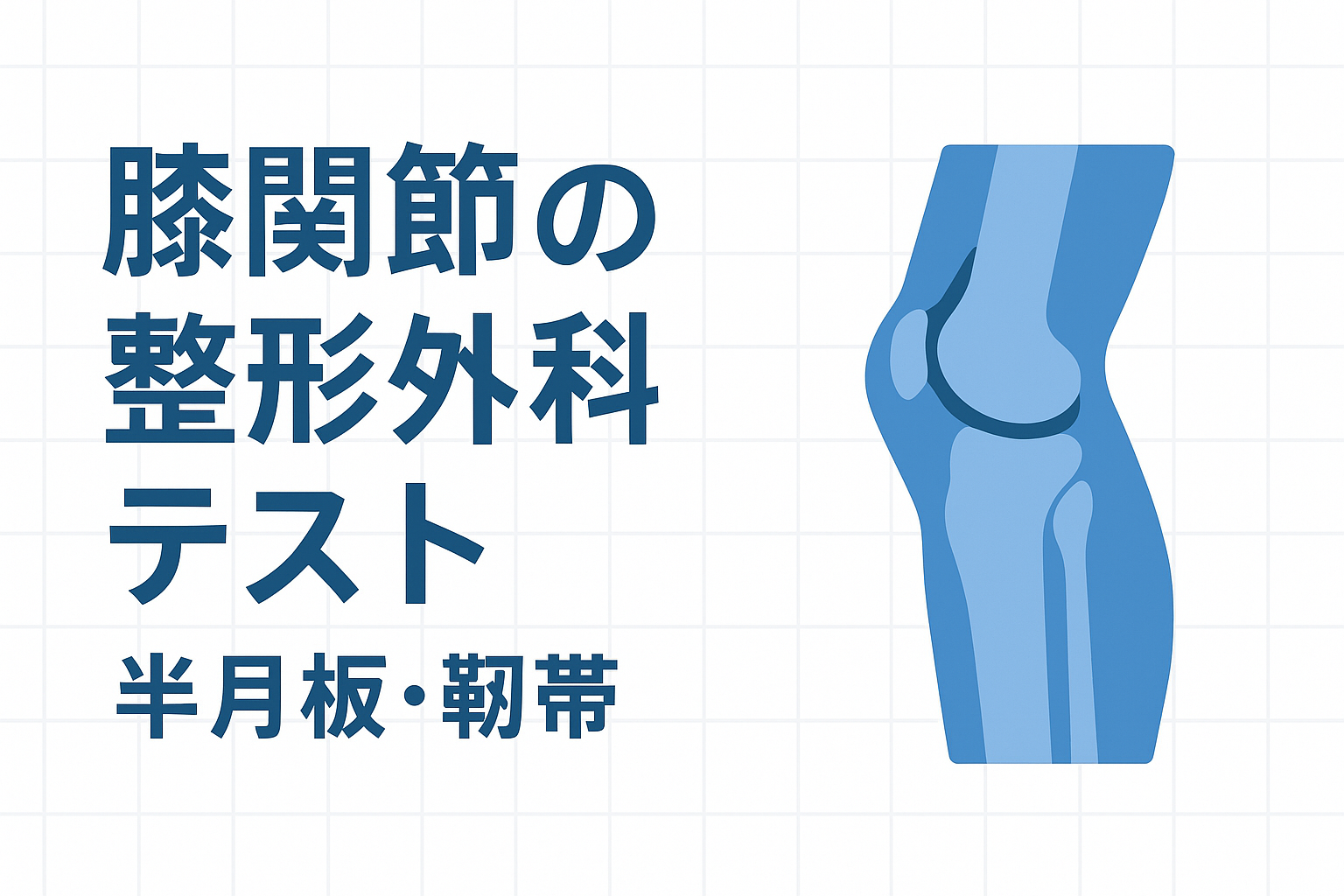医療安全管理体制と医療安全対策委員会の全体像|活動内容とリハビリ職の関わり
医療安全で「赤信号」が点いたときの動き方を見る(PTキャリアガイド)
医療安全管理体制は、インシデントや重大事故を個人の注意力ではなく 組織の仕組み で減らすための枠組みです。医療法や医療安全対策加算の施設基準では、医療安全管理指針の整備、医療安全管理者の配置、医療安全対策委員会の設置、職員研修(医療安全研修の年 2 回実施)、インシデント報告体制などを求めています。診療報酬や各種評価でも、こうした体制が前提として扱われることが多く、「書類上だけ整っている」状態ではなく、実際に回っているかどうかが問われます。
本記事では、医療安全管理体制と医療安全対策委員会の全体像を押さえつつ、医療安全委員会の活動内容・メンバー構成(組織図)・医療安全研修の設計といったポイントを整理します。特に、転倒・誤嚥・チューブ抜去など リハ場面で起こりやすい事故 に焦点を当て、PT・OT・ST などリハビリ職が委員会や日常業務の中でどう関わるとよいかを、チェックシートと合わせて解説します。「医療安全委員会 リハビリ」「医療安全委員会 理学療法士」としての立ち位置をイメージしながらご覧ください。
医療安全対策委員会の役割と開催頻度|活動内容とメンバー構成
医療安全対策委員会は、院内のインシデント情報を集約し、原因分析と再発防止策の検討・実行を担う場です。医療安全委員会の活動内容としては、インシデントの件数や傾向の共有、重大事例の検討結果の報告、マニュアル改訂や研修計画の立案、リスク評価と改善提案の承認などが挙げられます。構成メンバー(組織図)には、管理者(院長)・医療安全管理者・看護部・薬剤部・検査部・事務部門に加え、必要に応じてリハビリテーション部門や放射線部門なども含まれます。リハ職が入ることで、「動き」と「環境」の視点を議論に持ち込めるのが強みです。
開催頻度は「少なくとも年数回」が目安ですが、多くの施設では月 1 回程度の定例開催を行っています。PT・OT・ST が委員として参加する場合は、転倒・誤嚥・褥瘡・チューブ類の管理など、リハ関連のインシデントを事前に整理し、「なぜ起きたか」「どこを変えれば減らせるか」 を部署内で議論してから委員会に持ち込むと、会議が具体的な改善策につながりやすくなります。また、決定事項をリハ部門に確実に持ち帰り、カンファレンスや申し送りで共有する「情報のハブ」として機能することも重要です。
インシデント・ヒヤリハット報告と再発防止の流れ
医療安全管理体制の中心となるのが、インシデント・ヒヤリハット報告です。報告書には、発生日時・場所・職種・患者属性・出来事の概要・結果(影響度)・原因の考察・応急対応などを記載します。リハビリテーション領域では、ベッドからの転落、歩行中や移乗中の転倒、嚥下訓練中の誤嚥、チューブ・ドレーン・カテーテルの抜去、装具や車椅子の不適合などが典型的なインシデントです。「患者さんは大丈夫だったから」と報告をためらうと、パターンが見えず対策も立てにくくなります。
報告された事例は、医療安全管理者や委員会で集計・分析され、頻度の高いものや重症度の高いものから優先的に再発防止策が検討されます。例えば、歩行器使用中の転倒が多ければ「福祉用具選定と使用手順の見直し」「夜間のトイレ誘導方法の統一」など、リハビリテーション部門が中心となる対策が候補になります。重要なのは、対策を決めて終わりではなく、「何をいつまでに誰がやるか」「実施後どうなったか」 まで追跡することです。PT・OT・ST は、自部署の取り組み状況や効果を委員会に報告し、次の改善サイクルにつなげていきます。
医療安全研修とマニュアル整備:年 2 回研修をどう設計するか
医療安全管理体制では、職員に対する継続的な教育が必須です。多くの施設では「医療安全研修を概ね年 2 回以上実施すること」が医療安全研修(年 2 回義務)の目安として求められ、新人・中途採用者に対するオリエンテーションも必要になります。研修テーマとしては、医療安全の基本概念、インシデント・ヒヤリハット報告の目的と書き方、転倒・誤薬・誤嚥・感染・身体拘束などのリスク別対策が代表的です。ここに、施設の過去事例を交えたケーススタディや医療安全委員会主催の勉強会を組み合わせると、現場感のある学びになります。
マニュアル整備では、「何かあったときに読む分厚い資料」ではなく、日常で迷いやすい場面を短く切り出した手順書 が重要です。たとえば、「歩行器でのトイレ介助フロー」「嚥下訓練中にむせた場合の対応手順」「転倒時の初期対応と報告手順」など、リハスタッフが頻繁に遭遇する場面を 1 枚ものにまとめると、教育と実務の両方で活用できます。委員会では、インシデント分析の結果をもとにマニュアルを更新し、その変更点を研修や朝礼で周知していくことが求められます。
PT・OT・ST が医療安全対策で担う 5 つの役割
PT・OT・ST は、医療安全においても「身体機能と環境をつなぐ専門職」として独自の役割を持ちます。第一に、評価場面でのリスクアセスメントです。筋力・バランス・認知機能・視覚・嚥下機能などを踏まえ、転倒・誤嚥・装具トラブルのリスクを予測し、カルテやカンファレンスで言語化して共有することが、安全なケアの土台になります。第二に、移乗・歩行・ ADL 動作の具体的な介助方法をチームに伝えることで、「人によってやり方が違う」状態を減らすことができます。
第三に、リハ室や病棟環境の調整です。ベッドの高さ、手すり・歩行器・車椅子の配置、段差やマットの位置など、環境要因は事故の発生頻度に直結します。第四に、インシデント分析や事例検討会への積極的な参加があります。リハ関連事故では、運動課題の難易度設定や声かけのタイミング、装具の適合など、専門職でなければ気づきにくい要因が多く含まれます。第五に、学生・新人・他職種への教育です。「安全に動かす技術」 を丁寧に言語化して伝えていくことで、組織全体の医療安全レベルを底上げできます。
年間計画と記録の型を整える
医療安全管理体制を継続的に機能させるためには、年間計画と記録の型をそろえておくことが重要です。年間計画には、医療安全対策委員会の開催予定(月 1 回など)、医療安全研修のテーマと時期、新人オリエンテーション、インシデント集計・分析のサイクル、マニュアル見直しのタイミングなどを記載します。こうした予定を 1 枚のシートにまとめておくことで、監査や自己点検の際にも「いつ・何をしたか」を説明しやすくなります。
記録の型としては、①委員会議事録(開催日・出席者・議題・決定事項・担当者・期限)、②インシデント集計表(分類・件数・重症度・傾向)、③研修記録(テーマ・講師・対象職種・参加人数・内容要約・評価)、④年度末の総括レポートなどが挙げられます。PT・OT・ST は、転倒や誤嚥などのデータを整理して委員会に提供したり、リハ部門で実施した取り組みを総括したりする役割を担いやすいポジションです。フォーマットが統一されていれば、担当者が変わってもスムーズに引き継ぎが行え、医療安全対策加算の施設基準を満たしているかの確認にも活用しやすくなります。
医療安全管理体制・医療安全対策委員会チェックシート(ダウンロード)
この記事の内容を院内でそのまま自己点検に使えるよう、医療安全管理体制・医療安全対策委員会のチェックシートを A4 1 枚にまとめました。医療安全管理指針・医療安全管理者・委員会運営・インシデント報告・医療安全研修・マニュアル整備に加え、リハビリテーション部門としての確認項目も一覧でチェックできます。
年 1〜2 回の体制見直しや、医療安全委員会の新メンバーへのオリエンテーション、外部評価や監査前の抜け漏れ確認にご活用ください。印刷して手書きで記入しても、 PDF 化して電子保存しても構いません。
医療安全管理体制・医療安全対策委員会チェックシート(A4・無料ダウンロード)
おわりに:事故ゼロを目指す「仕組みづくり」に PT が関わる
医療安全対策委員会やインシデント報告は、ともすると「余計な事務仕事」と感じられがちです。しかし、転倒・誤嚥・チューブ抜去などの事例を丁寧に振り返り、原因を整理して再発防止策を組み立てていくプロセスは、そのまま リスクの少ないリハプログラムづくり に直結します。PT・OT・ST が医療安全委員会の活動内容に積極的に関わることで、「動き」や「環境」の視点が反映され、現場で実行しやすい対策を設計しやすくなります。
一方で、医療安全委員や書類対応が増えるほど、臨床や学習の時間が圧迫されるのも事実です。働き方を見直すときの抜け漏れ防止に、見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック( A4・ 5 分)と職場評価シート( A4 )を無料公開しています。印刷してそのまま使えますので、「今の職場でできる工夫」と「環境を変える選択肢」の両方を整理するツールとして活用してみてください。ダウンロードページを見る。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
医療安全委員を任されたとき、どのタイミングで転職を考えてもよいですか?
医療安全委員の役割自体は決して悪いことではなく、むしろ組織づくりを学べる貴重な機会です。ただし、十分な OJT や研修がないまま「書類作成だけ丸投げ」されていたり、インシデント報告を責める文化が強くストレスが大きい状態が続く場合は、心身の負担が大きくなりがちです。まずは上司や医療安全管理者に、役割とサポート体制について率直に相談し、それでも改善が見込めない場合は職場環境の見直しを検討してよいタイミングと言えます。
医療安全や委員会業務を通じて学びを深めつつ、「どんな職場なら安心して実務と学習を両立できるか」を整理する視点を持っておくことも大切です。必要に応じて、信頼できる第三者と一緒にキャリアの棚卸しを行い、今の職場で工夫できることと、転職を含めた選択肢の幅を確認しておくと安心です。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下