 評価
評価 Finkelstein テスト|ドケルバンを迷わず確認
Finkelstein テストの正しい手順・陽性所見・偽陽性の回避を “運用” に固定。Eichhoff との違い、痛みを出しすぎないコツまで解説。
 評価
評価  評価
評価  評価
評価 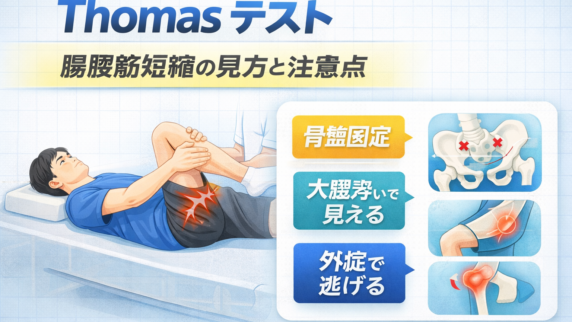 評価
評価  評価
評価 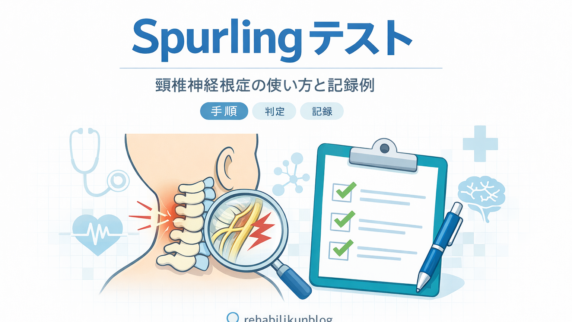 評価
評価  評価
評価  評価
評価  評価
評価 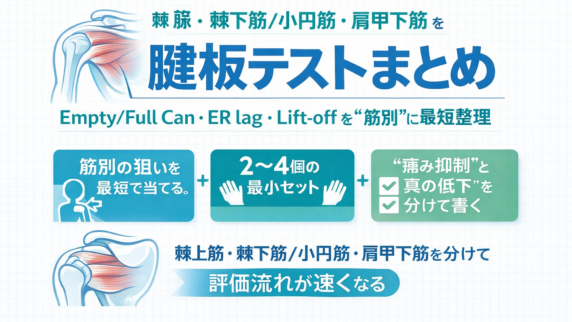 評価
評価