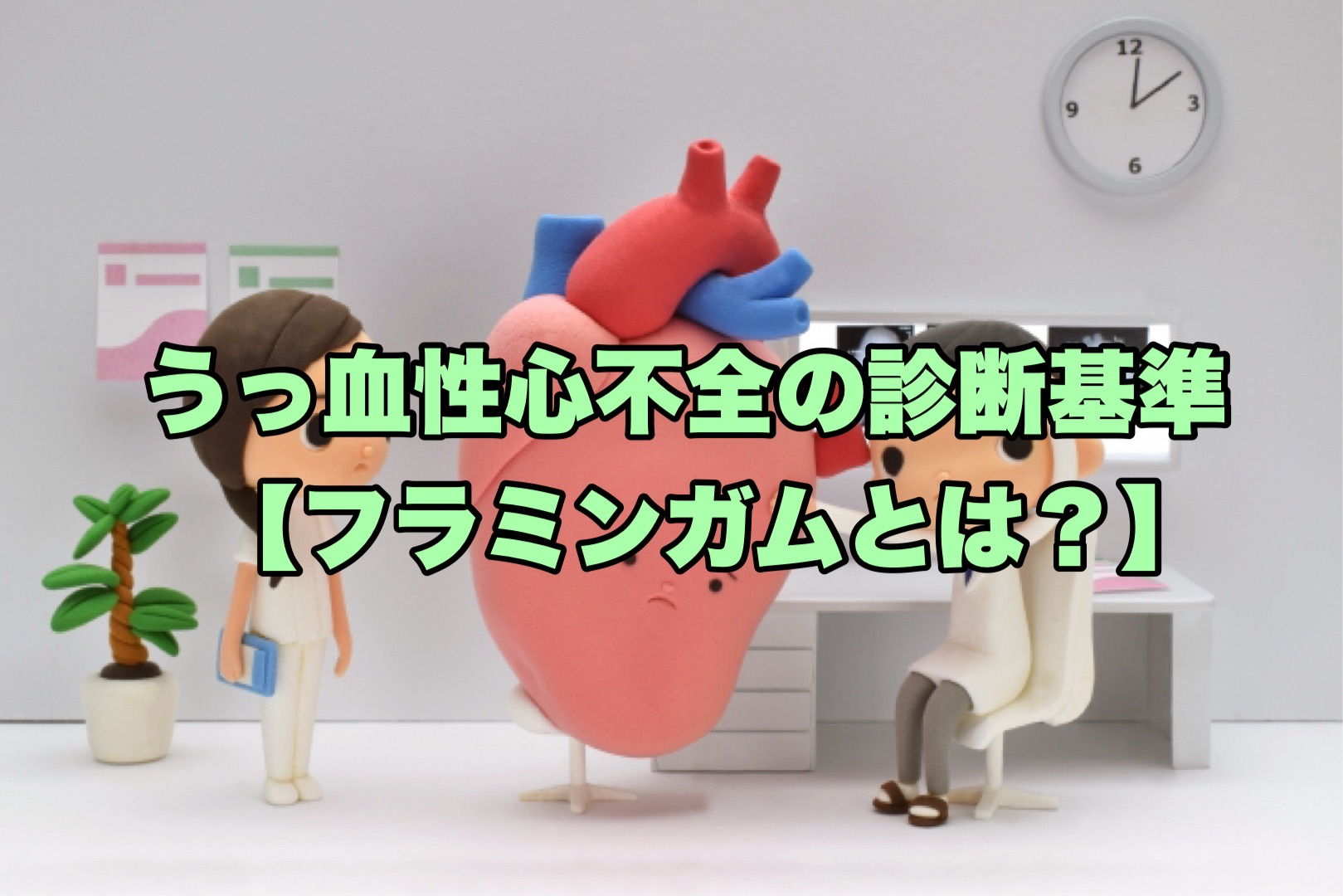心不全の臨床徴候チェック|フラミンガム基準の使い方【PT ベッドサイド実務】
フラミンガム基準( Framingham criteria )は、症状・身体所見・胸部 X 線を軸に、心不全( HF )の可能性をベッドサイドで素早く見立てるための古典的フレームです。PT が困りやすいのは「項目は知っているが、どの順番で見て、いつ中止し、次に何を共有するか」が曖昧なことです。
本稿では 大/小項目の判定を押さえたうえで、2025 年の診断アルゴリズム内での位置づけ(症候/所見 + BNP / NT-proBNP + エコー)を整理し、PT がうっ血/低灌流を見抜いて次アクションへ繋ぐ実務の型に落とし込みます。
評価の迷いは「見る順番」を固定すると一気に減ります。 評価 → 介入 → 再評価の流れを 3 分で復習する( #flow ) ※ 同一タブで開きます
要点まとめ(結論)
- 判定:大 2 または 大 1+小 2 で心不全。小項目は「他疾患で説明できない」が前提。
- 現在は 《症候/所見(フラミンガム)+ BNP / NT-proBNP + 心エコー》で診断確度を上げる運用が基本。
- PT は うっ血( wet )/ 低灌流( cold )の見立て → 離床の可否 → 再評価を “型” にして、所見の再現性を担保する。
PT が迷わない 5 分フロー(見る順番の固定)
心不全が疑わしい場面では、「危険徴候 → うっ血 → 低灌流 → 共有 → 再評価」の順に確認すると、観察の抜け漏れが減り、チーム連携も速くなります。フラミンガム基準は、このうちうっ血徴候の拾い上げに強い位置づけです。
循環・呼吸の評価を体系で整理したい場合は、内部障害ハブ(循環/呼吸/耐容能)にまとめています:内部障害ハブ(循環・呼吸・運動耐容能)(本文内のインライン内部リンクは本項のみ)。
フラミンガム基準とは?判定条件と大/小項目
判定は次の通りです:大項目 2 つ または 大項目 1 つ+小項目 2 つで「心不全あり」とする考え方です。小項目は他疾患( COPD ・腎不全・肥満など)で説明できる場合はカウントしないのが原則です。
臨床では「項目の丸暗記」よりも、同じ体位・同じ条件で再現性を取ることが重要です( JVD / HJR / S3 / ラ音は特に影響が大きい)。
| 区分 | 項目(代表) | 補足 |
|---|---|---|
| 大項目 | 発作性夜間呼吸困難( PND )/起坐呼吸、頸静脈怒張( JVD )、肺ラ音、S3( Ⅲ音 )、急性肺水腫、胸部 X 線での心拡大( cardiomegaly )、肝頸静脈逆流( HJR ) など | 身体診察と X 線でのうっ血徴候を重視 |
| 小項目 | 両側足背浮腫、努力性呼吸困難( DOE )、夜間咳嗽、肝腫大、胸水、頻脈(例:≳ 120 /分) など | 他疾患で説明できる場合はカウントしない |
| 参考 | 利尿での急速な体重減少(軽微項目) | 経過情報として判断補助に用いる |
現場で詰まりやすいポイント(よくある失敗)
フラミンガム基準は便利ですが、「小項目の過大評価」と「所見の取り方のブレ」で誤判定が起きやすいのが落とし穴です。特に PT は、観察条件(体位・呼吸指示・聴診環境)を整えるだけで所見の信頼性が上がります。
以下は、ベッドサイドで頻出する “詰まりどころ” と対策の早見です(記録にもそのまま使えます)。
| 詰まりどころ | 起こりやすいミス | 対策(型) | 記録のコツ |
|---|---|---|---|
| 小項目 | 浮腫や頻脈を「心不全」と決め打ち | 肥満・腎不全・静脈不全・薬剤性( Ca 拮抗薬)など代替説明を先に確認 | 「他疾患で説明困難」かどうかを 1 行で残す |
| JVD / HJR | 体位・視認条件が不十分で陰性/陽性がぶれる | 30–45° 半座位、斜光、顎上げ、右頸部で一定条件。HJR は10–15 秒の圧迫で再現を取る | 「体位(角度)」「右/左」「呼吸条件」をセットで記載 |
| S3 / ラ音 | 頻拍・騒音・体位で聴き取れず判断が曖昧 | S3 は左側臥位+ベル型+呼気終末、ラ音は背側下肺野から。体位変換や咳嗽で変化も確認 | 「聴診部位」「体位」「増減(座位で軽減など)」を残す |
| 用語混同 | 「フラミンガム基準」と「フラミンガムスコア」を混同 | 基準=心不全の臨床所見、スコア=冠動脈疾患リスクと目的を明確に分ける | カンファでは「診断フレーム(所見)」と一言添える |
2025 年の診断アルゴリズム内での位置づけ
現在の診断は 症候・所見(フラミンガム)+ ナトリウム利尿ペプチド( BNP / NT-proBNP )+ 心エコーの組合せが基本です。フラミンガム基準は “最初のフィジカルの型” として生き続け、バイオマーカーとエコーで確証を取りにいく運用が主流です。
外来ルールアウトの代表的な目安として BNP < 35 pg/mL または NT-proBNP < 125 pg/mL(急性期は BNP 100 / NT-proBNP 300)を用いつつ、肥満・高齢・腎機能で解釈を補正します。HFpEF では HFA–PEFF / H2FPEF などの補助スコアを使い、必要に応じて追加検査で確度を上げます。
PT のベッドサイド評価:うっ血 / 低灌流を見抜くコツ
PT が見たいのは「診断名」よりも、いまこの患者がうっ血( wet )で悪化しているのか、あるいは低灌流( cold )で耐容能が落ちているのか、という当日の病態です。所見は “単発” で結論を出さず、セットで見て一貫性を取りにいきます。
下表は、フラミンガム項目を PT が “次アクション” に繋げるための実務用マッピングです。
| 項目 | 観察ポイント(型) | 次アクション(例) |
|---|---|---|
| 頸静脈怒張( JVD ) | ベッド 30–45°・顎上げ・右頸部。吸気での変化も確認。 肝頸静脈逆流( HJR )は 10–15 秒圧迫で再現。 |
陽性+ラ音/浮腫でうっ血優位( wet )を想定。離床は短時間・低強度から、体位調整と併用して反応を確認。 |
| S3( Ⅲ音 ) | 左側臥位・ベル型で心尖・呼気終末。頻拍時は聞き取り低下。 | うっ血+心機能低下の示唆。強度を上げず自覚症状・血圧・ SpO2 を密に観察。 |
| 肺ラ音 | 背側下肺野から。体位で変化を確認。咳嗽での消失は分泌物寄与。 | 呼吸介助・排痰・座位保持を優先。増悪が明確なら医師へ早期共有。 |
| PND / 起坐呼吸 | 夜間の覚醒回数・枕枚数・座位での寛解を聴取。 | 頭高位など体位調整を徹底し、日中の離床量/強度を保守的に設計。 |
| 末梢浮腫 | 圧痕の左右差・圧痛・皮膚温。弾性ストッキング適合も確認。 | 圧迫療法は装着手順+再評価をセット(ずり下がりや過圧に注意)。 |
| 心拡大( X 線 ) | CTR ≳ 50 % を目安に他所見と併読。 | 急性増悪所見と併せて内科へフィードバック。強度は保守的に。 |
離床・運動の可否と中止目安(循環リハの視点)
可否や中止は施設の SOP と主治医指示を最優先し、以下は代表例の “赤信号” として扱います。ポイントは「中止」そのものより、中止した理由を言語化して共有し、次回の再評価条件を揃えることです。
入院急性期では Nohria–Stevenson( warm / cold × wet / dry )の臨床プロファイルで病態を把握し、wet(うっ血)優位なら除水/体位・呼吸介助を優先、cold(低灌流)優位なら過負荷回避・小刻み離床で反応を確認します。
- 安静時の強い呼吸困難・新規/増悪する胸痛・失神前駆
- 血行動態不安定(低血圧・起立での症状増悪・重度頻脈/徐脈・新規の致死性不整脈)
- 離床直後から SpO2 の持続低下・チアノーゼ・ラ音増強などのうっ血増悪所見
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q. フラミンガム基準とフラミンガムスコアは何が違う?
A. 基準は「心不全の臨床診断フレーム」(症状・所見ベース)。スコアは「将来の冠動脈疾患リスク予測」(年齢・脂質・喫煙など)。目的と対象がまったく異なります。
Q. HFpEF はどう見極める? HFA–PEFF / H2FPEF の使い分けは?
A. HFpEF の確度は「症候・所見+ BNP / NT-proBNP + 詳細エコー」で高め、スコアは補助として利用します。中間域では追加検査(例:ストレスエコー等)で詰め、臨床像と整合するかを確認します。
臨床でそのまま使える小ワンポイント
- JVD ・ HJR ・ S3 は体位とタイミングで再現性が変わる。30–45°・呼気終末・静音環境を合言葉に。
- 浮腫は他疾患の除外から。片側性は静脈/リンパ障害を先に疑う。
- 運動は症状・血圧・ HR ・ SpO2の 4 点セットでモニタし、悪化兆候があれば停止 → 条件を揃えて再評価。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に。見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック( A4 ・ 5 分)と職場評価シート( A4 )を無料公開しています。印刷してそのまま使えます。
配布物をみる
参考文献
- McKee PA, Castelli WP, McNamara PM, Kannel WB. The natural history of congestive heart failure: the Framingham study. N Engl J Med. 1971;285(26):1441–1446. doi:10.1056/NEJM197112232852601 / PubMed
- McDonagh TA, Metra M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur J Heart Fail. 2021;23(12):e876–e1032. Full text / Essential messages
- Heidenreich PA, Bozkurt B, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure. Circulation. 2022;145:e895–e1032. doi:10.1161/CIR.0000000000001062
- Pieske B, Tschöpe C, et al. HFA–PEFF diagnostic algorithm for HFpEF. Eur Heart J. 2019;40(40):3297–3317. doi:10.1093/eurheartj/ehz641 / PubMed
- Reddy YNV, Carter RE, et al. A Simple, Evidence-Based Approach to HFpEF: the H2FPEF score. Circulation. 2018;138(9):861–870. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035681
- Nohria A, Tsang SW, et al. Hemodynamic profiles predict outcomes in acute HF. J Am Coll Cardiol. 2003;41(10):1797–1804. PubMed
- JCS/JHFS 2025 心不全診療ガイドライン(日本循環器学会/日本心不全学会)ダイジェスト/オンライン. J-STAGE / PDF
- JCS/JACR 2021 心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン. Circulation Journal 87(1). PDF
- Ikeda S, Takata Y, Inoue K, et al. Validation of NT-proBNP cutoffs in Japan. Circ J. 2025. Article
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:心不全を含む循環リハ、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、摂食・嚥下、シーティング、脳卒中・褥瘡