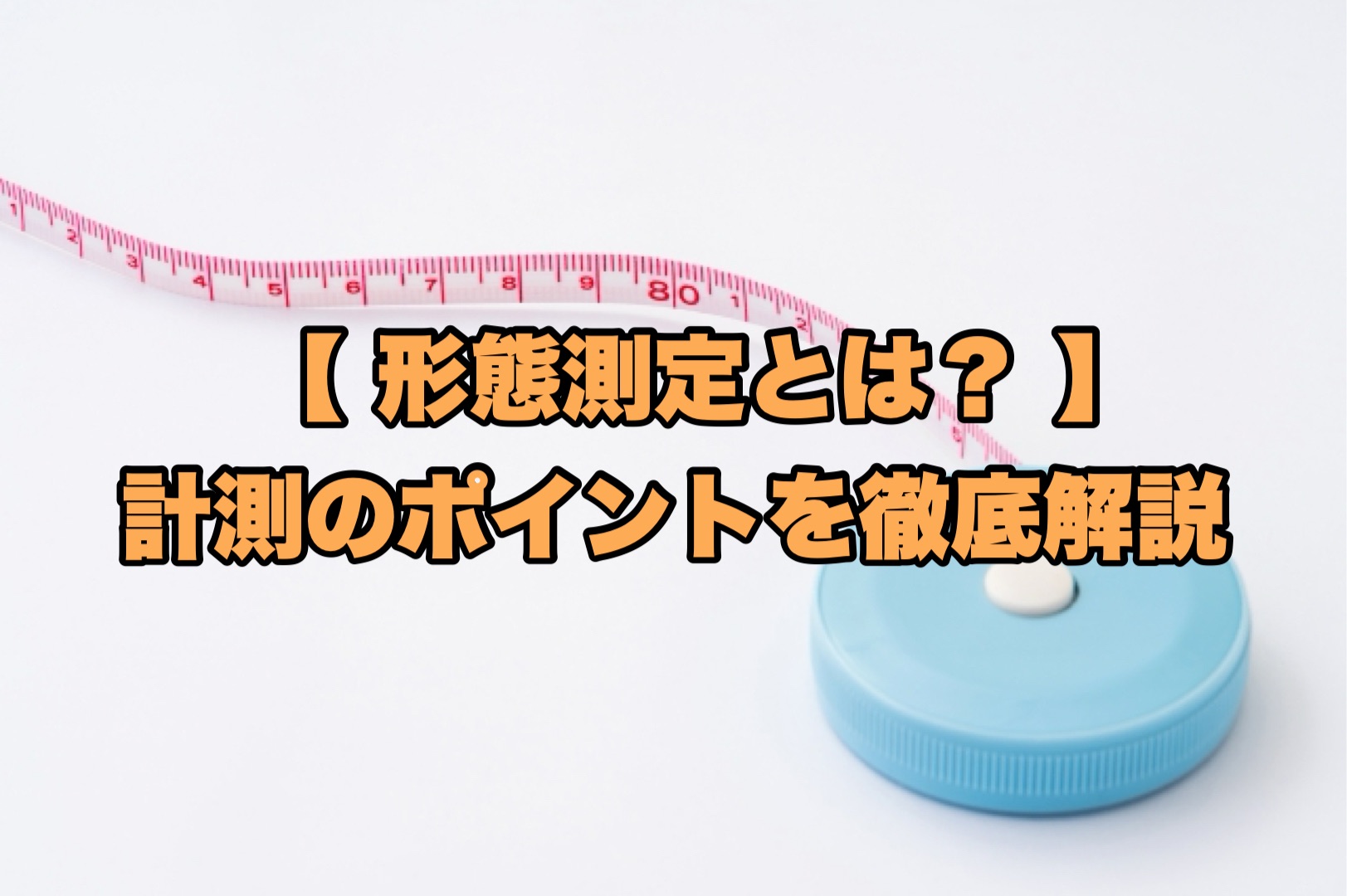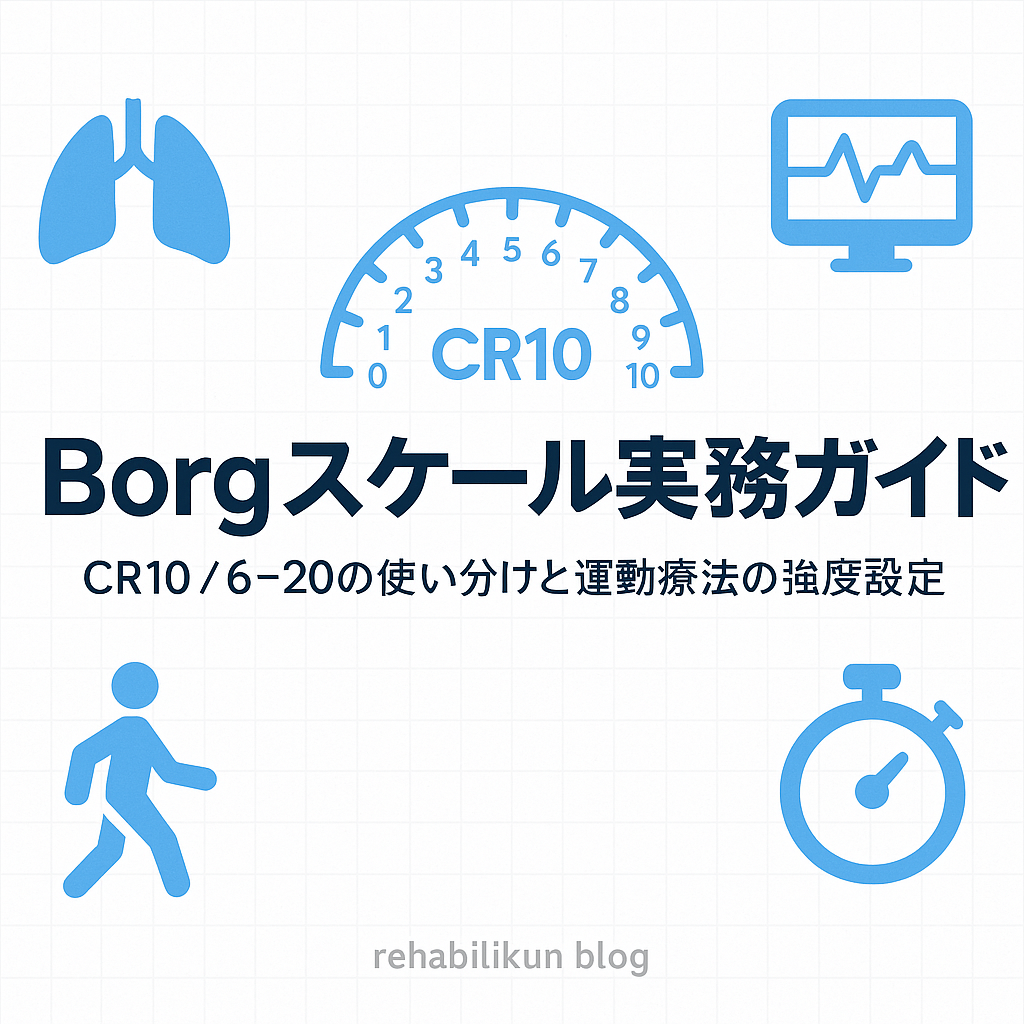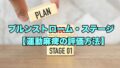形態測定(四肢長・周径)の測り方|ランドマークと記録のコツ
測定は「目的 → 条件固定 → ランドマーク → 記録」を揃えるだけで、同じ巻尺でも“使えるデータ”に変わります。 評価 → 記録 → 再評価の流れをまとめて確認する( #flow )
形態測定は、四肢の長さと周径をそろえた条件で測り、左右差と経時変化( Δ )を読み取るための基礎手技です。筋萎縮・浮腫・腫脹・拘縮などの所見を、触診や視診だけでなく“数値”で共有できるのが強みです。
本ページは「測り方の辞書」として、ランドマークと記録ポイントを最短で確認できる形に整理します。目的別の最小セットや標準化の全体像は、親記事の 身体計測(形態測定)まとめ に統一しています。
測定前にそろえる 4 つ(ここで誤差が決まる)
四肢長・周径は、同じ患者でも体位や肢位、テープの張力で数値が動きます。最初に「毎回固定する条件」を決めてから測ると、再評価( Δ )が読めるようになります。
おすすめは①目的(何を追うか)②体位 ③肢位 ④測定点の定義を 1 行で記録欄に残すことです。チームで共有しやすくなり、測定者が変わってもブレにくくなります。
| 固定するもの | 具体例 | 記録の書き方例 |
|---|---|---|
| 目的 | 筋萎縮/浮腫・腫脹/装具・シーティング | 目的:筋萎縮 |
| 体位 | 背臥位/座位/立位 | 体位:背臥位 |
| 肢位 | 股関節回旋中間、膝伸展、前腕回外など | 肢位:股関節回旋中間+膝伸展 |
| 測定点 | ランドマーク+距離(例:膝蓋骨上縁+ 10 cm ) | 測定点:膝蓋骨上縁+ 10 cm |
四肢長の測り方(四肢長・肢節長)
四肢長は、左右差から拘縮・骨折後の転位・骨盤傾斜などを推定する入口になります。巻尺は計測区間の最短距離を取り、単位( 0.1 cm/ 0.5 cm )は施設のルールで統一します。
ポイントは触診 → マーキング → 測定 → その場で記録です。マーキングを省くと「前回と違う場所」を測りやすく、 Δ が読めなくなります。
上肢:代表的な測定(解剖学的肢位を基本)
| 測定名 | 区間 | 体位・肢位 | ランドマーク(触診の要点) | 記録ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 上肢長 | 肩峰 〜 橈骨茎状突起 | 座位 or 背臥位/肘伸展・前腕回外 | 肩峰:肩甲棘を外側へ追い、前方へ折れる肩峰角周囲を確認/橈骨茎状突起:橈骨遠位の外側隆起 | 肩甲帯の挙上・前方突出が出ないように姿勢をそろえる |
| 上腕長 | 肩峰 〜 上腕骨外側上顆 | 同上 | 外側上顆:上腕骨遠位外側の隆起 | 肘伸展をそろえる(軽度屈曲で長さが短く出る) |
| 前腕長 | 上腕骨外側上顆 〜 橈骨茎状突起 | 同上 | 上記に同じ | 前腕回内で橈骨茎状突起が取りづらくなるので回外で統一 |
下肢:代表的な測定(背臥位+回旋中間を基本)
| 測定名 | 区間 | 体位・肢位 | ランドマーク(触診の要点) | 記録ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 棘果長( SMD ) | 上前腸骨棘( ASIS )〜 内果 | 背臥位/股関節回旋中間・膝伸展 | ASIS:腸骨前上方の突出/内果:脛骨遠位内側の最下点 | 骨盤の回旋・傾きがあると差が出るので、骨盤位をそろえてから測る |
| 転子果長( TMD ) | 大転子 〜 外果 | 同上 | 大転子:大腿骨近位外側の最大隆起(股関節回旋で触れ方が変わる)/外果:腓骨遠位外側の最下点 | 股関節回旋がズレると大転子の位置が変わるため、回旋中間を優先 |
| 大腿長 | 大転子 〜 大腿骨外側上顆(膝外側裂隙の目安) | 同上 | 外側上顆:大腿骨遠位外側の隆起 | 膝軽度屈曲で短く出やすいので伸展をそろえる |
| 下腿長 | 大腿骨外側上顆(膝外側裂隙の目安)〜 外果 | 同上 | 上記に同じ | 踵位置(足関節底背屈)は測定点に影響しにくいが、体位は固定する |
四肢周径の測り方(上腕・前腕・大腿・下腿)
周径は、筋の状態だけでなく皮下組織や浮腫の影響も反映します。だからこそ、左右差と同条件での Δが価値になります。巻尺は長軸に対して垂直に当て、張力をそろえます。
周径は測定者で誤差が出やすいため、測定点をペンでマーキングし、毎回同じ点で測る運用が有効です。
上肢の周径
| 測定名 | 体位・肢位 | 測定点 | 読み方のコツ |
|---|---|---|---|
| 上腕周径(肘伸展位) | 座位 or 背臥位/肘伸展・前腕回外 | 上腕中央付近(施設で定義を固定) | 肘屈曲位との“差”を追うより、同一肢位で Δ を追う方が運用しやすい |
| 上腕周径(肘屈曲位) | 上腕に力こぶが出るように肘屈曲 | 上腕二頭筋の最大膨隆部 | 努力量で変わるので、実施するなら手順(力の入れ方)をチームで統一 |
| 前腕周径(最大) | 座位 or 背臥位/肘伸展・前腕回外 | 前腕近位側の最大膨隆部 | 回内位だと最大部がズレやすいので回外で固定する |
| 前腕周径(最小) | 同上 | 前腕遠位の最も細い部位 | 浮腫が遠位に出る症例では、最小部の Δ が役立つことがある |
下肢の周径
| 測定名 | 体位・肢位 | 測定点(例) | 読み方のコツ |
|---|---|---|---|
| 大腿周径 | 背臥位/股関節回旋中間・膝伸展 | 膝蓋骨上縁+ 10 cm(など施設で固定) | “大腿周径”の指す部位が施設で混ざりやすいので、必ず定義をセットで記録する |
| 下腿周径(最大) | 背臥位/膝伸展 | 下腿三頭筋の最大膨隆部 | ベッド圧迫で最大部がつぶれると細く出るため、下腿が圧迫されない工夫を入れる |
| 下腿周径(最小) | 背臥位/膝は屈曲でも伸展でも可(固定推奨) | 内果・外果の直上で最も細い部位 | 足関節周囲の腫脹を追うときに役立つことがある |
誤差を減らす標準化(チェックリスト)
周径は「ちょっと強く締めた」「点が 1 cm ずれた」だけで数値が動きます。測定の前に、固定ルールを短く決めておくと、記録が“比較できるデータ”になります。
おすすめの固定ルールは測定点(ランドマーク+距離)・体位・肢位・時刻・張力です。最低限ここだけ揃えると、 Δ を迷わず読めます。
| 項目 | 固定ルール | メモ |
|---|---|---|
| 測定点 | ランドマーク+距離で固定(マーキング) | 例:膝蓋骨上縁+ 10 cm |
| 体位 | 背臥位 or 座位を固定 | 支持面や足底接地もそろえる |
| 肢位 | 回旋中間・膝伸展などを固定 | 回旋ズレは周径に影響 |
| 張力 | 皮膚を圧迫しない張力で統一 | “締め付けない”を言語化 |
| タイミング | 同じ時間帯/介入前後を固定 | 浮腫は日内変動が出やすい |
よくある失敗と対策( OK / NG 早見)
測定がうまくいかない原因の多くは「測り方」ではなく条件のブレです。 NG を潰すだけで、再評価( Δ )が一気に読みやすくなります。
特に多いのが測定点の未固定と肢位の回旋ズレです。マーキングと回旋中間の徹底が、最短の改善になります。
| 場面 | NG | OK | 理由 |
|---|---|---|---|
| 測定点 | 最大膨隆部を“目視”で決める | ランドマーク+距離で固定しマーキング | 点のズレが Δ を破壊する |
| 回旋 | 股関節外旋位で測る日がある | 回旋中間を固定して測る | 大転子位置や筋の張りが変わる |
| 張力 | 毎回締め具合が違う | 皮膚を圧迫しない張力で統一 | 数 mm 〜 cm 単位で動く |
| タイミング | 午前と夕方が混在 | 同じ時間帯で固定 | 浮腫の影響で比較不能になる |
ダウンロード(A4)
記録用に、A4 でそのまま使えるシートを用意しています。印刷設定はA4/余白 10–12 mm/ヘッダ・フッタ非表示が目安です。
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. 同じ部位は何回測れば良いですか?
A. 基本は 2 回測って平均を採用します。差が大きい場合は 3 回目を追加し、外れ値がないか確認します。測定者・器具・体位・肢位は同一条件に固定すると、 Δ が読みやすくなります。
Q2. どれくらいの変化が“意味あり”ですか?
A. 測定誤差(測定者差・張力・肢位)を加味し、目的に応じて判断します。まずは条件固定を徹底し、単発値より同条件の Δで追ってください。
Q3. 座位と背臥位、どちらで測れば良いですか?
A. 目的に合わせて選び、以後は同一条件で固定します。例:シーティングの確認なら座位(支持・足底接地も固定)、筋萎縮や浮腫を追うなら背臥位で統一、などが運用しやすいです。
Q4. ランドマークが取りづらいときは?
A. 代替ランドマークをチームで合意し、定義を記録します。触診 → マーキング → 再確認の 3 ステップで誤差を抑えられます。
Q5. 測定をいったん止める目安は?
A. 強い痛みや気分不快が出た場合は一度中断し、休息して状態を確認します。測定そのものより、患者の反応を優先して運用してください。
参考文献
- ISO 7250-1:2017. Basic human body measurements for technological design — Part 1: Body measurement definitions and landmarks. ISO.
- Chen LK, Woo J, Assantachai P, et al. Asian Working Group for Sarcopenia: 2019 Consensus Update on Sarcopenia Diagnosis and Treatment. J Am Med Dir Assoc. 2020;21(3):300-307.e2. DOI: 10.1016/j.jamda.2019.12.012. PubMed: 32033882.
- Foroughi N, Dylke ES, Paterson RD, et al. Inter-rater reliability of arm circumference measurement. Lymphat Res Biol. 2011;9(2):101-107. DOI: 10.1089/lrb.2011.0002. PubMed: 21688979.
- NCART. A Clinical Application Guide to Standardized Wheelchair Seating Measures of the Body and Support Surfaces. 2013. PDF.
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下
おわりに
形態測定は、目的の固定 → ランドマーク触診 → マーキング → 計測 → 記録 → Δ で再評価のリズムを作ると、数字がそのまま臨床判断に使えるようになります。面談前の準備チェックと職場評価シートも、必要なら こちら からまとめて確認できます。