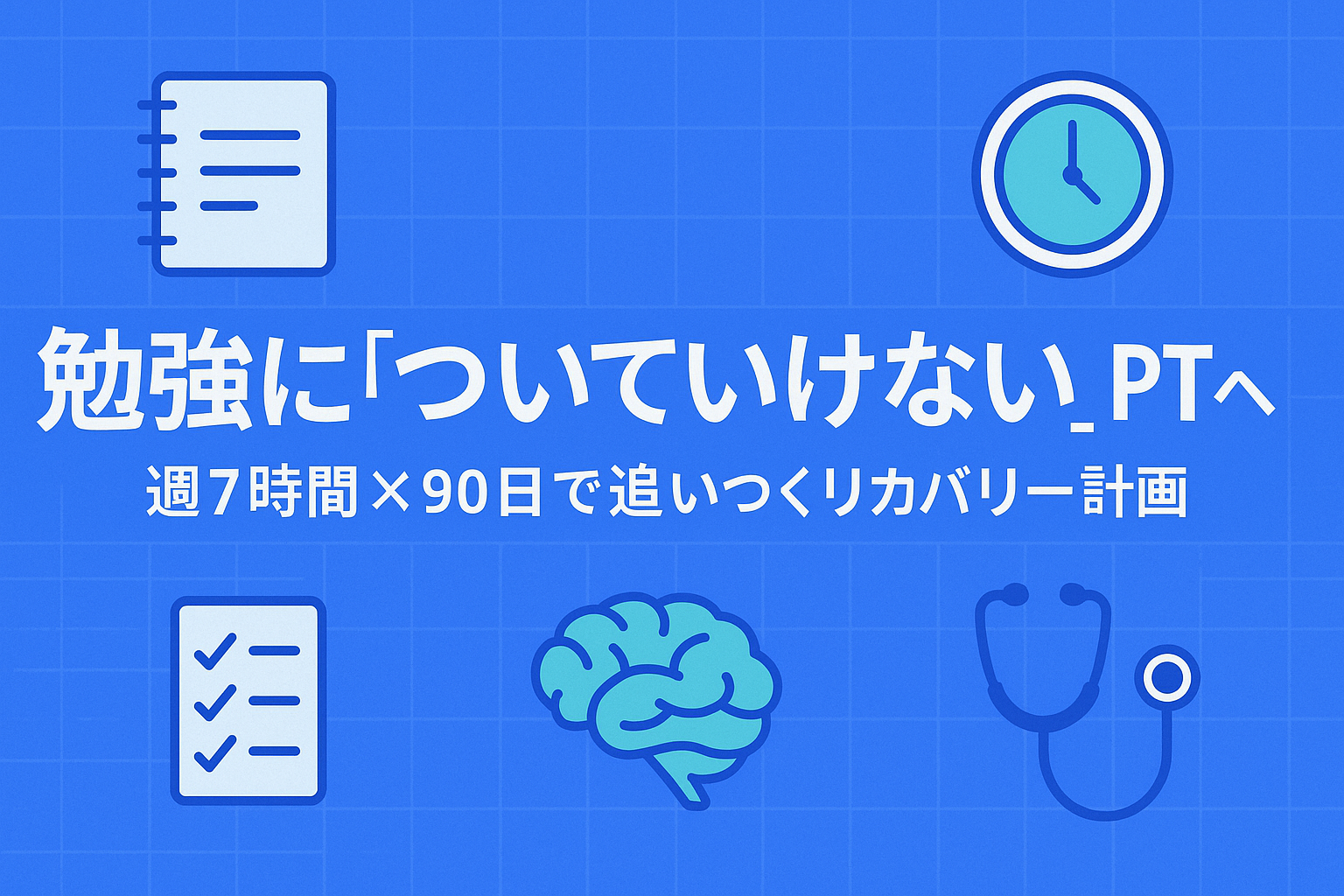勉強に「ついていけない」と感じたら:まず何をすべきか
結論、原因を 時間・内容・方法・メンタル の 4 つに分けて切り分け、週 7 時間の学習ブロックで 90 日のリカバリー計画 を回すのが最短です。本稿では「自己チェック → 優先順位 → 週次タスク → レッドフラグ(撤退基準)」までを、現場で使える形に落とし込みます。
ここでのゴールは「知識を増やす」より先に、明日から臨床で検証できる小さなアウトプット(口述・症例メモ・手順の声出し)を作り、反復して“追いつく感覚”を取り戻すことです。
現場の詰まりどころ:ついていけない人がハマる 5 パターン
「努力しているのに進まない」は、たいてい 学習設計(やり方・選び方・記録)で詰まっています。まずは自分の詰まり方を特定し、最短の修正だけ入れましょう。
| よくある詰まり | 起きていること | 修正(最小の一手) |
|---|---|---|
| 読むだけで終わる | 理解した“つもり”で、想起できない | 口述 30 秒(骨指標 → 筋 → 作用)を毎回入れる |
| テーマが多すぎる | 点が増えるだけで、線にならない | 束を 3 つ(解剖触診/力学/評価手順)に固定する |
| 週末にまとめてやる | 間隔が空き、定着しにくい | 平日 25 分 × 3〜4 回の“短冊”を優先 |
| メモが散らかる | 復習できず、改善が積み上がらない | 成果物を 1 枚に集約(目標 → 仮説 → 検証 →次週) |
| 自己否定が強い | 行動が止まり、さらに遅れる | 最小単位(口述 5 分)に落として“続けた”を作る |
自己チェック:原因の切り分け( 3 分)
以下に 1 つでも該当すれば、そのブロックを最優先でテコ入れします。ここを曖昧にすると、努力の方向がズレて消耗します。
- 時間:週の勉強確保が 5 時間未満。勤務後は 30 分未満の日が 4 日以上。
- 内容:解剖・運動学・評価法の 基礎語彙 を説明できない(例:モーメント、床反力、骨指標、ランドマーク)。
- 方法:読むだけ学習で 想起(思い出す) と アウトプット が不足。過去問・症例メモ・声出し手順がない。
- メンタル:不眠・食欲低下・動悸などが 1 週間以上。めまい・失神傾向、強い不安で学習が止まる。
ポイントは「全部を直そうとしない」ことです。まずは 1 ブロックだけ最短で改善し、追いつく手応えを作ります。
優先順位の決め方:最小限の“束”に絞る
90 日の間は「広く浅く」をやめ、① 解剖触診 ② 運動学(基礎力学)③ 主要評価法の運用 に絞ります。疾患は 1 つに寄せた方が、学びが線になりやすいです。
具体的には、次の順で“束”を固定します。
| 優先 | やること(最小) | やらないこと(いったん保留) |
|---|---|---|
| 最優先 | 骨指標・筋走行・作用を 口述できる/触れる | 細かい起始停止の丸暗記 |
| 次点 | てこ・モーメント・床反力を 症例の言葉に置換 | 高度な数式・専門領域の深掘り |
| 次点 | 評価を「目的 → 準備 → 観察 → 判定 → 記録」で 声出し | カットオフ表の暗記(必要時に確認で OK) |
90 日リカバリー計画(週 7 時間 × 12 週)
週 7 時間の配分例です。シフトに合わせて「出勤前 25 分 × 5 回+週末合計約 4.5 時間」に分割します。短く・高頻度が定着を作ります。
| 枠 | 時間 | やること | 成果物(残すもの) |
|---|---|---|---|
| 月・火・木・金 | 各 25 分 | 解剖触診:想起テスト → ランドマーク確認 → 30 秒口述 | 口述できなかった語彙を 3 つだけメモ |
| 水 | 80 分 | 運動学:てこ/モーメント/床反力を 1 症例で説明 | 「症例 → 力学の一文」× 3 行 |
| 土 | 120 分 | 評価法:手順を声出し → 相互チェック(可能なら) | 評価手順の“詰まる 1 手”を 1 つ修正 |
| 日 | 150 分 | 症例メモ整理:観察 → 仮説 → 確認観察 → 介入 → 再評価 | 翌週の「確認観察」 3 つ |
学習の成果物は 1 枚(または 1 ノート)に集約し、翌週の臨床で「検証 → 修正」を回します。ここが回り始めると、追いつくスピードが一気に上がります。
最低限ここだけ:科目別の押さえどころ
“全部やる”をやめて、最低限の芯だけ残します。芯ができると、周辺知識は後から自然に乗ります。
- 解剖触診:骨指標 → 筋走行 → 作用を 口述できること。触れない部位は「触れる代替」を決める。
- 運動学:てこ、関節モーメント、重心・床反力。症例に 力学の語彙を当てる(例:「膝伸展モーメントが不足」など)。
- 評価法:目的 → 準備 → 観察 → 判定 → 記録の順で 声出し手順。迷ったら「目的が 1 行で言えるか」に戻る。
- 疾患:まず 1 疾患に寄せ、「急性期 → 回復期 → 生活期」で 目的と禁忌が言えるようにする。
- 安全管理:バイタル前チェック、起立時の反応、症状の言語化。無理に負荷を上げない。
運用のコツ:続けるための“ 1 枚化”と週次レビュー
ついていけない状態から戻す鍵は、「何をやったか」ではなく 何が改善したかを見える化することです。週 1 回だけ、下の項目を埋めてください。
| 項目 | 書く内容(短く) |
|---|---|
| 今週の目標 | 口述できる語彙を 10 個、評価手順を 1 つ通す など |
| 詰まった点 | どこで止まったか(例:ランドマークが曖昧) |
| 仮説 | 止まった理由(例:想起不足/時間帯が悪い) |
| 検証 | 翌週に試す 1 手(例:朝 25 分に固定) |
| 次週の確認観察 | 臨床で見る 3 つ(例:立脚初期の骨盤前傾) |
これを 12 週続けるだけで、学習が「反省会」ではなく「改善ループ」になります。
レッドフラグ(中止・相談の基準)
学習は大事ですが、健康と安全が最優先です。次に当てはまる場合は、学習負荷を下げ、早めに相談してください。
- 不眠/食欲低下/動悸が 2 週間以上続く
- 勤務に支障が出る、ミスが増える、通勤や業務中の強い不安
- めまい・失神傾向、強い頭痛、しびれなどの身体症状が目立つ
- 抑うつ感が強く、日常生活が回らない
「勉強で巻き返す」より、まず回復させた方が最終的に早いケースは少なくありません。
よくある質問( FAQ )
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
平日が遅く帰宅で、時間が取れません。
週末にまとめるより、出勤前や休憩前後の 25 分ブロックを 3〜4 回確保する方が定着します。最初は「口述 30 秒+確認 10 分」でも十分です。週合計が 7 時間に届けば、 90 日で基礎は戻ります。
何から手を付けるべき?科目が多すぎます。
最初の 90 日は「解剖触診」「力学の語彙」「評価手順の声出し」に限定してください。疾患は 1 つに寄せて線にする方が、結果的に他領域も伸びます。
実習や新人指導で「できない」と言われました。巻き返せますか?
巻き返せます。鍵は 1 症例で「観察 → 仮説 → 確認観察 → 再評価」を回し、説明できる形で残すことです。評価の手順は、目的から順に声に出して詰まりを潰すと一気に通ります。
メンタルがしんどい時は、どうしたらいいですか?
睡眠・食事・入浴の 3 本を先に整え、学習は「口述 5 分」など 最小単位に落とします。しんどさが続く場合は、我慢せずに早めに相談してください。
おわりに
ついていけない時期は「学習量」より、安全の確保 → 最小のアウトプット → 記録 → 再評価のリズムを取り戻す方が、結果的に早く追いつけます。面談準備チェックと職場評価シートを使って“学び直しの設計”から整えたい場合は、マイナビコメディカルの面談準備チェック&職場評価シートも活用してみてください。
参考文献
- Dunlosky J, Rawson KA, Marsh EJ, Nathan MJ, Willingham DT. Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology. Psychol Sci Public Interest. 2013;14(1):4-58. doi:10.1177/1529100612453266
- Karpicke JD, Roediger HL. The Critical Importance of Retrieval for Learning. Science. 2008;319(5865):966-968. doi:10.1126/science.1152408
- Cepeda NJ, Pashler H, Vul E, Wixted JT, Rohrer D. Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. Psychol Bull. 2006;132(3):354-380. doi:10.1037/0033-2909.132.3.354
- Ericsson KA, Krampe RT, Tesch-Römer C. The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychol Rev. 1993;100(3):363-406. doi:10.1037/0033-295X.100.3.363
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下