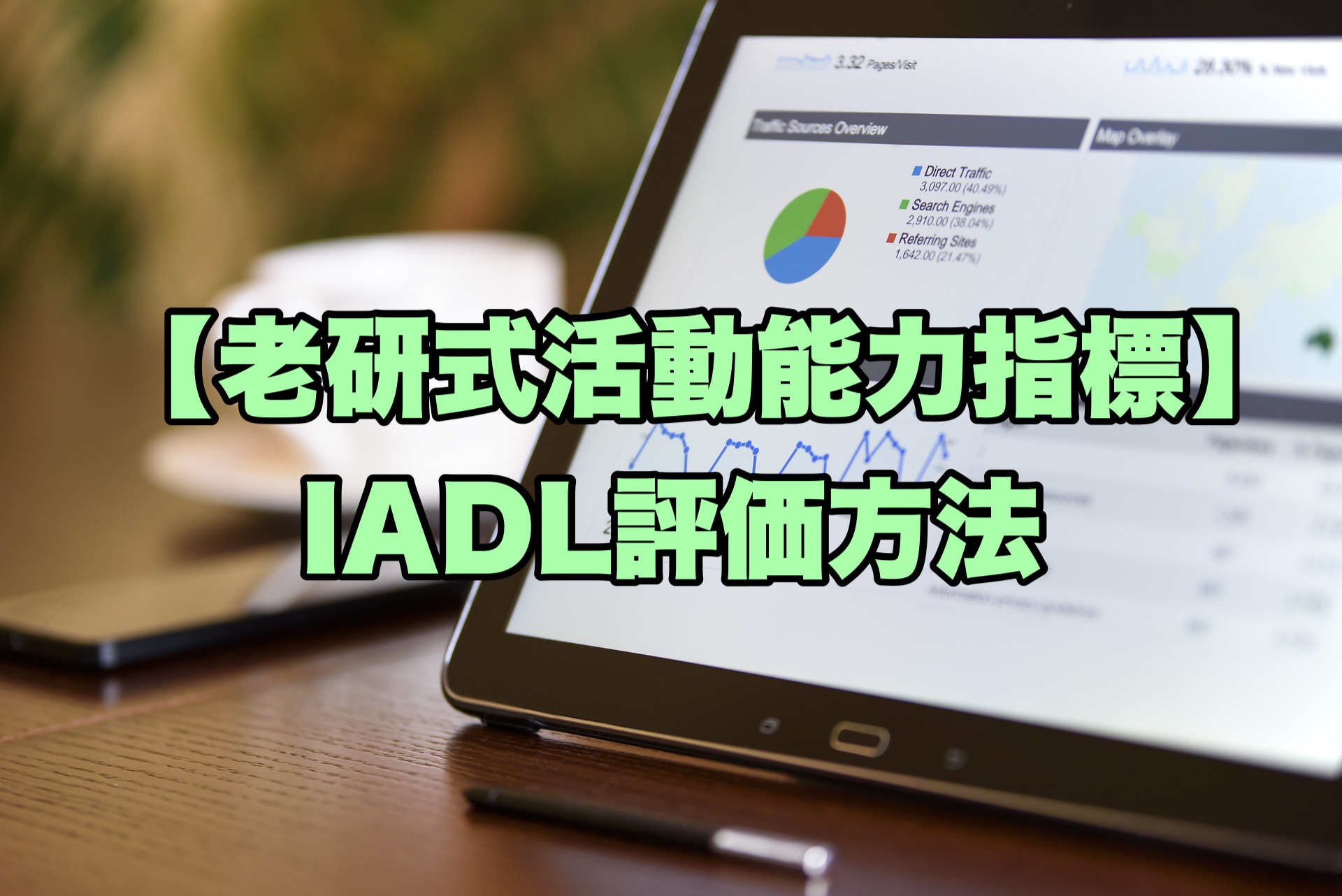老研式活動能力指標(Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology Index of Competence: TMIG-IC)は、IADL・知的能動性・社会的役割の 3 領域 13 項目で高次生活機能をとらえる日本発の標準尺度です。各項目は「できる=1/できない=0」の二値で採点し、合計 0–13 点。ベーシック ADL を超えた「暮らしの遂行度」を短時間で把握できます。
用語メモ:本記事は 老研式活動能力指標(TMIG-IC)(13項目:IADL/知的能動性/社会的役割)を扱います。「新・老研式」と呼ばれることの多い JST版活動能力指標(JST-IC) は別尺度(16項目:新機器利用/情報収集/生活マネジメント/社会参加)です。
新人 PT 向けの評価・臨床運用ハブも用意しています。
老研式IADLとは(TMIG-IC の位置づけ)
TMIG-IC は、既存の基本 ADL 尺度では拾いきれない「より高い次元の生活機能」を、短時間でスクリーニングする目的で開発されました。IADL(手段的 ADL)5 項目・知的能動性 4 項目・社会的役割 4 項目の計 13 項目で、地域在住高齢者の自立度やフレイル兆候の把握に用いられます。回答は本人または面接聴取で実施でき、数分〜10 分程度で完了します。
ベースラインの全体把握だけでなく、サブスケール単位の変化が臨床解釈に有用です。たとえば「IADL は保たれる一方で社会的役割が低下」なら、活動範囲や参加の縮小が示唆されます。退院前評価や在宅支援の初期アセスメント、地域包括ケアでの継続モニタリングに適します。
項目構成と採点(0/1 二値・合計 0–13)
各項目は「できる/している」を 1 点、「できない/していない」を 0 点で採点します。合計 0–13 点に加え、3 つのサブスコア(IADL 0–5、知的能動性 0–4、社会的役割 0–4)を併記すると、強みと課題が明確になります。面接時は「普段どおりの暮らし」を基準に、補助具や家族支援の有無も確認して判断してください。
下表は代表的な項目の一覧と採点のポイントです。施設で用いる質問票の文言は院内で統一し、「できる能力」ではなく「実際にやっているか」に基づき評価します。詳細の運用ルールは測定者間で共有し、再現性を高めます(様式は院内マニュアルに転載可)。
| 領域 | 項目(例) | 採点の目安 |
|---|---|---|
| IADL(5) | バスや電車を使って外出する/食事の支度をする/日用品の買物をする など | 直近の通常生活で自立的に実施していれば 1、していなければ 0 |
| 知的能動性(4) | 新聞や本を読む/健康情報に関心を持つ/新しいことに挑戦する など | 継続的な実施・意欲が確認できる場合は 1 |
| 社会的役割(4) | 友人や近所づきあい/地域活動への参加/家族・社会での役割 など | 定期的な参加・役割がある場合は 1 |
判定の読み方(合計+サブスケール)
TMIG-IC は合計点だけでなく、領域別スコアと項目単位の所見が意思決定に直結します。たとえば IADL が保たれていても、知的能動性や社会的役割が低い場合は「活動の質・幅」の低下が背景にあり、外出機会や社会参加の設計が介入の主戦場になります。逆に IADL 低下が先行する場合は、移動能力・呼吸循環・実用手段の再設計が優先です。
長期フォローでは、在宅の活動頻度を追う FAI(Frenchay) を併用し、行為の「実施頻度」の変化も捉えると具体的なゴール設定につながります。ADL/IADL の全体像は ADL/IADL ガイド にも整理しています。
Lawton/FAI との使い分け
Lawton IADL は電話・買物・料理・洗濯・交通・服薬・金銭管理などの「家事・道具使用」を中心に把握するのに対し、TMIG-IC は IADL に加えて知的能動性・社会的役割まで包含します。退院支援や在宅での暮らし設計では、まず TMIG-IC で全体像→詳細の家事動作は Lawton IADL で深掘り、活動頻度の追跡は FAI を併用、という分担が実務的です。
回復期〜生活期のモニタリングでは、TMIG-IC のサブスコアで弱点領域を抽出し、必要に応じて個別尺度(バランス、持久力、認知)に接続します。
実施・記録のテンプレ(面接 5–10 分)
実施は静かな場所で、本人または家族への面接形式が基本です。導入で「普段どおりの暮らしを基準に答えてください」と伝え、過去 1–2 週間の実際の行動を想起してもらいます。各項目は 0/1 の二値で迅速に判定し、補助具や家族支援の有無をメモします。終了後は合計点とサブスコアを算出し、前回との比較や弱点領域をコメントします。
記録例:「TMIG-IC 13/13(IADL 5/5・知的能動性 4/4・社会的役割 4/4)。家事・外出・地域活動いずれも自立。次回は活動頻度の変化を FAI で追跡。」/「TMIG-IC 8/13(IADL 3/5・知的能動性 2/4・社会的役割 3/4)。買物・交通が不安定のため、移動訓練と買物代行の併用を提案。」
よくある誤り(OK/NG 比較)
TMIG-IC は「能力」ではなく日常での実施を問う点が重要です。下表を用いて採点のバラつきを抑え、チーム内で判断基準を統一しましょう。
| 場面 | OK | NG/要修正 | 理由/対策 |
|---|---|---|---|
| 基準 | 「実際にやっているか」で 0/1 | 「やろうと思えばできる」で 1 | 過大評価 → 実施頻度にも触れて確認 |
| 期間 | 直近 1–2 週間の通常生活で判断 | 特別なイベント日で判断 | 代表性が低い → 期間を明示して質問 |
| 支援 | 家族・道具の支援の有無を記録 | 支援ありでも 1 にしてしまう | 条件不一致 → コメントで支援条件を併記 |
| 解釈 | 合計+サブスコアで弱点を抽出 | 合計点だけで判断 | 介入に落ちない → 領域別に目標化 |
まとめ
老研式IADL(TMIG-IC)は、3 領域 13 項目で高次生活機能を短時間に可視化できる尺度です。臨床では合計点+サブスコア+項目コメントで運用し、Lawton/FAI との分担で取りこぼしを防ぎます。本稿のテンプレと OK/NG 表を院内マニュアルへ転用すれば、評価の再現性と説明の質が同時に上がります。
|
Lawton IADL|評価用紙・点数・解釈 家事・道具使用の詳細把握に。 |
FAI(Frenchay)|頻度でみるIADL 在宅活動の「頻度」変化を追跡。 |
よくある質問(FAQ)
Q. 面接は本人・家族どちらに聞けばいい?
A. 原則は本人ですが、記憶があいまいな場合は家族の補助情報を加えて判断します。どちらに聴取したかは記録に明記してください。
Q. 合計点の基準値はありますか?
A. 集団では高得点に偏りやすい傾向が知られます。臨床では合計点の絶対値よりも、サブスコアの組み合わせと継時変化に重きを置いてください。
Q. Lawton/FAIと重複しませんか?
A. 目的が異なります。TMIG-IC は高次機能の全体像、Lawton は家事など IADL の詳細、FAI は在宅活動の頻度追跡に強みがあります。
参考文献
- Koyano W, Shibata H, Nakazato K, Haga H, Suyama Y. Measurement of competence: reliability and validity of the TMIG Index of Competence. Arch Gerontol Geriatr. 1991;13(2):103–116. DOI
- Koyano W, et al. The TMIG Index of Competence(13 項目・分布). Jpn J Public Health. 1993. PubMed
- Tomioka K, et al. Social participation and IADL using the 5-item TMIG-IC subscale. PLoS One. 2016;11(10):e0165103. PMC
- Kawai H, et al. Aging trajectories of TMIG-IC subscales. Geriatr Gerontol Int. 2024. PMC
- Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist. 1969;9(3):179–186. PubMed