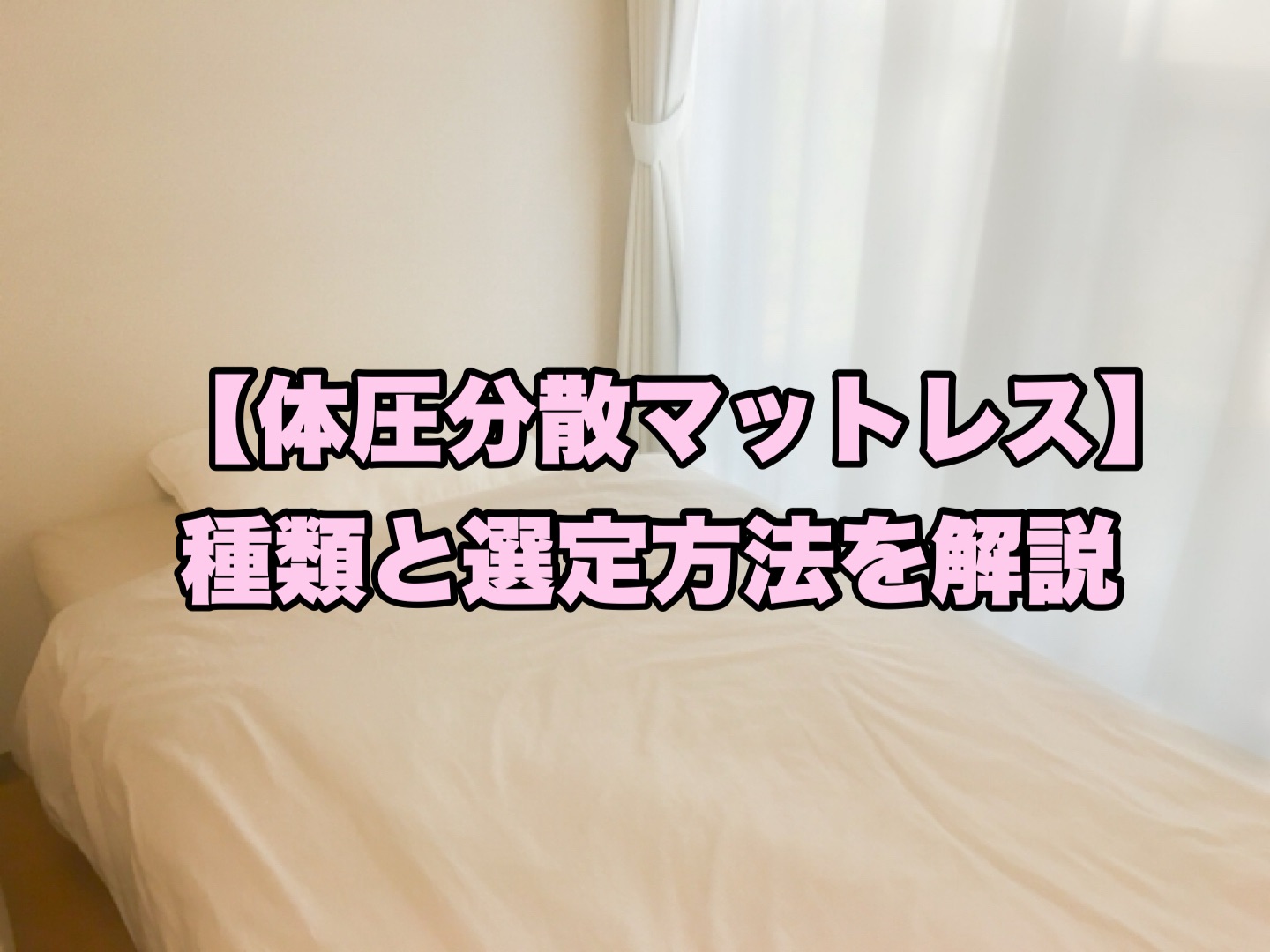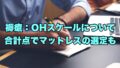体圧分散マットレスの種類と選び方|褥瘡(床ずれ)予防と離床を両立する理学療法士の視点
結論:体圧分散マットレスは「種類から選ぶ」のではなく、褥瘡リスク(皮膚)× 体動(寝返り)× 介助体制(夜間)× 離床目標から逆算して選ぶと失敗しにくいです。理学療法士( PT )は褥瘡予防だけでなく、マットレスが起き上がり・端座位・呼吸・睡眠に与える影響まで含めて「予防」と「離床」を両立させます。
体圧分散マットレス(医療用の支持面)は、骨突出部への圧集中と、同一部位への持続圧を減らすための用具です。メカニズムは大きく 2 つで、①圧の再分配(接触面積を広げるフォーム等の reactive surface)と、②圧の時間的移動(交互圧・自動体位変換など active surface)が中心となります。国際ガイドラインでは「圧再分配・摩擦/ずれの低減・マイクロクライメイト(温湿度)管理」を満たす支持面を、患者のリスクに応じて選択することが推奨されています。
| まず見る条件 | 推奨(目安) | PT のチェックポイント |
|---|---|---|
| 自力体位変換あり/離床を優先したい | 静止型(フォーム/ゲル等:reactive) | 沈み込み過多で起き上がりが崩れないか/端座位で滑り座りが増えないか |
| 自力体位変換が乏しい/高リスク | 交互圧(エア:active) | 体幹の揺れ・睡眠の質・呼吸パターン/エア圧・サイクル設定の妥当性 |
| 夜間の体位変換が回らない/介助負担が大きい | 自動体位変換付き(active) | 傾斜角度・サイクルで疼痛/めまい/覚醒が増えないか |
本稿では、フォーム/交互圧/自動体位変換付きといった体圧分散マットレスの種類と特徴を整理し、Braden スケールなどのリスク評価から、離床・環境調整までを一連の臨床フローとして解説します。褥瘡予防の全体像(皮膚観察→リスク評価→除圧/体位変換→寝具→栄養→再評価)を先に確認したい場合は、褥瘡予防の基本フロー(総論)も併読すると判断がぶれにくくなります。
定義と基本メカニズム
体圧分散用具は「支持面と接触する単位体表面が受ける圧力を軽減する用具」と定義されます。臥位では特殊寝台用マットレス・上敷き・交換用マットレス、座位では車いすクッションなどが該当し、ウレタンフォーム、ゲル、エア、ウォーターなど多様な材質が用いられます。
狙いは、点でなく面で支えることで局所圧を下げることに加え、時間的に圧を動かし、皮膚血流が回復する「オフ」の時間を確保することです。臨床運用では、皮膚所見・睡眠の質・離床時の安定性を総合して評価し、マットレスの種類や設定(圧・サイクル・傾斜)を動的に調整します。高機能なマットレスが常に最善とは限らず、「リスク・活動性・介助体制」に対して過不足がないことが選定の基本方針になります。
体圧分散マットレスの主要タイプと使い分け早見表
ここでは成人の褥瘡リスク管理を想定し、体圧分散マットレスの代表的な種類(フォーム/交互圧/自動体位変換付き)を比較します。フォームは reactive support surface、交互圧・自動体位変換は active support surface に相当します。
| タイプ | メカニズム | 適応の目安 | メリット | 留意点 |
|---|---|---|---|---|
| 静止型(フォーム/ゲル等) | 面で支え圧再分配(フォーム密度・多層構造など) | 自発的体位変換あり・軽〜中等度リスク( Braden 中等度以上で検討) | 電源不要・静音・故障リスクが少ない・メンテナンス容易 | 長時間同一体位では圧集中が残るため、定期的な体位変換は必須 |
| 交互圧(エアマットレス) | セルの膨張収縮により圧の時間的移動を繰り返す | 自力体位変換が乏しい・中等度〜高リスク(創部・易損性皮膚などを含む) | 同一部位への持続圧を避けやすく、高リスク患者の褥瘡予防に有効 | 電源・作動音・故障時の停止リスクあり。沈み込み過多による ADL・呼吸への影響に注意 |
| 自動体位変換付き | 交互圧に加え、傾斜/側方移動などで体位そのものを変化 | 夜間の体位変換が困難・介助負担が大きい・非常に高リスクの症例 | 夜間介助負担の軽減。マンパワーが限られた場面でも高リスクに対応 | 高価・大型で設置条件を要する。音や振動による睡眠障害、めまいや疼痛の訴えに留意 |
選び方(理学療法士の臨床フロー)
体圧分散マットレスを「種類から選ぶ」のではなく、「評価から逆算して選ぶ」ことが重要です。具体的には ①褥瘡リスク評価( Braden 等で層別化)、②活動性と自力体位変換(寝返り・起き上がり・ベッド上座位の可否)、③夜間マンパワー(スタッフ配置・家族介護力)、④既存マットレスでの問題点(疼痛・皮膚所見・睡眠障害・離床動作の安定性)、⑤リスクと目標に合ったタイプ選択の順で検討します。
フォームのみで十分なケースも多く、「リスクは高くないが体幹が不安定」「離床リハビリを優先したい」といった症例では、沈み込みの少ないフォームマットレス+ポジショニングで対応した方が、歩行練習や呼吸リハと両立しやすいこともあります。一方、体動が乏しく高リスクな症例では、交互圧や自動体位変換を早期から併用し、皮膚所見を定期的にチェックしてフィードバックすることが PT の役割です。
理学療法士が押さえたい評価とフォローのポイント
マットレスの種類によって、リハビリ場面で観察すべきポイントも変わります。フォームでは「沈み込み過多による起き上がり困難」「端座位での骨盤後傾・滑り座り」を、交互圧では「ポンプ作動時の体幹揺れによる平衡障害」「エア圧変化に伴う呼吸パターンの変化」などを確認します。自動体位変換付きでは、傾斜角度とサイクルが疼痛・めまい・睡眠の質に与える影響の聴取が欠かせません。
リハスタッフが関与できるのは「導入前の評価」「導入直後のフィッティング」「離床プログラムとの調整」「多職種カンファレンスでの情報共有」です。看護師・栄養士・医師と連携し、体重変化や浮腫、鎮静レベルの変化に応じてマットレス種別や設定を見直すことで、「褥瘡予防」「離床促進」「睡眠の質」のバランスを取りやすくなります。
よくある失敗と対策(離床が進まない/褥瘡リスクが下がらない)
上位を狙うなら、現場の詰まりどころを「原因→対策」に落とし込むとページ価値が上がります。以下は、 PT が遭遇しやすい失敗パターンと修正の方向性です。
| 起きやすい問題 | 主な原因 | まずやる対策 | 記録ポイント |
|---|---|---|---|
| 起き上がりが急に難しくなった | 沈み込み過多/身体が谷に落ち、体幹回旋が作れない | 静止型へ変更または硬さ調整、ベッド背上げ時の骨盤位置を再設定 | 起き上がり所要時間、介助量、骨盤後傾の増減 |
| 交互圧で体幹が揺れて不安定 | サイクル・圧設定が過剰/体幹支持が不足 | 圧とサイクルを緩和、体幹支持のポジショニングを追加 | ふらつき、恐怖感、端座位到達の可否 |
| 褥瘡リスクが下がらない | 支持面だけで解決しようとしている/体位変換・ずれ対策が不足 | 体位変換計画の再設計、ずれの評価とスライディング対策を同時に実施 | 発赤の部位・持続、ずれ徴候、体位変換実施率 |
| 眠れない/夜間覚醒が増えた | 作動音・振動/傾斜変化による不快 | 夜間設定の調整、必要最小限の active に絞る | 夜間覚醒回数、日中の傾眠、せん妄兆候 |
導入・見直しのチェックリスト( 5 分)
- 皮膚:骨突出部の発赤、圧痕、びらん、疼痛(持続時間を含む)
- 体動:寝返りの可否、同一体位の持続、介助量の変化
- 離床:起き上がり・端座位の安定、滑り座り、立ち上がり準備動作
- 呼吸:胸郭の可動性、努力呼吸の増減、体位変化での呼吸苦
- 睡眠:覚醒回数、作動音・振動の訴え、日中の傾眠
この 5 点を「導入前→導入直後→ 48–72 時間後」でそろえて比較すると、支持面が合っているかを短時間で判断しやすくなります。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
交互圧(エアマットレス)は「動ける人」にも使っていいですか?
使えますが、優先順位は「褥瘡リスク」と「離床目標」のバランスで決めます。寝返りが可能で離床を強く進めたい症例では、沈み込みや体幹の揺れが動作学習を邪魔することがあります。まずは静止型(フォーム等)を基準に、皮膚所見・体動・夜間体位変換の実施状況をみて不足があれば交互圧へステップアップする考え方が安全です。
自動体位変換付きは「体位変換が不要」になりますか?
不要にはなりません。自動体位変換は夜間の介助負担軽減に有用ですが、体位変換の目的は「圧のオフ」だけでなく、ずれの管理、皮膚観察、疼痛・不快の調整も含まれます。自動設定は「チームの体位変換計画の一部」として扱い、皮膚所見や睡眠の質に合わせて設定を見直す運用が前提です。
エア圧やサイクルは誰が決めますか?PT は関与できますか?
施設ルールにより担当は異なりますが、 PT は「離床動作の安定」「呼吸」「睡眠」への影響を評価できるため、設定調整の根拠を提示しやすい職種です。導入前後で所見をそろえて記録し、カンファレンスで共有すると、設定の最適化が回りやすくなります。
フォームだけで運用する場合、何が抜けやすいですか?
「体位変換の頻度」と「ずれ対策」が抜けやすいです。フォームは圧再分配に優れますが、同一体位が長いと圧集中は残ります。体位変換計画と、背上げ時の滑り・骨盤後傾など“ずれ”の要因を同時に点検することで、褥瘡予防と離床の両方が安定します。
おわりに
体圧分散マットレスの選び方は、「種類の知識」だけでなく、褥瘡リスク・活動性・介助体制・離床目標を一体として考えることがポイントです。まずはフォームマットレスを基準に、リスクが高い・自力体位変換が乏しい・夜間の体位変換が困難といった条件が揃ったときに、交互圧や自動体位変換付きへのステップアップを検討します。
運用は「皮膚所見の確認→設定とポジショニング→離床の段階づけ→記録→再評価」というリズムで回すと、導入して終わりになりません。チームで同じ観察軸を共有しながら、予防と離床の“ちょうどいい”落としどころを作っていきましょう。
参考文献
- EPUAP/NPIAP/PPPIA. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries – International Guideline(2019)Support Surfaces 章. PDF
- Guideline Governance Group. Support Surfaces — International Guideline(更新:2025-02-25). Link
- 日本皮膚科学会. 褥瘡診療ガイドライン 第 3 版(2023). J-STAGE
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下