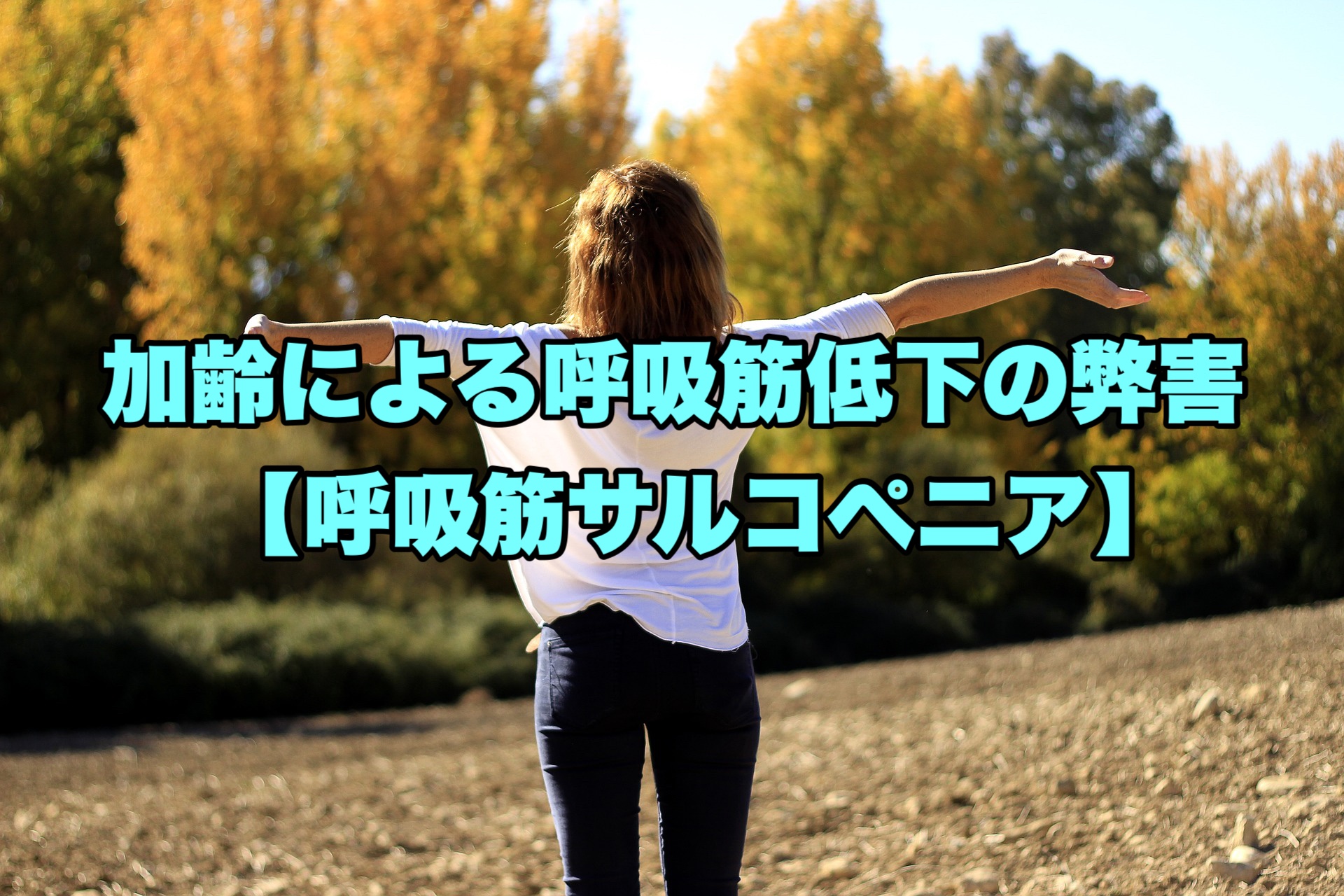呼吸筋サルコペニアとは(要点)
呼吸筋サルコペニアは、呼吸筋力の低下と呼吸筋量の低下が同時に進行する状態です。診断は possible → probable → 確定 の段階付けで整理され、筋力は MIP / MEP、筋量は 横隔膜超音波 や CT などで評価します。高齢者や慢性呼吸器疾患では、息切れや咳嗽力低下の背景に隠れていることが多く、早期から「呼吸筋サルコペニアの疑い」として拾う視点が重要です。
臨床では、まず 簡便な呼吸筋指標でスクリーニングし、疑わしい症例に対して MIP / MEP や 横隔膜エコー で確定評価へ進む二段構えが実用的です。安静時 SpO₂ や歩行距離だけで判断すると見逃しやすいため、「咳が弱い」「深呼吸が浅い」「吸気で肩がすくむ」といったベッドサイド所見も合わせて拾います。
加齢で何が落ちるか(スクリーニングの着眼点)
加齢に伴い、MIP / MEP の系統的低下に加えて、PEFR / CPF の低下や横隔膜厚さ変化率( thickening fraction:TF )の低下が生じます。絶対値だけで一喜一憂するよりも、同一条件・同一手順での縦比較と、息切れ・咳嗽・誤嚥などの症状や ADL と統合して解釈することがポイントです。
横隔膜 TF はカットオフがいくつか報告されていますが、研究間のばらつきが大きく個人差もあります。現場では「入院時からどれくらい変化したか」「急性増悪後にどこまで戻ったか」といった推移を重視し、測定条件をぶらさないことを最優先にします。
評価フロー(簡便 → 確定 → 統合)
まずは ①簡便指標( PEFR / CPF、発声持続時間、SNIP など )で「怪しいかどうか」をふるい分け、陽性所見が出たら ②確定評価( MIP / MEP、横隔膜エコー )につなげます。最後に ③症状・機能(息切れ、咳嗽、活動量、 ADL )と統合して「今の課題は筋力なのか、筋量 / 動員なのか、併存要因なのか」を整理すると、介入がぶれにくくなります。
続けて読む:呼吸・運動耐容能の評価ハブ
現場の詰まりどころ:簡便指標だけで安心して確定評価に進まない/逆に MIP / MEP だけで全体像を決めてしまう、の 2 パターンが多いです。簡便 → 確定 → 統合の 3 段階をワンセットで運用します。
| 指標 | 主目的 | 現場の使いどころ |
|---|---|---|
| PEFR / CPF | 咳流量・排痰力の推定 | 感染期の重症化リスク把握、補助排痰法の要否判断、見守り強度の調整 |
| SNIP | 吸気筋力の簡便推定 | MIP 低値時に「努力不足か、本当に弱いのか」を見極める補助 |
| MIP / MEP | 呼吸筋力の標準評価 | IMT 初期負荷の設定、縦比較の基準化、方針転換の判断材料 |
| 横隔膜 US(厚さ・ TF ・可動性) | 筋量・機能の複合評価 | 廃用や病態変化のモニタリング、介入反応の見立て、説明材料 |
測定のコツ(再現性を出すチェック)
| 評価 | 統一する条件 | つまずきやすい点 | 対策(声かけ / 手順) |
|---|---|---|---|
| MIP / MEP | 体位(端座位 / 半座位)、鼻クリップ、マウスピース密閉、休憩 | リーク、努力が出ない、反復で疲労 | デモ→練習→本番の順、3 〜 5 回で最良値、試行間に十分休む |
| SNIP | 同側鼻孔、姿勢、装着、試行回数 | 「思い切り吸う」が伝わらず浅い努力になる | 「鼻で勢いよくスッと吸う」を具体化、最初の数回は学習として扱う |
| 横隔膜 US | 肋間、プローブ角度、呼吸相(吸気末 / 呼気末)、保存方法 | 毎回場所がずれて TF がぶれる | 同じ肋間・同じ角度で固定、画像保存+数値記録をセットで残す |
記録の最小セット(カルテに残す型)
数値だけを残すと「次回比較できない」「介入の根拠にならない」ことが起きやすいです。数値+条件+妥当性+次アクションを 1 セットで記録すると、チームで共有しやすくなります。
| 項目 | 記録例 | ポイント |
|---|---|---|
| 測定条件 | 半座位、鼻クリップ使用、試行 5 回、休憩 60 秒 | 縦比較の再現性が上がる |
| 筋力(MIP / MEP) | MIP:○○、MEP:○○(最良値) | 採用値(最良値 / 平均)を固定 |
| 簡便指標 | PEFR / CPF:○○、SNIP:○○ | 確定評価へ進む根拠になる |
| 横隔膜 US | 厚さ:吸気末 ○○ / 呼気末 ○○、TF:○○ | 画像保存の有無も残す |
| 症状・機能 | 息切れ( Borg ○ )、咳嗽弱く痰貯留あり、 ADL:○○ | 数値と臨床像をつなぐ |
| 次アクション | IMT 開始(負荷 ○○)、再評価は 1 週後 | 介入設計の一貫性が出る |
介入:IMT(吸気筋トレーニング)の実践方針
標準的な例としては、30 呼吸 × 1 〜 2 セット / 日、週 5 〜 7 日、6 〜 8 週程度の継続が目安です。初期は 30 〜 50% PImax から開始し、主観的強度は RPE 4 〜 6(ややきつい〜きつい)を目安に、週単位で負荷を漸増します。歩行訓練・下肢筋力トレーニング・排痰法・栄養介入と組み合わせて、全身持久力の底上げにつなげます。
よくある失敗は、「 IMT デバイスを渡しただけで終わる」「負荷を見直さない」ことです。週 1 回は筋力( MIP / MEP )と症状(息切れ、痰、活動量)を確認し、負荷・頻度・セット数を微調整します。
安全管理(禁忌・中止基準)
呼吸筋トレーニングは基本的に安全性が高い一方、状態によっては「始めない」「その日は中止する」の判断が必要です。開始前に禁忌ラインを共有しておくと、現場で迷いにくくなります。
| 区分 | 例 | 現場の対応 |
|---|---|---|
| 禁忌(原則開始しない) | 不安定狭心症、最近の心筋梗塞など不安定な循環器疾患、急性呼吸不全、原因不明の急性胸痛、治療未調整の重度高血圧 など | 主治医へ確認し、代替介入(姿勢・呼吸介助・活動量調整)を先行 |
| 中止(その場で止める) | 著明な息切れ、胸痛、失神前駆、強いめまい、新規の不整脈所見、患者が「これ以上は無理」と訴える | バイタル確認→安静、再開条件をチームで合意 |
| 一時中断(調整して再開) | SpO₂ の急激な低下(例: 4 ポイント以上)、過換気、強い咳込みで続行困難 | 負荷・呼吸数・休憩を調整し、別日に再評価 |
現場の詰まりどころ(よくある失敗と対策)
| つまずき | 起きやすい原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 簡便指標だけで止まる | 「低い / 高い」で安心してしまう | 簡便 → 確定 → 統合の 3 段階を明文化し、陽性時の次アクションを固定 |
| MIP / MEP の値が毎回ぶれる | 体位・リーク・説明が毎回違う | 測定条件(体位、鼻クリップ、試行回数、休憩)をテンプレ化して記録 |
| IMT の負荷が上がらない | 週次の見直しがない | 週 1 回の再評価( MIP / 症状 / RPE )をルーチン化し、漸増ルールを共有 |
| 「数値は改善したが ADL が変わらない」 | 介入が呼吸筋だけに偏る | 歩行・下肢筋力・排痰・栄養を組み合わせ、アウトカム(活動量 / ADL )を同時に追う |
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. MIP / MEP がうまく取れません(努力が出ない・リークする)。どうしますか?
まず「体位」「鼻クリップ」「マウスピースの密閉」「デモ → 練習 → 本番」の順番を統一します。それでも努力が出にくい場合は、短い努力で実施しやすい SNIP を併用して「努力不足か、本当に弱いのか」を見立て、後日に再測定できる条件(疲労・不安・疼痛)を整えます。
Q2. どのタイミングで「確定評価(MIP / MEP・横隔膜 US)」に進めばいいですか?
簡便指標( PEFR / CPF、発声持続、 SNIP )やベッドサイド所見(咳が弱い、深呼吸が浅い、息切れが強い)で「疑い」が立った時点で、確定評価へ進むのが実用的です。見逃しやすいのは「 SpO₂ は保たれているが咳嗽力が弱い」ケースなので、症状と指標をセットで判断します。
Q3. IMT はどれくらいの頻度で見直せばいいですか?
目安として週 1 回、筋力( MIP など )と症状(息切れ、痰、活動量)と主観的強度( RPE )を確認し、負荷やセット数を微調整します。「実施できているか」だけでなく、「同じ負荷が楽になっていないか」を確認すると、漸増の判断がしやすくなります。
Q4. 横隔膜 US はカットオフよりも推移を重視していいですか?
はい。研究間で手技や対象が異なるため、臨床では同一条件での縦比較が特に重要です。肋間・角度・呼吸相を固定し、画像保存と数値(厚さ、 TF )をセットで残すと、変化の解釈がぶれにくくなります。
おわりに
呼吸筋サルコペニアは「数値を測って終わり」ではなく、拾う → 確かめる → 介入を設計する → 同じ条件で再評価するというリズムで回すほど、見逃しや介入の迷いが減っていきます。明日からは、まず測定条件の統一と記録テンプレ化から始め、必要に応じて IMT と全身運動・排痰・栄養を組み合わせていきましょう。
面談準備チェックと「職場の評価シート」もまとめて整えたい方は、マイナビコメディカルのダウンロードも合わせて活用してみてください。
参考文献
- Sato S, et al. Geriatr Gerontol Int. 2023;23:5–15. PMID / DOI
- Laveneziana P, et al. Eur Respir J. 2019;53:1801214. DOI
- Boussuges A, et al. Front Med. 2021;8:742703. Full text
- Langer D, et al. Phys Ther. 2015;95:1264–1273. Link
- Vázquez-Gandullo E, et al. Int J Environ Res Public Health. 2022;19:5564. Link
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下