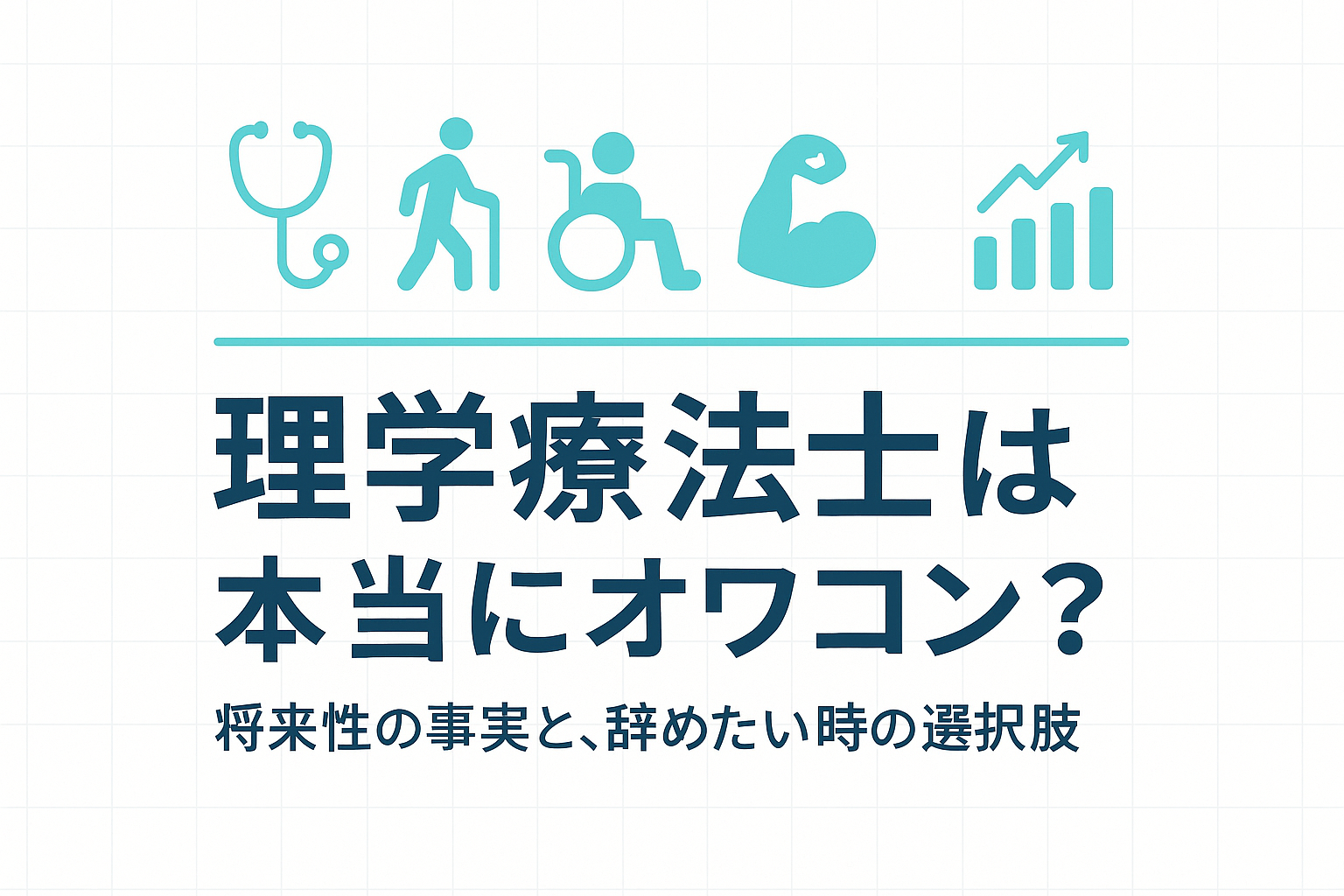ICARS の評価方法| 0 〜 100 点の見方と採点のコツ、SARA との使い分け
ICARS( International Cooperative Ataxia Rating Scale )は、小脳性運動失調を「姿勢・歩行/四肢協調/構音/眼球運動」の 4 領域で整理し、合計 0 〜 100 点として重症度を定量化するスケールです。点数が高いほど重症の方向で解釈します。 [oai_citation:0‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9094050/?utm_source=chatgpt.com)
本記事は、ICARS を現場で“回せる形”にするために、(1) 点数の読み方、(2) ブレを減らす標準化、(3) よく割れるポイントの対策を実務寄りにまとめます。運動失調スケール全体の選び方は、先にこちらで整理しています(関連:運動失調の評価まとめ|ICARS・SARA・BARS の選び方)。
転職で「評価が回る職場」を探す(無料)| PT キャリアガイド
いつ使う?ICARS と SARA の使い分け
ICARS は網羅性が高く、初回評価や方針決定(入院時/外来初診/装具・補助具変更前後など)で「どこが主因で崩れているか」を分解して説明しやすいのが強みです。 [oai_citation:1‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9094050/?utm_source=chatgpt.com)
一方で、頻回の再評価(外来フォローなど)では、短時間で回しやすい SARA を併用すると運用が安定します。実務の型は「初回=ICARS」「経過=SARA」「イベント(転倒/薬剤変更/用具変更)時に ICARS を差し込む」です。 [oai_citation:2‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16769946/?utm_source=chatgpt.com)
スコアの構造| 4 下位尺度( 0 〜 100 点 )の読み方
ICARS は合計点だけで終わらせず、「どの下位尺度が増えたか」をセットで読むのがコツです。合計点は“結論”、内訳は“介入ターゲット”になります。 [oai_citation:3‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9094050/?utm_source=chatgpt.com)
とくに臨床では、点数の変化だけでなく「同じ条件で取れているか」が解釈を左右します。補助具・介助量・靴・指示文・休息ルールが変わったら、点数より先に“条件差”を記録しておくとブレの原因が追えます。 [oai_citation:4‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16450347/?utm_source=chatgpt.com)
| 下位尺度 | 見ている機能(要約) | 配点(満点) | 点が増えやすい場面(例) |
|---|---|---|---|
| 姿勢・歩行 | 立位・歩行の安定性、移行・方向転換、環境適応 | 0 〜 34 | 狭路・段差、停止、方向転換でふらつく |
| 四肢協調 | 到達の正確性、反復・交互運動、速度の一貫性と協調 | 0 〜 52 | 終末の過不足、リズムの乱れ、疲労で破綻 |
| 構音 | 発話の明瞭性、テンポ・抑揚の乱れ | 0 〜 8 | 長文・早口で聞き取りにくい |
| 眼球運動 | 注視、追従、素早い視線移動の正確性 | 0 〜 6 | 注視が保てない、追従が途切れる |
下位尺度別:判定の観点と観察ポイント(実務版)
ここでは設問本文の転載を避け、臨床での観察テーマに置き換えて整理します。再評価の精度は「同条件で取れるか」で決まるため、補助具・介助量・靴・指示文・デモ回数・休息ルールを、先に“固定ルール”として決めます。 [oai_citation:5‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16450347/?utm_source=chatgpt.com)
また ICARS は項目の重なりがあり、境界ケースで評価者間のズレが起こりやすい点が指摘されています。迷った場面は動画・録音を残し、チームで“同じ場面を見て合意”を作ると、次回から一気にブレが減ります。 [oai_citation:6‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16450347/?utm_source=chatgpt.com)
姿勢・歩行(小計 0 〜 34 )
| 見る場面(テーマ) | 判定の観点 | 観察ポイント(コツ) | 記録に残す一言(例) |
|---|---|---|---|
| 静的保持(座位・立位) | 支持の要否/動揺の大きさ/保持の持続 | 足幅・足部位置・上肢ポジションを固定して比較 | 「支持なしで 10 秒保持可、動揺は中等度」 |
| 移行・方向転換 | 立ち上がりの一貫性/回旋時の逸脱/停止の確実性 | 反復で“ばらつき”を見る( 3 回程度 ) | 「方向転換で失歩あり、停止で 1 歩追加」 |
| 直線・狭路・段差 | 歩隔/左右差/路面適応/介助の必要度 | 同じ距離・同じ環境で再現(床材や照明も意識) | 「狭路で逸脱 2 回、段差は介助必須」 |
四肢協調(小計 0 〜 52 )
| 見る場面(テーマ) | 判定の観点 | 観察ポイント(コツ) | 記録に残す一言(例) |
|---|---|---|---|
| 到達の正確性(上肢) | 狙いのズレ/終末の過不足/反復での崩れ | ターゲット位置を固定、テンポは一定(メトロノームが便利) | 「終末で過大 3/10 回、後半で増加」 |
| 反復・交互運動 | リズムの乱れ/切替の遅れ/誤動作 | 短時間で区切って休息を固定し、疲労の影響を切り分ける | 「切替が遅れ、 5 回目以降でリズム崩れ」 |
| 下肢協調と体幹 | 軌跡の安定/速度の一貫性/体幹代償 | 注視点を一定にし、必要なら動画で再評価の再現性を上げる | 「軌跡が波打つ、体幹側屈で代償」 |
構音(小計 0 〜 8 )
| 見る場面(テーマ) | 判定の観点 | 観察ポイント(コツ) | 記録に残す一言(例) |
|---|---|---|---|
| 明瞭性とテンポ | 聞き取りの困難さ/区切り/話速の揺れ | 短文→長文で負荷を上げ、録音で“再評価の耳”を統一 | 「長文で明瞭性低下、テンポの揺れあり」 |
眼球運動(小計 0 〜 6 )
| 見る場面(テーマ) | 判定の観点 | 観察ポイント(コツ) | 記録に残す一言(例) |
|---|---|---|---|
| 注視・追従・視線移動 | 注視の破綻/追従の途切れ/過少・過大 | 頭部をできるだけ固定し、目標の距離と速度を一定にする | 「追従が途切れ、注視保持が不安定」 |
実施フロー(当日の回し方)
ICARS は“評価者の段取り”が点数の再現性に直結します。先に安全と標準化のルールを決めてから実施すると、時間もブレも減ります。 [oai_citation:7‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16450347/?utm_source=chatgpt.com)
コツは「固定できるものを固定し、固定できないものは“変更あり”として残す」ことです。結果の解釈が楽になり、次回の再評価設計にもそのまま使えます。
- 事前説明:目的(全体像/経過)と所要時間、転倒予防の方針を共有
- 安全設定:介助配置、補助具、靴、休息タイミングを先に決める
- 指示文を統一:デモの有無、反復回数、テンポ(速度)を固定
- 実施:姿勢・歩行 → 四肢協調 → 構音 → 眼球運動(各セクションで小休止)
- 記録:小計 → 合計、逸脱要因(疼痛/眠気/薬剤変更/装具変更)を所見に残す
現場の詰まりどころ(よくある失敗と対策)
ICARS で詰まりやすいのは「点数が動いたのに理由が追えない」「時間がかかりすぎる」「評価者で点が割れる」の 3 つです。対策は“条件の固定”と“境界ケースの合意”に集約されます。 [oai_citation:8‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16450347/?utm_source=chatgpt.com)
特に ICARS は項目の重なりによる評価の矛盾が指摘されているため、迷いやすい場面ほど“短い所見”を残し、次回の同条件につなげるのが実務的です。 [oai_citation:9‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16450347/?utm_source=chatgpt.com)
| 詰まりどころ | なぜ起きる? | その場の対策 | 記録の工夫 |
|---|---|---|---|
| 再評価で点が動いたが理由が不明 | 補助具・靴・介助量・指示文が固定されていない | 条件を先に揃え、揃えられない要因は「変更あり」として扱う | 「補助具/靴/介助量/指示文」の 4 点セットを毎回書く |
| 時間がかかりすぎる | 反復回数が多い/休息ルールがない/順番がぶれる | 反復は最小限、セクション間休息を固定し、順番をテンプレ化 | 所要時間と「中断理由」を残して次回の設計に使う |
| 評価者で点が割れる | 観察ポイントの言語化不足/境界の合意がない | 動画・録音で“同じ場面を見て合意”を作る | 境界ケースを院内メモに蓄積し、判定の軸を更新する |
| 疲労で後半だけ悪化する | 持続性の影響が混ざり、純粋な協調性を評価しにくい | 短時間で区切り、休息を固定して“疲労の影響”を切り分ける | 「前半/後半で差あり」を明記し、介入の狙いに変換する |
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
ICARS と SARA は、同日にどう使い分けますか?
初回は ICARS で「どの領域が主因か」を分解し、同日に SARA を短時間で回して“経過で追いやすい指標”を決めると運用が安定します。以後は SARA を定期フォローにして、症状変化が大きい時だけ ICARS を差し込む設計が回しやすいです。 [oai_citation:10‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16769946/?utm_source=chatgpt.com)
再評価の頻度はどれくらいが目安ですか?
外来では 4 〜 8 週ごと、病棟では週 1 回程度が回しやすい目安です。転倒、感染、薬剤調整、装具・補助具の変更など“条件が変わった時”は、できるだけ同条件で早めに再評価します。
点数が上がった(悪化した)時、まずどこを見直しますか?
まずは条件差(靴、補助具、介助量、指示文、疲労、疼痛、眠気)を確認します。そのうえで小計(姿勢・歩行/四肢協調/構音/眼球運動)のどこが増えたかを見て、狙いを「転倒予防」なのか「上肢の作業性」なのかに落とし込みます。 [oai_citation:11‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16450347/?utm_source=chatgpt.com)
ICARS の“評価者で割れやすい”問題はどう対策しますか?
境界ケースは、同じ場面を動画で共有して“院内の基準”を作るのが最短です。ICARS は項目の重なりによる矛盾が指摘されているため、迷う場面ほど「どこが崩れたか(所見)」を短文で残し、次回の同条件につなげるとズレが減ります。 [oai_citation:12‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16450347/?utm_source=chatgpt.com)
おわりに
ICARS は「安全の確保 → 条件の統一 → 段階的に課題を提示 → 小計と合計を記録 → 同条件で再評価」という“評価のリズム”を作ると、チームでの共有が一気に楽になります。初回で全体像を揃え、フォローは短時間の指標で回す設計にすると、忙しい現場でも評価が続きます。
あわせて、面談準備のチェックと職場評価シート(ダウンロード)を使って、学びやすい環境づくりも進めたい方は マイナビコメディカル(面談準備チェック/職場評価シート) も活用してみてください。
参考文献
- Trouillas P, Takayanagi T, Hallett M, et al. International Cooperative Ataxia Rating Scale for pharmacological assessment of the cerebellar syndrome. J Neurol Sci. 1997;145(2):205-211. doi: 10.1016/S0022-510X(96)00231-6 / PubMed: 9094050. [oai_citation:13‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9094050/?utm_source=chatgpt.com)
- Schmitz-Hübsch T, du Montcel ST, Baliko L, et al. Scale for the assessment and rating of ataxia: development of a new clinical scale. Neurology. 2006;66(11):1717-1720. doi: 10.1212/01.WNL.0000219042.60538.92 / PubMed: 16769946. [oai_citation:14‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16769946/?utm_source=chatgpt.com)
- Schmitz-Hübsch T, du Montcel ST, Baliko L, et al. Reliability and validity of the International Cooperative Ataxia Rating Scale: a study in 156 spinocerebellar ataxia patients. Mov Disord. 2006;21(5):699-704. doi: 10.1002/mds.20781 / PubMed: 16450347. [oai_citation:15‡movementdisorders.onlinelibrary.wiley.com](https://movementdisorders.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mds.20781?utm_source=chatgpt.com)
- Storey E, Tuck K, Hester R, Hughes A, Churchyard A. Inter-rater reliability of the International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS). Mov Disord. 2004;19(2):190-192. doi: 10.1002/mds.10657 / PubMed: 14978674. [oai_citation:16‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14978674/?utm_source=chatgpt.com)
- Cano SJ, Hobart JC, Hart PE, Korlipara LV, Schapira AHV, Cooper JM. International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS): appropriate for studies of Friedreich’s ataxia? Mov Disord. 2005;20(12):1585-1591. doi: 10.1002/mds.20651 / PubMed: 16114019. [oai_citation:17‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16114019/?utm_source=chatgpt.com)
- Schmahmann JD, Gardner R, MacMore J, Vangel MG. Development of a brief ataxia rating scale (BARS) based on a modified form of the ICARS. Mov Disord. 2009;24(12):1820-1828. doi: 10.1002/mds.22681 / PubMed: 19562773. [oai_citation:18‡movementdisorders.onlinelibrary.wiley.com](https://movementdisorders.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.22681?utm_source=chatgpt.com)
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下