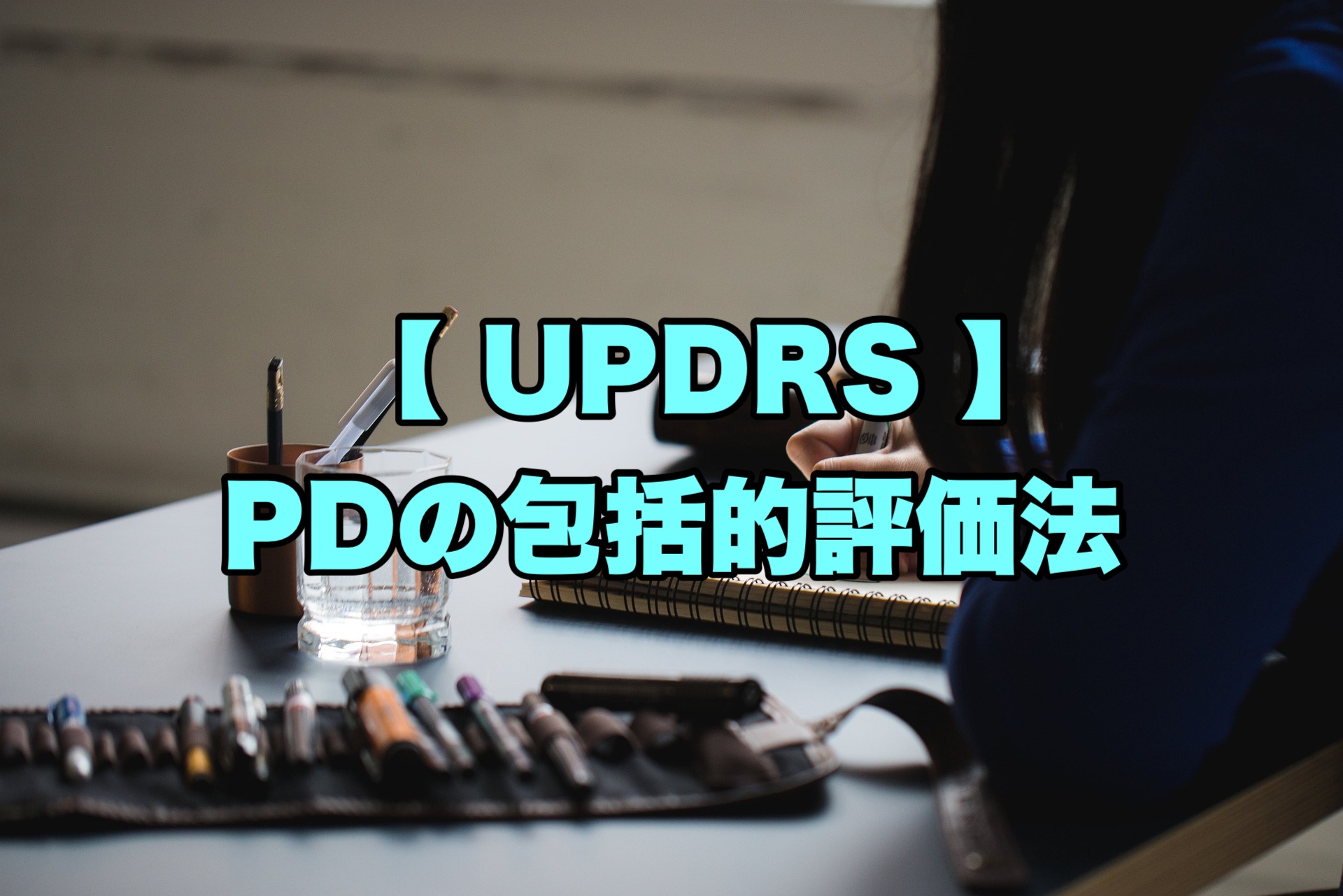MDS-UPDRS と UPDRS の違い(まず結論)
MDS-UPDRS は、旧 UPDRS を臨床実装しやすく改訂した包括スケールです。いちばん大きい違いは、0–4 の判定基準(アンカーポイント)が明確になり、再現性と変化検出が上がったこと。さらに Part の意味づけが整理され、非運動( Part I )・運動 EDL( Part II )・運動診察( Part III )・運動合併症( Part IV )の読み方が揃えやすくなりました。
なお読み方は、UPDRS(ユー・ピー・ディー・アール・エス)、MDS-UPDRS(エム・ディー・エス・ユー・ピー・ディー・アール・エス)が一般的です。改訂の原典は Goetz ら( 2008 ) を参照してください。
UPDRS と MDS-UPDRS の違い(早見表)
| 観点 | UPDRS | MDS-UPDRS |
|---|---|---|
| パート構成 | Part I〜IV(非運動/日常/運動診察/合併症) | Part I〜IV( I = 非運動 EDL、 II = 運動 EDL、 III = 運動診察、 IV = 運動合併症 ) |
| 採点レンジ | 0–4 だが基準がやや曖昧 | すべて 0–4 で定義が明確(アンカーポイントが厳密) |
| 回答様式 | 面接・観察が中心 | 自己記入(該当部)+面接・観察を組み合わせ |
| 評価用紙・日本語版 | 歴史的に広く用いられるが、新規導入は減少傾向 | MDS 公式サイトから申請のうえ入手(日本語版も用意) |
| 臨床での推奨 | 既存コホートや古い報告で利用 | 現行標準(研究・縦断評価で利用が主流) |
評価の全体設計(病期 → 症状定量 → QOL )を先に押さえたい場合は、パーキンソン病の理学療法評価【一覧と使い分け】に全体像をまとめています。
MDS-UPDRS の評価条件と再現性アップのコツ
- 薬剤状態( ON/OFF ):どちらの状態で評価するかを事前に決め、評価時刻と服薬時刻を毎回記録します。治療反応の確認では両条件の比較も有効です。
- 刺激治療:DBS などの設定や有無を明記します。再プログラミング直後はスコア変動に注意します。
- 補助具:Part III は原則「能力」を評価します。杖・歩行器・装具の使用有無を記録し、同条件で再評価します。
- 所要時間:初回は 20〜30 分、運用が整えば 10〜15 分程度まで短縮できます。自己記入部分の活用が鍵です。
- 導線固定:椅子・歩行路・指タップのスペースを固定し、日内・日差のばらつきを抑えます。
重症度の共有には Hoehn & Yahr、出口指標には PDQ 系( PDQ-8 / PDQ-39 など )を併用すると、介入目標の優先順位づけがしやすくなります。
MDS-UPDRS 評価のやり方(手順書フロー)
- 準備( 2 分 ):ON/OFF、補助具、DBS の状態を確認しカルテへ記載します。評価スペース(椅子・歩行路・回転スペース・安全確保者)を整えます。
- 説明( 1 分 ):評価の目的・所要時間・途中休憩が可能であることを説明し、「普段どおりの動作」でよいことを強調します。
- 自己記入と面接( Part I/II の補助; 3〜5 分 ):自己記入(該当部)を進めてもらい、面接で具体例を引き出します(過去 1 週間の頻度・困りごと)。介護者からの情報も併せて整理します。
- 運動診察( Part III; 7〜15 分 ):代表的タスクを決めた順番で連続実施します。各タスクの声かけ・観察ポイント・安全対策は下表を参照し、左右差・代償の有無を記録します。
- 合併症の確認( Part IV; 2〜3 分 ):日内の波、wearing-off、dyskinesia の持続時間と支障度を分けて把握します。睡眠・幻覚・抑うつなど他の症状も整理します。
- 集計と共有( 2 分 ):パート別合計と所見を集計し、介入目標(転倒・すくみ・服薬調整など)を患者と共有します。変化量は次回以降の説明資源にもなります。
運動診察タスク別の評価ポイントと安全管理
| タスク | セットアップ | 声かけ例 | 観察ポイント(例) | 安全対策 |
|---|---|---|---|---|
| 発語・表情 | 静かな環境、検者と正面向かいの座位 | 「普段どおりに話してください。笑顔もお願いします。」 | 声量・明瞭さ、単調さ、表情の乏しさ、口唇舌の可動 | 嚥下評価は別の手順で実施 |
| 上肢反復運動(例:指タップ) | 肘を体側に近づけ座位、前腕は机上で安定 | 「できるだけ大きく・速く・一定のリズムで続けてください。」 | 振幅の減少、途中での減速や停止、リズムの乱れ、側差 | 疲労時はこまめに休憩 |
| 前腕回内外(回内回外) | 肘屈曲 90°、前腕前方で手掌を下にして開始 | 「手のひらを返す動きを繰り返してください。」 | 可動域、速度、途中の減速、左右差 | 椅子は背もたれ付き、足底接地で安定 |
| 下肢反復運動(例:つま先タップ) | 座位、膝 90°、足底接地 | 「つま先を持ち上げて下ろす動きを続けてください。」 | 振幅、速度、減衰、左右差 | 滑りやすい床材を避ける |
| 椅子からの起立 | 肘掛けなし椅子、足底接地、後方に十分なスペース | 「普段どおりに座位から立ち上がってください。」 | 準備動作、立ち上がり時間、代償(手支え)の有無 | 後方保護者 1 名、周囲に障害物なし |
| 歩行(回転を含む) | 直線 6〜10 m、回転スペースを確保 | 「普段の速度で歩き、向こうで向きを変えて戻ってください。」 | ストライド、腕振り、前傾、回転時のすくみ・歩幅低下 | 歩行路は混雑禁止、側方・後方の保護を確保 |
| 姿勢反射(引き戻し試験) | 立位、後方に十分なスペース(ベッドやマット等) | 「今から軽く後ろへ引きます。準備はいいですか?」 | 反応の有無、ステップ数、保護要否 | 二人体制(後方と側方)、転倒リスクが高い場合は環境優先 |
| 姿勢・体幹 | 立位・座位を通して観察 | 「普段どおりの姿勢で楽に立ってください。」 | 前屈、側弯、前傾の程度、軀幹の柔らかさ | 長時間立位は避け、椅子をすぐ使える位置に配置 |
| 振戦(安静/姿勢/動作時) | 安静座位、上肢挙上、指鼻運動など条件を切り替え | 「力を抜いて楽にしてください。次に腕を前に伸ばしてください。」 | 部位、振幅、持続、誘発される条件 | 長時間の保持は避け、随時休憩 |
上記は代表例です。施設の標準手順に従い、回数や時間設定は院内で統一してください(例:一定回数・一定時間など)。
声かけスクリプト集(短く・迷わない例文)
- 共通冒頭:「普段どおりにお願いします。疲れたらいつでも休憩できます。」
- 反復運動:「できるだけ大きく・速く・一定のリズムで続けてください。」
- 歩行:「普段の速度で歩き、向こうで向きを変えて戻ってください。」
- 引き戻し試験:「今から軽く後ろへ引きます。準備はいいですか?」
よくある評価ミスと対策(早見)
| よくあるミス | 起きやすい理由 | 対策(運用ルール) |
|---|---|---|
| ON/OFF が混在する | 服薬・診療予定で評価時刻が毎回ズレる | 評価時刻と服薬時刻をテンプレに固定し、次回も同条件で実施 |
| 評価順序が毎回違う | 担当者や場所が変わる | タスク順を固定(上肢 → 下肢 → 体幹 → 歩行 → 回転 → 姿勢反射) |
| 代償・補助具の記録漏れ | スコアに集中して条件メモが抜ける | 手支え・補助具・介助量を必ず 1 行で併記(同条件で再評価) |
| 安全管理が甘い | 診察タスクが流れ作業になる | 姿勢反射は二人体制をルール化し、環境(スペース・マット)を優先 |
集計シートと評価用紙の運用
パート別合計や ON/OFF 条件、補助具の有無を整理するために、集計用シート(A4/HTML)のような「記録補助」を用意しておくと、情報共有と再評価がスムーズになります。
評価は公式版の評価用紙に従い、院内では「入手 → コピー管理 → 評価後の保管(スキャン等)」までの流れを決めておくと、スコアの再確認や多職種共有が安定します。
FAQ:UPDRS/MDS-UPDRS でよくある疑問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. 旧 UPDRS と MDS-UPDRS、どちらを使うべきですか?
新規に導入する施設では MDS-UPDRS で統一するのが実務的です。縦断評価(経過)を揃えやすく、近年の研究でも標準的に用いられています。旧 UPDRS は、過去データとの比較が必要な場面で補助的に位置づけると整理しやすくなります。
Q2. 評価は薬の ON/OFF どちらで行いますか?
目的に合わせて選び、毎回同じ条件で再評価することが重要です。治療反応をみる場合は両条件の比較も有用なので、評価メモに「評価時刻・服薬時刻・ON/OFF」をセットで残すとブレが減ります。
Q3. 日本語版の MDS-UPDRS はどこから入手できますか?
公式版・日本語版は Movement Disorder Society( MDS )の公式サイトから申請のうえ入手します。用途(臨床/研究)で手続きが異なる場合があるため、最新の案内を確認してください。
Q4. 所要時間を短縮するコツはありますか?
自己記入(該当部)の事前準備、評価スペースと導線の固定、評価順序のテンプレ化で 10〜15 分程度まで短縮できます。病棟内で「誰が行っても同じ流れになるチェックリスト」を共有しておくと、若手の習熟にも役立ちます。
参考文献
- Goetz CG, Tilley BC, Shaftman SR, et al. Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale ( MDS-UPDRS ): Scale presentation and clinimetric testing results. Movement Disorders. 2008;23(15):2129–2170. doi:10.1002/mds.22340
- Movement Disorder Society. MDS-Unified Parkinson’s Disease Rating Scale ( MDS-UPDRS ). MDS 公式サイト
- Hoehn MM, Yahr MD. Parkinsonism: onset, progression and mortality. Neurology. 1967;17(5):427–442. PubMed:6067254
- Jenkinson C, Fitzpatrick R, Peto V, et al. The PDQ-39: development and validation. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997;67:308–312. PubMed:9351479
おわりに
MDS-UPDRS は「安全の確保 → 条件固定( ON/OFF・補助具・環境 )→ スコア記録 → 再評価」のリズムを崩さないほど、臨床の判断が速くなります。まずは Part ごとの意味をそろえ、同じ条件での変化を説明できる形に整えてみてください。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下