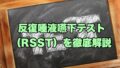改訂水飲みテスト/水飲みテストの使い方( MWST・WST )|やり方・評価・中止基準
結論:「改訂水飲みテスト( MWST:3 mL )→(安全域が確認できた場合のみ)水飲みテスト( WST:30 mL )」の順に、少量から段階的に安全域を確認します。どちらも確定診断ではなくスクリーニングなので、「試してよいか/やめるか」を素早く判断し、危険サインがあれば中止して精査( VE/VF など)へ切り替えます。
MWST/WST は不顕性誤嚥を 1 本で拾い切れません。 RSST、湿性嗄声、呼吸状態、既往(脳卒中・COPD・気管切開など)や栄養状態と合わせて総合判断し、必要に応じて VE/VF に速やかにつなぐ前提で運用します。
スクリーニングと精査の関係(迷わない並べ方)
基本は「低負荷→高負荷」の順です。少量( MWST )で危険が出るのに、いきなり 30 mL( WST )を試すとリスクが上がります。
- 安全確認:意識・呼吸・体位の確保(必要なら「今日はやらない」を選ぶ)。
- RSST:空嚥下がそもそも成立するか(準備性の確認)。
- MWST( 3 mL ):むせ/湿性嗄声/呼吸切迫を見ながら 1–5 点で段階評価。
- WST( 30 mL ): MWST で安全域が確認できた場合のみ(少しでも不安なら中止して精査へ)。
改訂水飲みテスト( MWST )の使い方|やり方と評価
改訂水飲みテスト( Modified Water Swallowing Test: MWST )は、冷水 3 mLを口腔内へ注入し、嚥下反応とリスクサイン(むせ・湿性嗄声・呼吸切迫など)を 1〜5 点で段階評価するベッドサイドのスクリーニングです。
少量で実施できる一方、 MWST 単独で不顕性誤嚥を否定できないため、結果は「安全域の目安」として扱い、臨床情報と組み合わせて記録・共有します。
改訂水飲みテストのやり方(実施手順)
準備物:シリンジ(またはスポイト)、冷水、ストップウォッチ(反復嚥下確認用)、パルスオキシメータ(可能なら)。
- 体位:基本は座位。困難ならギャッジアップ位で頭頸部を軽く前屈(安全を最優先)。
- シリンジで冷水 3 mLを準備。
- 口腔底へゆっくり注入(舌背へ勢いよく当てない)。
- 「ごっくんと飲んでください」と指示し、嚥下の有無・タイミング・むせ・湿性嗄声・呼吸状態を観察。
- 必要に応じて反復嚥下を促し、 30 秒以内に 2 回可能かを確認。
- 最大 2 回まで繰り返し、最も低い点を MWST スコアとして記録(体位・水温・性状も併記)。
改訂水飲みテストの評価・判定基準( 1〜5 点 )
スマホ閲覧では横にスクロールできます。
| 点数 | 内容(要点) | 次の判断 |
|---|---|---|
| 1 | 嚥下なし、むせ・呼吸切迫あり(強い誤嚥疑い) | 中止 → 精査( VE/VF など) |
| 2 | 嚥下あり、呼吸切迫あり(不顕性誤嚥も含め高リスク) | 中止 → 精査( VE/VF など) |
| 3 | 嚥下あり、呼吸良好だがむせまたは湿性嗄声 | 原則中止(臨床情報で精査優先) |
| 4 | 嚥下あり、呼吸良好、むせ・嗄声なし | 状況により次段階( WST )検討 |
| 5 | 4 の条件に加え、 30 秒以内に反復嚥下 2 回可能 | 次段階( WST )を検討しやすい |
改訂水飲みテストの運用のコツ(記録で差がつく)
- 水条件:原則は冷水。常温/とろみ水に変更した場合は必ず記録(同条件で再評価)。
- 観察ポイント:むせの有無だけでなく、湿性嗄声、呼吸数、努力呼吸、 SpO2 変化、反復嚥下の可否をセットで見る。
- 記録項目:体位、実施回数、各回の点数、咳・湿性嗄声、本人の訴え(つかえ感・嚥下痛など)。
- 限界:不顕性誤嚥は拾いにくい ⇒ ベッドサイド所見+精査へつなぐ前提で解釈。
よくある失敗(現場の詰まりどころ)
「点数は付けたが次の動きが揃わない」を避けるため、中止基準と申し送りをセット化しておくと安全です。
スマホ閲覧では横にスクロールできます。
| よくある失敗 | 起きること | 対策 | 記録のコツ |
|---|---|---|---|
| 体位が不安定なまま実施 | むせ・呼吸切迫が増え、再現性が落ちる | 座位優先/ギャッジ角度と頸部位置を固定 | 体位(角度)を必ず併記 |
| 注入位置が舌背寄り/勢いが強い | 咳反射が強く出て「評価」にならない | 口腔底へゆっくり注入、再現しやすい手技に統一 | 注入方法の工夫(スポイト等)もメモ |
| 「むせ」だけで判定する | 湿性嗄声・呼吸変化を見落とす | むせ+声質+呼吸(努力呼吸/ SpO2 )の 3 点セット | 湿性嗄声の有無を必ず書く |
| スコアは付けたが“次の一手”が曖昧 | スタッフごとに WST 実施や経口判断がブレる | 施設で「 1–3 は中止」「 4–5 は状況次第」など運用ルール化 | 中止理由と報告先を定型で残す |
とろみの分類(学会分類 2013:要約)
スマホ閲覧では横にスクロールできます。
| 段階 | 特徴(要点) | 現場メモ |
|---|---|---|
| 薄いとろみ | コップを傾けるとややゆっくり落ちる。細いストロー可。 | 「水より少し遅い」程度 |
| 中間のとろみ | スプーンで混ぜると跡が少し残る。ストローにはやや力が必要。 | 施設間でズレやすいので濃度は統一 |
| 濃いとろみ | まとまりがよく「食べる」動作が必要。ストロー不適。 | 誤嚥は減っても残留が増えることがある |
水飲みテスト( WST:30 mL )の使い方|やり方と評価
水飲みテスト( Water Swallowing Test: WST )は、水 30 mLを飲んでもらい、むせの有無・飲み方(分割か一気か)・所要時間を観察するスクリーニングです。 MWST より負荷が高いため、MWST で安全域が確認できた対象に限定し、少しでも危険兆候があれば中止して精査へ切り替えます。
「 WST を必ずやる」ではなく、「必要があるときに、やってよい条件が整っているか」を優先します。
水飲みテストのやり方(実施手順)
- 準備:常温の水 30 mL 、ストップウォッチ、安定した座位(またはギャッジアップ)。
- 「この水をいつものように飲んでください」と指示し、飲水開始と同時に計時。
- むせ、口唇からの流出、過度の慎重さ、湿性嗄声、呼吸状態の変化を観察しながら全量の飲水状況を記録。
- 危険サインがあれば直ちに中止(体勢確保・吸引準備・報告・精査へ)。
WST:プロフィール判定( 1〜5 )
スマホ閲覧では横にスクロールできます。
| プロフィール | 内容 | 解釈の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 一度でむせず全量を飲める | 所要時間も合わせて評価 |
| 2 | 2 回以上に分けるが、むせない | 慎重さ/体力低下の可能性 |
| 3 | 一度で飲めるが、むせる | 誤嚥リスクが高い |
| 4 | 2 回以上に分け、むせる | 誤嚥リスクが高い |
| 5 | むせ頻発で全量困難 | 中止 → 精査へ |
判定メモ:正常=プロフィール 1 かつ 5 秒以内/疑い=プロフィール 1 で 5 秒超 または プロフィール 2/異常=プロフィール 3–5 とされることが多いです。ただし年齢・基礎疾患・水量調整の可否などを踏まえた総合判断が必要です。
MWST/WST の禁忌・中止基準(安全第一)
「危険かもしれない」と思ったら、評価で押し切らず中止が最適解になる場面があります。施設のルールや主治医指示がある場合はそれを優先してください。
スマホ閲覧では横にスクロールできます。
| 区分 | 例 | その場の対応 | 次の一手 |
|---|---|---|---|
| 禁忌(原則やらない) | 明らかな意識障害(例: JCS 1 以上)、重度の呼吸切迫、安静時の激しい咳、座位保持が困難 | 評価を見送り、環境・全身状態の立て直し | チームで精査( VE/VF )や方針検討 |
| 中止(途中でやめる) | 明らかなむせ、チアノーゼ、吸気困難、湿性嗄声の増悪、 SpO2 低下(例: 90 % 未満を目安) | 体勢確保(側臥位・前屈など)、吸引準備、報告 | 精査へ切り替え/再評価条件の統一 |
| 慎重(条件付き) | 発熱・肺炎疑い、痰の増加、倦怠感が強い、強い不安・拒否 | 量・性状・タイミングを見直す(または延期) | 観察中心+必要時 VE/VF |
RSST・MWST・WST の違いと使い分け(要点比較)
「どれをやるか」より、「どこで止めるか」を事前に揃えると、チームの安全性が上がります。
スマホ閲覧では横にスクロールできます。
| 指標 | RSST | MWST | WST |
|---|---|---|---|
| 目的 | 嚥下反射の準備性 | 安全域の段階判定 | 飲水パターン+所要時間 |
| 方法 | 30 秒の空嚥下回数 | 冷水 3 mL(口腔底) | 水 30 mL を飲む(負荷が高い) |
| 判定の見方 | 回数低下で疑い | 1–5 点で段階評価 | プロフィール( 1–5 )+時間で総合 |
| 注意 | 触診・観察の熟練度に依存 | 不顕性誤嚥を拾いにくい | 誤嚥リスクが相対的に高い |
よくある質問( MWST/WST )
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
改訂水飲みテストは何点以上なら経口摂取を開始してよいですか?
一般に MWST で 4–5 点を安全域の目安とすることが多い一方、スコアのみで経口開始の可否を決めることは推奨されません。既往や認知・体力、呼吸状態、胸部所見、 RSST や他のスクリーニング結果と合わせて総合判断し、曖昧な場合は VE/VF による精査を優先します。
水飲みテスト( 30 mL )は嚥下評価で必ず実施すべき検査ですか?
WST は簡便ですが、 30 mL の飲水は負荷が高く、全例で必須という位置づけではありません。 MWST や RSST でリスクが高いと判断される症例では、無理に WST を行わず、ベッドサイドの観察と VE/VF を組み合わせた評価へ切り替える方が安全です。
MWST を「とろみ水」で実施してもよいですか?
施設や症例によっては、とろみ水で安全域を確認する運用が行われます。ただし「冷水 3 mL 」とは条件が変わるため、水温・性状・濃度を必ず記録し、再評価も同条件で比較してください。迷う場合は、ベッドサイドで無理に進めず精査( VE/VF )を優先します。
おわりに
実地では「安全の確保 → 姿勢・環境調整 → 段階的スクリーニング( RSST → MWST → 必要なら WST )→ 必要時 VE/VF で精査 → 再評価」というリズムを持っておくと、嚥下リスクの見落としを減らしつつ、チームで同じ基準を共有しやすくなります。
現場で困りやすいのは「点数」よりも「次の動き」です。中止基準と申し送り(誰に・何を・どの条件で)をセット化し、同じ条件で再評価できる形にしておくと、判断がブレにくくなります。
参考文献
- 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 医療検討委員会.摂食嚥下障害の評価 2019( PDF ).https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/assessment2019-announce.pdf
- 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 医療検討委員会.日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013.日摂食嚥下リハ会誌.2013;17(3):255–267.( PDF )https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf
- Nishiwaki K, Tsuji T, Liu M, Hase K, Tanaka N, Fujiwara T. Identification of a simple screening tool for dysphagia in patients with stroke using factor analysis of multiple dysphagia variables. J Rehabil Med. 2005;37(4):247-251. doi: 10.1080/16501970510026999. PMID: 16024482
- Brodsky MB, Suiter DM, González-Fernández M, et al. Screening Accuracy for Aspiration Using Bedside Water Swallow Tests: A Systematic Review and Meta-Analysis. Chest. 2016;150(1):148-163. doi: 10.1016/j.chest.2016.03.059. PMID: 27102184
- 才藤栄一.(解説)水飲みテスト( 30 mL / 3 oz など)の位置づけと注意点.医書.jp.doi: 10.32118/cr033090886