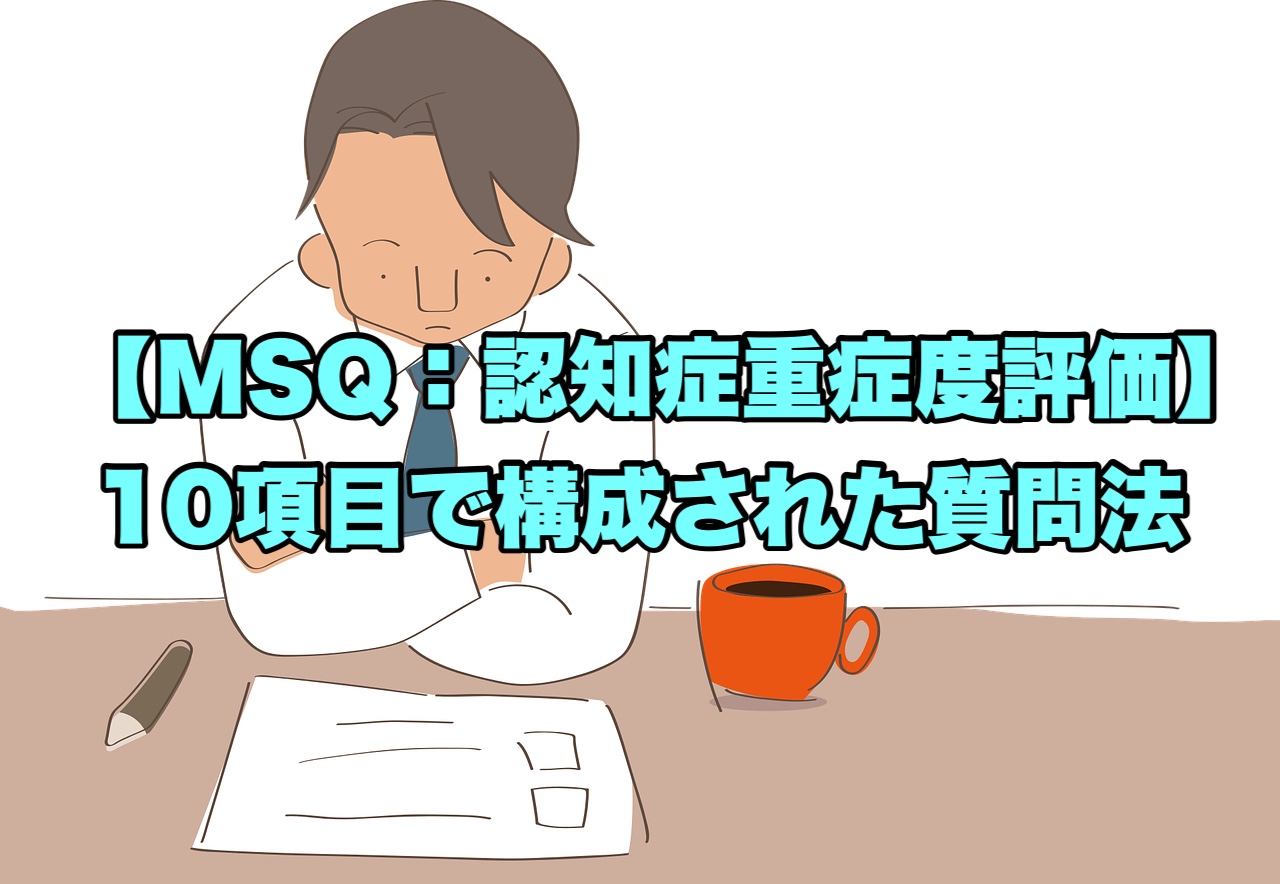MSQ(Mental Status Questionnaire)とは?【 10 項目の簡便スクリーニング 】
MSQ( Mental Status Questionnaire )は、Kahn らが 1960 年に報告した 10 項目の簡便な認知スクリーニングです。短時間で実施しやすい一方、環境・説明・再提示(ヒント)の扱いで結果がぶれやすいため、手順の一定化+実施条件の記録が運用の要点になります。
関連:認知機能評価の全体像(スクリーニング → 重症度 → BPSD )は 認知機能評価の選び方(総論) にまとめています。
MSQ の位置づけと注意点
MSQ は、回答から 誤答数 を把握し、認知機能低下の可能性を “拾う” ための古典的ツールです。現在の国内臨床では MMSE や HDS-R、CDR などの採用が中心ですが、「ベッドサイドで短時間に状態を確認したい」場面では MSQ が役立つことがあります。
ただし MSQ 単体での診断は行わず、他検査・全身状態・生活情報と統合して判断します。また「 MSQ 」という略称は他領域でも用いられるため、本記事では 認知スクリーニングとしての Kahn-Goldfarb 版 MSQ を扱います。混同しやすい SPMSQ( Pfeiffer, 1975 ) とは別の指標です。
印刷できる記録シート(質問文なし・記入式)
質問文の転載は行わず、質問内容は記入式にした A4 フォーマットを用意しました(採点欄・備考欄付き)。下のリンクからブラウザで開いて印刷できます。
- MSQ 実施記録シート( A4 ・印刷ボタン付き・ HTML ):こちらを開く
本記事では MSQ の質問文そのものは掲載せず、記入式の記録シートを前提に解説しています。質問文の確認や院内の教育では原著論文や既存の解説資料を参照してください。
実施手順(現場最適化のコツ)
- 環境整備:静かな場所で実施し、補聴器・眼鏡など通常使用の補助具は装着します。前置きは簡潔にし、注意が向く状態を作ります。
- 統一手順:説明・再提示・ヒントの扱いは施設内で統一し、再提示の有無を記録シートに明記します。
- 反応の取り扱い:曖昧な回答はそのまま記録し、面接者が意図を補完しないようにします。必要以上に粘らず、適切なところで次項目へ進みます。
- 安全面:せん妄が疑われる(急性発症・日内変動・注意障害など)場合は、別途 CAM などのプロトコルで確認します。
採点と所見のまとめ方( “ 点数だけ ” にしない)
基本は 誤答数(エラー数)の合計で把握します。MSQ は研究・運用により解釈が揺れるため、施設の運用基準か原著の記述に合わせて所見を付すとよいでしょう。
臨床では「点数」と同じくらい、実施条件(聞こえ・見え・眠気・疼痛など)と誤り方(見当識なのか注意なのか)が重要です。下の “最小セット” を残すと、経過観察や多職種カンファレンスで再解釈がしやすくなります。
| 項目 | 書き方(例) | ねらい |
|---|---|---|
| 実施条件 | 午前、病室、疼痛 NRS 2、眼鏡あり、補聴器なし | 点数の解釈を安定させる |
| 運用(再提示) | 再提示なし(施設ルール)/再提示あり( 1 回まで) | 再現性を確保する |
| 結果(要約) | 誤答 3、低下疑い。翌日同条件で再評価予定 | 次アクションに繋げる |
| 誤り方 | 日付の取り違え、場所は保たれる/注意が逸れやすい | 介入(指示・環境調整)に落とす |
現場の詰まりどころ(評価がぶれやすいポイント)
| よくある詰まり | 起こりやすい誤解 | 対策(その場) | 再評価のコツ |
|---|---|---|---|
| 感覚器の影響を見落とす | 認知症と早合点する | 補助具の確認、静穏化、話速・声量の調整 | 条件を固定して比較(時間帯も揃える) |
| 教育歴・文化差の影響 | 点数を機械的に解釈する | 誤答の “意味” を所見で補足する | カットオフ依存を避け、誤り方を追う |
| せん妄・抑うつ・全身状態 | 慢性的な認知低下と決めつける | 急性発症・日内変動・注意障害を確認する | 睡眠・バイタル・服薬と合わせて解釈する |
| 記録が断片的 | 点数の比較ができない | 実施条件+再提示+行動観察を最小で残す | 再評価の予定(いつ・何を揃えるか)まで書く |
MSQ と SPMSQ の違い(混同注意)
| 項目 | MSQ( Kahn-Goldfarb, 1960 ) | SPMSQ( Pfeiffer, 1975 ) |
|---|---|---|
| 設問数 | 10(原著から識別力の高い項目を抽出) | 10 |
| スコアの考え方 | 主に誤答数で把握(施設運用で解釈差あり) | 誤答数に基づく 定番カットオフ(教育歴で補正) |
| 教育歴補正 | 明確な補正式の定番はなし | あり(低学歴は +1、高学歴は −1 の補正が広く紹介) |
| 代表文献 | Kahn RL, 1960( PubMed ) | Pfeiffer E, 1975( PubMed ) |
| 比較研究 | Fillenbaum GG, 1980( MSQ と SPMSQ の比較)( PubMed ) | |
次に読む(小記事候補から 1 本)
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
MSQ は何分くらいで終わりますか?
患者さんの反応や説明の長さにもよりますが、準備が整っていれば 3〜5 分程度で終わることが多いです。再提示・説明の長さを統一し、記録シートに「再提示の有無」を残すと結果の比較がしやすくなります。
SPMSQ とどう違いますか?
両方とも 10 項目ですが、SPMSQ は教育歴補正と定番カットオフが広く紹介され、運用が標準化されています。MSQ は古典的で、研究・施設により解釈が揺れやすい点が特徴です。結果は MMSE・HDS-R・CDR など他検査と併せて解釈します。
質問文を掲載しないのはなぜ?
本記事では原著どおりの設問文を直接記載せず、記入式の記録シートで運用しています。質問文の確認や教育目的での利用には、原著論文や公表されている資料を参照してください。
MMSE や HDS-R、CDR とどう使い分けますか?
MSQ は短時間スクリーニングとして有用ですが、国内臨床では MMSE・HDS-R・CDR などの採用が中心です。疑い例では、いずれかの標準的ツールと併用し、睡眠・身体疾患・薬剤・感覚器障害・教育歴といった背景要因に注意して解釈します。
おわりに
MSQ は 10 項目で短時間に実施できる一方、感覚器・教育歴・全身状態などの影響を強く受けるスクリーニングです。手順の一定化 → 実施条件の記録 → 誤り方の観察 → 再評価の流れで運用すると、「スコアだけ」に振り回されにくくなります。
臨床のリズムは、条件の確認 → 段階的に実施 → 記録(条件も含む) → 再評価です。評価が噛み合わないときほど条件を揃えて取り直し、生活情報や他検査と統合して判断してください。
転職や職場環境の見直しを検討している方は、面談準備チェックや職場評価シートもまとめた マイナビコメディカル活用ガイド もあわせて参考にしてみてください。
参考文献
- Kahn RL, Goldfarb AI, Pollack M, Peck A. Brief objective measures for the determination of mental status in the aged. Am J Psychiatry. 1960;117:326-328. doi: 10.1176/ajp.117.4.326 / PubMed
- Pfeiffer E. A short portable mental status questionnaire for the assessment of organic brain deficit in elderly patients. J Am Geriatr Soc. 1975;23(10):433-441. doi: 10.1111/j.1532-5415.1975.tb00927.x / PubMed
- Fillenbaum GG. Comparison of two brief tests of organic brain impairment, the MSQ and the Short Portable MSQ. J Am Geriatr Soc. 1980;28(8):381-384. PubMed
- Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res. 1975;12(3):189-198. doi: 10.1016/0022-3956(75)90026-6 / PubMed
- Morris JC. The Clinical Dementia Rating( CDR ): current version and scoring rules. Neurology. 1993;43(11):2412-2414. doi: 10.1212/WNL.43.11.2412-a / PubMed
- Cummings JL, Mega M, Gray K, Rosenberg-Thompson S, Carusi DA, Gornbein J. The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia. Neurology. 1994;44(12):2308-2314. doi: 10.1212/WNL.44.12.2308 / PubMed
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下