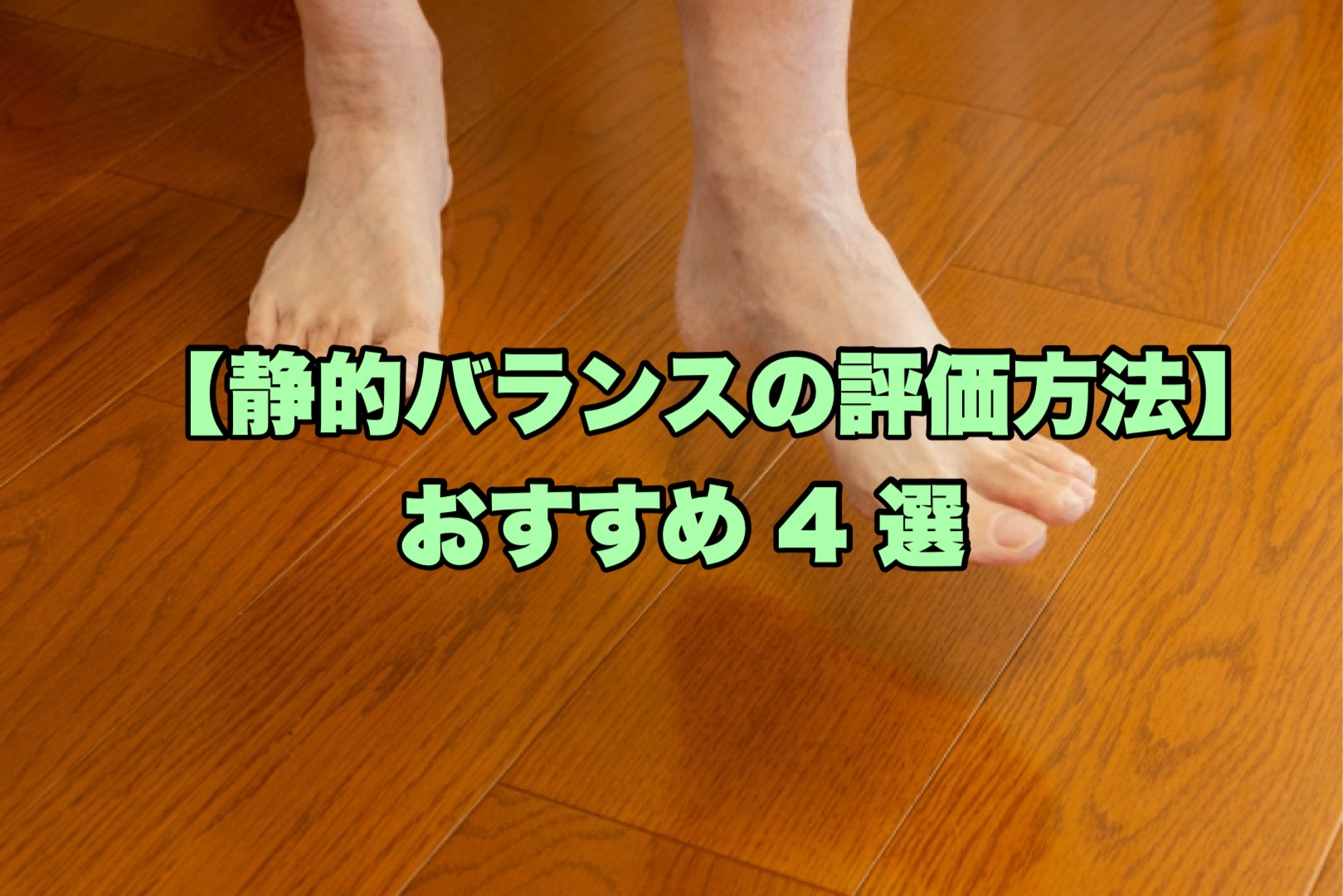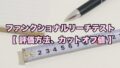静的バランスの評価:目的別の使い分けと臨床運用(直立検査/片脚立位/マン試験/ロンベルグ試験)
静的バランスは「立位姿勢を崩さず保つ力」です。本記事では、直立検査・片脚立位・マン試験(Mann 検査)・ロンベルグ試験の 4 法を、目的(転倒リスク抽出/深部覚・前庭・小脳の鑑別)に合わせて使い分ける手順と判定を整理します。安全準備→実施→判定→次アクションまでを 1 ページで確認できます。
静的バランスの評価方法(早見表+個別手順)
表はスマホで横にスクロールできます。
| 検査 | 姿勢・眼条件 | 保持時間・回数 | 終了条件 | 判定の観点 | 示唆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直立検査 | 両脚立位(足幅を段階的に狭小化)/開眼(必要時に閉眼比較) | 各足位で 20–40 秒の保持可否/可・不可 または段階評点 | 転倒危険・明らかな動揺・手離し | 足幅ごとの保持可否/保持時間/動揺 | 屋内=閉脚保持、屋外=継足保持の可否が歩行自立と関連 |
| 片脚立位 | 支持脚膝伸展・両手は腰/開眼で実施(必要時に閉眼) | 最大 120 秒で打切り/2 回まで実施し良い方を採用 | 足接触・足位置移動・手離し | 保持時間+フォーム逸脱 | 転倒リスク抽出(代表閾:5 秒など※文献差) |
| マン試験 | タンデム位(一直線/足尖と踵を接する)/開眼→閉眼 | 各 30 秒/左右を入れ替えて評価 | 足の位置ずれ・手離し・明らかな動揺 | 開閉眼差・左右差・動揺方向 | バランス限界の抽出(継足姿勢の耐性) |
| ロンベルグ | 閉脚立位/開眼→閉眼 | 各 30 秒(必要時に短縮) | 転倒リスク・著明動揺 | 閉眼で動揺増大=ロンベルグ徴候陽性 | 深部覚・前庭障害の示唆(小脳性は開閉眼とも動揺) |
直立検査(静的バランス|足幅・保持時間の評価)
準備:壁際/見守り者、滑り止めの床。
実施:足幅を 開脚 → 閉脚 → 継足 の順で段階的に狭め、各足位で20–40 秒の立位保持を観察(開眼。必要時に閉眼比較)。
判定:足位ごとの保持可否・保持時間・動揺。閉脚保持は屋内歩行、継足保持は屋外歩行の自立と関連が報告されています。
片脚立位(静的バランス|開眼基準・打切り・判定)
準備:壁際/見守り者配置、滑り止めの床、体調・血圧確認。
実施:両手は腰・支持脚膝伸展・挙上脚は非接触。開眼で 2 回まで実施し良い方を採用(長くできる場合は最長 120 秒で打切り)。
判定:保持時間とフォーム逸脱(足接触・位置移動・手離し)。
マン試験(静的バランス|タンデム位・開閉眼のやり方)
準備:一直線の床目印/壁際。
実施:タンデム位で開眼 30 秒→閉眼 30 秒。左右を入れ替えて同様に実施。
判定:開閉眼差・左右差・動揺方向を観察。
ロンベルグ試験(静的バランス|陽性の意味・鑑別)
準備:閉脚立位が安全にとれる広さ/壁際。
実施:閉脚立位で開眼 30 秒→閉眼 30 秒。
判定:閉眼で動揺増大または転倒=ロンベルグ徴候陽性(深部覚・前庭障害を示唆)。小脳性は開閉眼とも動揺。
安全管理と中止基準
- 環境:壁際・見守り者の配置、滑りにくい床/靴。
- 体調:めまい・悪心・疼痛・血圧異常・低血糖の疑いがあれば中止。
- 中止基準:転倒の危険を伴う動揺、顔面蒼白・冷汗、胸部症状、急激な血圧変動。
- 再評価:同一条件・同一時刻帯で再現性を担保(同一測定者が望ましい)。
判定から次アクションへ
直立検査・片脚立位・マン・ロンベルグで静的耐性と感覚寄与(視覚・前庭・固有感覚)を確認します。動揺増大の有無や方向、左右差を読み、歩行・方向転換・立ち上がりなど機能課題へ接続します。必要に応じて動的バランスの評価も追加しましょう(例:ファンクショナルリーチテスト(FRT))。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
片脚立位は何秒で「異常」と考えますか?
文献により閾値は異なります。例として片脚立位5 秒(開眼)をハイリスクの目安とする報告がありますが、年齢・対象背景・測定条件で変動します。施設基準を明示し、推移で判断するのが実務的です。
マン試験とロンベルグ試験の使い分けは?
マンは姿勢難度(タンデム)で限界を引き出す目的、ロンベルグは開閉眼差で深部覚・前庭・小脳の寄与を読む目的が中心です。両者を併用すると解釈が明瞭になります。
靴と裸足、どちらで測るべき?
転倒リスクが低い条件を優先します。施設 SOP に合わせ、靴底の滑りやすさが測定に影響する点に留意してください。再評価は同条件で行います。
参考文献
- 望月 久. バランス能力測定法としての直立検査. 理学療法—臨床・研究・教育. 2008;15:2–8. J-STAGE
- 日本理学療法士協会. 理学療法ガイドライン(13. 身体的虚弱). 公式PDF
- 日本整形外科学会. 運動器不安定症の診断基準. 公式ページ
- 村永 信吾, 平野 清孝, 田代 尚範. 高齢者の運動機能(健康増進)と理学療法. PTジャーナル. 2009;43(10):861–868.
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下