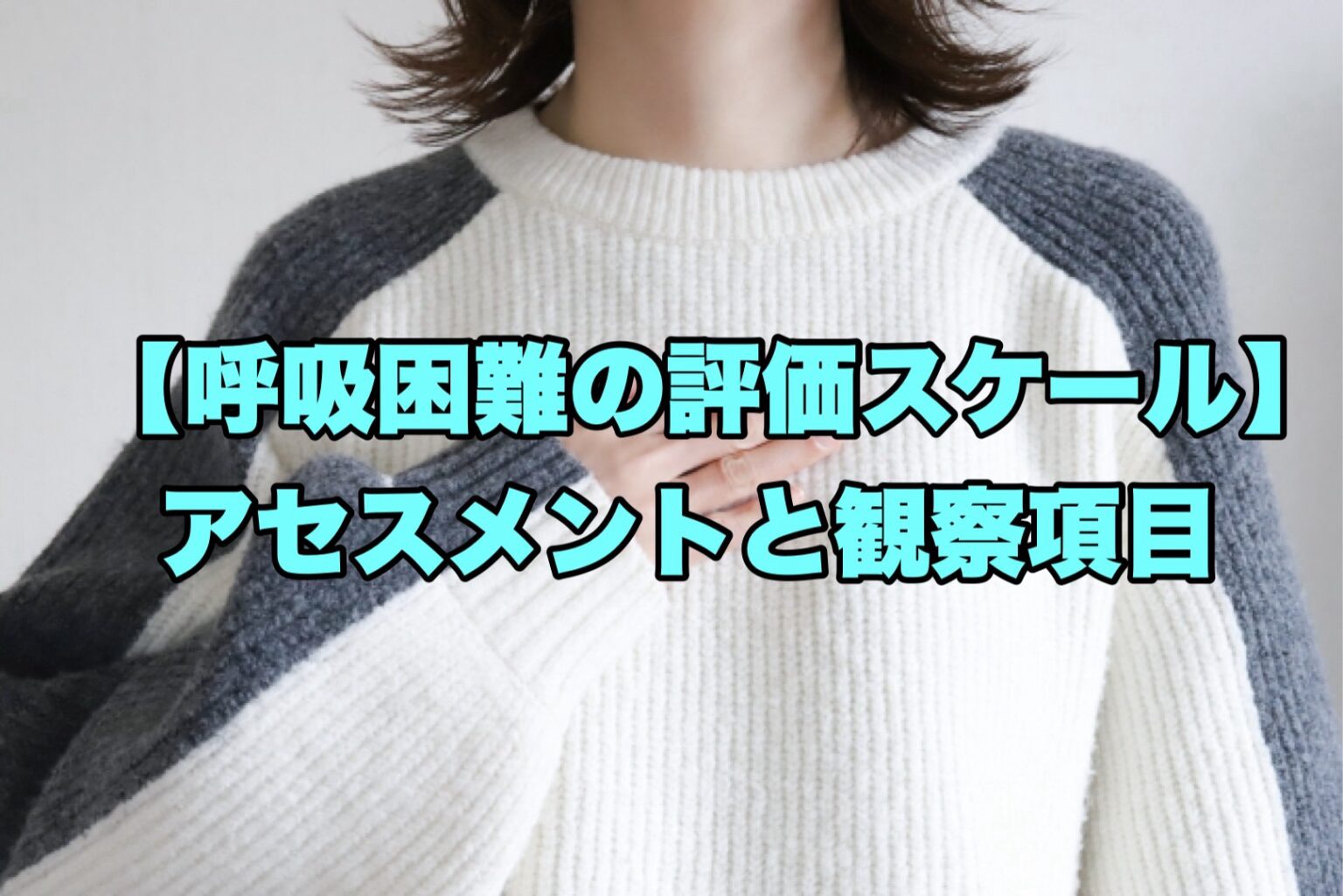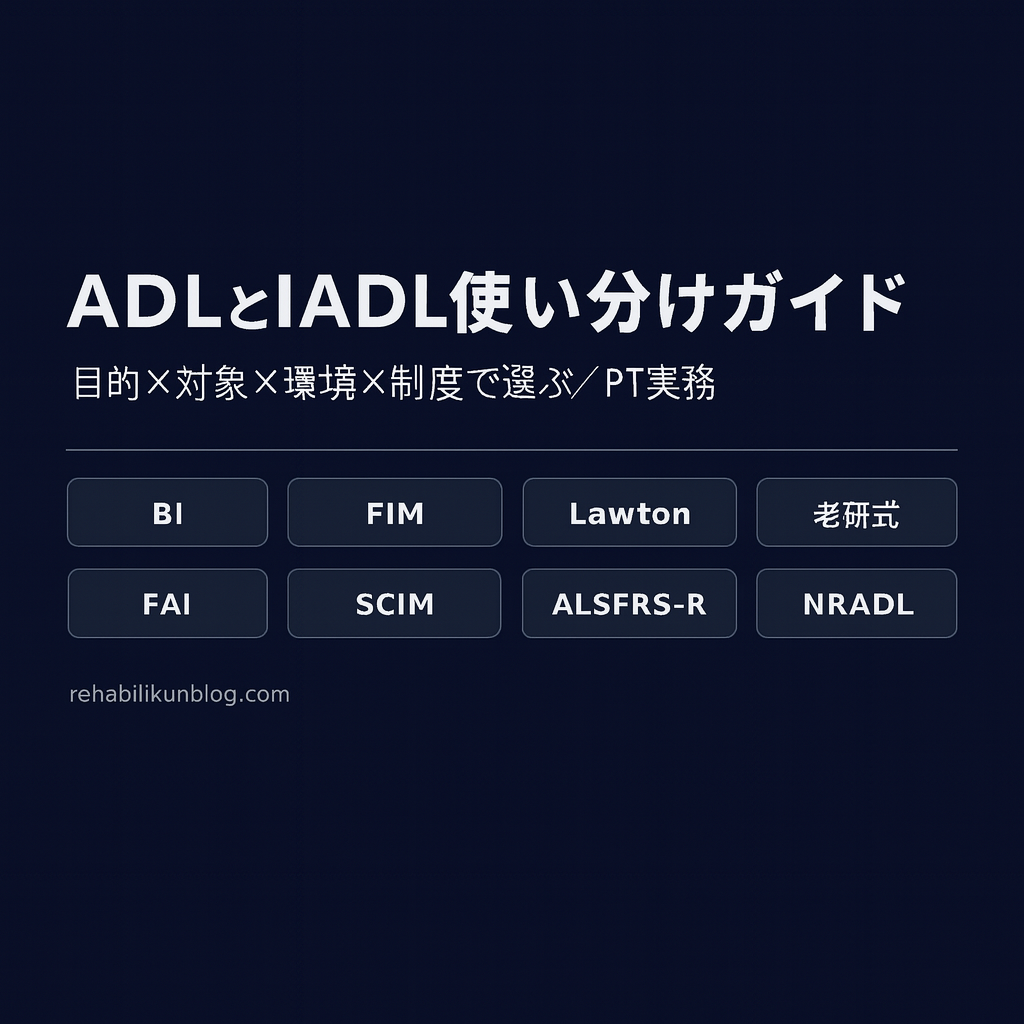呼吸困難の評価スケール総論【使い分けガイド】mMRC・Borg・NRS/VAS・D-12・MDP・RDOS
本ページは「呼吸困難(息切れ)の評価スケール」の総論(使い分け)です。ベースラインの障害度をみる mMRC、運動“中”の強度を刻々と扱う Borg(CR10/6–20)、いまの強さを短時間で数値化する NRS/VAS、質の違いをとらえる D-12・MDP・CDS、自記困難時に観察で推定する RDOS の役割を整理します。
なお、Borg の配布物(CR-10 ラベル・セッション記録ログ)は Borg 実務ガイド(配布物つき) へ、主観的評価の体系(NRS/VAS・D-12・MDP・RDOS の解説)は 呼吸困難の主観的評価(体系) に詳説しています。
まずは早見表|目的別の第一選択
| 臨床の目的 | 第一選択 | 代替/補助 | メモ |
|---|---|---|---|
| ベースラインの息切れ障害度(生活場面) | mMRC(0–4) | NRS/VAS | 長期の重症度層別に有用。急性の即時変化には不向き。 |
| 運動“中”の強度設定・中止基準 | Borg(CR10/6–20) | NRS/VAS | 分時・終了時に取得。SpO₂/HR/会話テストと併用。 |
| 今この瞬間のつらさの数値化 | NRS / VAS | Borg | 安静→活動直後→回復で同条件比較。MCID は概ね 2 前後を目安。 |
| 息切れの“質”や不快の多面的把握 | D-12 | MDP / CDS | 項目全文は転載せず、公式配布先を案内。 |
| 自記困難・終末期などの観察評価 | RDOS | 疼痛/不安スケール | 閾値は施設 SOP に合わせて運用。 |
mMRC と Borg は“用途”が違う
- mMRC:日常生活での息切れ障害度を 0–4 の序数で段階化。重症度層別・長期経過に向くが、数分~数日の即時変化は捉えにくい。
- Borg(CR10/6–20):運動中の主観的強度(努力感/呼吸困難)を連続的に扱う。セッション内の増減・中止判断・負荷調整に最適。
併用の定石:初診/節目に mMRC で層別化し、実施日は Borg を分時+終了時で記録。必要に応じて NRS/VAS を“いま”の強さ確認に追加。
mMRC(改変 MRC 息切れスケール):要約表
| スコア | 定義(患者説明用の言い換え) |
|---|---|
| 0 | 激しい運動の時だけ息切れ(全力運動レベル) |
| 1 | 早歩きや坂道で息切れ(平地でも急ぐと苦しい) |
| 2 | 同年代より遅れる/自分のペースでも途中で立ち止まることがある |
| 3 | 平地で約 100 m または数分歩くと立ち止まる |
| 4 | 外出が難しい/着替えなど軽い動作でも息切れする |
注:本表は教育・説明の要約です。実際の評価・記録は施設の標準票(原文)で行い、版数と日付を記録してください。外部の総合情報:GOLD
NRS / VAS:いまの強さを短時間で
NRS(0–10)/VAS(10cm, 0–100mm)は、教育コストが低く、安静→活動直後→回復の同条件で比較しやすいのが利点。目標は「数値の変化」そのものではなく、主観(スコア)×客観(SpO₂/HR/呼吸数)×介入変更点の三点で意思決定することです。図解は体系ページ:呼吸困難の主観的評価(体系)
D-12 / MDP / CDS:質の違いを捉える
“息切れの質”や情動反応まで含めて把握したい場合は D-12・MDP・CDS を選択。本文では目的・構成・解釈に絞り、項目全文の転載は行いません。公式配布先(ATS / ePROVIDE / 国立がん研究センター 等)へのリンクは下段「公式導線」に整理。
RDOS:自記困難時の観察
終末期・ICU 等で自己申告が難しい時は RDOS を用いて表情・呼吸パターン・筋使用・バイタル等から推定。閾値は施設 SOP と対象に合わせて設定し、疼痛・不安・せん妄などの併存にも留意します。
主要スケールの比較(特性と注意)
| 尺度 | 対象/場面 | 出力 | 強み | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| mMRC | 日常生活での息切れ障害度 | 0–4(序数) | 重症度層別・長期経過 | 即時変化には不向き |
| Borg(CR10/6–20) | 運動“中”の強度設定・中止判断 | 連続値(0–10 / 6–20) | セッション内の比較が容易 | スケールの教育と固定が必須 |
| NRS / VAS | 「いま」の強さの把握 | 0–10 / 0–100mm | 所要時間が短い | 質的情報は拾いづらい |
| D-12 / MDP / CDS | 質・不快・情動反応の多面的評価 | 合計・下位尺度 | 介入の効きどころが見える | 項目転載は不可/配布先で入手 |
| RDOS | 自記困難・終末期等の観察 | 観察スコア | 意思疎通困難でも評価可 | 閾値運用は施設 SOP に準拠 |
主なスケールの表(NRS/VAS・BDI/TDI・OCD/NYHA)
NRS / VAS(呼吸困難)の要約表
| スケール | 目的 | 範囲/出力 | 実施のポイント | 解釈の目安 |
|---|---|---|---|---|
| NRS | 「いま」の息切れの強さを数値化 | 0–10(整数/小数可) | 0=全くない/10=想像できる最大、を30秒で共有。 安静→活動直後→回復で同条件比較。 |
対象により幅があるが臨床では約2前後の変化を目安に、 SpO₂・HR等と併せて判断。 |
| VAS | 線分上で強さを連続値で可視化 | 10 cm(0–100 mm) | 0/10 の端点説明+指差し/マーキング。 測定器具の目盛り誤差に注意。 |
同一個人内の比較に強い。記録は mm で残すと再現性↑。 |
BDI / TDI(Baseline & Transition Dyspnea Index)要約表
※項目全文は転載しません。目的・構成・採点の要点のみを記載し、配布・手続きは公式へ案内します。
| 尺度 | 目的 | 構成 | 採点/範囲 | 解釈の要点 | 注意/入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| BDI | ベースラインの呼吸困難の重症度を把握 | 3ドメイン:機能障害度 / 作業の大きさ / 努力の大きさ | 各 0–4(0=重い~4=なし)合計 0–12。 高得点=息切れが軽い。 |
初診や節目の層別化に有用。 同一担当者・標準手順での面接が望ましい。 |
項目・アンカー語は転載不可。 ePROVIDE や学会資料で入手/手続き。 |
| TDI | BDI からの変化量を評価 | 同じ3ドメイン構造 | 各 -3~+3、合計 -9~+9。 正値=改善/負値=悪化。 |
臨床研究では +1 程度を最小有意変化の目安に用いる報告あり(対象依存)。 | 実施間隔・出来事の記憶バイアスに留意。 ATS Outcome Measures 参照。 |
OCD / NYHA の要約と対照
OCD(Oxygen Cost Diagram)は、日常活動を 0–100 の目盛に並べ、息切れなく達成できる最大の活動レベルに印を付ける自己評価図です(高いほど活動許容量が大)。NYHA は心不全の機能分類(I–IV)で、活動制限の程度を段階化します。下表は対照の目安であり、診断や適格性判定に用いる場合は原図/原文を参照してください。
| 分類 | NYHA の言い換え定義 | OCD の例示的レベル(目安) | メモ |
|---|---|---|---|
| NYHA I | 日常活動で症状なし(制限なし) | 速歩・階段の昇降も概ね可能(OCD 高位) | 競技的運動は個別評価 |
| NYHA II | 通常活動で軽い症状(軽度制限) | 平地歩行は可能、坂/長距離で息切れ(OCD 中高位) | 間欠休止を併用 |
| NYHA III | 軽い活動で症状(高度制限) | 短距離歩行・軽作業で息切れ(OCD 中位) | ADL 優先の個別処方 |
| NYHA IV | 安静時も症状、活動不可 | 身の回り動作も困難(OCD 低位) | 安静時管理・緩和ケア含め検討 |
注:OCD の原図(活動リスト/スケール)は配布元の版に依存します。Web 掲載は避け、院内利用は公式図版を入手してください。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に。見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック(A4・5分)と職場評価シート(A4)を無料公開しています。印刷してそのまま使えます。
公式配布・情報ページ(導線)
- American Thoracic Society:Outcome Measures(Dyspnea)
- Mapi Research Trust(ePROVIDE):BDI/TDI・D-12・MDP 等の入手・手続き(サイト内検索)
- GOLD(COPD ガイドライン)
参考文献
- American Thoracic Society. Dyspnea: Mechanisms, Assessment, and Management. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(4):435–452. DOI:10.1164/rccm.201108-1575ST
- Bestall JC, et al. Usefulness of the MRC dyspnoea scale as a measure of disability in COPD. Thorax. 1999;54:581–586. PubMed
- Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc. 1982;14(5):377–381. PubMed
- Yorke J, et al. The Dyspnoea-12: a new measure of breathlessness. Thorax. 2010;65(1):21–26. DOI:10.1136/thx.2009.118521
- Banzett RB, et al. Multidimensional Dyspnea Profile: validation and application. Chest. 2015;148(1):134–142. PubMed
- Campbell ML, Templin T. Intensity of distress in respiratory failure: validation of RDOS. Res Nurs Health. 2010;33(5):467–475. PubMed
- Tanaka K, et al. Development and validation of the Cancer Dyspnoea Scale. Br J Cancer. 2000;82(10):2007–2011. PubMed
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下