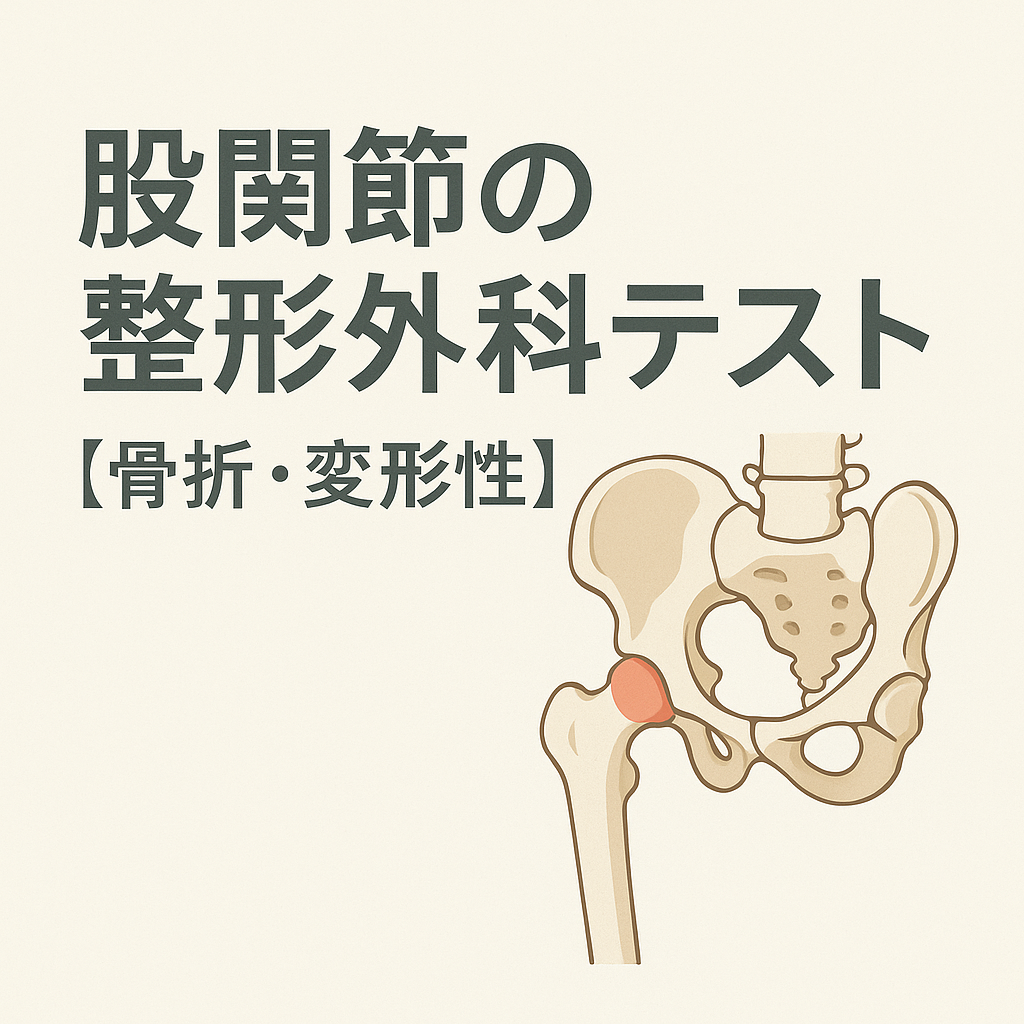院内感染対策と施設基準の全体像
臨床力を底上げする学び方の流れを見る(PT キャリアガイド)
院内感染対策は「法律で決められているからやるもの」というだけでなく、診療報酬や外部評価にも直結する仕組みです。医療法では、感染対策の指針・委員会・研修・マニュアル・サーベイランスなどを整備することが求められており、感染対策向上加算や外来感染対策向上加算などの施設基準とも結びついています。理学療法士として委員会メンバーや研修講師を任されたとき、どこまで理解しておけばよいかを整理しておくことが大切です。
本記事では、院内感染対策に関する施設基準の「骨組み」を押さえたうえで、院内感染対策委員会の役割、年 2 回以上の研修とマニュアル整備、感染対策向上加算との関係を概説します。そのうえで、PT・OT・ST が関わりやすい 5 つの場面と、年間スケジュール・記録の型を紹介し、明日からの委員会運営や現場実務にそのまま落とし込めることを目指します。
院内感染対策委員会の役割と開催頻度
院内感染対策委員会は、多職種で院内感染対策の方針を決め、実行状況をモニタリングする場です。医療法関連の通知では、管理者(院長)を責任者とし、看護部・薬剤部・検査部・医療安全管理者などとともに、必要に応じてリハビリテーション部門も委員に含めることが望ましいとされています。委員会では、標準予防策や感染経路別予防策の遵守状況、アウトブレイクの有無、抗菌薬の使用状況、サーベイランス結果などを共有し、改善策を検討します。
開催頻度の目安は「少なくとも年数回」、多くのガイドラインやモデル事例では月 1 回程度が推奨されています。理学療法士が出席するときは、褥瘡・呼吸器・ADL 場面など、自部署に関わる感染リスクのデータや事例を持参しておくと、委員会の場で具体的な議論につなげやすくなります。また、議事録に「誰が」「いつまでに」「何をするか」が残るように意識し、リハ部門に関わるアクションプランは部署内で確実に共有・実行していくことが重要です。
指針・マニュアルと年 2 回研修の押さえどころ
院内感染対策の「指針」は、施設における感染対策の基本方針を示す文書です。通常、目的・組織体制(委員会・感染管理者)・標準予防策と感染経路別予防策・サーベイランス・アウトブレイク対応・職員教育・職業感染対策などの項目を含みます。指針自体はやや抽象的な文章になりやすいため、現場で使用する具体的な手順やチェックリストは、病棟マニュアルや部署マニュアルとして階層化して整理しておくと運用しやすくなります。
医療法や診療報酬の施設基準では、感染対策に関する職員研修を「概ね年 2 回以上」実施することが求められています。研修テーマとしては、毎年必須の標準予防策・手指衛生・個人防護具の使用方法に加え、抗菌薬適正使用( AMS )、結核・インフルエンザなどの空気・飛沫感染対策、褥瘡や人工呼吸器管理( VAP 対策 )、リハ室での共有物品の管理などが候補になります。PT・OT・ST が講師を務める場合は、「ポジショニングと褥瘡・誤嚥性肺炎」「車椅子・歩行器の清拭ルール」など、自分たちの専門を活かしたテーマを提案するのがおすすめです。
感染対策向上加算・外来感染対策向上加算と施設基準
感染対策向上加算は、院内感染対策の体制整備を評価する入院料の加算であり、加算 1〜3 まで段階的な施設基準が設定されています。主な要件として、院内感染対策委員会の設置と定期的な開催、感染管理者( ICT の専任または専従スタッフ)の配置、職員研修(概ね年 2 回以上)の実施、サーベイランスなどが挙げられます。加算区分によって、地域の他医療機関との連携体制や、専門資格を持つスタッフの配置など、求められる水準が異なります。
外来感染対策向上加算は、外来患者に対する感染対策の体制(発熱患者の動線分離、トリアージ、情報提供など)を評価するものです。外来での標準予防策や呼吸器症状のある患者へのマスク着用案内はもちろん、発熱外来の運用、地域の診療・検査医療機関との連携も含めて体制整備が求められます。リハビリテーション部門としては、外来リハ患者のマスク・手指衛生・更衣室や物品の管理、待合での密集防止など、日常業務の中でどのように感染対策を組み込むかを委員会と共有しておくとよいでしょう。
PT・OT・ST が院内感染対策で関われる 5 つの場面
PT・OT・ST が院内感染対策に関わる場面は、「委員会出席」だけにとどまりません。まずベッドサイドでは、移乗・歩行・車椅子操作・排泄動作介助など、患者さんに密接に接する機会が多く、標準予防策の徹底や手袋・エプロン・マスクなど個人防護具の適切な選択が求められます。褥瘡予防や呼吸リハ、嚥下リハなど、感染リスクの高い場面では、ポジショニングや口腔ケアとの連携も含め、感染対策を組み込んだプログラム設計が必要です。
第二に、サーベイランスやインシデントレビューへのデータ提供があります。例えば褥瘡や転倒・誤嚥性肺炎の発生状況は、リハビリテーション計画や経過と組み合わせることで、予防策の検討に活かしやすくなります。第三に、職員研修の講師や実技デモとして参加すること、第四に、リハ室や共用物品(平行棒・エルゴメータ・歩行器など)の清拭ルールや動線設計に関する意見出し、第五に、アウトブレイク時の離床制限やリハ提供方法の調整などです。「感染対策チームの一員」として、診療報酬上の施設基準にも貢献していることを意識して関わると、委員会内での発言もしやすくなります。
年間スケジュールと記録の型を整える
院内感染対策の施設基準を満たし続けるためには、「何をどの頻度で実施するか」を年間スケジュールで見える化し、実施後の記録を抜けなく残しておくことが重要です。具体的には、院内感染対策委員会の開催予定(月 1 回など)、年 2 回以上の職員研修、サーベイランスの集計・報告サイクル、指針やマニュアルの見直し時期などを 1 枚のシートに整理しておくと、監査や自己点検の際にも説明しやすくなります。理学療法士が委員となっている場合は、褥瘡・転倒・誤嚥性肺炎など、リハ由来のテーマを年間計画に組み込めるよう提案しておくとよいでしょう。
記録の型としては、①委員会議事録(開催日時・出席者・議題・討議内容・決定事項・担当者と期限)、②研修記録(テーマ・講師・対象職種・参加人数・内容要約・評価と次回への課題)、③サーベイランスまとめ(対象感染症・指標・結果と対応)などをひとまとめにしておくと、施設基準の確認や外部評価に対応しやすくなります。これらの書式を部署共通でそろえておけば、委員の交代や多職種間の連携時にもスムーズに引き継ぎが可能です。最終的な運用方針や書式の採用は、必ず施設長や医療安全管理者、看護部・事務部門と相談して決定してください。
院内感染対策 施設基準チェックシート(ダウンロード)
記事で解説してきた内容を、院内でそのまま自己点検に使えるよう A4 1 枚のチェックシートにまとめました。医療法に基づく院内感染対策の基本要件(指針・委員会・研修・サーベイランス)と、感染対策向上加算・外来感染対策向上加算に関連する項目、リハビリテーション部門として押さえておきたいポイントを一覧形式で確認できます。
年 1〜2 回の体制見直しや、委員会の新メンバーへのオリエンテーション、監査前の抜け漏れチェックにご活用ください。印刷して手書きで記入しても、PDF として電子保存しても構いません。
院内感染対策 施設基準チェックシート( A4 ・無料ダウンロード)
おわりに:委員会業務を「負担」から「臨床への投資」に変える
院内感染対策委員会や施設基準への対応は、どうしても「本来業務とは別の仕事」と感じられがちです。しかし、標準予防策や褥瘡・誤嚥性肺炎予防、抗菌薬適正使用といったテーマは、リハビリテーションの質や患者さんの転帰にも直結します。委員会や研修、サーベイランスを通じて、自部署のリスクや強みを客観的に振り返ることは、結果的に日々の評価・治療の精度を高めることにもつながります。
一方で、委員会や書類対応が増えるほど、学習時間や臨床の振り返り時間が削られてしまうのも現実です。働き方を見直すときの抜け漏れ防止に、見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック( A4・5 分 )と職場評価シート( A4 )を無料公開しています。印刷してそのまま使えるので、「今の職場でできる工夫」と「環境を変える選択肢」の両方を整理するツールとして活用してみてください。ダウンロードページを見る。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
院内感染対策委員の仕事量が多くて不安なとき、どうすればよいですか?
院内感染対策委員会や医療安全委員会のメンバーになると、慣れない書類作成や会議準備が増え、「本来業務と両立できるか不安」という声も少なくありません。まずは直属の上司や感染管理者に、現在担っている役割と時間的負担を共有し、優先順位の整理や業務分担の見直しについて相談してみることが大切です。
同時に、委員会の業務を「負担」だけでなく、自部署のリスクを可視化し、リハビリの質を高めるチャンスとして捉え直すことも有用です。チェックシートや議事録フォーマットを共通化し、「何をいつまでに誰が行うか」が見える状態を作ることで、個人の属人的な頑張りに依存しない体制づくりにつながります。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下