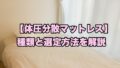てんかん発作をリハビリ中に目撃したら:一次対応とリスク管理
発作を目撃したとき、リハビリスタッフにまず求められるのは「危険排除・禁忌回避・計時(スタート時刻)」です。本稿は現場の PT / OT / ST 向けに、リハビリ中の一次対応の Do / Don’t 、 “いつ 119 ”の境界、そして失神・ PNES との違いを、表とチェックで整理します。
加えて「てんかん リハビリ リスク管理」の検索意図に合わせ、発作が起きる前の訓練設計(開始前チェック/訓練別のハイリスク場面/チーム共有の型)もまとめました。関連する安全管理の索引は 制度・実務ハブ(安全管理) に集約しています。
てんかんリハビリのリスク管理:発作を起こさせない設計
結論:リハビリ場面のリスク管理は「開始前に誘因を減らす → ハイリスク訓練を条件付きで実施 → 発作時の対応プランを全員で共有」の 3 点で事故が減ります。一次対応だけ整えても、訓練設計が不安定だと転倒・外傷・窒息のリスクが残ります。
現場では “分類を覚える” より、①睡眠・体調・服薬などの変動を拾う ②水場・高所・屋外など危険が跳ねる場面を先に避ける ③観察語彙と連絡フローを固定する、の順に整えると運用が回りやすいです。
開始前チェック( 60 秒 )
| 項目 | 確認のコツ( 1 行 ) | リハ側の調整 | 中断/延期の目安 |
|---|---|---|---|
| 睡眠不足・疲労 | 夜間覚醒/寝不足、日中の眠気を 1 問で確認 | 強度を 1 段階下げ、見守りを厚く、休憩を先に置く | 極端な眠気・反応低下、ふらつき増悪 |
| 服薬(飲み忘れ) | 内服タイミングが “いつも通り” かを確認 | 当日の目標を下げ、危険の高い訓練を後回しにする | 飲み忘れが明確、発作パターンが変化 |
| 発熱・感染兆候 | 発熱、悪寒、咳痰、尿路症状など | 離床は短時間、体位変換中心へ。医師へ共有を優先 | 発熱+意識/呼吸の変化、全身状態の破綻 |
| 低血糖・脱水 | 食事摂取、糖尿病治療、口渇・尿量 | 起立・歩行は段階付け。長時間連続を避ける | 冷汗・動悸・ふらつきの増悪、明らかな脱水所見 |
| 直近の発作変化 | 頻度/持続/回復の “いつもと違う” を 1 行で | 見守り強化、環境を安全側へ(ベッド周囲、床面) | 群発傾向、回復遷延、外傷の合併 |
訓練別:ハイリスク場面と代替案
| 訓練/場面 | 主リスク | 事前にやる調整 | 代替(同じ目的を安全側で) |
|---|---|---|---|
| 起立・立位保持 | 転倒、頭部打撲 | ベッド/手すり/壁沿い、足元クリア、スタッフ配置を先に決める | 端座位で重心移動、立位は短時間の反復へ |
| 歩行練習(病棟内) | 転倒、二次外傷 | 最初は “直線+広い場所” 、方向転換と狭所は後回し | 平行棒/歩行器で距離を刻む、段階付け |
| 階段・段差 | 高所転落、骨折 | 実施条件(手すり、介助者数、疲労)を固定してから | ステップ台で練習、昇降は介助量が安定してから |
| 浴室・水場(入浴動作/洗体) | 溺水、滑倒 | 単独実施を避ける。先に “乾いた環境” で手順練習 | 更衣・移乗・手すり動作を陸上で反復してから |
| 屋外歩行・外出練習 | 転倒、交通、単独時の対応遅れ | 同行者・連絡手段・休憩地点を先に決める | 屋内で二重課題と休憩導入を固めてから段階的に |
| マシン/エルゴ | 転落、離脱困難 | 緊急停止、固定具、乗降介助の役割分担を固定 | 座位での反復下肢運動、短時間インターバルで代替 |
Seizure Action Plan(院内版ひな形)
発作対応は “その場の頑張り” ではなく、チームで迷いを減らす設計が重要です。患者ごとに、最低限これだけを 1 枚で共有します。
| 項目 | 記入例(短く) | 共有先 |
|---|---|---|
| 普段の発作型 | 強直間代 1–2 分、回復に 15 分 | PT / OT / ST /看護 |
| 誘因(多いもの) | 寝不足、発熱、内服遅れ | 病棟スタッフ全員 |
| 実施 NG / 条件付き | 浴室は単独 NG 、屋外は同行者必須 | リハ/介護者 |
| 薬(レスキュー含む) | 指示薬の有無、投与条件、連絡先 | 看護/主治医 |
| 救急要請の基準 | 5 分超、群発で意識回復なし、外傷/溺水 | 全員 |
てんかん発作の基本|“定義”より現場で役立つ要点
発作は一過性・可逆的な神経活動の破綻が作る症候群で、意識・運動・自律神経・感覚の変化として現れます。リハビリ中に問題になるのは「転倒・外傷・窒息リスク」と「発作後の麻痺や疲労でどこまで続行してよいか」です。分類は大別して焦点発作と全般発作。定義や分類の精緻化は ILAE に委ね、現場では ①危険排除 ②回復体位 ③計時( 5 分 )の 3 点を最優先します。
なお “けいれん = てんかん” ではありません。低血糖や失神でも短時間のミオクロニーは起こり得ます。鑑別は最終的に医師が行いますが、リハ側は “観察の抜け” を減らすことが役割です。
一次対応( Do / Don’t )
結論:押さえない・口に物を入れない・側臥位で安全確保・計時。周囲の危険物をどけ、頭部を保護し、衣類はゆるめます。歩行練習や起立訓練中なら、まず転倒と頭部打撲を防ぐ位置へ誘導します(無理な拘束はしません)。
| 区分 | やること | やらないこと | メモ(申し送り用) |
|---|---|---|---|
| 安全確保 | 危険物を除去、頭部を保護、衣類をゆるめる | 無理に押さえつける(外傷リスク) | 体位、転倒/外傷の有無 |
| 呼吸/気道 | 回復体位(側臥位)へ、呼吸と皮膚色を観察 | 口に物を入れる、水や薬を飲ませる(誤嚥/窒息) | 呼吸状態、チアノーゼ |
| 計時 | 開始時刻を時計で記録し、持続を把握 | “たぶん 2 分” など曖昧な記録 | 開始時刻、総持続 |
“いつ 119 するか”の目安
以下のいずれかに該当したら、施設の連絡体制に従って主治医へ報告し、 119 を検討します。5 分超の持続は、とくに強直間代で重積が懸念され要救急です。
- 5 分以上続く/短時間に反復し意識が戻らない。
- 初回の発作/妊娠中/外傷・溺水/高熱や代謝異常が疑われる。
- 呼吸が戻らない・チアノーゼが強い・回復が極端に遅い。
院内連絡フロー(簡易)
| 順番 | 伝える内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1 | 開始時刻と総持続 | 13:12 開始、 2 分 20 秒で停止 |
| 2 | 体位/状況、外傷 | 歩行練習中に崩れ、頭部打撲なし |
| 3 | 運動と左右差 | 強直 → 間代、右上肢優位など |
| 4 | 呼吸/皮膚色、介入 | 側臥位、 SpO2 低下なし、吸引なし |
| 5 | 回復状況(傾眠/混迷) | 回復に 15 分、会話は可能 |
てんかんと失神・ PNES の違い(早見表)
| 所見 | てんかん | 失神(心血管性含む) | PNES(心因性非てんかん性発作) |
|---|---|---|---|
| 誘因 | とくに無し/睡眠不足・発熱・光刺激など | 起立・排尿・疼痛・情動・徐脈/頻脈 | 場面依存・目撃者の有無で変動 |
| 発声 | うめき声・叫声があり得る | 通常なし | 持続・変動が目立つ |
| 運動 | 強直 → 間代の律動性けいれん | 短時間の不規則ミオクロニー | 非律動、回避的、長時間化 |
| 舌咬傷 | 側縁が比較的特異 | 先端寄りが多い | まれ |
| 回復 | 傾眠・混迷が数分〜数時間 | 速やか(数十秒) | 遷延・反応のばらつき |
PNES は “作為” ではない非てんかん発作です。否定的ラベリングを避け、観察所見を淡々と共有します。
観察・記録(最低限これだけ)
①開始時刻と総持続時間( 秒 ) ②体位・転倒・外傷 ③眼球偏倚/頭位回旋 ④運動(強直・間代・ミオクロニー・脱力)と部位 ⑤発声・呼吸・皮膚色 ⑥舌咬傷の部位 ⑦介入内容と時刻 ⑧回復までの時間・ Todd 麻痺の有無/部位 ⑨トリガー(睡眠不足・発熱など) ⑩主治医連絡・救急要請の有無。
ポイントは “所見を実況しない” ことです。医療者が解釈語(重積っぽい、失神っぽい)を先に置くと共有がぶれます。まずは時刻・体位・運動・回復の順に、観察語彙でそろえます。
FAQ(よくある質問)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. 5 分未満でも 119 すべき状況は?
群発して意識が戻らない、初回の発作、妊娠中、外傷・溺水・高熱の合併、呼吸が戻らない・チアノーゼが強い、といった場合は時間に関わらず救急要請を検討します。
Q2. 初回の発作は受診が必要?
はい。初回や “いつもと違う” 発作は、代謝異常・感染・心血管性失神などの鑑別が必要です。状況により救急受診、または早期受診を案内します。
Q3. 家族・介護者へ 3 つだけ共有するなら?
押さえない/口に物を入れない/側臥位で危険を減らす。この 3 点と “開始時刻の記録” を共有します。屋外や水場は単独を避け、同行者と連絡手段を先に決めておくと運用が回りやすいです。
参考文献
- Fisher RS, et al. A practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014;55(4):475–482. DOI
- Epilepsy Foundation. Seizure First Aid. Web
- 公益社団法人 日本てんかん協会「発作の介助と観察」. Web
- NICE. CG109: Transient loss of consciousness in adults and young people. Web
- Brignole M, et al. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J. 2018;39:1883–1948. DOI
- Brigo F, et al. Value of tongue biting in the differential diagnosis between epileptic seizures and syncope. Seizure. 2012;21(8):568–572. DOI