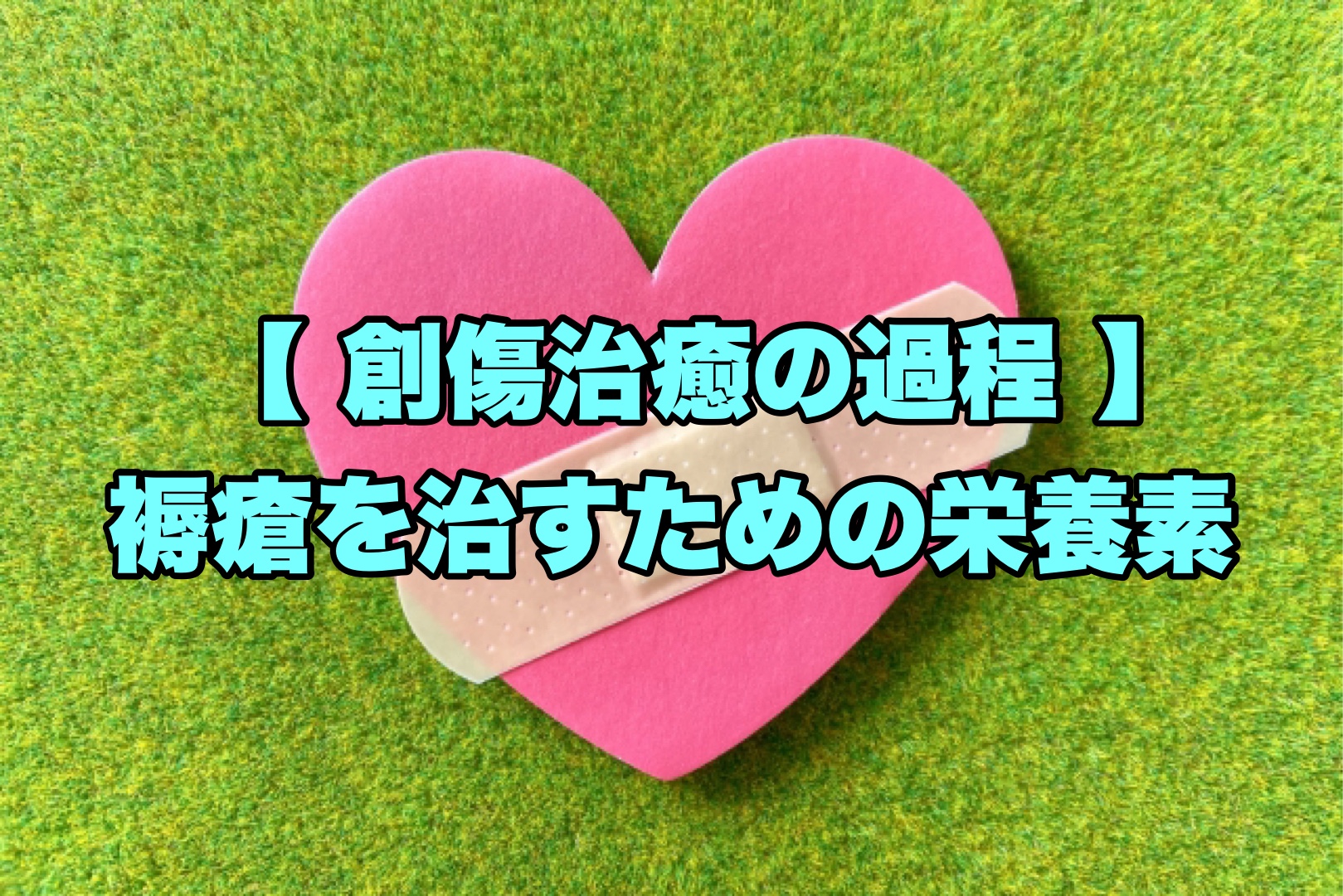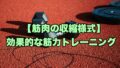創傷治癒過程の全体像(まず結論)
臨床で迷わない!評価〜介入の流れを素早く確認する( PT キャリアガイド )
創傷治癒は「損傷を受けた組織が、失われた構造と機能を取り戻そうとする一連の反応」です。整理すると、止血期(凝固期)・炎症期・増殖期(血管新生・肉芽形成期)・成熟期(再構築期)の 4 期に分けられます。
実際の治癒は 再生(元どおりに近い復元)と 修復(瘢痕での置き換え)が重なり合いながら進み、創の性状や清浄度、血流、感染の有無によって経過が大きく左右されます。外力(圧迫・剪断)や感染、循環不全、栄養不良は停滞因子の代表で、いずれかの段階で足踏みすると慢性化します。
創傷治癒過程と再生・修復の考え方
損傷後、止血と炎症制御で「汚れを除く」段取りをつけ、ついで肉芽形成と上皮化で「埋める・覆う」、最後にコラーゲン配列の最適化で「強度を上げる」という順序で創傷治癒過程は進みます。再生と修復は並行して起こり、器官や創条件により比率が変わります。
「創傷治癒過程で上皮化はいつ起こるのか?」とよく聞かれますが、一般に上皮化は増殖期後半から成熟期にかけて進み、炎症の長期化や感染・虚血があると遅延します。臨床側は「清浄化・感染制御・滲出液コントロール・血流・圧の除去・栄養」を整えることで、各期のスムーズな移行を支援します。
一次治癒と二次治癒で異なる創傷治癒過程
一次治癒(閉鎖創)
切創のように創縁が整い、汚染や異物がなく、縫合で密着できる創では一次治癒となります。炎症が短く、瘢痕は比較的少なく、創傷治癒過程の全体も速やかに完了します。
二次治癒(開放創)
熱傷・採皮創・潰瘍・褥瘡など、創欠損が面として残り縫合できない場合は二次治癒です。感染や滲出液、創縁の不適合が関与しやすく、肉芽形成・上皮化・創収縮で徐々に充填・閉鎖しますが、時間を要し瘢痕も目立ちやすくなります。
急性創傷と慢性創傷:どこで創傷治癒過程が止まるか
急性創傷は外傷や術創などで、4 段階が秩序立って進みます。一方、慢性創傷は炎症期や増殖期で停滞しやすく、感染・バイオフィルム、虚血、浮腫、持続する外力(圧迫・剪断)、栄養不良などが併存します。代表例は褥瘡や下腿潰瘍で、治療は「原因制御+創局所の準備( TIMERS など)+全身管理(栄養・循環・基礎疾患)」の三本柱で考えます。
要するに、褥瘡は“二次治癒 × 慢性創傷”で難しい。圧の除去(体圧分散・体位変換)と感染・滲出液コントロール、血流改善、栄養介入を並行して行い、停滞した創傷治癒過程を“ほどく”発想が重要です。
創傷治癒過程の 4 期(止血期・炎症期・増殖期・成熟期)
4 段階の主な出来事と観察ポイント、支援の観点を簡潔にまとめます。慢性化では特に炎症期・増殖期での停滞が多く、ここを越えられるよう局所・全身を整えます。
| 段階 | 主な出来事 | 観察・評価の要点 | 支援の観点 |
|---|---|---|---|
| 1. 止血期(凝固期) | 血管収縮・血小板凝集・フィブリン形成で止血 | 出血の持続有無、抗凝固薬の影響 | 止血と創保護。汚染の最小化。 |
| 2. 炎症期 | 好中球・マクロファージが異物 / 細菌を除去、サイトカイン産生 | 発赤・腫脹・疼痛・滲出液の量 / 性状、感染徴候 | 感染制御、滲出液コントロール、外力の除去。 |
| 3. 増殖期(血管新生・肉芽形成期) | 線維芽細胞と内皮細胞が増殖し、血管新生・肉芽形成・上皮化が進行 | 肉芽の色 / 充実度、創縁の上皮進展、ポケット | 創湿潤環境、デブリドマン適応、適切な被覆材、栄養(タンパク質・亜鉛など)。 |
| 4. 成熟期(再構築期) | コラーゲン再配列・架橋、強度向上 | 瘢痕の可動性 / 牽引痛、拘縮・機能障害 | 過度な張力回避、瘢痕ケア、関節可動の維持。 |
創傷治癒過程と栄養:タンパク質・微量栄養素の押さえどころ
炎症期
炎症期は発赤・疼痛・腫脹・滲出液のピークで、感染徴候の観察と創清浄化が最優先です。同時に、エネルギーとタンパク質を十分に確保することが、免疫応答と創清浄化を支えます。食思不振が出やすいため、少量高栄養・間食・飲水量の確保をチームで支援します。
増殖期
増殖期は肉芽形成・上皮化が前面に出る時期で、「肉芽の質」を決める局面です。十分なタンパク質摂取が、コラーゲン合成と血管新生・肉芽形成を支えます。亜鉛やビタミン C などの不足が長引くと上皮化が遅れ、創傷治癒過程の期間が延びやすくなります。
成熟期
成熟期(再構築期)はコラーゲン再配列と強度向上の局面です。適切な栄養摂取を維持しつつ、瘢痕の可動域制限や牽引痛に注意し、過度な張力を避けながら機能訓練やスキンケアを継続します。
TIMERS でみる「創傷治癒過程のつまずき」の整理
- Tissue(壊死組織):デブリドマン適応と方法の確認。壊死組織が残ると炎症期にとどまりやすくなります。
- Infection / Inflammation:感染徴候・バイオフィルム、抗菌戦略。炎症期の遷延や増殖期への移行遅延の主要因です。
- Moisture:滲出液量に合わせた被覆材・吸収材。過乾燥でも過湿でも停滞しやすく、「適度な湿潤」を目指します。
- Edge(創縁):上皮進展の阻害要因(ポケット、張力)。創縁のロールやポケットは上皮化を妨げます。
- Regeneration:血流改善、疼痛管理、栄養介入。虚血や疼痛、栄養不足は再生力を弱めます。
- Social:体圧分散・ポジショニング、ケア環境、服薬・嚥下など。体位管理が不十分だと、圧迫・剪断が再燃しやすくなります。
現場の詰まりどころ
病棟・施設では「創自体の処置」に目が向きやすく、圧の除去やポジショニング、栄養・循環といった全身側の調整が後手に回りがちです。その結果、増殖期に入っても肉芽が出てこない、上皮化が進まない、といった“停滞”として現れます。
T(壊死)と I(感染)に集中しすぎて、M(湿潤)・E(創縁)・R(再生)・S(ケア体制)が十分に評価されていないケースも多く見られます。創の写真・サイズだけでなく、「圧・感染・循環・栄養・ケア体制」をセットで評価し、どの期で何がボトルネックになっているかをチームで共有しておくと、介入の優先順位がつけやすくなります。
関連リンク(当ブログ内・同一タブ)
- 褥瘡が発生する要因と 7 つの危険因子
- Braden スケールから考える褥瘡予防ケアの優先順位
- 体圧・接触圧の測定方法(褥瘡予防)
- 低栄養と褥瘡:ポジショニングまで含めた考え方
- 褥瘡治癒に有効な ONS(アルギニン・亜鉛・ビタミン)
よくある質問(FAQ)
※各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
慢性創傷では、どの段階で停滞しやすいですか?
多くは炎症期または増殖期(血管新生・肉芽形成期)で停滞します。感染やバイオフィルム、虚血・浮腫、持続する圧迫 / 剪断、栄養不良などが背景にあり、まず原因制御(圧の除去・感染対策・循環改善)と全身管理(栄養)を優先します。
褥瘡で最優先に整えるのは何ですか?
1) 圧の除去(体位・寝具・座面)、2) 感染 / 滲出液コントロール、3) 血流改善と疼痛対策、4) 栄養管理の 4 点を同時並行で行うことです。原因別に介入を積み重ねます。
創傷治癒に重要な栄養素は何ですか?
ベースとなるのは十分なエネルギーとタンパク質で、これにビタミン A・C・E、亜鉛・鉄・銅などの微量栄養素が加わります。炎症期には免疫と創清浄化、増殖期にはコラーゲン合成と肉芽形成、成熟期には架橋・再配列を支える役割をもちます。
おわりに
創傷治癒過程の 4 期を意識すると、臨床のリズムは「危険因子の評価 → 圧・感染・循環・栄養の調整 → ポジショニング・リハビリテーション → 再評価」というサイクルとして整理できます。どの期でつまずいているのかをチームで共有し、局所と全身の両面から少しずつ条件を整えていくことが重要です。
一方で、創傷ケアや褥瘡評価を日常業務として担う理学療法士にとっては、「どんなチーム体制・人員配置・教育環境の職場なら、実務と学びを両立しやすいか」を見極めることも大切です。転職や職場見直しを考える際には、マイナビコメディカルの面談準備チェック&職場比較シートも活用しながら、自分が創傷ケアの強みを活かせる環境を具体的にイメージしてみてください。
参考文献
- Singer AJ, Clark RAF. Cutaneous wound healing. N Engl J Med. 1999;341(10):738-746. doi: 10.1056/NEJM199909023411006 / PubMed
- Guo S, DiPietro LA. Factors Affecting Wound Healing. J Dent Res. 2010;89(3):219-229. doi: 10.1177/0022034509359125 / PubMed
- Almadani YH, Vorstenbosch J, Davison PG, Murphy AM. Wound Healing: A Comprehensive Review. Semin Plast Surg. 2021;35(3):141-144. doi: 10.1055/s-0041-1731791 / PubMed
- Atkin L, et al. Implementing TIMERS: the race against hard-to-heal wounds. J Wound Care. 2019;28(Sup3a):S1-S49. doi: 10.12968/jowc.2019.28.Sup3a.S1
- Stechmiller JK. Understanding the role of nutrition and wound healing. Nutr Clin Pract. 2010;25(1):61-68. doi: 10.1177/0884533609358997 / PubMed
- Barchitta M, Maugeri A, Favara G, et al. Nutrition and Wound Healing: An Overview Focusing on the Beneficial Effects of Curcumin. Int J Mol Sci. 2019;20(5):1119. doi: 10.3390/ijms20051119 / PubMed
- Bauer JD, Isenring E, Waterhouse M. The effectiveness of a specialised oral nutrition supplement enriched with arginine, vitamin C and zinc on pressure ulcers: a pragmatic randomised trial. Clin Nutr. 2013. doi: PubMed
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下