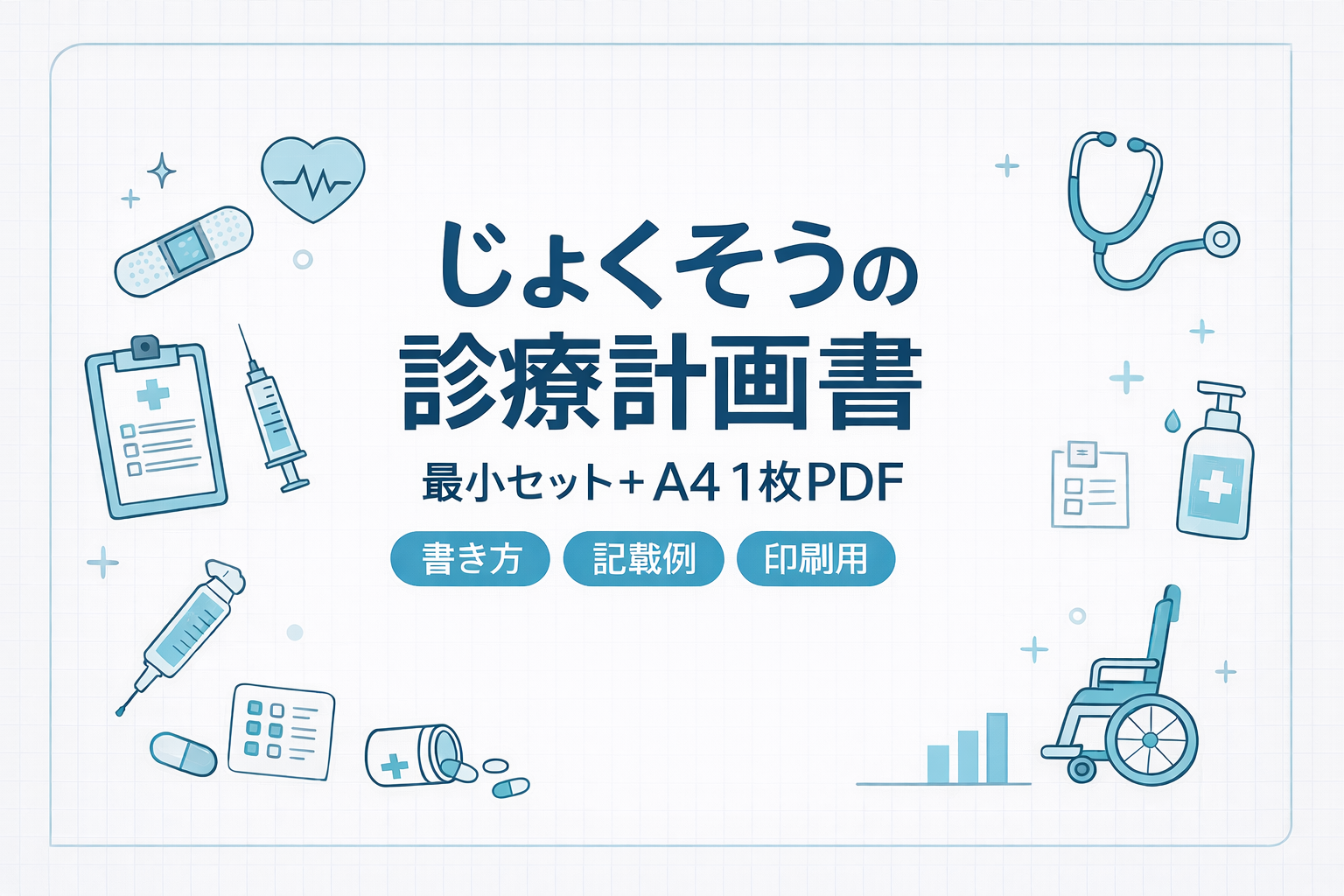褥瘡の診療計画書|「迷わず埋まる」最小セットと書き方
褥瘡の診療計画書は、様式を埋めるだけでなく「誰が・いつまでに・何を変えるか」を多職種で共有するための“運用の紙”です。書く量を増やすより、評価→対策→再評価の流れが一筆で追える形に整えると、カンファや申し送りが一気にラクになります。
この記事では、現場で使いやすい A4 1 枚の記録用ひな形と、埋まりにくい欄が埋まる考え方をセットでまとめます。関連:評価の全体像(リスク評価の整理)を先に確認したい場合は 評価ハブ もどうぞ。
褥瘡対応は「標準化(誰でも同じように書ける)」で差がつきます。現場の型づくりを短時間で整理したい方はこちら。 評価 → 記録 → 再評価の流れを 3 分で整理する
配布 PDF(A4・印刷用)
下のボタンから、印刷してそのまま使える A4 1 枚の診療計画書(記録用ひな形)を開けます。病棟・回復期・施設で共通運用しやすいよう、余白と記入欄を広めに確保しています。
プレビューを表示(タップで開く)
書き方のコツ|「埋まる順番」で考える
埋まりにくいのは、最初から “対策” を書こうとするパターンです。おすすめは ①スクリーニング → ②褥瘡の状態(あれば) → ③具体策 → ④再評価 の順番。先に「いま何が起きているか」を短く押さえると、対策欄が自然に埋まります。
特に 1 枚運用では、文章を長くするより頻度・条件・担当をそろえる方が伝達ミスが減ります(例:2 時間毎、30°側臥位、夜勤帯も含む、など)。
| 欄 | 最小で書くこと | よくある失敗 | すぐ効く対策 |
|---|---|---|---|
| 日常生活自立度・危険因子 | 寝たきり度、体位変換、除圧、皮膚湿潤、栄養、骨突出・拘縮 | 「低栄養あり」など抽象語だけで終わる | “観察で言える事実”を 1 つ入れる(例:摂取量 6 割、尿失禁あり 等) |
| 褥瘡の状態(あれば) | 部位、深さ、サイズ( L × W )、ポケット、滲出液、局所所見 | 局所所見が空欄で、判断材料が残らない | “壊死/肉芽/周囲皮膚/疼痛”を 1 語ずつでも良いので埋める |
| 具体策(方法・頻度・目標) | 体圧分散、体位変換、シーティング、スキンケア、離床、栄養 | 方法だけで頻度や担当が抜ける | 「誰が」「何時間/何回」「いつ再評価」をセットで書く |
| 再評価・署名 | 再評価予定日、カンファ日、変更点(要点) | 再評価日が未記載で、計画が回らない | “次のカンファ”に合わせて日付を先に入れる |
スクリーニングで押さえるポイント
褥瘡の予防では、スキンケアだけでなく体圧・湿潤・栄養・活動が同時に絡みます。計画書は「原因の当たり」をつける工程なので、ここでの書き漏れが後工程の漏れにつながります。
- 体位変換・除圧:自力か介助か、どの程度の頻度が現実的か
- 皮膚湿潤:尿・便失禁、多汗、ドレッシングの浸出で湿る時間が長くないか
- 栄養:体重変化、摂取量、低栄養が疑われる根拠(数字か観察)
- 活動・離床:臥床時間が長い/座位が長い、どちらが主因か
局所所見の書き方|短くても“次が決まる”言葉
局所所見は長文にしなくて OK です。重要なのは、次の介入(ドレッシング・除圧・体位・疼痛)に直結する語を残すこと。目安は次の 4 つです。
- 壊死:なし/薄い痂皮/厚い痂皮/壊死主体
- 肉芽:良好/不良
- 周囲皮膚:発赤/浮腫/びらん/硬結 など
- 疼痛:なし/軽度/中等度/高度(体位変換時など条件も短く)
現場の詰まりどころ(よくある失敗)
ここが詰まると、計画書が「書いたけど回らない」状態になります。ありがちな失敗を先に潰しておくと、回診・カンファ・申し送りが安定します。
- 対策が “一般論” で、頻度・条件・担当が抜ける
- スキンケアだけに寄って、除圧と活動が薄くなる
- 再評価日が未記載で、更新のタイミングが消える
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
診療計画書は「いつ」作って、どれくらいの頻度で見直しますか?
現場では「入院/入所直後に作成 → カンファに合わせて更新」が運用しやすいです。最初に再評価予定日を入れておくと、更新がルーチン化します。褥瘡の状態や除圧方法が変わったときは、予定日前でも要点だけ更新して共有するのがおすすめです。
褥瘡が「ない」人にも、この計画書は使いますか?
使えます。褥瘡がない場合は、スクリーニング欄(危険因子)と対策欄(予防策)を中心に運用すると、予防の抜けが減ります。特に体位変換・除圧・湿潤対策・栄養は、褥瘡ができる前に型を作るほど効果が出ます。
局所所見が書けない(自信がない)ときはどうすれば?
最初は “観察できる事実” に寄せて短く残すのが安全です。例:滲出液が多い/少ない、周囲皮膚が発赤している、体位変換時に痛みがある、など。評価語を増やすより、同じ条件で観察できる形に整える方が再評価で役に立ちます。
次の一手
- まずは PDF を印刷して、1 回だけカンファで試運用(埋まらない欄が出たら、運用ルール側を調整)
- 評価の整理を先に整える:評価ハブ
- 環境の詰まり(教育体制・記録文化・標準化)も点検する:無料チェックシートを確認
参考文献
- European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA; 2019. 公式
- Bergstrom N, Braden BJ, Laguzza A, Holman V. The Braden Scale for Predicting Pressure Sore Risk. Nurs Res. 1987;36(4):205-210. PMID: 3299278
- Sanada H, et al. Clinical wound assessment using DESIGN-R total score can predict pressure ulcer healing. Wound Repair Regen. 2011. PMID: 22092794
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下