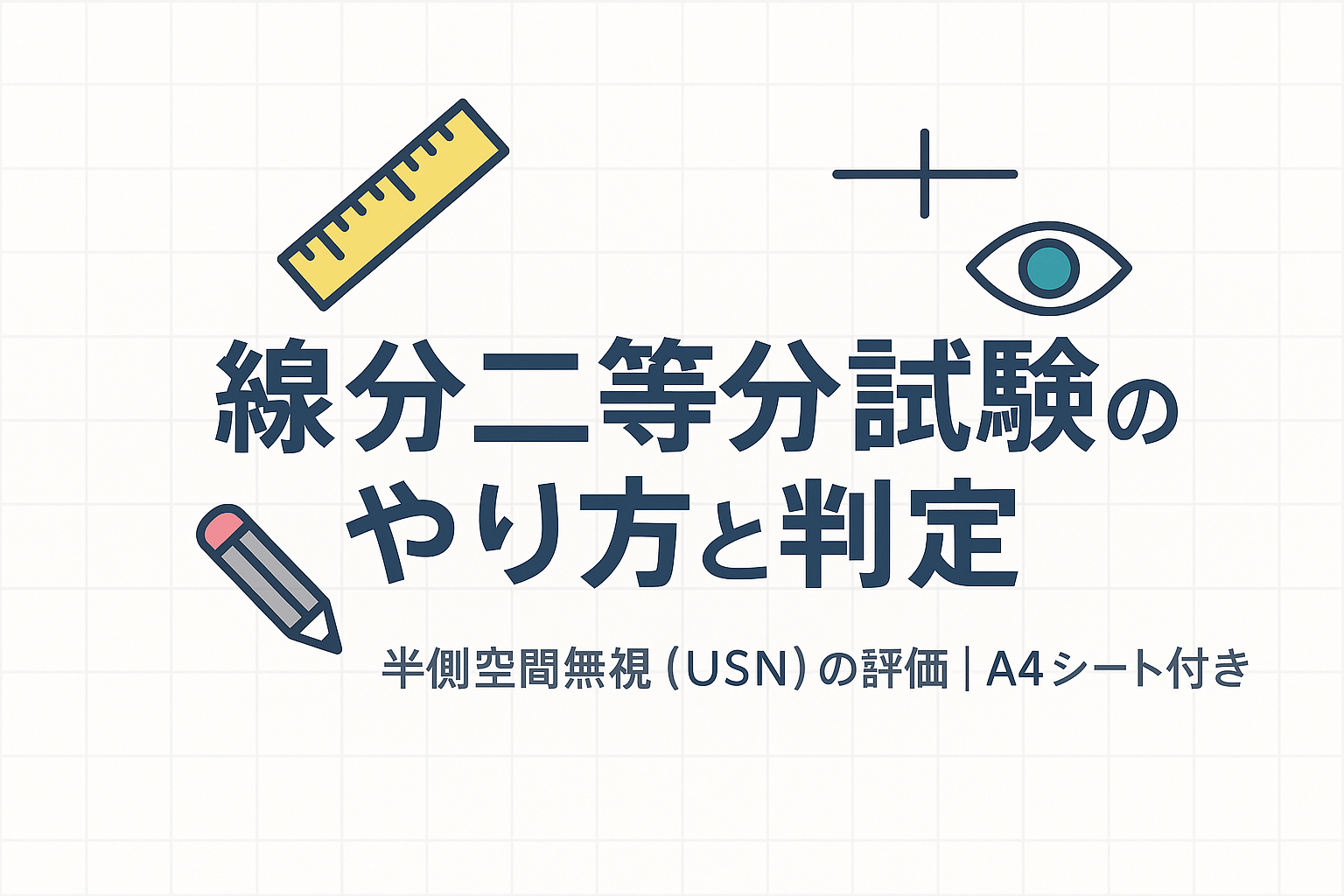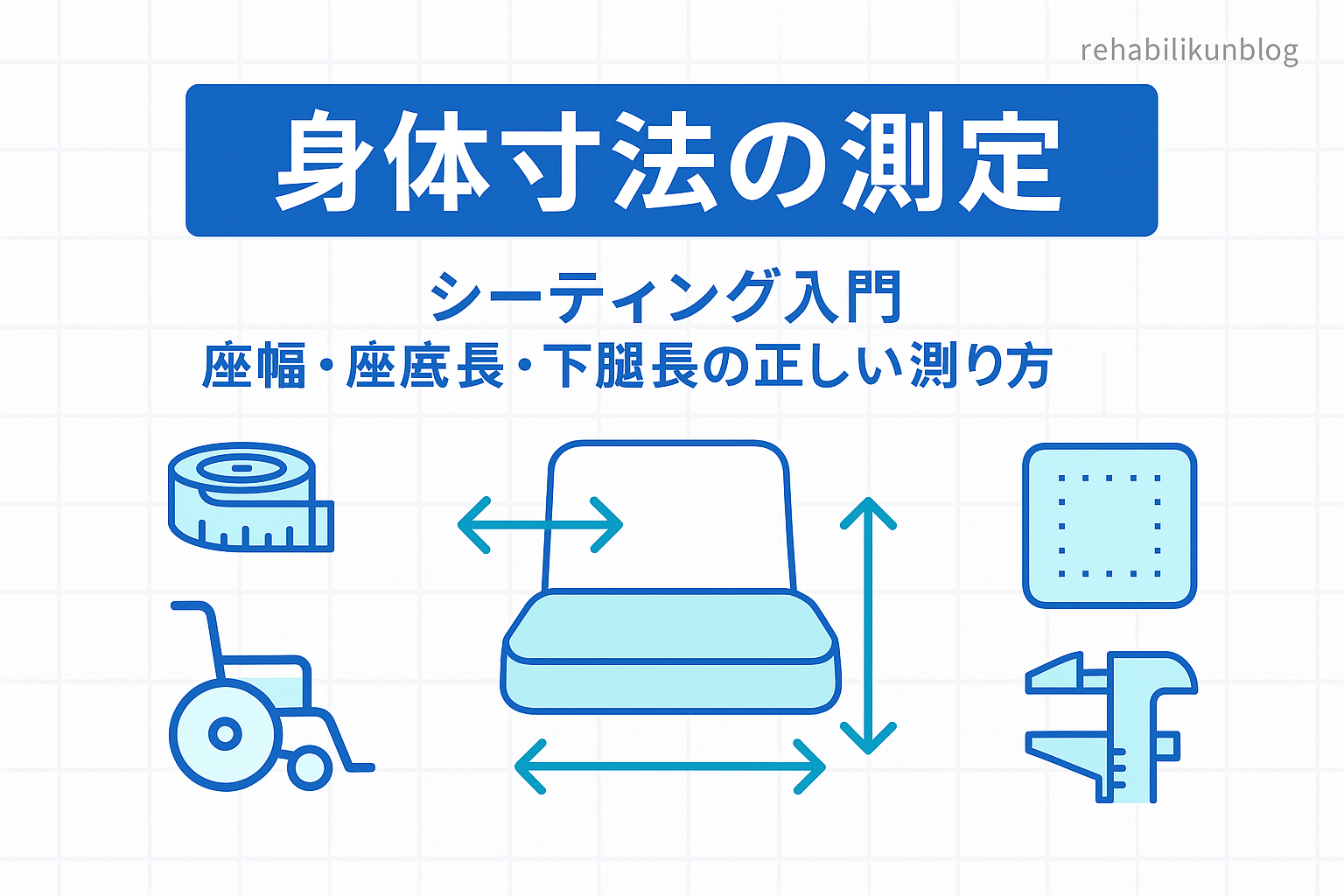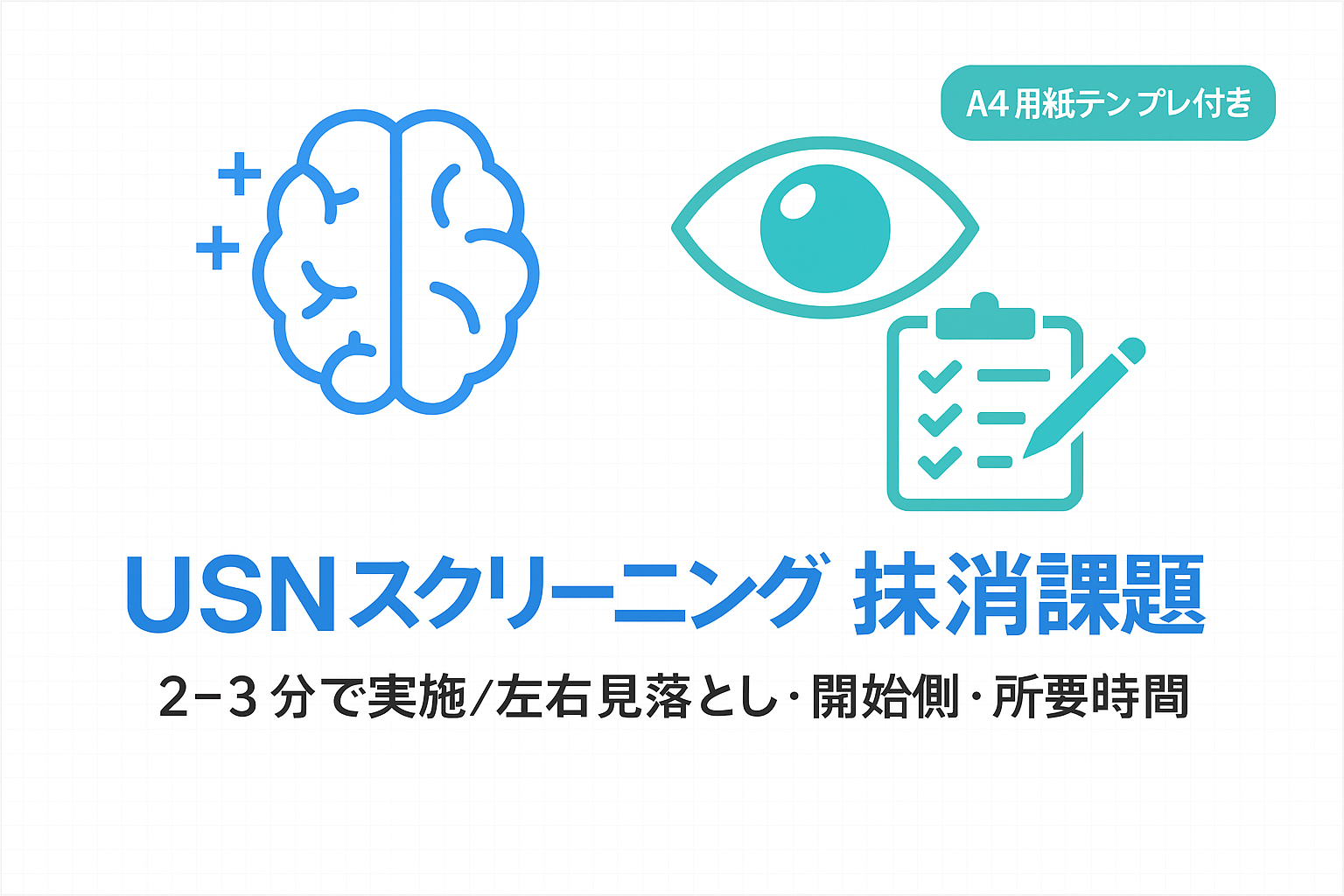線分二等分試験とは(USN を “短時間で定量” する)
線分二等分試験( Line Bisection Test )は、提示された線分の “中心” を指示してもらい、真の中心からの偏位( mm / % )を残すことで、USN(半側空間無視)の偏りを短時間で定量できる机上テストです。ポイントは「検査を増やす」より、用紙位置・姿勢・教示・線長を固定して、同条件で再評価できる形にすることです。
1 分でわかる:手順と判定の結論
- 線分の中心に “短い縦線” を引いてもらい、真の中心からの偏位を mm で測ります。
- 記録は ① 偏位量( mm )、② 方向(右+/左−)、③ 条件セット(姿勢・用紙位置・利き手など)の 3 点を固定します。
- 迷ったら “方向の一貫性” と “条件ズレ” を先に点検し、必要に応じて他検査・観察所見と整合を取ります。
線分二等分試験のやり方( 1〜2 分で標準化 )
- 準備:A4 用紙、筆記具、机上(肘が置ける高さ)。眼鏡が必要なら装着します。
- 姿勢:骨盤を椅子の奥に、体幹正中を机に向けます(可能なら両足接地)。
- 用紙位置:まずは体幹正中に置きます(左右にずらす運用をする場合は “何 cm 右 / 左” を固定して記録します)。
- 教示(例):「この線のちょうど真ん中だと思うところに、短い縦線で印をつけてください。」
- 練習:練習を 1 本だけ。理解が不十分なら再説明し、以後の教示は同一にします。
- 本試行:複数本で実施し、偏位を記録します(本数は施設運用で固定)。
ポイントは「毎回同じやり方」に揃えることです。検者が変わっても比較できるように、条件セットをカルテに固定で残します。
判定で残すべき 3 点( mm / % / 方向 )
※スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 要素 | 何を残す? | 理由 | 記載例 |
|---|---|---|---|
| 偏位量 | 真の中心から標記まで( mm ) | 経時変化が追える | 平均 + 8 mm(右) |
| 方向 | 右+/左− など符号で統一 | 所見がブレにくい | 右偏位(+) |
| 条件セット | 姿勢・用紙位置・利き手・眼鏡・覚醒 | 比較の前提が崩れにくい | 座位、正中、右手、眼鏡あり |
偏位量の測り方と計算( mm と % )
偏位( mm )は、実線両端の真の中心から、患者の標記までの距離です。右偏位を(+)、左偏位を(−)のように、符号を揃えると記録が安定します。
- 符号つき平均:方向の一貫性を見る(例: + 8 mm )
- 絶対値平均:ズレの大きさだけを見る(例: 8 mm )
% 表記にする場合は、線分長で割って 100 を掛けます(線長が混在する運用では % が便利です)。
計算式:偏位( % )= 偏位( mm )÷ 線分長( mm )× 100
例:線分長 200 mm、偏位 + 8 mm → 8 ÷ 200 × 100 = 4 %(右)
解釈のコツ(USN / 半盲 / 理解・運動要因)
線分二等分の偏位は USN の重要所見になり得ますが、半盲・理解・上肢運動で “それっぽく見える” こともあります。迷ったら、次の OK / NG で最小限に整理します。
※スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 観察 | USN らしい | 別要因の可能性 | 次の一手 |
|---|---|---|---|
| 方向が一貫 | 同方向へ安定して偏位 | 試行ごとに方向がバラつく | 条件セット確認、試行数を固定 |
| 探索の偏り | 左側への注意が薄い所見が併存 | 視野欠損や見えづらさが主 | 視野・眼鏡・視力、他検査で整合 |
| 教示理解 | 教示は理解できている | 失語・注意低下で理解が不安定 | 短文化、練習 1 本、再現性を優先 |
| 運動の影響 | 上肢運動は安定 | 振戦・失調・巧緻低下で線がぶれる | 前腕支持、筆記具変更、所見に併記 |
品質管理(条件ズレを潰す:OK / NG )
線分二等分は “測り方” よりも、条件ズレで比較不能になりやすい検査です。運用を回すための最小ポイントだけ整理します。
※スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 詰まりどころ | NG(起きがち) | OK(最小の修正) | 記録に残す一言 |
|---|---|---|---|
| 用紙位置 | 毎回置き方が違う | 正中 or 右/左にずらす cm を固定 | 用紙:正中 |
| 姿勢 | 体幹が回旋したまま | 骨盤・体幹正中を先に作る | 座位:正中 |
| 教示 | 検者で言い方が違う | 短い定型文で統一 | 教示:統一 |
| 学習効果 | 同じ用紙を頻回に実施 | 再評価間隔と用紙を固定(運用ルール化) | 再評価:同条件 |
現場の詰まりどころ/よくある失敗( OK / NG 早見 )
線分二等分は「数値が出る」ぶん、条件ズレがあると誤解釈が起きやすい検査です。チーム共有では “偏位量” と同じくらい、条件セットを残すことが大切です。評価が増えて回らないときは、まず条件の棚卸しから整えるとラクになります(関連:面談準備チェックで条件を棚卸しする)。
※スマホでは表を左右にスクロールできます。
| 失敗 | 起きること | 修正(最小) | 所見の書き方 |
|---|---|---|---|
| 偏位だけで断定 | 半盲や理解で混線 | 他検査・観察と整合確認 | 総合所見として記載 |
| 符号が統一されない | 左右が逆に読まれる | 右+/左− を固定 | +(右)で統一 |
| 用紙位置が毎回違う | 再評価が比較不能 | 正中基準、ずらすなら cm 固定 | 用紙:正中 |
| 運動で線がぶれる | 偏位が過大に見える | 前腕支持、筆記具変更、所見に併記 | 運動影響あり |
判定・記録テンプレ(コピペ可)
カルテに残すための最小テンプレです。偏位( mm )+方向+条件セットが入っていれば、チーム共有が崩れにくくなります。
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 条件 | 座位、体幹正中、用紙正中、右手、眼鏡あり、覚醒良好 |
| 結果(符号つき平均) | 平均 + 8 mm(右偏位) |
| 結果(絶対値平均) | 平均 8 mm |
| 所見の解釈 | 右偏位が一貫。観察所見とあわせて USN を疑う。 |
| 次の一手 | 同条件で再評価。必要に応じて ADL 観察へ。 |
よくある質問( FAQ )
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
線分の長さや本数は、毎回変えてもいいですか?
基本は運用で固定するのがおすすめです。線長や本数が変わると、再評価の比較が難しくなります。用紙と条件セットを決めて「同じレイアウトで回す」方が、経時変化を説明しやすくなります。
右+/左− の符号は、なぜ必要ですか?
方向の一貫性が “所見の軸” になるためです。符号を揃えると、左右が逆に読まれる事故が減り、カルテの再現性が上がります。
偏位が小さいのに、生活場面で明らかに困っています。どう扱いますか?
机上テストが軽度でも、生活場面で悪化することがあります。観察所見や他検査とあわせて総合的に判断し、「机上」と「ADL」のズレを所見として残すと安全です。
失語があって教示が通りません。代替はありますか?
教示を短くし、練習を 1 本だけにします。理解が不十分な場合は、線分二等分の結果を “参考所見” にとどめ、観察所見を厚めに残す運用が安全です。
ダウンロード(A4 記録シート PDF )
印刷してそのまま使える A4 記録シートです。
プレビュー(タップで開く)
次の一手(次に読む)
- 評価の全体像(親記事):半側空間無視( USN )評価| 5〜10 分フロー
- 机上テスト(兄弟):抹消課題のやり方と判定【USN・注意障害】
- 迷ったら戻る:評価ハブ(リハビリ評価の索引)
参考文献
- Schenkenberg T, Bradford DC, Ajax ET. Line bisection and unilateral visual neglect in patients with neurologic impairment. Neurology. 1980;30(5):509-517. doi: 10.1212/WNL.30.5.509
- Wilson B, Cockburn J, Halligan P. Development of a behavioral test of visuospatial neglect. Arch Phys Med Rehabil. 1987. PubMed: 3813864
- Kwon S, et al. Relationship Between Line Bisection Test Time and Prognosis of Hemispatial Neglect in Stroke Patients. Ann Rehabil Med. 2020. PMC: PMC7463114
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下