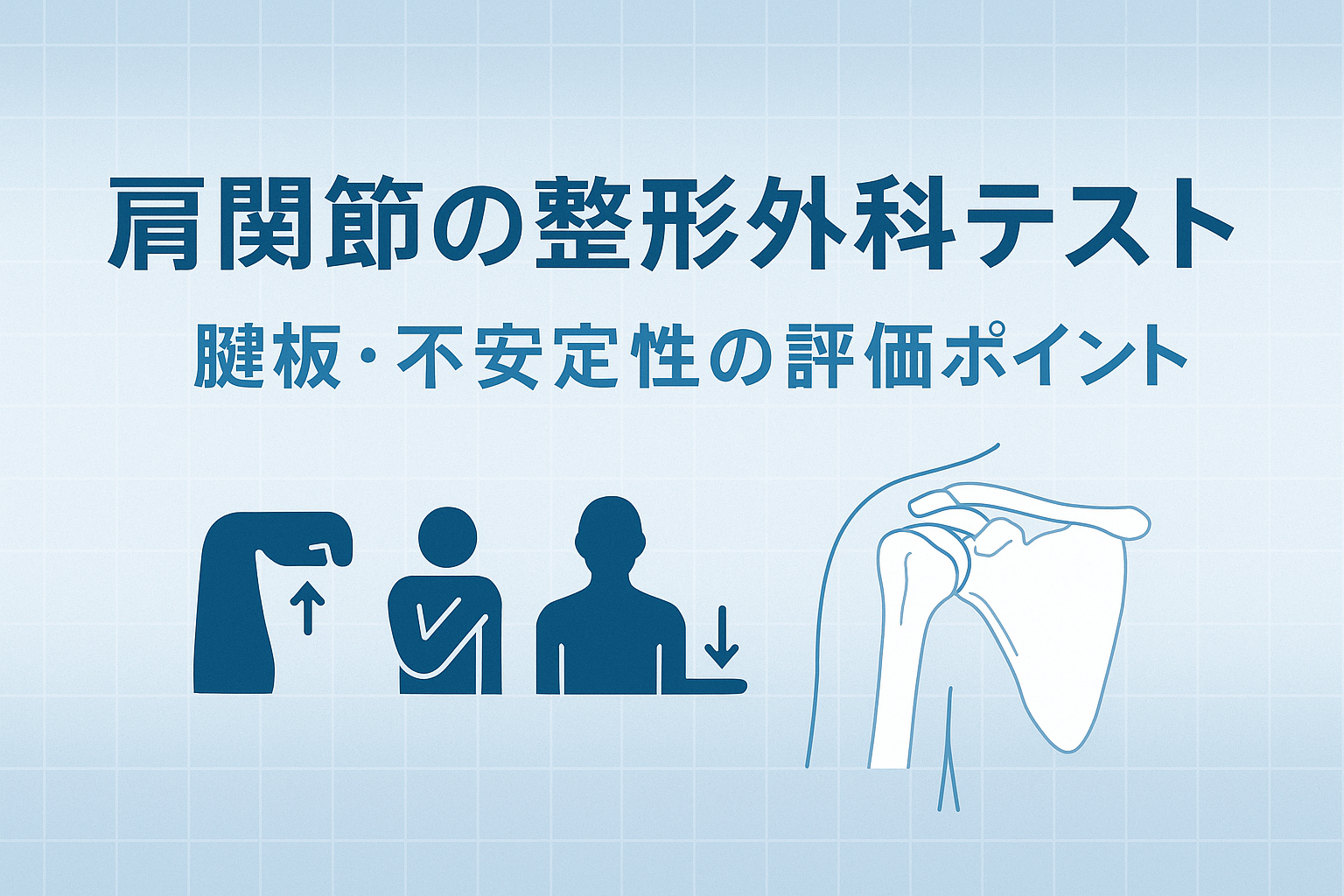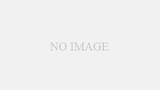- 肩関節の整形外科テスト一覧|Neer/Hawkins の違いと“最小セット”運用
- まずはここへ|子記事 3 本で “迷いどころ” を最短解決
- 5 分で回す|肩の評価フロー(問診→最小テスト→次アクション)
- 痛みパターン × 疑う病態|最短で当たりを付けるマトリクス
- 病態別“最小セット”|どれをいつ使うか(一覧+使い分け)
- テスト別の要点|Neer/Hawkins/Painful Arc ほか(“違い”と記録の型)
- 評価結果をリハへ落とす|“陽性”を介入の言葉に変換する
- 現場の詰まりどころ|迷いを減らす“解決の三段”
- よくある失敗|“偽陽性”と“やり過ぎ”を避ける
- 回避の手順・チェック|再評価でブレない“固定項目”
- よくある質問(FAQ)
- 次の一手|運用を整える→共有の型→環境の詰まりも点検
- 参考文献
- 著者情報
肩関節の整形外科テスト一覧|Neer/Hawkins の違いと“最小セット”運用
肩関節の整形外科テストは、腱板・インピンジメント、不安定性、関節唇( SLAP )、肩鎖関節、上腕二頭筋長頭腱などの病態候補を絞るための仮説づくりです。テスト単独で確定診断はできないため、受傷機転・年齢・痛みの部位と角度・可動域・筋力(痛み抑制か真の低下か)をセットで見て、介入と再評価につなげます。
本記事は、現場でブレないように① 5 分フロー→② 痛みパターン×病態マトリクス→③ 病態別“最小セット”→④ よくある失敗の回避までを 1 ページで固定します。
同ジャンルで回遊して、判断を速くする:肩だけで迷うときは「部位ハブ→親(本記事)→子記事(各論)」で整理するとブレが減ります。
まずはここへ|子記事 3 本で “迷いどころ” を最短解決
肩の評価は、親(本記事)で全体像を作り、子記事で筋別・病態別の運用を固定すると回ります。特に臨床で詰まりやすい 3 つ(インピンジメント/腱板/不安定性)は、先に子記事へ飛ぶ方が早いです。
どの記事でも、「何が起きたか」ではなく「どの角度で・どこが・どんな反応(痛み / 不安感 / 力の抜け)か」を 1 行で残すと、再評価がブレません。
| 迷いどころ | まず読む | この親記事で見る場所 | 得られること |
|---|---|---|---|
| 挙上で外側が痛い(疼痛アーク) | インピンジメントのテスト( Neer / Hawkins ) | 痛みマトリクス / 最小セット | 偽陽性を増やさず、最小セットで当てる |
| “力が出ない” が混ざる(腱板) | 腱板テストまとめ(筋別) | 最小セット / テスト別の要点 | 痛み抑制と真の低下を分けて記録できる |
| 外旋で “抜けそう / 怖い”(不安定性) | 不安定性テスト(安全運用) | 最小セット / よくある失敗 | 恐怖感( apprehension )中心で安全に評価できる |
5 分で回す|肩の評価フロー(問診→最小テスト→次アクション)
肩は「テストを増やす」ほど迷いやすい領域です。まずは少数の情報で仮説を作り、必要なら追加テストへ進みます。初回は下の流れだけで十分に方針が立ちます。
ポイントは、“陽性 / 陰性”よりも「どの角度・どの部位で・どんな反応(痛み / 不安感 / 力の抜け)か」を 1 行で記録することです。
| 順序 | 見ること | 観察・記録の型(例) | 次の一手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 受傷機転・既往 | 外傷 / 脱臼既往 / 投球歴 / 夜間痛 / クリック | 危険なら医師連携・負荷回避 |
| 2 | 痛みの主座と角度 | 外転 “ 70–120° ” で外側痛、前面痛、上方痛など | マトリクスで仮説を置く |
| 3 | AROM / PROM | 可動域制限の型(痛みで止まる / 硬い / 代償が強い) | 拘縮優位なら ROM 戦略へ寄せる |
| 4 | “最小セット” 2〜4 個 | 病態別(インピンジメント / 腱板 / 不安定性 / 関節唇 / AC / 長頭腱) | 疑いを 1〜2 個に絞る |
| 5 | 介入→再評価 | 痛み角度・反応・できる動作( ADL / スポーツ)を再測定 | 同じ条件で 2〜3 指標を追う |
痛みパターン × 疑う病態|最短で当たりを付けるマトリクス
肩は「どれも痛い」になりやすいので、まず痛みの主座(どこが一番つらいか)と出やすい動作・角度で当たりを付けます。ここが揃うと、テスト選択が一気に速くなります。
“混在”が多いのが前提です。マトリクスは最初の仮説として使い、必要なら次章の“最小セット”へ進めます。
| 痛みの主座 | 出やすい動作・角度 | まず疑う | まずやる最小セット(例) | 次に確認する |
|---|---|---|---|---|
| 外側(上腕外側) | 挙上で増悪/疼痛アーク(例: 70–120° ) | 肩峰下インピンジメント / RCRSP | Neer 、 Hawkins 、 Painful Arc | ROM(代償込み)+ “痛み抑制か真の低下か” |
| 前面(結節間溝付近) | 肘屈曲+回外で増悪/前方挙上で痛む | 長頭腱の負荷関連 / 合併(腱板・唇) | Speed (補助)、 Yergason (必要時) | 圧痛部位(溝 / 大結節 / AC )+混在痛の整理 |
| 上方( AC 付近) | 水平内転で増悪/上方限局の圧痛 | 肩鎖関節障害 | 水平内転での症状再現(動作テスト) | 局所圧痛・腫脹・荷重 / 支持での増悪 |
| 後方・深部 | 投球動作/引っかかり・クリック | 関節唇( SLAP 等)/ 不安定性の合併 | O’Brien 、不安定性の確認(方向) | 機転・反復動作・クリックの場面を問診で特定 |
| 「抜けそう」「怖い」 | 外旋位で不安/防御性収縮 | 不安定性 | Apprehension (反応で止める)、 Relocation | 中止基準の徹底+危険域の回避と動的安定化 |
病態別“最小セット”|どれをいつ使うか(一覧+使い分け)
テストは 2〜4 個に絞ると回ります。まずは下表の“最小セット”で仮説を固め、必要なら追加テストへ進みます。臨床では同じ患者にテストを増やしすぎないことが、評価の再現性(再評価の精度)に直結します。
陽性の定義は「痛い」だけで終わらせず、痛みの部位・角度・反応(痛み / 不安感 / 力の抜け)を 1 行で残してください。
| 疑う病態 | 最小セット(例) | 見るポイント | 次に確認する |
|---|---|---|---|
| インピンジメント / 腱板関連疼痛 | Neer / Hawkins / Painful Arc | 痛み角度・主座、代償(肩甲帯の前方化・挙上) | 棘上筋: Empty / Full Can を追加(必要時) |
| 腱板(筋別に当てたい) | Full / Empty Can / ER 抵抗 / Lift-off(できる範囲) | “痛み抑制” と “保持不能(真の低下を示唆)” を分ける | 追うテストを 1〜2 個に固定して再評価 |
| 大断裂(疑い) | Drop Arm / ER 抵抗(外旋)/挙上の抗重力の可否 | “力が抜け落ちる” 反応、常位での脱力感 | 負荷を上げずに医師連携(必要時) |
| 不安定性(前方 / 下方) | Apprehension / Relocation /(必要時) Sulcus Sign | 痛みではなく “ apprehension(怖さ)” を重視 | 危険域の回避+動的安定化(肩甲帯・体幹) |
| 関節唇( SLAP など) | O’Brien /(必要ならクリック再現動作) | 回内で増悪→回外で軽減など “条件差” | 混在( AC / 長頭腱 / 腱板)を除外していく |
| 肩鎖関節( AC ) | 水平内転での症状再現(動作テスト)+局所圧痛 | 上方限局痛・圧痛の一致 | 挙上角度と荷重ラインの調整へ |
| 上腕二頭筋長頭腱(合併が多い) | Speed / Yergason(必要時)+溝部圧痛 | 前面痛の主座が “溝” に一致するか | 腱板・唇の合併を前提に負荷を調整 |
テスト別の要点|Neer/Hawkins/Painful Arc ほか(“違い”と記録の型)
同じテスト名でも、条件がバラつくと再評価で比較できません。ここでは「やり方」よりも条件固定と記録の型に絞って整理します。
迷ったら、固定すべき条件(体位・肩甲骨固定・角度)と陽性の書き方(どこが・どの角度で・何が起きたか)だけを揃えるのが先です。
| テスト | 主に狙う | 条件固定(例) | 記録の型(例) |
|---|---|---|---|
| Neer | 肩峰下インピンジメント(棘上筋・滑液包など) | 肩甲骨を固定して前方挙上、代償を抑える | “挙上 120° 付近で外側痛(肩峰下)再現” |
| Hawkins | 肩峰下インピンジメント | 肩関節 90° 屈曲位から内旋、肩甲帯のすくみを抑える | “内旋で外側痛↑、角度と部位を記録” |
| Painful Arc | 肩峰下インピンジメント(疼痛アーク) | 自動外転の角度帯(例: 70–120° )を観察 | “ 80–110° で痛み、終末で軽減” |
| Empty / Full Can | 棘上筋機能(痛み抑制との鑑別が重要) | 外転位で抵抗、肢位と回旋を固定 | “痛みで抑制 / 保持不能” を分けて書く |
| Drop Arm | 大きな腱板断裂(疑い) | 他動挙上→ゆっくり降ろす、疼痛で無理はしない | “保持できず落下 / 疼痛で中止” を明確化 |
| Sulcus Sign | 下方不安定性 | 下方牽引で溝の出現を観察(左右差) | “下方溝:左右差あり / apprehension あり” |
| Apprehension / Relocation | 前方不安定性(方向) | “痛み”より “怖さ” を優先、怖さが出た時点で止める | “外旋で apprehension 、支持で軽減” |
| O’Brien | 関節唇( SLAP など)/ ただし混在が多い | 回内(母指下)と回外(母指上)で条件差を見る | “回内で前上方痛↑→回外で軽減” など条件差を書く |
| Speed / Yergason | 上腕二頭筋長頭腱(合併前提) | 溝部圧痛と合わせて解釈 | “前面痛:溝部圧痛一致 / 混在あり” |
評価結果をリハへ落とす|“陽性”を介入の言葉に変換する
肩のテストはチェックリストではなく、介入の優先順位を決める材料です。陽性だった“構造名”よりも、どの動作で・どの角度で・何が起きたかを言語化すると、チーム共有と再評価が揃います。
たとえばインピンジメント疑いなら、いきなり高負荷より肩甲帯と体幹を含む挙上パターンの再学習を先に置くと、痛み角度が先に改善しやすいです。不安定性疑いなら、怖さが出る危険域を避けつつ、安全域での動的安定化(ローテーターカフ+肩甲帯)を積むのが基本になります。
| まとめる観点 | 書き方(例) | 介入の方向性(例) |
|---|---|---|
| 痛みの主座 | 外側 / 前面(溝)/ 上方( AC )/ 深部 | 主座に負荷が集まる動作を特定 |
| 痛み角度・条件 | 挙上 90–120° で増悪、回内で増悪など | 角度と負荷ラインを調整して再現性を取る |
| 反応の種類 | 痛み / apprehension / 力の抜け | 不安感優位なら安全域の安定化へ |
| 筋力の解釈 | 痛み抑制か真の低下か(条件を添える) | 痛み抑制なら負荷よりパターン修正を優先 |
| 再評価指標 | 痛み角度( 1 つ)+代表テスト( 1〜2 個) | 同じ条件で追い、変化を 1 行で共有 |
現場の詰まりどころ|迷いを減らす“解決の三段”
肩は「情報が多いのに決め切れない」が起きやすい領域です。まずはページ内で迷いどころを潰す→回避手順を固定→共有指標で言語化の順で整理すると、方針が通りやすくなります。
- よくある失敗(まずここを潰す)へ
- 回避の手順・チェック(再評価でブレない)へ
- 同ジャンルの内部リンク 1 本:QuickDASH(上肢の困りごとを 1 行で共有)
よくある失敗|“偽陽性”と“やり過ぎ”を避ける
肩のテストは偽陽性が増えやすいのが前提です。特に疼痛が強い症例では、「どれも痛い」で情報価値が下がります。下の表で NG → OK の置き換えを先に決めておくと、評価の再現性が上がります。
| ありがち( NG ) | なぜ起きる | 回避( OK ) | 記録ポイント |
|---|---|---|---|
| テストを増やしすぎる | 痛みが増えて “全部陽性” になる | 最小セット 2〜4 個に絞る | 実施数を残す( “本日は 3 個まで” ) |
| “痛い=陽性” で終わる | 痛みの主座・角度が不明で再評価不能 | 部位+角度+反応を 1 行で書く | “外側痛/ 90–120° /痛みのみ” など |
| 肩甲帯の代償を見ない | 胸椎後弯・肩甲帯前方化で偽陽性 | AROM / 代償を先に観察し条件を揃える | 肩甲帯挙上・前方化の有無 |
| Apprehension を押し切る | 心理的ストレス・危険域で悪化 | 怖さが出た時点で止め、方向だけ取る | “怖さ / 防御性収縮” を明記 |
| 筋力低下を断裂と決める | 痛み抑制で力が出ないことが多い | 痛み抑制か真の低下かを分けて評価 | 疼痛条件(肢位・角度)を残す |
回避の手順・チェック|再評価でブレない“固定項目”
再評価で比較できない原因は「条件が毎回違う」ことです。次の 4 つだけ固定すると、肩の評価は一気に安定します。
固定できたら、共有は 1 行で十分です(例:“挙上 90–120° の外側痛は軽減、 Hawkins は痛み減、 ADL は上衣更衣が改善”)。
| 固定すること | 具体 | 理由 |
|---|---|---|
| 体位 | 座位 / 立位 / 背臥位を決める | 肩甲帯の代償が変わる |
| 角度・肢位 | 90° 屈曲位など “開始条件” を揃える | 痛みが出る条件差が本体 |
| 肩甲骨固定の有無 | 固定する / しないを明記 | 再現性と解釈が変わる |
| 実施テスト数 | 最小セット( 2〜4 個)を毎回同じに | 痛み増悪による偽陽性を避ける |
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Neer と Hawkins はどう違う?どちらを優先する?
両者はどちらも肩峰下の圧迫で症状を誘発しやすいテストですが、臨床では「どちらが正しいか」よりも条件固定と痛みの主座・角度の記録が重要です。まずは Painful Arc と合わせて “挙上のどこで何が起きるか” を押さえ、必要なら棘上筋テスト( Empty / Full Can )で “痛み抑制か真の低下か” を確認すると、介入に落ちやすくなります。
テストは何個までやればいい?
基本は最小セット 2〜4 個で十分です。肩はテストを増やすほど疼痛が増え、“全部陽性” になりやすく情報価値が落ちます。初回は「痛み角度・主座」「 AROM / 代償」「病態別最小セット」で仮説を置き、次回以降は同じ条件で追うのがおすすめです。
Apprehension テストが怖がられて進められない時は?
“怖さ( apprehension )” が出た時点で十分な情報です。無理に外旋を進めず、その場で負荷を緩め、どの方向で不安が出るかを記録します。以降は危険域の回避と、安全域での動的安定化(肩甲帯・体幹を含む)を優先して進めます。
O’Brien 陽性なら SLAP と考えてよい?
短絡は避けたほうが安全です。 O’Brien は関節唇の関与を示唆し得ますが、 AC 関節や長頭腱、腱板などでも症状が変化します。臨床では、クリックや引っかかりの場面、投球歴、痛みの主座(深部か上方か)を合わせて “混在をほどく” 意識が重要です。
次の一手|運用を整える→共有の型→環境の詰まりも点検
肩は症例差が大きいので、個人の経験に依存すると運用が揺れやすい領域です。まずは院内で「回す型」を整え、共有の言葉を揃えると、介入の意思決定が速くなります。
- 運用を整える:上肢評価の全体像を “最小セット” で固定する → 上肢機能評価の使い分け(目的→最小セット→比較表)
- 共有の型を作る:上肢の困りごとを 1 行で共有できるようにする → QuickDASH(計算・欠損ルール・解釈)
- 環境の詰まりも点検:教育体制・人員・記録文化など“環境要因”を一度見える化すると、次の打ち手が決めやすくなります。
チェック後に『続ける/変える』の選択肢も整理したい方は、PT キャリアナビで進め方を確認しておくと迷いが減ります。
参考文献
- Hegedus EJ, Goode A, Campbell S, et al. Which physical examination tests provide clinicians with the most value when examining the shoulder? Br J Sports Med. 2012;46(14):964-978. doi:10.1136/bjsports-2012-091066
- Alqunaee M, Galvin R, Fahey T. Diagnostic accuracy of clinical tests for subacromial impingement syndrome: a systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2012;93(2):229-236. doi:10.1016/j.apmr.2011.08.035
- Lafrance S, Dyer JO, et al. Diagnosing, Managing, and Supporting Return to Work of Adults with Rotator Cuff Disorders: A Clinical Practice Guideline. J Orthop Sports Phys Ther. 2022. doi:10.2519/jospt.2022.11306
- American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). Management of Rotator Cuff Injuries Clinical Practice Guideline. 2025. PDF
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下