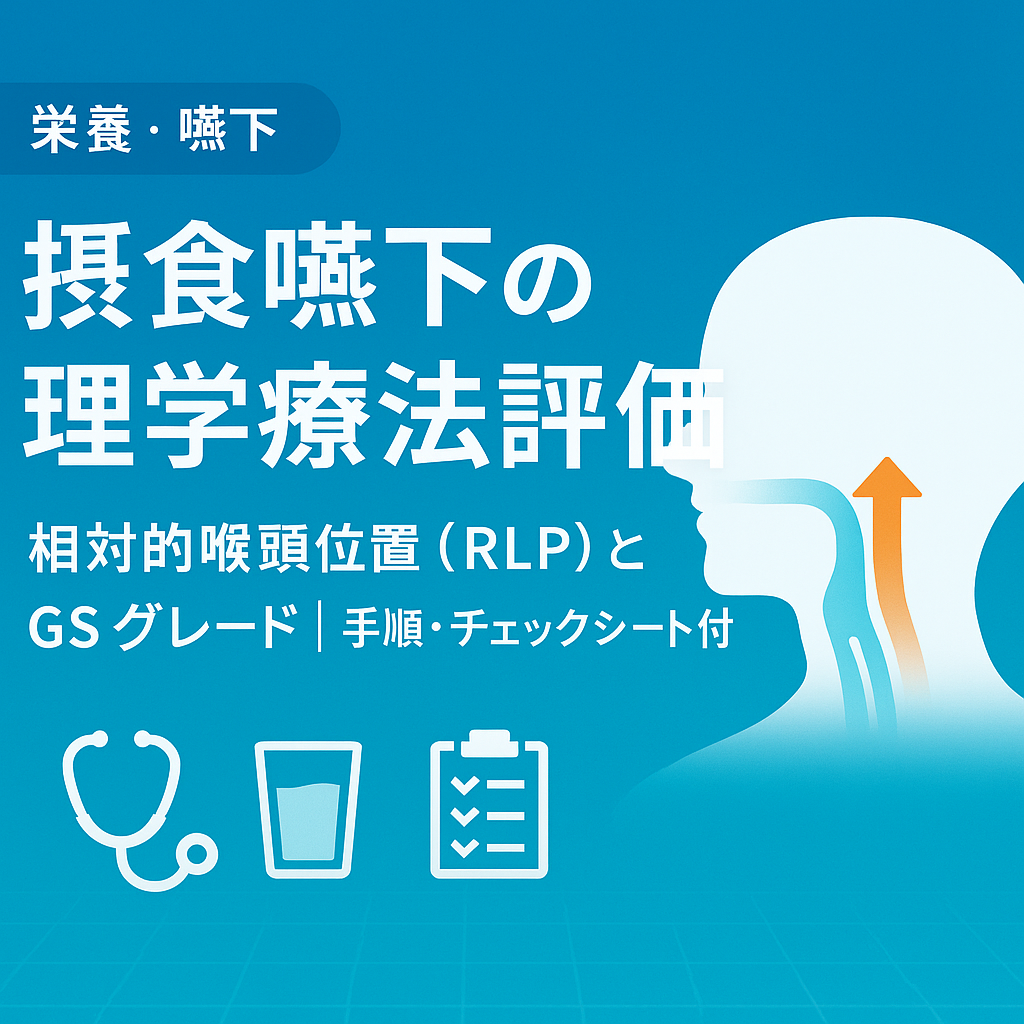本記事は医療従事者向けの一般情報です。実施は各施設の手順・安全基準に従ってください。強いむせ、吸気性喘鳴、SpO₂の顕著な低下などが出現した場合は直ちに中止し、適切な対応を行ってください。
摂食嚥下の理学療法評価:相対的喉頭位置(RLP)と GS グレードの手順
嚥下評価を“手順で学ぶ”|ST キャリアガイド(#flow)
相対的喉頭位置(RLP)とは
嚥下に関わる喉頭・舌骨の相対位置を、オトガイ(下顎骨先端)/甲状軟骨上端/胸骨上端(頸切痕)の3点から数値化した指標です。RLP = GT ÷(GT + TS)。値が大きいほど喉頭が上方を意味します。
RLP の測定方法(側臥位・頸部伸展)
- 肢位:ベッド上側臥位、痛みのない範囲で頸部は伸展位(枕・タオルで支持)。
- ランドマーク:①オトガイ ②甲状軟骨上端 ③胸骨上端(頸切痕)を触診。
- 測定器具:柔らかいメジャー。皮膚を引っ張らないよう軽く接触。
- 測定部位:GT(オトガイ—甲状軟骨上端)、TS(甲状軟骨上端—胸骨上端)。
- 再現性:左右の固定/頸部角度をメモ/メジャーの当て方統一。
RLP の計算式と計算例
RLP = GT ÷(GT + TS)
- 例)GT= 7.5 cm、TS= 5.5 cm →
RLP = 7.5 ÷( 7.5 + 5.5 )= 7.5 ÷ 13 ≒ 0.58(上方寄り)。 - 文献例(高齢者):0.41 ± 0.05。測定条件に依存するため院内基準へ置換して運用。
RLP 簡易計算:GT と TS を入力すると自動計算します。
RLP:
RLP 評価でのよくある誤り(是正ポイント)
| 状況 | NG | OK | 理由 |
|---|---|---|---|
| 頸部位 | 過伸展で評価 | 中間〜軽度屈曲 | 過伸展は喉頭が低く見え偽陰性 |
| 肩 | すくめ動作を許容 | 肩の脱力を促す | 僧帽筋収縮でランドマーク不明瞭 |
| 触診 | 甲状腺腫大を見落とす | 舌骨体で評価 | 腫大で高さを誤認しやすい |
| 一口量 | 普段と違う条件 | 常用の食形態・一口量 | 再現性が落ち比較不能 |
記録・前後比較のコツ
- 条件メモ:体位・一口量・介助量・補助具。
- 所見:上方/前方移動の量・速度・滑らかさ、再呼吸、湿性嗄声、咳/むせ。
- 再評価:同条件・同時間帯で実施。
舌骨上筋群の筋力評価:GS グレード(背臥位)
測定方法
- 肢位:背臥位。検者が頸部を他動的に最大前方屈曲位へ誘導。
- 説明:「下顎を引いて、顔の向きをそのまま保持してください」と指示し、検者の手を離す。
- 観察:その後の頭部落下の程度を 4 段階で評価。
判定基準(4 段階)
| グレード | 定義 |
|---|---|
| 1:完全落下 | 頭部の落下を途中で静止できず床上まで落下 |
| 2:重度落下 | 頸部屈曲可動域の 1/2 以上落下するが床上までは落下せず途中で静止し保持 |
| 3:軽度落下 | ある程度落下するが可動域 1/2 以内で落下を静止し保持 |
| 4:静止保持 | 落下せず、頭部最大屈曲位で保持 |
GS での誤判定と対策
- 頸部屈曲の起点が胸椎になる → 枕・タオルで後頭部支持し、顎引きを明確化。
- 腹直筋・股屈筋の代償 → 骨盤固定と口頭指示で最小化。
- 疼痛で保持困難 → 無理に実施しない。安全基準を優先。
RLP × GS の組み合わせ(臨床判断のヒント)
| RLP 値 | GS | 示唆 | 対応例 |
|---|---|---|---|
| 低値 | 1–2 | 喉頭下方化+舌骨上筋群の筋力低下 | 姿勢再設定、嚥下促通、食形態・一口量調整、筋力訓練 |
| 中等度 | 2–3 | 条件依存のばらつき | 体位・頸角度・同側固定で再測、RSST/水飲みテスト併用 |
| 高値 | 3–4 | 喉頭位置は良好 | 疲労や注意低下での変動をモニター、在宅指導へ |
評価シート(自動計算・印刷可)
GT / TS を入力すると RLP が自動計算されます。入力後に「印刷する」を押してください。
安全配慮・中止基準
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 強い頸部痛・めまい・嚥下時痛 | 即時中止。疼痛評価・医師へ共有。 |
| SpO₂ 低下(目安 3% 以上)・チアノーゼ | 休止し体位・呼吸を再設定。必要時は吸引・連絡。 |
| 強いむせ・吸気性喘鳴・湿性嗄声の持続 | 同条件での再試行は避け、段階を戻す/別日に再評価。 |
執筆:山田 太郎(PT)
監修:佐藤 花子(ST)
最終更新:2025-10-13 / 編集方針:編集ポリシー
参考文献
- 喉頭位置と舌骨上筋群の臨床的評価指標に関する報告(DOI / PubMed 追記予定)
- ベッドサイド嚥下評価の総説(DOI / PubMed 追記予定)