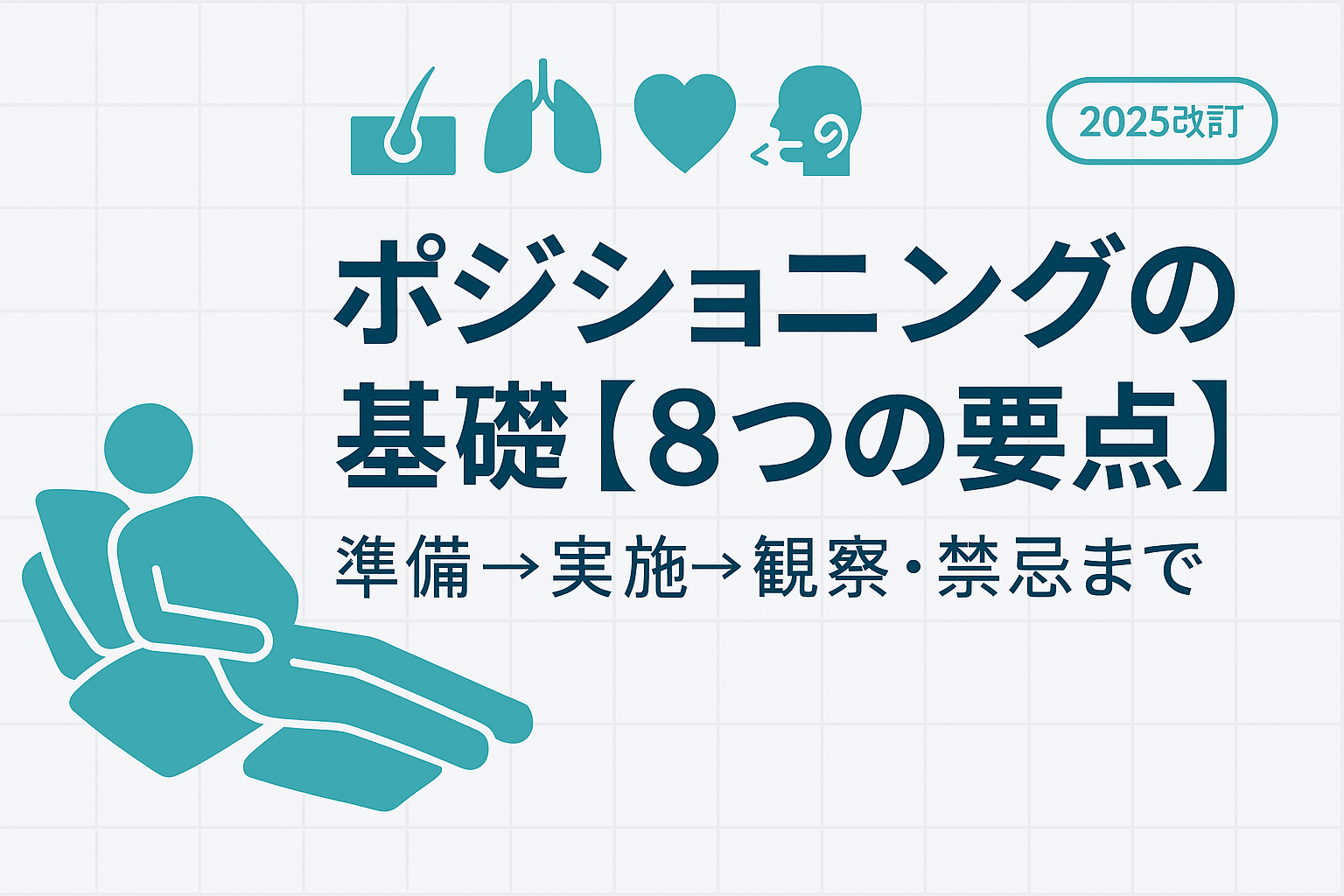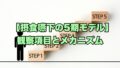ポジショニングとは?(結論と読者メリット)
ポジショニングは、褥瘡予防・呼吸循環の安定・嚥下安全性・疼痛軽減・拘縮予防を同時にねらう「土台づくり」の介入です。本記事では、単なる体位変換のルール集ではなく、基本 8 ポイントと準備 → 実施 → 観察・記録の実務フロー、禁忌・中止基準、物品選びまでを 1 本の流れとして整理します。
なお、褥瘡予防に絞って「ずれ(剪断)対策」「踵骨免荷」「体位変換の個別化」まで深掘りした実務は、記事末の関連記事でまとめています。
目的と役割(一次予防としての位置づけ)
ポジショニングの目的は、圧とずれの管理、呼吸循環の安定、嚥下の安全性、疼痛と不快感の軽減、可動域と筋緊張の正常化です。ベッド上で過ごす時間が長い高齢者では、ここが崩れると褥瘡・誤嚥性肺炎・廃用が連鎖しやすくなります。単に「楽そうな姿勢」にするのではなく、合併症を一次予防する介入として位置づけることが大切です。
またポジショニングは、静的ではなく動的な介入です。観察から仮説を立て、体位を設計し、効果を確認しながら再配置を繰り返します。評価(皮膚・呼吸・嚥下・筋緊張・疼痛)と体位設計が噛み合うほど、チームでの再現性が上がります。
基本 8 ポイント(要点)
- 捻れや過度な側屈を避け、可能な範囲で正中位を目標にする
- 頭部 → 胸郭 → 骨盤 → 下肢の順にアライメントを整える
- 点ではなく面で支え、支持基底面を広げて安定性を確保する
- 物品は入れ過ぎ・浅過ぎを避け、役割を言語化して入れる
- 体位変換後は必ず背抜きを行い、摩擦とずれ力を解放する
- 重力を味方につける体位(過緊張を抜きやすい方向)を選ぶ
- 拘縮予防のため、体位調整時に関節を少し動かす機会を組み込む
- 呼吸・嚥下に応じて頭頸部・体幹角度を微調整する(高すぎるファウラー位に注意)
実務フロー(準備 → 実施 → 観察・記録)
準備(観察と仮説)
- 皮膚:骨突出部の発赤・硬結・湿潤、デバイス圧の有無
- 呼吸循環: SpO₂ 、呼吸数、努力呼吸、下肢浮腫、起座呼吸の有無
- 嚥下:咳や湿性嗄声、経口摂取状況、経管栄養の管理状況
- 筋緊張 / 拘縮:痙縮の強い関節、疼痛トリガーになる方向
- 仮説:目的(例:仙骨部の負担軽減+呼吸パターン改善)と体位案(例: 30° 側臥位+ファウラー 30〜45°)
実施(手順のコツ)
- まず頭頸部 → 胸郭 → 骨盤 → 下肢の順でアライメントを整える
- クッションはできるだけ面接触となるよう配置し、局所圧の集中を避ける
- 体位変換後に背抜きを行い、ずれ力とシワを解除する
- 嚥下・呼吸が目的の場合は、頸部軽度前屈・体幹角度・骨盤後傾のバランスを微調整する
- 最後に「皮膚(発赤)・呼吸(努力呼吸)・安楽(表情 / 訴え)」の 3 点を再確認する
観察・記録(ミニテンプレ)
- 体位名 / 角度(例: 30° 側臥位+ファウラー 30°)
- 支持物の種類・数・位置・役割(例:骨盤前方支持、踵骨免荷 など)
- 皮膚所見(発赤・硬結・湿潤・デバイス圧)と体位前後の変化
- 呼吸 / 嚥下の変化、疼痛や安楽の主観的評価
- 再配置の予定(いつ・どの体位へ・どの指標を見て判断するか)
現場の詰まりどころ(判断が止まりやすい場面)
「体位を作ること」よりも、「何を優先して、どこを調整するか」で判断が止まりやすくなります。下の早見で、迷いの型をつかんでおくとチームで共有しやすくなります。
| 場面 | よくある迷い | 考え方(方向性) |
|---|---|---|
| 褥瘡と呼吸の優先度 | 仰臥位で SpO₂ が安定するが仙骨部が危険、側臥位で呼吸が苦しそう | まず呼吸・循環の安定を優先しつつ、支持物と体位バリエーションで局所圧とずれを分散する |
| 痙縮と安楽の両立 | 矯正すると苦痛が強く、本人は崩れた姿勢を「楽」と訴える | すぐに矯正し過ぎず、重力を利用した脱力位へ段階的に近づける(ステップ設計) |
| 体位変換の頻度 | 「 2 時間ごと」に縛られ、状態変化や日内リズムに合わせた調整ができない | 皮膚所見・覚醒・呼吸を組み合わせ、「その人の 1 日のリズム」に合わせて再配置計画を作る |
禁忌・中止基準(早見表)
| 場面 | 注意 / 禁忌 | 中止・医師連絡の目安 |
|---|---|---|
| 呼吸 | 強い呼吸困難、 SpO₂ 低下傾向、痰喀出困難で気道分泌が貯留している | SpO₂ ≦ 90% が持続、呼吸数 ≥ 30 / 分、チアノーゼ新規出現、会話困難 |
| 循環 | 著明な浮腫、心不全増悪が疑われる前負荷増大(過度な頭低位など) | 胸痛・起坐呼吸・急激な血圧変動(収縮期血圧が 40 mmHg 以上変動) |
| 皮膚 | 新規発赤、デバイス圧迫、湿潤皮膚への長時間荷重 | 発赤が 30 分以上で消退しない、水疱・びらん・潰瘍の新規出現 |
| 神経筋 | 末梢神経の過牽引位、痙縮を明らかに誘発する肢位 | 疼痛やしびれの増悪、新たな運動麻痺・感覚障害の出現 |
物品選びの要点(ピロー / フォーム / マット)
- クッションは面圧分散と位置再現性を両立できる形状(くさび型 など)を選び、役割別に使い分ける
- マットレスは体圧分散性能とケア体制に応じて選択し、寝具の選択も含めて「整えやすい環境」を作る
- 酸素チューブ・胃瘻・ドレーンなどのデバイス圧は、延長・保護パッド・経路変更で局所圧を避ける
- 枕は「頭頸部支持」「肩甲帯の沈み込み防止」「骨盤位置の保持」など、目的ごとに高さと硬さを検討する
よくある失敗と対策(早見表)
| 失敗(あるある) | 起きる理由 | 対策(優先手) | 記録の一言例 |
|---|---|---|---|
| 物品の入れ過ぎ / 浅過ぎ | 役割のない物品が局所圧や緊張を増やす | 一度すべて抜き、クッションの役割を言語化して再配置する | 役割別に再配置し、局所圧の集中なし |
| 背抜き省略でずれ力が残る | シワとずれが残り、皮膚損傷の引き金になる | 手順に「背抜き」を組み込み、チェックリスト化して抜けを防ぐ | 背抜き実施、シワ・ずれ所見なし |
| 目的不明の定時体位変換 | 評価と体位が結び付かず、効果が検証できない | 目的(皮膚 / 呼吸 / 疼痛)と観察指標を決め、記録と再評価で回す | 目的:皮膚と呼吸。指標:発赤と努力呼吸 |
参考文献
- 日本褥瘡学会学術教育委員会 編. 褥瘡予防・管理ガイドライン 第 5 版. 照林社; 2022.
- EPUAP/NPIAP/PPPIA. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. 2019. link
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会. 呼吸リハビリテーションに関するガイドライン. 2021.
おわりに
ポジショニングは、安全確認 → 目的設定 → 体位設計 → 背抜き・微調整 → 記録 → 再評価のリズムで回すと、褥瘡・誤嚥性肺炎・廃用の “まとめて予防” が現場で再現しやすくなります。忙しい日でも「ここだけは必ず整える」タイミングを 1 つ決めるだけで、チームの介入品質がそろいやすくなります。
面談準備チェック( A4・ 5 分)と職場評価シート( A4 )を無料公開しています。印刷してそのまま使えます。ダウンロードはこちらからどうぞ。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下