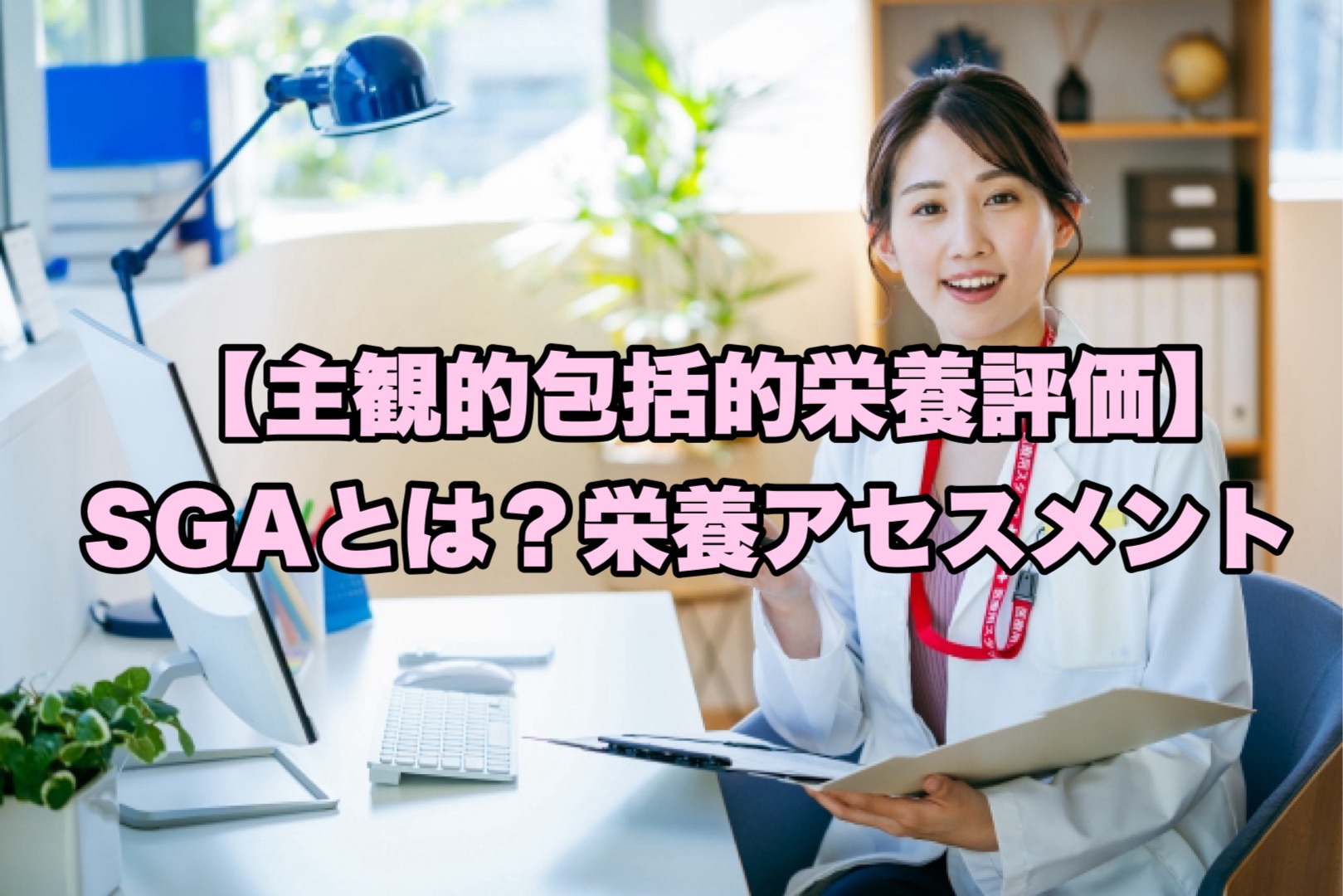SGA 評価方法|手順 5 分フローと A / B / C 判定のコツ(結論)
結論:SGA( Subjective Global Assessment )は、病歴( 5 本柱)+身体所見を統合して栄養状態を A(良好)/B(中等度低栄養)/C(高度低栄養)の 3 段階で判定する栄養アセスメントです。点数カットオフで決める検査ではなく、「なぜ低栄養に至ったのか」「どの程度深刻か」を因果の線として整理し、介入優先度をチームで揃えるのに向いています。
実務は①スクリーニング陽性 → ②SGA(病歴+所見)→ ③必要時 GLIM(診断・重症度)でつなぐと迷いが減ります。スクリーニングとアセスメントの役割分担は、総論として 栄養スクリーニングと栄養アセスメントの違い にまとめています。
SGA(主観的包括的栄養評価)とは?
SGA は、病歴と身体所見を統合し栄養状態を A(良好)・B(中等度低栄養)・C(高度低栄養)の 3 段階で判定する臨床評価です。特別な機器を必要とせず、短時間で “いま低栄養が疑われるか” とその重みを把握できる点が利点です。体重減少、摂取量、消化器症状、活動性、基礎疾患の侵襲度に加え、皮下脂肪・骨格筋量・浮腫 / 腹水などの身体所見を総合して判断します。
SGA は 1987 年に Detsky らが臨床技法として定式化され、術前、がん、腎、 ICU など幅広い集団で予後との関連が示されています。日本ではスクリーニング的に用いられてきた歴史がありますが、原則は “アセスメント” です。実務では在宅での栄養スクリーニングや栄養アセスメントと接続し、必要時に GLIM 診断へ進む流れを整えておくと安全です。
SGA の評価方法(手順)|スクリーニングから GLIM まで
SGA の評価方法(実務フロー)は次の 3 段階が基本です。
- 短時間スクリーニングで栄養リスクを抽出(施設で採用している票で可)。
- リスク陽性例に対して SGA を実施(病歴 5 項目+身体所見の総合判定)。
- 必要に応じて GLIM 基準で診断・重症度判定を行い、栄養計画へ接続。
SGA は “カットオフ値” で決まる点数スコアではなく、複数情報を統合して A / B / C を決める総合判断ツールです。スコアリングに置き換えようとするより、「なぜ低栄養に至ったのか」「どの程度深刻か」をストーリーとして整理することが重要になります。
リハ場面では、面接(食事状況・症状)→ 身体計測・観察 → 歩行や ADL の聴取を 1 セッションで束ねると効率的です。週 1 回の再評価タイミングを固定化し、体重や症状の記録フォーマットをチームで統一しておくと再現性が高まります。
| ステップ | 何を見る(最小セット) | 記録の型 | 次アクション |
|---|---|---|---|
| 1 | 体重変化( 6 か月 / 1 か月)+背景(輸液・利尿・浮腫) | 時系列(いつから・どれくらい) | 変化が大きいほど B / C を疑う |
| 2 | 摂取量(量・形態・回数・中断) | 「食べられない理由」まで 1 文で | 口腔 / 嚥下や症状の確認へ |
| 3 | 消化器症状(悪心・嘔吐・下痢・腹痛の持続期間) | 期間(何日 / 何週)を添える | 原因検索・介入(薬 / 食形態) |
| 4 | 活動性(歩行距離、家事 / 就労の変化)+疾患侵襲(感染・手術・炎症) | 出来事の前後関係(原因−結果) | 廃用 / 炎症の影響を見積もる |
| 5 | 身体所見(皮下脂肪・筋量・浮腫 / 腹水) | 部位+所見(減少 / あり) | A / B / C の根拠を 3 点で共有 |
SGA の評価項目(病歴):5 つの柱
病歴の評価では、(1)体重変化: 6 か月・ 1 か月の減少率と時系列。(2)摂取量:量・形態・回数・所要時間・ムセや食事中断。(3)消化器症状:悪心・嘔吐・下痢・腹痛などの持続期間。(4)活動性:歩行距離、家事 / 就労の変化。(5)疾患侵襲:感染、手術、炎症性疾患、発熱などの 5 本柱を整理します。個々の数値より “因果の線” を描けるかが重要です。
体重や摂取の解釈では利尿薬、輸液、浮腫 / 腹水の影響に注意します。活動性の低下は摂取減少・炎症・疼痛などと併走しやすいため、症状と出来事の前後関係を整理しておくと判定が安定します。聴取は患者負担が少ない順に並べ、具体例で確認するのがコツです。
SGA の評価項目(身体所見):観察部位のポイント
皮下脂肪の減少(上腕三頭筋・胸壁)と骨格筋量の減少(三角筋・大腿四頭筋)を視・触診し、むくみ(踵・下腿・仙骨)や腹水の有無を合わせて把握します。浮腫は体重減少を覆い隠すため、病歴情報と必ず照合します。再評価は “同じ体位・同じ照明・同じ観察順” を徹底すると再現性が向上します。
以下の表は成人を想定した観察チェックです。写真や動画に依存せず、触れて判断できる指標を意識しましょう。必要に応じて上腕周囲長や皮下脂肪厚などの簡便計測を補助的に用いると、所見の言語化がスムーズになります。
| 部位 | 見る・触るポイント | 低栄養を示唆 |
|---|---|---|
| 上腕三頭筋 | 皮下脂肪の厚み、つまみ取りの薄さ | 皮下脂肪の著明な減少 |
| 胸壁(肋間) | 肋骨輪郭の強調、皮下脂肪 | 肋間の凹み・皮下脂肪減少 |
| 三角筋 | 外側輪郭、筋腹の張り | 肩の骨ばり・筋量減少 |
| 大腿四頭筋 | 大腿前面の筋腹、膝周りの凹凸 | 筋腹の扁平化・腱ばり |
| 踵・仙骨 | 圧痕の残り方、左右差 | 圧痕浮腫・腹水の合併 |
SGA の判定基準(A / B / C)の考え方
SGA は「○点以上で低栄養」といった点数カットオフ型のツールではなく、病歴と身体所見を組み合わせて A / B / C を決める総合判定です。点数化したい場合は MNA や GNRI など他の指標を併用し、SGA は「いま低栄養が疑われるか」「どの程度深刻か」を判断する役割と整理すると混乱が少なくなります。
最終分類では “重大な所見が一つでもあれば B 以上になり得る” ことを意識します。とくに「体重減少+摂取低下+身体所見の変化」が揃うと B / C に傾きます。数値の閾値よりも、説明可能な “原因 − 結果” の線が描けているかを重視しましょう。判定根拠は短い文で共有できる形に整えます。
| 分類 | 病歴のまとまり(例) | 身体所見(例) | 共有するときの一言 |
|---|---|---|---|
| A(良好) | 体重変化が小さく、摂取量と症状が安定している | 脂肪・筋量の減少が目立たず、浮腫 / 腹水が乏しい | 「現状は維持、モニタリング継続」 |
| B(中等度) | 体重減少または摂取低下があり、症状や活動性低下が併存する | 脂肪 / 筋量の減少が疑われる、または浮腫で評価が揺れる | 「原因整理して介入開始、再評価を早める」 |
| C(高度) | 体重減少と摂取低下が明確で、症状や侵襲の影響が強い | 脂肪 / 筋量の減少がはっきりし、浮腫 / 腹水が併発し得る | 「緊急度高い、栄養介入を最優先」 |
SGA チェックシート(A4)のダウンロード
SGA をベッドサイドで評価するときに使える 面接・身体所見のチェックシート(A4・ 1 枚) を用意しました。体重変化・摂取状況・消化器症状・活動性・疾患侵襲の 5 本柱と、上腕三頭筋・胸壁・三角筋・大腿四頭筋・浮腫 / 腹水の観察ポイントを 1 ページに整理しています。
SGA 面接・身体所見チェックシート(A4)をダウンロードする
※施設の正式な記録様式がある場合は、併用または転記してご使用ください。
PT のチェックリスト(評価用紙と一緒に)
以下は面接・観察の下書き用メモです。施設の様式がある場合はそちらを優先し、欄外メモとして活用してください。週 1 回の定点観測(同曜日・同条件)で “変化に気づく” 精度が高まります。口腔や嚥下の影響が疑われる場合は食事姿勢や形態の確認を追加しましょう。
スクリーニング結果と併せて保存しておくと、退院支援や在宅移行時の説明が一段と明確になります。次の表はコピー & ペーストでメモとして使えます。
| 項目 | 要点(例) | 所見 / 期間 |
|---|---|---|
| 体重変化 | 6 か月 / 1 か月、利尿薬・浮腫の影響 | |
| 摂取量・食形態 | 量・形、回数、時間、ムセ有無 | |
| 消化器症状 | 悪心・嘔吐・下痢・腹痛(持続期間) | |
| 活動性 | 歩行距離、家事 / 就労の変化 | |
| 身体所見 | 皮下脂肪・筋量、浮腫 / 腹水 |
判定の落とし穴とコツ
(1)浮腫・腹水で体重減少を過小評価しやすい。(2)急性炎症やステロイドで体液・食欲が揺れる。(3)廃用性筋萎縮と低栄養由来の筋量低下は鑑別が必要。(4)口腔機能低下は摂取量のボトルネック。これらは病歴の時間軸と併せて整理し、再評価タイミングを固定化することで再現性が上がります。
チーム共有は「分類( A / B / C )」「主要根拠(体重・摂取・身体所見)」「想定原因(疾病・炎症・口腔など)」の 3 点セットで伝えると合意が早まります。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
SGA はどのくらいの頻度で再評価すべきですか?
急性期〜回復期では、全身状態が動きやすいため おおむね週 1 回程度 を目安に再評価すると、変化の見落としが少なくなります。栄養介入や病態変化(手術・感染など)があったタイミングでは、その前後で SGA を取り直し、病歴と身体所見の両方がどう変化したかを確認します。慢性期や外来では、外来受診や状態変化のタイミングに合わせて柔軟に頻度を調整してください。
MNA や MUST などのスクリーニングと役割はどう違いますか?
MNA や MUST は「リスクがあるかどうか」を短時間でふるい分ける スクリーニング ツールで、カットオフ値が明確です。一方、SGA は病歴と身体所見を統合して A / B / C を判定する アセスメント であり、「なぜ低栄養に至ったのか」「どの程度深刻か」を整理する役割を持ちます。実務では、まずスクリーニングで陽性になった患者に対して SGA を行い、必要に応じて GLIM 診断や栄養計画につなげる流れが推奨されます。
PT が SGA を評価しても問題ありませんか?
SGA は本来チームで活用するツールですが、病歴の聴取や身体所見の観察は PT も日常的に行っている領域です。施設の運用ルールや診療報酬上の扱いを確認したうえで、管理栄養士・医師と連携しながら PT が評価に関わる ことは、栄養とリハビリを一体として設計するうえで有用です。評価結果は、「分類(A / B / C)」「主要根拠」「想定原因」を簡潔にまとめて共有し、栄養ケア計画やリハ目標に反映させていくことが大切です。
参考文献
- Detsky AS, McLaughlin JR, Baker JP, et al. What is subjective global assessment of nutritional status? JPEN. 1987;11(1):8-13. PMID:3820522 / DOI
- Baker JP, Detsky AS, Wesson DE, et al. Nutritional assessment: a comparison of clinical judgement and objective measurements. N Engl J Med. 1982;306(16):969-972. PMID:6801515
- Makhija S, Baker J. The Subjective Global Assessment: a review of its use in clinical practice. Nutr Clin Pract. 2008;23(4):405-409. PMID:18682592
- Secker DJ. How to Perform Subjective Global Nutritional Assessment. J Acad Nutr Diet. 2012;112(5):824-832. DOI
- Cederholm T, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9. PMID:30181091
- Jensen GL, et al. GLIM consensus approach: 5-year update. JPEN. 2025. DOI
- JSPEN. GLIM 基準における SGA の位置づけ(公式解説). Web
おわりに
低栄養の実務は「疑う → 根拠を揃える → 介入へつなぐ → 同じ条件で再評価」というリズムで回すと安定します。栄養スクリーニング → SGA → GLIM 診断 → 栄養計画 → 再評価という流れをチームで共有しておくことで、「誰が・どのタイミングで・どこまで見るか」が明確になり、初動の抜け漏れが減ります。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に、見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック( A4・ 5 分)と職場評価シート( A4 )も用意しています。印刷してそのまま使えますので、キャリアや学び方を整理する際の土台として活用してみてください。ダウンロードページを見る。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下