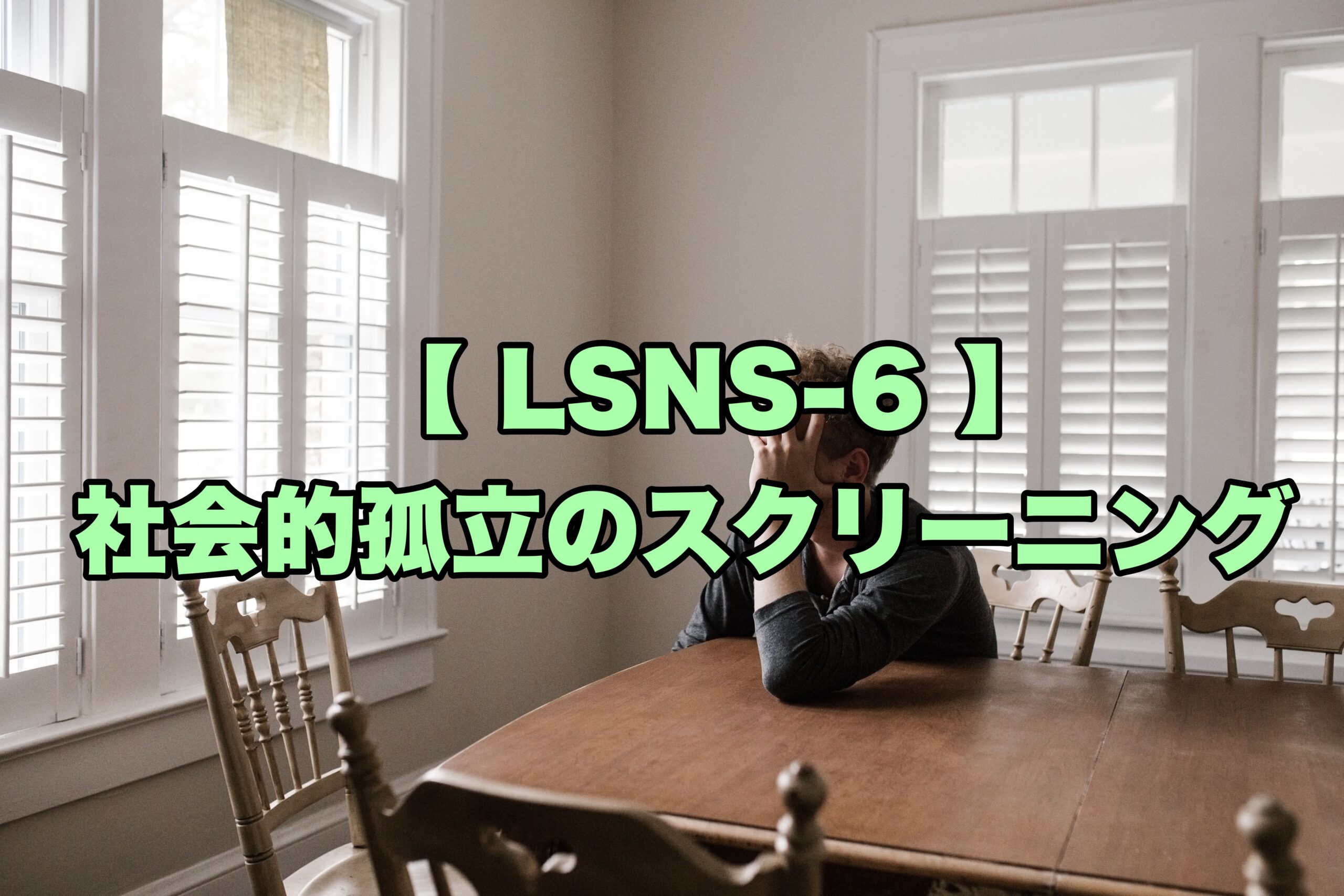LSNS-6 を初めて運用するための要点( 6 項目・ 30 点で社会的孤立リスクを整理)
LSNS-6( Lubben Social Network Scale-6 )は、家族・友人とのつながりを 6 項目( 0〜30 点)で整理し、社会的孤立のリスクを短時間で拾うスクリーニングです。点数が低いほど「支援が入りにくい状況」になりやすく、退院支援や訪問導入、通所開始など“環境が変わる局面”で特に役立ちます。
本稿では、初見でも迷わないように、聞き取りの観点(パラフレーズ)・問い方の例・採点早見表・記入例・つまずき回避をセットでまとめます。生活範囲や社会参加の評価をまとめて整理したい場合は、生活空間( Life-Space )評価ハブもあわせて活用してください。
60 秒でわかる実施手順(クイック版)
結論として、LSNS-6 は「対象期間を固定」し、「家族と友人を分けて人数を数える」だけで精度が上がります。まずは短時間で同条件の情報を集め、“次の支援調整”に変換するのがコツです。
運用は 5 ステップで十分です。施設内で「期間」「数え方」「記録様式」を揃えるほど、担当者が変わっても縦断比較が崩れにくくなります。
- 期間宣言:「直近 1 か月で答えてください」
- 定義共有:家族=血縁・婚姻/友人=血縁以外の親しい人(実際に交流がある相手)
- 人数を数える:家族・友人それぞれで「交流」「頼れる」「相談できる」の 3 観点を確認
- 採点:採点早見表で人数→点(各 0〜5 点)に置換
- 合計と方針:合計 12 点未満は高リスクの目安→支援調整(多職種連携・参加先提案)へ
面接スクリプト( 90 秒で読み上げ)
- 「直近 1 か月の様子でお答えください。」
- 「家族は血縁・婚姻、友人は血縁以外の親しい人として伺います。」
- 「まず家族です。この 1 か月で会う・電話や LINE をした家族は何人いましたか?」
- 「そのうち、急用や体調不良のときに実際に頼れる家族は何人ですか?」
- 「健康やお金など、個人的な相談を気軽にできる家族は何人ですか?」
- 「次に友人です。同じように、交流人数/頼れる人数/相談人数を伺います。」
- 「人数を表の基準で 0〜5 点に置き換え、合計します。 12 点未満なら支援策を一緒に検討しましょう。」
観点と問い方の例(臨床用パラフレーズ)
ここでは、聞き取りで確認すべき“観点”を、現場でそのまま使える問い方に落とし込みます。フレイル、抑うつ、独居支援、退院支援などの場面で、面接の抜け漏れ防止に役立ちます。
ポイントは「形式より実態」で数えることです。名目上の関係ではなく、“現実に交流があるか/動いてくれるか/深い相談ができるか”で整理すると、支援導線が作りやすくなります。
| 領域 | 観点(確認したい中身) | 問い方の例 | 採点のコツ |
|---|---|---|---|
| 家族 | 定期的な交流がある家族の人数 | 「この 1 か月で、会う・電話や LINE をした家族は何人いましたか?」 | 別居でも交流があれば含める(実態重視)。 |
| 家族 | 困ったときに実際に頼れる家族の人数 | 「急用や体調不良のとき、頼れる家族は何人ですか?」 | 動いてくれる相手に限定する。 |
| 家族 | 気兼ねなく個人的な相談ができる家族の人数 | 「健康・お金・不安などを気軽に話せる家族は何人ですか?」 | 世間話ではなく“深い相談”を基準にする。 |
| 友人 | 定期的な交流がある友人の人数 | 「この 1 か月で、会う・連絡を取り合った友人は何人いましたか?」 | オンラインのみでも継続交流なら含める。 |
| 友人 | 困ったときに頼れる友人の人数 | 「通院の付き添いなど、具体的に頼れる友人は何人ですか?」 | 支援の現実性(移動・金銭・見守り)で判断する。 |
| 友人 | 気兼ねなく個人的な相談ができる友人の人数 | 「体や家の事情など、深い話をできる友人は何人ですか?」 | 知人・顔見知りは除外する。 |
採点のやり方(人数 → 点の置き換え)
各観点で数えた人数を 0〜5 点へ置き換え、合計 0〜30 点を算出します。結論として、点数を“孤立の断定”に使うより、「どこが薄いか(家族/友人)」を見つける目的で運用すると、支援調整につながりやすいです。
下表は運用テンプレです。チーム内でこの基準を固定しておくと、担当者が変わっても点数のブレが減ります。
| 人数 | 点数 | メモ |
|---|---|---|
| 0 人 | 0 点 | 該当者なし |
| 1 人 | 1 点 | |
| 2 人 | 2 点 | |
| 3〜4 人 | 3 点 | |
| 5〜8 人 | 4 点 | |
| 9 人以上 | 5 点 | 比較的広いネットワーク |
合計 12 点未満はリスクが高い目安として扱われることが多い一方、対象(地域在住/疾患/介護度)で分布は変わります。合計だけでなく、家族と友人のどちらが薄いか、そして「頼れる/相談できる」に偏りがないかをセットで確認します。
迷いやすいカウント基準(運用ルール化)
| ケース | 含める? | 理由/メモ |
|---|---|---|
| 同一人物を家族・友人の両方に数える | × | 重複カウントは避け、どちらかに統一する |
| 月 1 回のビデオ通話のみ | ○ | 継続的交流があればカウントする |
| 年 1 回の年賀状のみ | × | 交流の実態が薄い場合は含めない |
| 形式上の家族(疎遠・援助不可) | × | “実際に動く支援者”を数える |
記入例(合計の出し方)
点数は「合計」よりも、「家族小計」と「友人小計」を分けて残すと、カンファで次の手が決まりやすくなります。
例:合計が低い場合でも、家族側が厚いのか、友人側が薄いのかで支援の方向性は変わります。
| 領域 | 交流 | 頼れる | 相談 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 家族 | 2 人 → 2 点 | 1 人 → 1 点 | 1 人 → 1 点 | 4 点 |
| 友人 | 0 人 → 0 点 | 1 人 → 1 点 | 0 人 → 0 点 | 2 点 |
| 合計 | 6 / 30 点 | |||
実施フローと“つまずき”回避(記録 → つなぐまで)
結論として、LSNS-6 は「点数化して終わり」にしないほど価値が出ます。点数を“支援調整の材料”に変換するために、記録に 1 行だけでも次アクションを残すのがコツです。
おすすめは「合計+家族小計+友人小計」と、「つなぐ先」をセットで書く形です(例:友人側が薄い→通所導入で参加の入口づくり、など)。
- 対象選定:独居、外出減、食欲低下、抑うつ徴候、転倒歴などがある場合は優先的に実施。
- 面接の要点:期間を区切る(直近 1 か月)。家族と友人を分けて数える。重複カウントを避ける。
- 記録:合計だけでなく、家族小計/友人小計を残す。短いコメント(薄い側と理由)も 1 行残す。
- 支援調整:12 点未満を目安に、ケアマネ連携、通所・サロン紹介、見守り体制など具体策へつなげる。
- 再評価:介入後、または 3〜6 か月ごとにフォローし、量(人数)と質(頼れる/相談)の変化を確認。
現場の詰まりどころ(よくある失敗)
LSNS-6 は短い分、聞き方が曖昧だと点数がぶれやすいのが弱点です。ここでは失敗を先に潰し、評価を支援調整へつなげます。
- ① 「知り合い」と「友人」が混ざる:深い相談ができるか、具体的に頼れるかで分けて確認します。
- ② 同じ人を何度も数える:家族/友人の重複だけでなく、交流/頼れる/相談の 3 観点で冷静に人数を整理します。
- ③ 複雑な家族関係への聞き方に迷う:“無理に数えない”をチームで共有し、実態ベースで記録します。
- ④ 点数だけが一人歩きする:「誰が薄いか(家族/友人)」「次にどこへつなぐか」を 1 行で残すと活きます。
併用が有効な評価(多面的に解釈する)
LSNS-6 は「社会的ネットワーク」を捉える評価です。身体機能(歩行速度・筋力・転倒歴)や栄養状態(体重変化・食事量)、抑うつや認知などとあわせて見ると、「外に出にくい理由」と「どの支援から始めるか」を立体的に整理できます。
特に地域包括ケアでは、LSNS-6 を“関係性の見取り図”として位置づけると、カンファレンスでの共有がスムーズになります。
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q. 12 点未満なら必ず介入しますか?
A. 目安として有用ですが、LSNS-6 だけで決めず、身体機能・生活機能・本人希望などとあわせて総合的に判断します。実務では「家族/友人のどちらが薄いか」と「つなぐ先」をセットで決めると動きやすいです。
Q. 家族がいない/友人がいない場合の聞き方は?
A. 「今の暮らしで連絡を取る人」「困った時に頼れる人(近所・支援者)」のように、実態に沿って確認します。専門職しか出てこない場合も、そのまま記録しておくと支援調整の材料になります。
Q. 点数が上がりにくい方への支援例は?
A. 参加のハードルを下げる(送迎・付き添い・初回同行)、役割づくり(係・当番)、連絡頻度の固定化など「続けやすい形」から始めると変化が出やすいです。
おわりに
LSNS-6 は、短時間で「支援が入りにくい理由」を言語化しやすいツールです。スクリーニング → どこが薄いか(家族/友人) → 入口づくり → 再評価のリズムで回すと、点数が“次の一手”に変わります。
転職や職場選びを考えるときの抜け漏れ防止に、面談準備チェック( A4 )と職場評価シート( A4 )を無料公開しています。必要なときにすぐ使える形なので、マイナビコメディカルの資料ダウンロードから確認してみてください。
参考文献
- Lubben J, Blozik E, Gillmann G, et al. Performance of an abbreviated version of the Lubben Social Network Scale among three European community-dwelling older adult populations. The Gerontologist. 2006;46(4):503-513. DOI: 10.1093/geront/46.4.503 / PubMed: PMID:16921004
- Kurimoto A, Awata S, Ohkubo T, et al. Reliability and validity of the Japanese version of the abbreviated Lubben Social Network Scale (LSNS-6). Nihon Ronen Igakkai Zasshi (Jpn J Geriatr). 2011;48(2):149-157. DOI: 10.3143/geriatrics.48.149 / PubMed: PMID:21778631
- Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB. Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review. PLoS Med. 2010;7(7):e1000316. DOI: 10.1371/journal.pmed.1000316 / PubMed: PMID:20668659
- Valtorta NK, Kanaan M, Gilbody S, Ronzi S, Hanratty B. Loneliness and social isolation as risk factors for coronary heart disease and stroke: systematic review and meta-analysis of longitudinal observational studies. Heart. 2016;102(13):1009-1016. DOI: 10.1136/heartjnl-2015-308790 / PubMed: PMID:27091846
- Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56(3):M146-M156. DOI: 10.1093/gerona/56.3.M146 / PubMed: PMID:11253156
- Clegg A, Young J, Iliffe S, Rikkert MO, Rockwood K. Frailty in elderly people. Lancet. 2013;381(9868):752-762. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)62167-9 / PubMed: PMID:23395245
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下