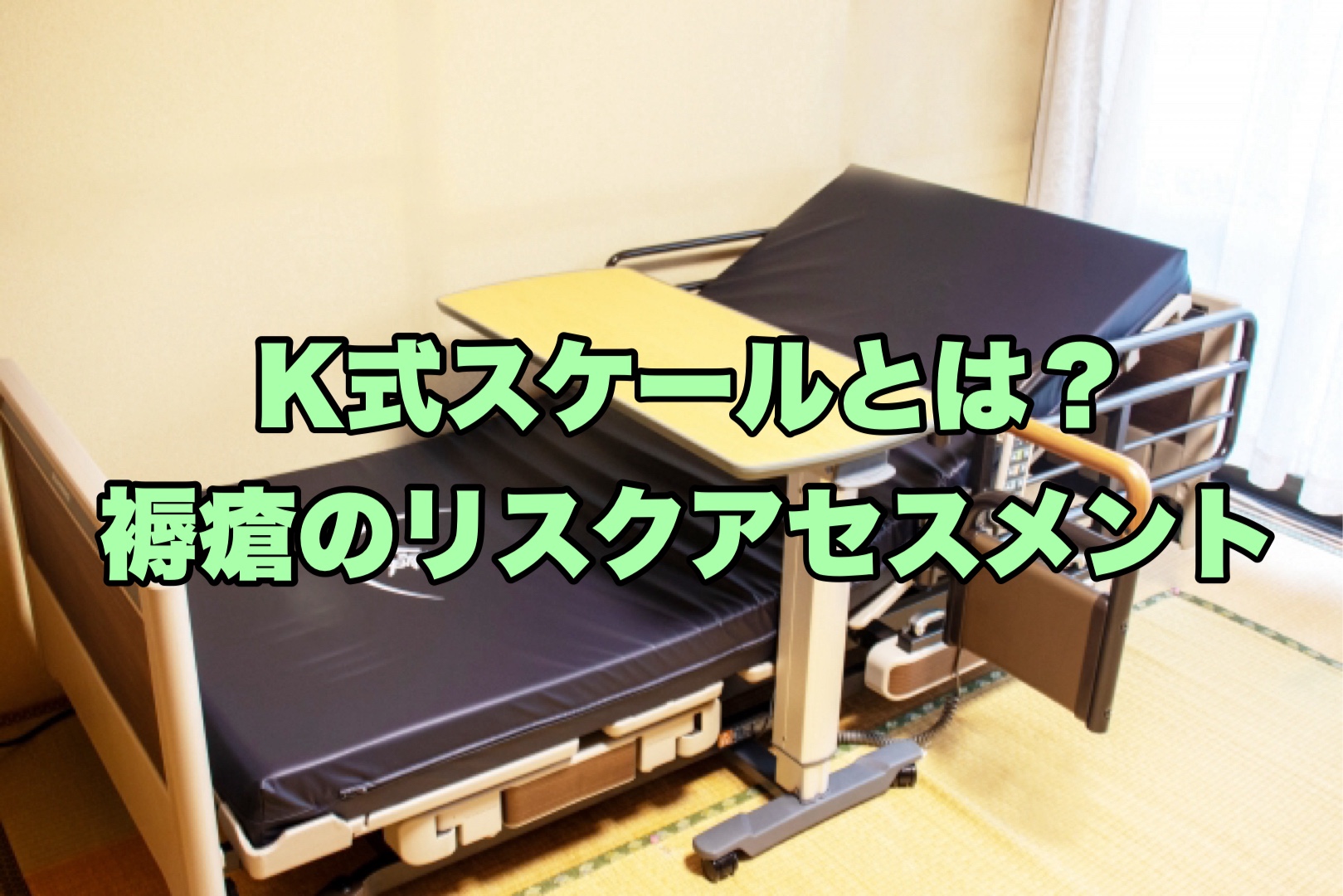K 式スケールとは?在宅版との違い(まず結論)
K 式スケール(正式名:金沢大学式褥瘡発生予測スケール)は、前段階要因と引き金要因を Yes / No で判定し、短時間で褥瘡発生リスクを把握できる日本発の評価法です。在宅版 K 式は在宅療養の実情を反映し、介護力(介護知識・環境)や栄養の観点が加わるのが大きな違いです。K 式スケールの評価方法は、前段階要因と引き金要因をチェックし、合計点と陽性パターンから褥瘡リスクを判断するシンプルな仕組みです。
実務では「評価→用具・ポジショニング→再評価」の流れに K 式スケールを組み込み、院内スクリーニングやマットレス選定、在宅での介護力評価とセットで運用すると、リスクの見落としを減らしやすくなります。
評価項目と構成の比較(K 式/在宅版 K 式)
原票の文言は各施設の規約に従ってください。ここでは臨床での解釈の“型”を示します。表はスマートフォンでは横スクロールしてご覧ください。
| 区分 | K 式(入院・施設) | 在宅版 K 式(在宅療養) | 判定の観点(例) |
|---|---|---|---|
| 前段階要因 | 自力体位変換不可/骨突出/栄養不良 など | 上記+介護知識・介護力 | 活動性・痩せ・突出部保護・介護者の理解と手順 |
| 引き金要因 | 体圧/湿潤/ずれ | 体圧/湿潤/ずれ/栄養 | 寝具硬さ・蒸れ・シーツのしわ・滑走・摂取量 |
| 採点と解釈 | 各項目 Yes(1)/ No(0)で簡便採点(区分ごと 0–3 or 0–4) | 引き金要因が 1 つでも陽性なら注意度 ↑(介入を強化) | |
在宅版 K 式スケールの特徴(介護力と栄養)
在宅版 K 式スケールは、K 式スケールの 6 項目に加えて「介護知識」と「栄養」の 2 項目を評価します。家族等の介護力や食支援の体制をスコア化することで、「リスクは高いが介護力が高いケース」や「リスクは中等度だが介護力が乏しいケース」など、在宅ならではのギャップを早期に拾いやすくなるのが特徴です。在宅リハでは、この結果をもとに体位変換頻度や用具導入、訪問栄養・訪問看護との連携内容を調整していきます。
点数の目安とリスクのイメージ
K 式スケールの合計点は、前段階要因・引き金要因ともに 0–3 点です。前段階要因 0 点かつ引き金要因 0 点であればリスクは低め、前段階要因のみ 1–3 点で引き金要因 0 点なら「潜在的なリスクあり」、前段階要因に加えて引き金要因が 1 つでも陽性なら高リスクとして体圧分散やポジショニングを強化する目安になります。
ガイドラインでは「引き金要因が 1 つでも加わると褥瘡発生リスクが高くなる」とされており、点数そのものよりも“どの要因が陽性か”というパターンに着目することが重要です。臨床では、合計点と陽性パターンをセットで記録し、経時的な変化を追うようにしましょう。
K 式スケールの評価方法と介入の流れ(現場 10 分版)
- 観察(2–3 分):突出部・シーツしわ・湿潤・滑走、介護者人数/時間帯、寝具・リフト・体位変換可否。
- 判定(2 分):K 式(在宅なら在宅版)で Yes / No を即時記録。
- 初期介入(3–4 分):体位変換頻度・ポジショニング、失禁/発汗対策、ズレ低減、栄養の連携。
- 共有(1 分):家族・看護・ケアマネへ短文フィードバック、48–72 時間で再評価を合意。
よくある誤りと対策
K 式スケールはシンプルな分、「湿潤」「ずれ」「介護力」などの解釈が現場ごとにブレやすい評価でもあります。代表的なつまずきポイントと、すぐに実装できる対策を整理します(表はスマートフォンでは横スクロールしてご覧ください)。
| 誤り | なぜ問題? | 対策(実装) |
|---|---|---|
| 「湿潤」を失禁のみで判断 | 発汗・滲出・蒸れも皮膚脆弱化の要因であり、見落とすと高リスク患者を過小評価する。 | 背部・臀部の発汗やドレッシングの滲出量も観察し、通気性の改善や吸収材の交換タイミング最適化をルール化する。 |
| 在宅で介護力を具体的に聴取しない | 「毎日体位変換」と計画しても、実際には介護者数や時間帯の制約で実行できない場合が多い。 | 介護者数/時間帯・用具の有無を定型聴取し、“実行可能な頻度”を家族と合意したうえでプランを立てる。 |
| ずれの観察が場面限定(臥位のみ) | 背上げ・移乗・端座位での滑走が見逃され、K 式の引き金要因を過小評価する。 | 評価時に少なくとも「背上げ」「ベッド⇔車いす移乗」「端座位」の 3 場面で骨盤・仙骨周囲のずれを確認し、角度や手順をカルテに記載する。 |
評価用紙(院内配布用)
K 式スケールと在宅版 K 式スケールを 1 枚ずつにまとめた A4 記録シートを用意しました。褥瘡委員会やリンクナースと共有し、評価手順とあわせて配布しておくと定着しやすくなります。
評価用紙をダウンロード(施設の著作権規程に従ってご利用ください)。
参考文献
- 岡田克之.褥瘡のリスクアセスメントと予防対策.日本老年医学会雑誌.2013;50(5):583–591.PDF
- 大桑真由美ほか.K 式スケールの信頼性と妥当性の検討.日本褥瘡学会誌.2001;3(1):7–13.CiNii
- 在宅版 K 式スケール(看護向け解説).ナース専科
- 褥瘡予防におけるリスクアセスメントと用具選定.AlmediA
おわりに
実地では「リスク評価→体圧・湿潤・ずれ対策→用具選定→再評価」というリズムが最重要です。K 式/在宅版 K 式は、前段階要因と引き金要因を短時間で整理し、ポジショニング・寝具・介護力調整などの優先順位付けに役立ちます。評価結果をチームで共有し、48–72 時間ごとの再評価をルーチン化することで、褥瘡発生の“未然防止”に近づけます。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止には、面談準備チェックや職場評価シートのようなツールも役立ちます。日々の褥瘡予防実務を通して「どの職場なら自分の知識・技術を活かせるか」を整理しておくと、中長期のキャリア設計もしやすくなります。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
K 式スケールとブレーデンスケールはどう使い分ければよいですか?
ブレーデンスケールは全身状態や活動性を含めた包括的なリスク評価に向いており、病棟全体のスクリーニングや施設内比較に便利です。一方、K 式スケールは「前段階要因」と「引き金要因」を分けて整理できるため、ポジショニングや寝具、ずれ対策など具体的な介入内容を決めるのに適しています。同じ患者さんでも、ブレーデンで全体像を把握しつつ、K 式で“どこから手をつけるか”を決めるイメージで併用すると、評価と介入が結び付きやすくなります。
在宅版 K 式スケールは PT も評価してよいですか?
在宅版 K 式スケールは看護職向けに整備された経緯がありますが、在宅リハに関わる PT・OT も観察や聴取を共有することで、介護力や栄養状態を統一的に把握しやすくなります。実際には、主担当(訪問看護など)と役割分担を相談し、誰がいつスコアリングするか、どのように情報共有するかをチームで決めておくと運用しやすくなります。
評価に時間が取れないとき、どこだけは必ず見ておくべきですか?
時間が限られる場面では、①骨突出部(仙骨・踵など)、②湿潤(失禁・発汗・滲出)、③ずれが出やすい動作(背上げ・移乗)、④介護力(誰がどの頻度で体位変換できるか)の 4 点を優先して確認するとよいです。K 式スケールの前段階要因と引き金要因に直結する項目なので、ここを押さえておくだけでもリスクの見落としを減らせます。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下