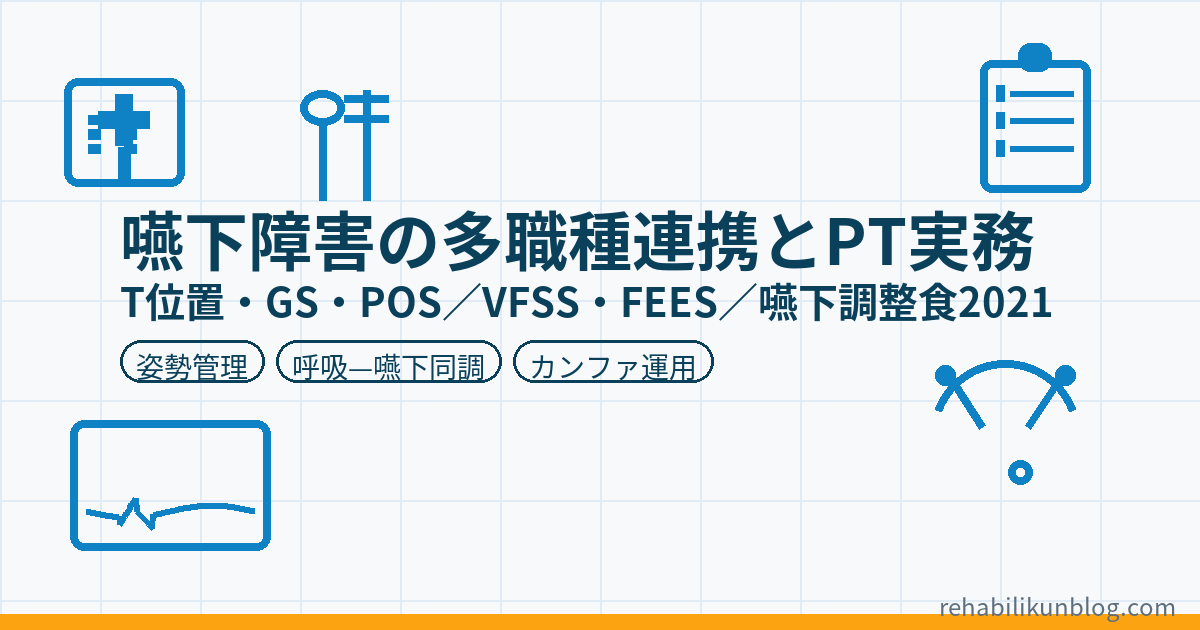- 嚥下カンファレンスの進め方: SBAR × T 位置・ GS × POS で「決める」
- なぜ「多職種で決める」と嚥下が安定するのか
- 本ページのフレーム: SBAR ×( POS → T 位置 → GS )
- POS(姿勢管理):嚥下安全の“土台”を共通言語に
- T 位置(相対的喉頭位置):形態の偏りを“数字”で共有
- GS:舌骨上筋群筋力(機能)を“優先度”に変換する
- SBAR テンプレ:カンファで 3 分で「決める」書式
- 決定事項の最小セット:誰が・何を・いつまでに・どう測るか
- モニタリング:現場で書ける 8 項目
- 現場の詰まりどころ:「条件の揺れ」で所見がブレる
- よくある失敗( OK / NG 早見)
- よくある質問
- 次の一手(同ジャンルで最短導線)
- 参考文献
- 著者情報
嚥下カンファレンスの進め方: SBAR × T 位置・ GS × POS で「決める」
本ページは、嚥下支援を「多職種で決め切る」ための実務ガイドです。ポイントは、POS(姿勢)→ T 位置(形態)→ GS(機能)の順でボトルネックを言語化し、SBARで会議の決定事項を“書式”に落とすことです。
スクリーニング検査や食形態の詳細そのものではなく、誰が・何を・いつまでに・どう測るかを揃えて、現場のブレ(条件の揺れ)を減らす構成にしています。
なぜ「多職種で決める」と嚥下が安定するのか
嚥下は「安全(誤嚥・窒息)」と「摂取量・服薬・ QOL 」を同時に成立させる必要があり、単一職種の最適化だけでは破綻しやすい領域です。さらに、病棟・施設・在宅では環境や介助者が変わり、同じ患者でも条件が毎回ズレることで所見が揺れます。
そこで、会議のゴールを「評価の報告」ではなく、条件の統一と決定事項の固定に置きます。POS を土台に、 T 位置(形態)と GS(機能)で“変えられる要因”を示し、 SBAR で短く合意する――この型があると、再評価の比較が成立しやすくなります。
本ページのフレーム: SBAR ×( POS → T 位置 → GS )
| 手順 | 見るもの | アウトプット |
|---|---|---|
| 1 | POS(座位・支持・頸部) | 「続く姿勢」の条件を固定(誰が見ても同じ) |
| 2 | T 位置(相対的喉頭位置) | 形態の偏り(上方/下方寄り)を共有 |
| 3 | GS(舌骨上筋群筋力) | 機能の不足(保持困難など)を共有 |
| 4 | SBAR | 短く結論へ(方針・担当・期限) |
| 5 | モニタリング | 再評価の指標とトリガーを合意 |
POS(姿勢管理):嚥下安全の“土台”を共通言語に
嚥下は口腔・咽頭の局所だけでなく、骨盤・体幹・頸部の姿勢に強く影響されます。まずは「評価前に整える条件」を固定し、毎回同じ条件で観察できる状態を作ります。
座位が取れる場合は、骨盤ニュートラル → 足底全接地 → 体幹の左右対称 → 頭頸部の軽度前屈〜中間位の順で調整し、疲労なく再現できる“続く姿勢”にします。臥位中心なら、頭部挙上角度と頸部の支持を固定して比較します。
| 項目 | チェック | 記録例 |
|---|---|---|
| 骨盤 | 後傾/側屈の有無、支持の安定 | 骨盤:中間位(クッション 1 枚) |
| 足底 | 全接地、踏み込みの左右差 | 足底:全接地(台 2 cm) |
| 体幹 | 前崩れ、回旋、疲労で崩れるか | 体幹:軽度前傾で安定 |
| 頭頸部 | 前方頭位、顎の上がり、支持の有無 | 頸部:中間位(枕高さ固定) |
| 上肢 | 肘支持、食具操作の自由度 | 肘:前腕支持あり(テーブル高固定) |
T 位置(相対的喉頭位置):形態の偏りを“数字”で共有
T 位置(相対的喉頭位置)は、オトガイ・甲状軟骨・胸骨上端を基準に、喉頭・舌骨周囲の相対位置を定量化する考え方です。多職種連携では「なんとなく喉頭が低い/高い」を、同じ言葉で共有できるのが利点です。
臨床では、姿勢・頸部可動域・頸部筋緊張・支持の作り方で変化しうる指標として扱い、単独で断定せず、所見とセットで“介入の優先順位”を作ります。
| 項目 | 方法 | 記録例 |
|---|---|---|
| 基準点 | オトガイ/甲状軟骨上端/胸骨上端 | 3 点を触診で同定 |
| 計測 | テープで GT と TS を 2 回測って平均 | GT 5.2 cm、 TS 7.5 cm |
| 算出 | T 位置= GT /( GT + TS ) | T 0.41 |
| 解釈 | 偏りは “外れ値” として全体像の材料にする | 中間〜下方寄り |
GS:舌骨上筋群筋力(機能)を“優先度”に変換する
GS は、舌骨上筋群の筋力(頭部保持の可否)を簡便に段階化して共有する枠組みです。嚥下そのものの評価というより、「強化を先行すべきか」「緊張・ ROM ・支持を先行すべきか」の判断材料に使うと運用が安定します。
目安として、GS 低下 × T 位置が下方寄りなら強化( CTAR など)を優先しやすく、GS 低下 × T 位置が上方寄りなら頸部緊張・ ROM ・支持条件の修正を先行しやすい、という形でチームに提示すると議論が短くなります。
| 項目 | 方法 | 記録例 |
|---|---|---|
| 体位 | 背臥位で頸部を他動最大前屈位 → 保持を指示 | 背臥位・前屈位保持 |
| 判定 | 頭部の落下程度・保持の可否で段階化 | GS: Gr.2(保持困難) |
| 併記 | 疲労で悪化するか、再現性があるか | 反復で低下あり |
SBAR テンプレ:カンファで 3 分で「決める」書式
SBAR は、情報共有を“短く結論へ”寄せるための枠組みです。嚥下では「決める項目」を固定しないと、毎回議論が散りやすくなります。下の表を、議事録やカルテの雛形として使えます。
| 枠 | 書く内容 | 例 |
|---|---|---|
| S(状況) | いま困っていること/リスク | むせ増・完食率低下・湿性嗄声あり |
| B(背景) | 疾患・経過・直近の変化 | 脳卒中後 2 週、離床量増で疲労増 |
| A(評価) | POS/ T 位置/ GS +所見 | POS:骨盤後傾あり、 T 0.46、 GS Gr.2 |
| R(提案) | 決定事項(担当・期限・再評価) | 座位条件固定、 一口量 5 g、 7 日で再評価 |
決定事項の最小セット:誰が・何を・いつまでに・どう測るか
会議の最後に「決める」項目を固定します。ここが曖昧だと、翌日から条件がズレて所見も揺れます。以下は、最小セットの雛形です。
| 決める項目 | 担当 | 内容 | 再評価の期限 |
|---|---|---|---|
| POS(姿勢) | PT /看護 | 骨盤中間位+足底全接地、頸部中間位を標準 | 7 日 |
| 一口量・ペース | OT /看護 | 一口量 5–7 g、 2 口ごと反復嚥下 | 7 日 |
| 食形態・水分 | ST /栄養 | 制限は最小限から開始、段階アップ前提 | 7–14 日 |
| 口腔ケア | 看護/歯科 | タイミングと手順を標準化 | 毎週 |
| 訓練(優先順位) | PT /ST | POS →(必要なら) ROM /その後に強化 | 7–14 日 |
| 検査の要否 | 医師/ST | 必要なら VFSS / FEES の相談へ | 随時 |
モニタリング:現場で書ける 8 項目
抽象的な KPI より、誰でも同じように記録できる項目に統一します。「増悪トリガー」を先に決めると、臨時カンファが回しやすくなります。
| 項目 | 観察・測定 | トリガー(例) |
|---|---|---|
| むせ/咳 | 1 食あたり回数 | 前週比で増、または連日 3 回以上 |
| 声質 | 湿性嗄声の有無 | 食前後で湿性が持続 |
| 呼吸 | 呼吸数・ SpO₂ ・息切れ | SpO₂ 低下や息切れ増 |
| 食事時間 | 配膳〜完了(分) | 60 分超が連日 |
| 摂取量 | 主食/副食%、飲水量( mL ) | 完食率 50%未満が連日 |
| 体位逸脱 | 骨盤後傾・前方頭位の回数 | 1 食で 3 回以上 |
| FOIS | 1–7 の段階で共有 | 低下/降段が出現 |
| 体重・脱水 | 体重・尿量・口腔乾燥など | 摂取低下+乾燥が進行 |
現場の詰まりどころ:「条件の揺れ」で所見がブレる
うまくいかない原因の多くは、嚥下そのものより条件(姿勢・一口量・ペース・環境・介助者)が毎回変わることです。まずは POS と一口量を固定し、同じ条件で観察・再評価できる状態を作るだけで、議論が一気に短くなります。
記録が散らばっていると、会議の結論が「印象」に寄りやすくなります。面談準備のチェックと一緒に、職場の評価・記録の整え方も見直したい方は、面談準備チェック&職場評価シートを先に揃えると、チーム運用の改善点が見えやすくなります。
よくある失敗( OK / NG 早見)
| 場面 | NG | OK |
|---|---|---|
| 会議 | 所見が多くて結論が出ない | POS → T 位置 → GS の順で 3 行に圧縮して SBAR へ |
| 介助 | 介助者ごとに姿勢や一口量が変わる | POS と一口量を標準条件として掲示・共有 |
| 制限 | 不安で制限を強めたまま戻せない | 最小制限 → 短期再評価( 7–14 日 )をセットで決める |
| 再評価 | 比較条件が違って変化が読めない | 「同条件」で測る項目( POS / 一口量 / ペース )を固定 |
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. カンファで一番大事なことは何ですか?
A. 「姿勢( POS )と条件(一口量・ペース)を固定して、同じ条件で再評価できる状態を作る」ことです。評価が良くても、条件が揺れると所見はブレて、結論が出にくくなります。
Q2. T 位置と GS は、毎回測るべきですか?
A. 毎食での測定が目的ではなく、「介入の優先順位をチームで揃える」ための共通言語として有効です。まずは週次など、施設の運用に合わせて“同条件”での比較が成立する頻度から始めるのが現実的です。
Q3. SBAR で書き切れません。
A. A(評価)を POS / T 位置 / GS の 3 行に固定すると、自然に短くなります。細かい所見は別欄に残し、SBAR には「決めるための最小情報」だけを載せるのがコツです。
Q4. 臨時カンファは、いつ開くべきですか?
A. 「むせ増」「湿性嗄声の持続」「摂取量の急落」「体位逸脱が続く」など、モニタリングで決めたトリガーに一致したときです。事前にトリガーを決めておくと、迷いが減ります。
次の一手(同ジャンルで最短導線)
- 栄養・嚥下ハブ(索引):スクリーニング → 栄養 → 嚥下安全の全体像
- 摂食嚥下評価の基本(総論):ベッドサイドのフローと使い分け
- 嚥下 5 相の観察プロトコル( PT 向け ):姿勢づくりと観察の順番
参考文献
- ASHA. Adult Dysphagia Practice Portal. Link
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会. 嚥下調整食分類 2021. Web
- Rosenbek JC, Robbins JA, Roecker EB, et al. A penetration-aspiration scale. Dysphagia. 1996;11(2):93-98. doi: 10.1007/BF00417897. PubMed
- Martin-Harris B, Brodsky MB, Michel Y, et al. MBS measurement tool for swallow impairment—MBSImP: establishing a standard. Dysphagia. 2008;23(4):392-405. doi: 10.1007/s00455-008-9185-9. PubMed
- Suiter DM, Leder SB. Clinical utility of the 3-ounce water swallow test. Dysphagia. 2008;23(3):244-250. doi: 10.1007/s00455-007-9127-y. PubMed
- Trapl M, Enderle P, Nowotny M, et al. Dysphagia bedside screening for acute-stroke patients: the Gugging Swallowing Screen. Stroke. 2007;38(11):2948-2952. doi: 10.1161/STROKEAHA.107.483933. PubMed
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下