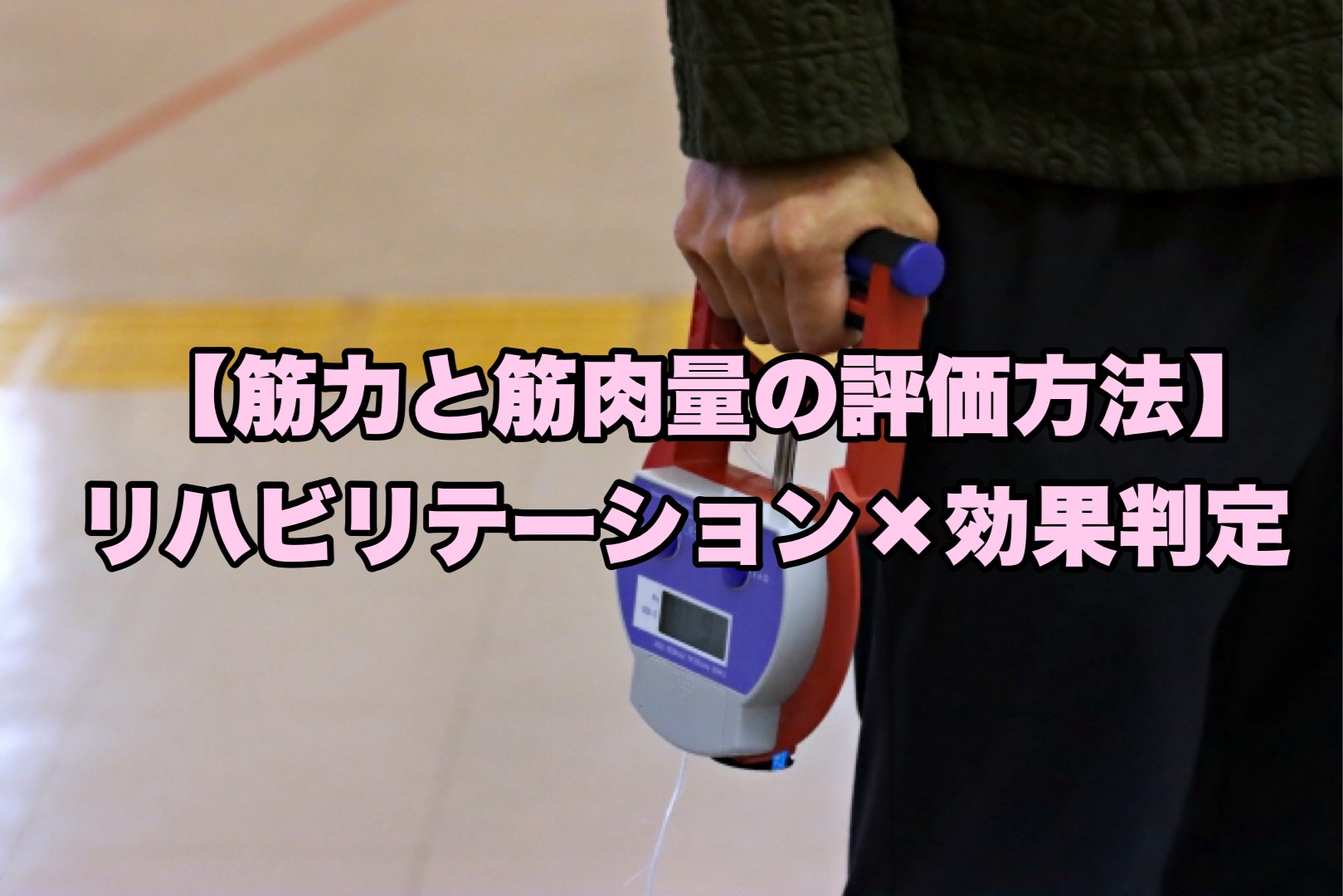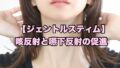筋力評価の実務ガイド(MMT/HHD/握力/5回立ち上がり/SPPB)
本稿は「筋力 評価方法」を趣旨/判定基準/観察ポイント/閾値で整理し、現場で迷わない最短ルートを示します。ベッドサイドの迅速スクリーニングは MMT・握力、左右差や経時変化の定量は HHD、転倒・フレイルの俯瞰は 5STS/SPPB。MMT の詳細は徒手筋力テスト(MMT)専用ガイドをご参照ください(本文インラインは本リンクのみ)。
要約表(項目別:趣旨・判定・観察・閾値)
| 項目 | 趣旨(何がわかる?) | 判定基準(代表) | 観察ポイント(凡ミス回避) | 閾値・目安 |
|---|---|---|---|---|
| MMT | 機器なしで主要筋群の低下を迅速把握 | 0–5 等級(+/−は極力回避) | 近位固定/抵抗方向・距離・速度の標準化 | 3/5(重力克服)を機能分岐点に |
| HHD | 左右差・微小変化の定量(等尺) | 最大努力 3 試行の最大値 or 平均 | ベルト固定、体位・角度 SOP 化、疼痛併記 | 左右差 10–15%超に留意(施設基準) |
| 握力 | 全身筋力のスクリーニング/フレイル指標 | 座位・肘 90°・3 試行最大値 | グリップスパン調整/号令と休息の統一 | 男 < 28 kg/女 < 18 kg(AWGS2019) |
| 5回立ち上がり(5STS) | 下肢筋力と遂行機能の橋渡し | 肘掛なし椅子(座面上端 43–45 cm)・胸前組み・所要時間 | 失敗理由(疼痛・恐怖・失衡)も重要所見 | 12 秒以上で低筋力の可能性(AWGS2019) |
| SPPB | バランス・歩行・5STS の総合(0–12) | 各 0–4 点の合計 | 路面・靴・距離固定、介助基準を共有 | 9 点以下で機能低下を示唆 |
MMT(徒手筋力テスト)
- 項目の趣旨: 機器不要で主要筋群の概況を迅速に把握。疼痛・可動域制限下でも等尺で評価可。
- 判定基準: 0–5 等級を厳密運用。4–5 の判別は抵抗の方向・距離・速度を標準化し、同一検者・同条件で縦比較。
- 観察ポイント: 近位固定で代償抑制/疼痛・恐怖・疲労を NRS 等で併記/同時間帯・同前処置で再現性↑。
- 閾値(目安): 3/5(重力克服)を機能分岐点としてプログレッションを判断。
HHD(ハンドヘルドダイナモメータ/メーター)
- 項目の趣旨: 等尺最大筋力を数値化し、左右差・微小変化を捉える。介入効果判定や説明責任に強い。
- 判定基準: サブマックス 1–2 回 → 最大努力 3 回。外れ値は再試行、最大値または平均を採用。
- 観察ポイント: 非伸縮ベルト固定を第一選択(例:膝伸展=膝屈曲 60°、股外転=0–10°、肘屈曲=90°、肩外転=30° 等尺)。体位・角度・固定点を SOP 化。疼痛/痺れの併記。
- 閾値(目安): 施設基準で左右差 10–15%超は留意。術後や疼痛例ではタスク遂行・神経学的所見も併せて解釈。
握力(Handgrip Strength)
- 項目の趣旨: 全身筋力や転帰と関連し、スクリーニングに有用。機器普及・標準化が容易。
- 判定基準: 座位/肩内外回中間/肘 90°/前腕中間位/手関節 0–30°背屈。3 試行の最大値採用。
- 観察ポイント: グリップスパン最適化/号令法と休息時間の統一/疼痛・しびれは注記。
- 閾値: 男性 < 28 kg・女性 < 18 kgで低筋力の可能性(AWGS2019)。
5回立ち上がり(Five Times Sit-to-Stand:5STS)
- 項目の趣旨: 下肢筋力と遂行機能の橋渡し。実行可否自体が重症度の手掛かりに。
- 判定基準: 肘掛なし椅子(座面上端 43–45 cm)、背もたれ接触で開始、腕は胸前組み、合図で 5 回立座の所要時間を測定。
- 観察ポイント: 前方移動・荷重戦略・代償(両上肢使用)を観察。失敗理由(疼痛・恐怖・失衡)は重要所見として記録。
- 閾値: 12 秒以上で低筋力の可能性(AWGS2019)。
SPPB(Short Physical Performance Battery)
- 項目の趣旨: 立位バランス・歩行速度・5STS の 3 項目合計で移動関連機能を総合評価(0–12 点)。
- 判定基準: 路面・距離(例:4 m)・靴の有無・補助具の扱いを固定。各サブテスト 0–4 点の合計。
- 観察ポイント: 介助基準をチームで共有。中止判断・安全確保を最優先。
- 閾値: 一般に9 点以下で機能低下を示唆(転倒・再入院リスクと関連)。
信頼性を上げる 8 つのコツ
- SOP 化: 体位・角度・固定・号令を写真つきで明文化(検者間差を縮小)。
- 同一検者・同一時間帯: 薬効・疲労・日内変動の影響を一定化。
- 疼痛・恐怖・痺れ: NRS 等で併記し数値の背景を透明化。
- HHD: ベルト固定+3 試行、外れ値は再試行。
- 握力: グリップスパン最適化と休息 30–60 秒の固定。
- 測定不能の扱い: 重大所見として理由を記録(転倒リスク・退院可否の議論に資する)。
- 継時比較: 同条件・同機種を最優先(機種変更時は校正ログ)。
- 連携: 低筋力例は栄養評価(GLIM/MNA)や活動量指導とバンドルで介入。
FAQ(タップで開閉)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
AWGS の基準はこれで最新ですか?
臨床実装では AWGS2019 が広く用いられます。対象特性や民族差を踏まえ、BIA/DXA と併用して運用してください。
HHD は保持でも良い?ベルト固定は必須?
保持のみでも可能ですが、ベルト固定の方が再現性(ICC)が高い報告が多く、可能な部位では固定法を第一選択にします。
MMT の 4 と 5 の見分けが難しい…
抵抗の方向・距離・速度を標準化し、等尺での“崩れ”を観察。必要に応じて HHD で数値化し縦比較の解像度を上げます。
参考文献
- Chen LK, et al. Asian Working Group for Sarcopenia: 2019 Consensus Update. J Am Med Dir Assoc. 2020;21(3):300–307. doi:10.1016/j.jamda.2019.12.012. PubMed
- Guralnik JM, et al. Short Physical Performance Battery. J Gerontol. 1994;49(2):M85–M94. doi:10.1093/geronj/49.2.M85. PubMed
- Bohannon RW. Reference values for five-times sit-to-stand test. Physiotherapy. 2006;92(1):11–15. doi:10.1016/j.physio.2005.05.003. PubMed
- Chamorro CE, et al. Test–retest reliability of hand-held dynamometry. PM&R. 2014;6(4):324–331. doi:10.1016/j.pmrj.2013.08.605. PubMed
- Roberts HC, et al. A review of grip strength measurement in clinical practice. Age Ageing. 2011;40(4):423–429. doi:10.1093/ageing/afr051. PubMed
関連記事(カード2件)
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下