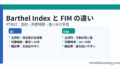家屋調査の PT チェックリスト【評価→採寸→理由書】住宅改修にも使える実務フロー
本ページは、退院前訪問などで家屋調査を行う理学療法士・リハビリ職向けに、臨床評価・採寸・設計・理由書作成までを 1 枚にまとめたチェックリストです。介護保険の住宅改修や福祉用具選定とセットで使うことを想定しています。制度の適用可否・上限・受領委任・減税の比較は「支援制度ガイド」で確認してください。
家屋調査の経験をキャリアにも活かす(理学療法士の転職ガイド)
家屋調査の現場フロー(5 ステップ)
- ゴール設定:退院後の生活像を共有し、自立目標・介助量(移乗/更衣/入浴/排泄)と転倒リスクを合意
- 評価:玄関→居室→トイレ/浴室まで動線を一気通貫で確認しつつ、身体機能・住環境・介護体制を整理
- 採寸:高さ・幅・奥行・段差・傾斜・下地の有無を実測(後述の表に記録)
- 設計:浴室・トイレ・玄関などを機能の連鎖で捉え、住宅改修や福祉用具の案を作成
- 根拠化:理由書・図面・写真(同アングル前後)を整備し、工事後に同指標で再評価
家屋調査でみるフィジカル・安全チェック(必須)
| 項目 | 観察ポイント | 設計への反映例 |
|---|---|---|
| 立ち座り | 立ち上がり回数・介助量・足底接地 | 座面高の最適化、L 字手すり位置、踏み台/式台の段差調整 |
| 移乗 | 回転半径・補助具の干渉・方向性 | 有効開口幅の確保、引き戸化、手すりの連続配置 |
| 歩行 | 歩行補助具の種類・ステップ幅・躓き | 段差解消、高さ見切り、ノンスリップ床材、視認性の向上 |
| 認知/視覚 | 見当識・指示理解・コントラスト感度 | 色コントラスト、ピクトグラム、動線の単純化 |
| 介護体制 | 介護者の身長/筋力・同居/訪問の有無 | 介助側の立ち位置/動線、作業空間(奥行と幅)の確保 |
採寸チェックリスト(高さ・幅・段差・傾斜)
家屋調査では「見た目の印象」だけで判断せず、メジャーやレーザー距離計で数値を押さえることが重要です。住宅改修や福祉用具の選定根拠としてそのまま理由書・図面に転記できるよう、以下のように現場で記録しておきます。
| 場所/項目 | 実測欄 | 目安/設計のヒント |
|---|---|---|
| 手すり高さ | ______ mm | 立位 700–850 mm 程度を基点に、把持径 32–36 mm、身体寸法と動線で微調整 |
| 便座高さ | ______ mm | 膝関節 90°基準で 400–450 mm 目安(移乗手順・下肢筋力で調整) |
| 有効開口幅 | ______ mm | 杖/歩行器:700–750 mm、車いす:750–800 mm 以上を目安 |
| 段差高 | ______ mm | 式台/スロープ等で分割。見切り材で段差エッジを明確化 |
| スロープ傾斜 | 1 : ___ | 屋内は緩やか(例 1:12 前後)、屋外は環境/距離に応じて緩和・踊り場設置 |
| 下地/固定 | 有 / 無(位置:__________) | 手すり位置で下地を確認。必要に応じて下地補強=付帯工事 |
設計パターン(機能の連鎖で考える)
家屋調査で得た情報は「個々の場所」だけでなく、住宅改修全体の流れに落とし込むことが重要です。浴室・トイレ・玄関・廊下/居室を機能の連鎖として整理し、優先順位をつけて提案します。
- 浴室:段差解消+ノンスリップ床+縦横手すり+シャワーチェア導線(濡れ面摩擦を優先)
- トイレ:便器更新/座面高調整+L 字手すり+回転半径の確保(扉干渉の回避)
- 玄関:式台 or スロープ+手すり+転落防止柵(外構→アプローチまで動線一体で)
- 廊下/居室:段差見切り・照度とコントラスト・カーペット継ぎ目段差の最小化
写真・図面の撮り方チェック
審査側やケアマネ・施工業者と共通言語を持つには、家屋調査の所見を写真と図面で残すことが重要です。住宅改修の有無にかかわらず、次回評価にも使える「再現性のある証拠」を意識します。
- 施工前/後は同一アングル・同焦点距離で比較できるよう撮影
- 寸法入り平面図(有効幅・半径・段差高・手すり芯々)
- 手すりは固定部位と下地が分かる近接写真を追加
- スロープは傾斜と立上り/踊り場位置を明示
- 足元・開閉時の扉稼働範囲(干渉の有無)
- 夜間動線の照度/スイッチ位置
- 介助動線(介助者の立ち位置・回避スペース)
理由書テンプレ(家屋調査→住宅改修用のコピペ調整)
ここでは、家屋調査の所見を住宅改修や福祉用具の理由書に落とし込むときの「ひな型」を示します。実際には対象者・住環境に合わせて語尾や具体例を調整してください。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 対象動作・困難 | トイレ立ち上がりに介助を要し、転倒歴あり。廊下〜トイレの段差 8 mm で躓きやすい。 |
| 評価所見 | 立ち上がり困難、回転半径不足、濡れ面での足滑りを確認。 |
| 改修内容 | トイレ:L 字手すり(横 700 mm・縦 800 mm)、便座高 420 mm に調整。廊下:段差処理+ノンスリップ。 |
| 付帯工事の必要性 | 手すり固定に下地補強が必要(主工事に付随して必要)。 |
| 期待効果・代替検討 | 自立立位・介助量軽減・転倒リスク低減。代替案:玄関側手すり延長。 |
| 写真・図面 | 施工前後の同一角度写真、寸法入り平面図を添付。 |
よくある落とし穴(審査/実務)
- 機能追加のみ(温水洗浄便座の追加等)を「対象」と誤記→ 仕様書で対象/対象外を分離
- 付帯工事の範囲が広すぎる→ 主工事に付随して必要な範囲に限定
- 開口幅・回転半径の不足→ 図面で実寸を明示し、引き戸化/扉位置変更を検討
- 屋外アプローチの抜け漏れ→ 玄関〜道路までの一気通貫で動線設計
- 再評価不足→ 同指標でのビフォー/アフター、写真・動画で変化を可視化
工事後の再評価(タスク)
- 目標タスクで再評価(転倒件数・介助時間・移乗の独立度)
- 手すりの高さ/位置の再フィット、床材・照度の最終確認
- 家族/介護者への使用説明と練習、掲示用の注意カード設置
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に。面談準備チェック(A4・5分)と職場評価シート(A4)を無料公開しています。印刷してそのまま使えます。配布ページを見る
関連記事
参考資料(一次情報)
- 厚生労働省. 介護保険における住宅改修(対象 6 類型・上限・申請フロー). PDF
- 厚生労働省. 福祉用具・住宅改修に関する法令(居宅介護住宅改修費の根拠規定). PDF
- 厚生労働省. 日常生活用具給付等事業の概要(居宅生活動作補助用具:住宅改修費). Web
- 国土交通省. バリアフリー施策(建築物移動等円滑化基準 等:設計の考え方). Web
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下
監修:rehabilikun(理学療法士)/ 最終更新:2025-11-08 / 記事種別:実務チェックリスト(一次情報リンク付き)