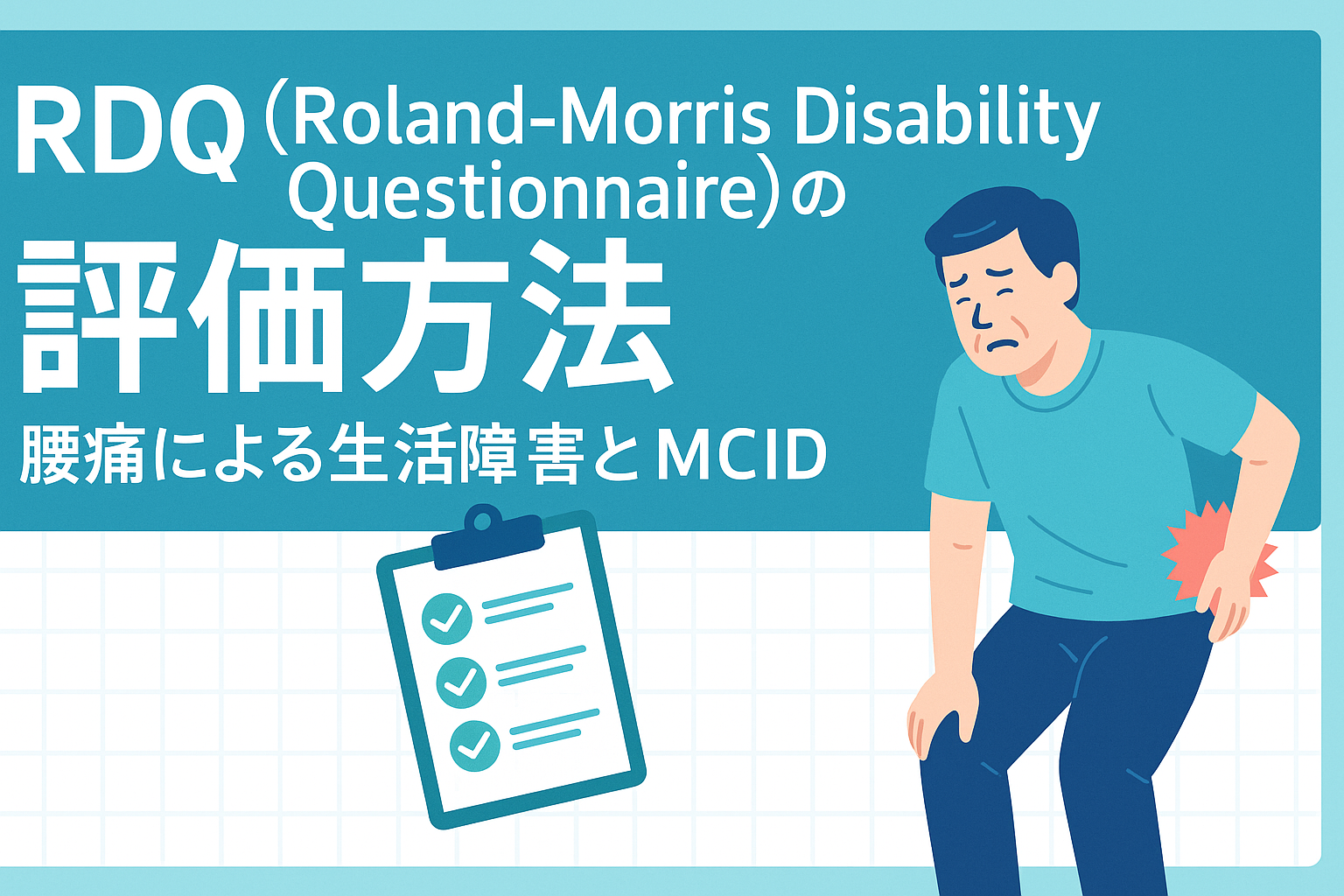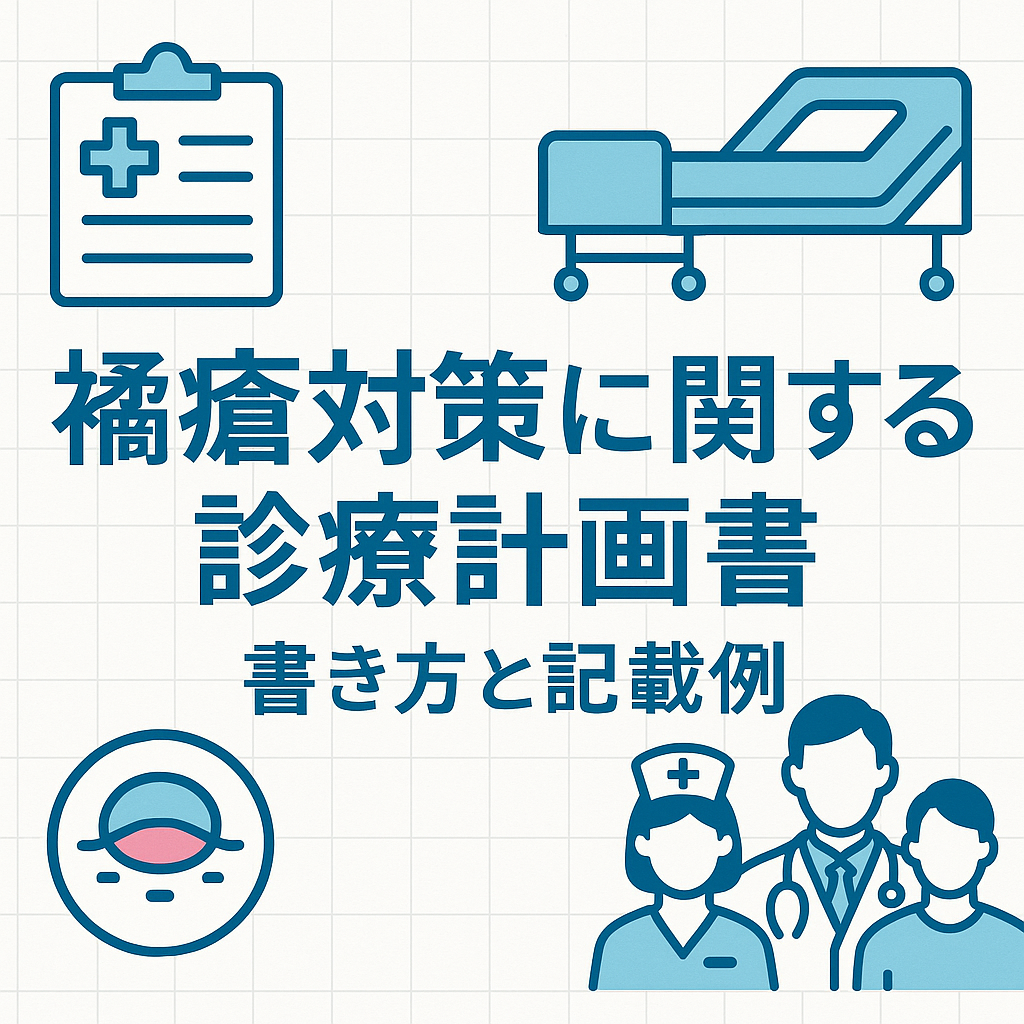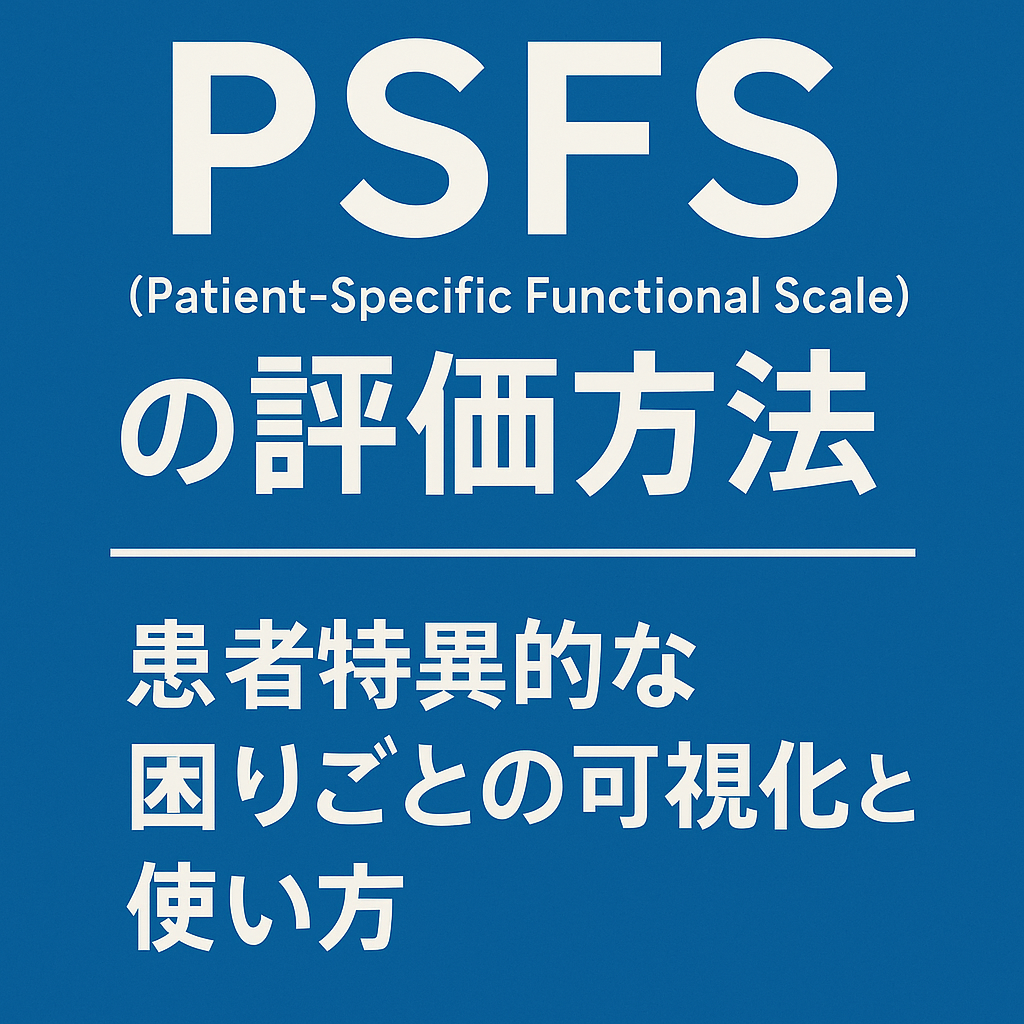RDQ(Roland-Morris Disability Questionnaire)とは?|腰痛による生活障害の患者立脚評価
腰痛評価を武器にしたい PT へ|臨床力を高める学び方とキャリアの整え方を見る
RDQ(Roland-Morris Disability Questionnaire)は、腰痛によって日常生活がどの程度制限されているかを患者自身が評価する、腰痛特異的な患者立脚型質問票です。腰痛のために「立つ」「歩く」「座る」「服を着る」「仕事をする」などの行動がどのくらい難しくなっているかを 24 項目で尋ね、「はい/いいえ」で回答してもらうシンプルな構造が特徴です。得点は 0〜24 点で、高得点ほど腰痛による生活障害が大きいことを示します。
項目数と回答形式がコンパクトで、5 分程度で実施できることから、外来・病棟・在宅いずれの場面でも使いやすい評価ツールです。国民調査に基づく基準値や、日本語版の信頼性・妥当性・反応性も検証されており、慢性腰痛のアウトカム研究から日常の臨床評価まで幅広く利用されています。腰痛患者の「痛みそのもの」だけでなく、「生活機能へのインパクト」を定量的に把握したいときに有用なスケールです。
RDQ の構成項目とカバーする生活機能
RDQ は、腰痛のために日常生活でどのような困りごとが生じているかを、「今日の状態」に基づいて 24 項目で尋ねます。すべての項目が「はい(あてはまる)」か「いいえ(あてはまらない)」の 2 択で、「はい」の数がそのまま RDQ スコア(0〜24 点) になります。項目は「家にこもりがち」「ゆっくり歩く」「階段昇降」「家事・仕事の中断」「長く座れない」「横になる時間が増える」など、多様な生活場面を網羅しています。
下図は、個々の設問文をそのまま示すのではなく、RDQ がカバーしている生活機能を「姿勢・基本動作」「移動・階段」「家事・仕事」「休息・心理」の 4 ブロックに整理したイメージ図です。評価チーム内で「この患者さんはどの領域に訴えが集中しているか」を共有する際のメモとして活用してください。他の腰痛評価スケールとの位置づけや組み合わせ方は、腰痛・評価のまとめページ(評価ハブ)で整理しておくと便利です。
RDQ の実施方法と採点ルール
RDQ は自己記入式で、「今日の腰痛のために起きていること」について回答してもらいます。各項目は「今日、腰痛のために〜である」という文章になっており、あてはまる場合は「はい」、あてはまらない場合は「いいえ」を選択してもらいます。読み書きが難しい方には代読・代筆も可能ですが、どちらの選択肢にするかは必ず本人に確認することが重要です。
採点は非常にシンプルで、「はい」と答えた項目数がそのままスコア(0〜24 点) になります。高得点ほど腰痛による生活障害が大きい状態です。再評価では、同じ条件(コルセット着用の有無、就労状況、治療介入の有無 など)で回答してもらうよう確認します。紙ベースだけでなく、電子カルテ上にチェックシートのテンプレートを用意しておくと、看護師・リハ職・医師が共通言語として使いやすくなります。
スコアの解釈と基準値・MCID の目安
日本の一般成人を対象とした調査では、腰痛の訴えがある群で RDQ の平均値がおよそ 4 点前後、全体では 1〜2 点程度と報告されています。これは「多くの腰痛有訴者は、日常生活の一部に軽度〜中等度の制限を感じている」水準と解釈できます。一方、10 点を超えるようなスコアでは、家事・仕事・外出など複数の領域で生活障害が目立つケースが多くなります。
変化の解釈については、原著やシステマティックレビューなどから、2〜3 点程度の改善 を「最小限の臨床的に意味のある変化(MCID)」とみなすことが提案されています。また、ベースラインスコアの 30 % 以上の改善を目安とする方法もあり、たとえば初回 10 点の患者さんであれば、3 点以上の減少が 1 つの目安となります。小さな変化に過度な意味付けをしないよう、「スコアの変化量」「痛みスケール」「患者さん自身の主観的な変化」をセットで確認することが大切です。
ODI など他の腰痛スケールとの使い分け
腰痛に対する機能評価としては、RDQ のほかに ODI(Oswestry Disability Index)や EQ-5D、SF-36 などの包括的 QOL 尺度もよく用いられます。RDQ は「腰痛に特化した日常生活の機能障害」をコンパクトに測る道具 であり、外来や病棟でのルーチン評価や、地域調査のアウトカムとして扱いやすいのが長所です。一方、重症例を個別に丁寧に追う場合や、精神面・社会参加を含めてより広く QOL を捉えたい場合は、ODI や包括的 QOL 尺度を併用する方が適しています。
研究デザインとしては、腰痛特異的な機能指標として RDQ、全身的な健康関連 QOL の指標として EQ-5D や SF-36、痛みの強さとして数値評価スケール(NRS)・視覚的アナログスケール(VAS)を組み合わせるのが定番です。臨床では、このようなフルセットを毎回行うのは現実的ではないため、「日常診療では RDQ+痛みスケール」「研究やフォローアップでは RDQ+包括的 QOL+仕事関連指標」といった使い分けが現実的です。
臨床での活用例:外来・回復期・在宅
外来では、慢性腰痛や脊柱管狭窄症などで通院中の患者さんに対し、初診時と 1〜3 ヶ月ごとに RDQ を実施することで、「自覚的な生活障害の変化」を数値で追うことができます。例えば「痛み自体はやや減っているが RDQ の改善が乏しい」症例では、痛み回避行動や身体活動量の低下がボトルネックとなっている可能性を考え、認知行動的アプローチや運動習慣の再獲得を重視したプログラムを検討できます。
回復期や在宅では、FIM や Barthel Index が「介助量」を把握するためのスケールであるのに対し、RDQ は「腰痛ゆえに避けている動き」や「できるがつらい動き」を拾いやすいのが利点です。家事・仕事・余暇活動など、本人が「本当はやりたいが控えていること」を明確にしていくことで、ゴール設定や退院後の生活デザインに反映しやすくなります。
RDQ を使うときの注意点と限界
RDQ は簡便で反応性の高い指標ですが、項目数が 24 と比較的少ないため、個人の微妙な変化を精密に追うには限界がある と指摘されています。また、精神面・社会参加・職場のストレスなどを直接問う項目は多くなく、心理社会的な要因を十分に捉えるツールではありません。抑うつ傾向や仕事上の葛藤が強いケースでは、RDQ だけで意思決定を行わず、問診や他の心理スケールの結果も合わせて解釈する必要があります。
さらに、「はい/いいえ」の 2 択であるため、患者さんの中には「どちらともいえない」と感じる場面も少なくありません。そのような場合は、「今日はどちらに近いですか?」と補足説明を入れつつ、毎回なるべく同じ説明で評価することで、測定誤差を抑える工夫が求められます。医師・看護師・リハ職のあいだで RDQ の位置づけと限界を共有しておくと、過度な期待や過小評価を避けやすくなります。
記録とチーム共有のコツ
カルテには、「RDQ の絶対値」「前回からの変化量」「変化した(または残存した)生活場面」の 3 点をセットで記載すると、他職種にも状況が伝わりやすくなります。例えば「RDQ 12→6(6 点改善)。家事の継続と屋外歩行が楽になった一方で、長時間座位では依然として腰痛を自覚」といった書き方をすれば、医師や看護師も「何が改善し、何が残っているのか」を具体的にイメージできます。
複数回の評価が見込まれる症例では、RDQ スコアの経時的変化を折れ線グラフにして患者さんと共有するのも有効です。「痛みの波はあるが、生活のしづらさとしては徐々に改善している」と視覚的に示すことで、運動療法やセルフマネジメント継続のモチベーションにつながります。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
RDQ は何点くらい変化したら「リハビリの効果あり」と考えて良いですか?
研究報告では、RDQ の変化量がおおむね 2〜3 点以上 であれば、最小限の臨床的に意味のある変化(MCID)の候補とみなせることが示されています。また、ベースラインスコアの 30 % 以上の改善を基準とする方法もあり、たとえば初回 10 点 → 7 点(3 点改善)は、臨床的に意味のある変化として検討する価値があります。ただし、変化量の解釈は評価間隔や介入内容、痛みスケール・患者の主観的な回復感などと合わせて行う必要があります。
それでも RDQ の改善が乏しいケースが続くと、「自分のリハビリの力量不足では?」と感じてしまうこともありますが、実際には介入時間の制約や職場体制、フォローアップの仕組みなど、環境要因が大きく影響していることも少なくありません。「いまの職場では、評価に見合うだけの介入やフォローを組みにくい」と感じる状況が続くときは、一度働き方や職場選びを整理するタイミングかもしれません。そうした“危険サイン”を整理するには、理学療法士の転職・職場選びガイドも参考になります。
おわりに
腰痛リハビリでは、「レッドフラッグの除外 → 神経学的評価 → 可動域・筋力・姿勢の評価 → RDQ などによる生活障害の把握 → 目標設定とプログラム立案 → 再評価」というリズムを押さえておくと、評価と介入の流れが整理しやすくなります。RDQ は、患者さんが日常生活のどの場面で困っているのかを短時間で把握でき、TUG や歩行テストなどの客観指標と組み合わせることで、より立体的な評価につながります。
一方で、「本当はもっと丁寧に腰痛評価と教育をしたいのに、時間や体制的に難しい」と感じる場面も少なくありません。そうしたときは、自分の働き方やキャリアの選択肢を一度整理することで、日々の臨床への向き合い方も前向きに変わりやすくなります。働き方を見直すときの抜け漏れ防止に使える面談準備チェック( A4・5 分)と職場評価シート( A4 )を無料公開していますので、転職に限らず情報収集や見学の場面でもダウンロードページを活用してみてください。印刷してそのまま使えます。
参考文献
- Suzukamo Y, Fukuhara S, Kikuchi S, et al. Validation of the Japanese version of the Roland-Morris Disability Questionnaire. J Orthop Sci. 2003;8(4):543–548. doi:10.1007/s10776-002-0640-6. PubMed
- 鈴鴨よしみ. Roland-Morris Disability Questionnaire(RDQ)によるアウトカム評価. 日本腰痛学会雑誌. 2009;15(1):17–22. J-STAGE
- 腰痛特異的 QOL 尺度 RDQ 日本語版制作委員会. RDQ 日本語版マニュアル―腰痛特異的 QOL 尺度. 東京: 医学書院; 2004.
- Bombardier C, Hayden J, Beaton DE. Minimal clinically important difference. Low back pain: outcome measures. J Rheumatol. 2001;28(2):431–438. PubMed
- Jordan K, Dunn KM, Lewis M, Croft P. A minimal clinically important difference was derived for the Roland-Morris Disability Questionnaire for low back pain. J Clin Epidemiol. 2006;59(1):45–52. doi:10.1016/j.jclinepi.2005.03.018. PubMed
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下