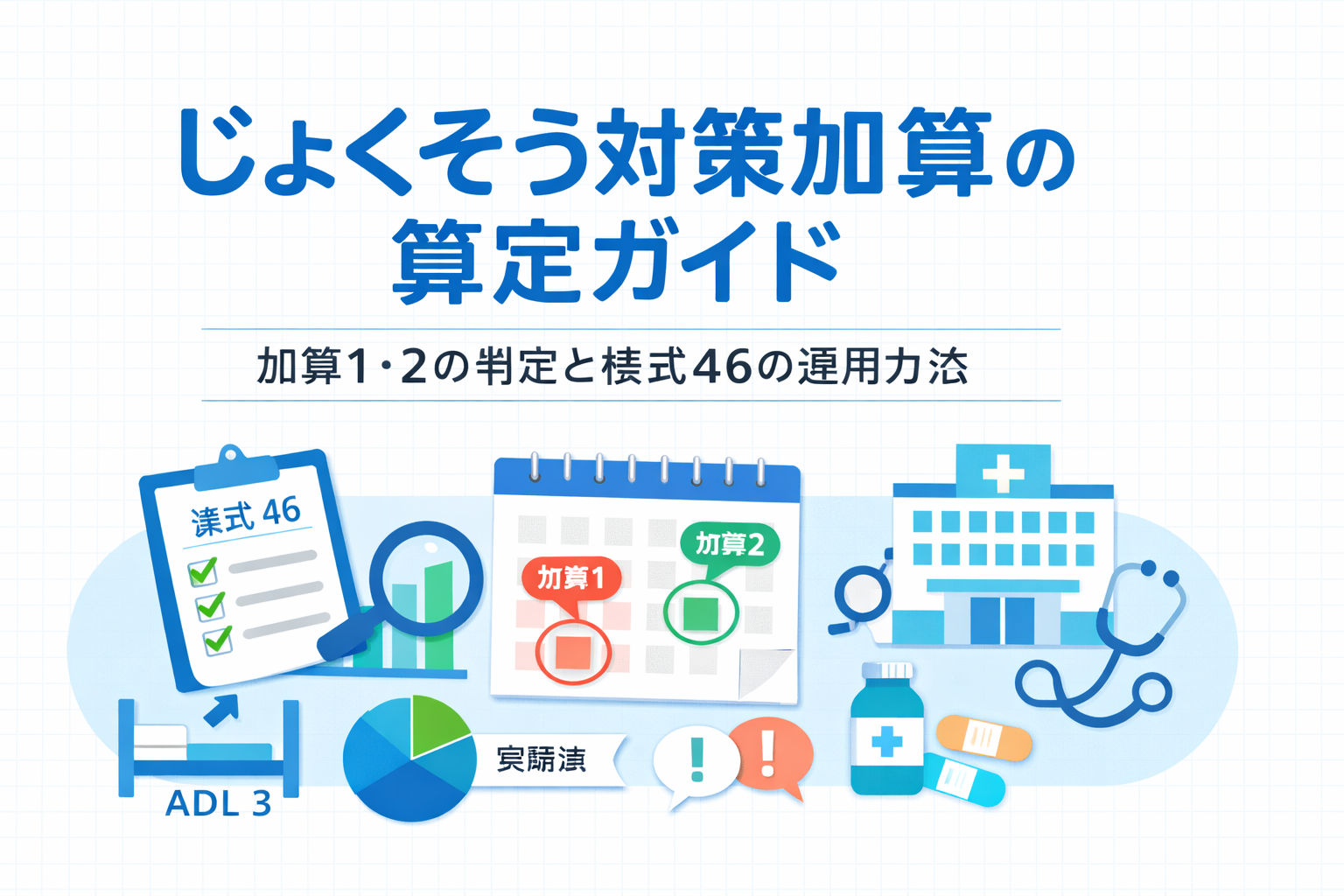- 褥瘡対策加算の算定ガイド|加算 1 / 2 の判定と「様式 46」運用の型(療養病棟)
- まず結論|点数・対象・判定の「確認順」
- 褥瘡対策加算とは|療養病棟( A101 )で「褥瘡の状態に応じて」上乗せする評価
- 点数と算定要件|加算 1 / 2 の違いは「暦月 3 月」と「直近 2 月の実績点」
- 運用フロー|“様式 46 → 実績点 → 判定”を毎月同じ手順にする
- DESIGN-R2020 と「実績点」|合計点は“深さ”を足さない
- PT が押さえる役割|“荷重・体位・座位”を「評価→介入→記録」でつなぐ
- 現場の詰まりどころ/よくある失敗|「監査で落ちる」ズレを先に潰す
- よくある質問(FAQ)
- 次の一手|院内で「迷わない型」を完成させる
- 参考文献
- 著者情報
褥瘡対策加算の算定ガイド|加算 1 / 2 の判定と「様式 46」運用の型(療養病棟)
褥瘡対策加算は、「今日は加算 1?それとも 2?」を毎月迷いやすい一方で、確認ポイントはかなり固定できます。結論は、対象( ADL 区分 3 )・点数(加算 1=15 点 / 加算 2=5 点)・判定(暦月 3 月・直近 2 月の実績点・当月の上回り日)を、同じ順番で見ていけば OK です。
制度の暗記より「確認の順番」を固定すると、算定も記録もブレません。 評価と記録の型を 3 分で整理する ※内部リンク(同一タブ)です。臨床の「型」を先に揃えたい方向け。
まず結論|点数・対象・判定の「確認順」
点数は、療養病棟入院基本料( A101 )の「注」に基づき、褥瘡対策加算 1 は 15 点、褥瘡対策加算 2 は 5 点( 1 日につき)です。
対象は、通知上「 ADL 区分 3 の状態の患者」について、別紙様式 46(褥瘡対策に関する評価)を用いて褥瘡の状態を確認し、治療・ケア内容を踏まえて毎日評価します。加算 1 / 2 の判定は、暦月 3 月と直近 2 月の実績点、そして当月の上回り日の 3 点で決まります。
褥瘡対策加算とは|療養病棟( A101 )で「褥瘡の状態に応じて」上乗せする評価
褥瘡対策加算は、療養病棟入院基本料( A101 )を算定する患者のうち、所定の状態にある患者に対して、必要な褥瘡対策を行った場合に、患者の褥瘡の状態に応じて加算する仕組みです。実務上は、「様式 46 の評価→実績点→加算 1 / 2 判定」までを 1 セットで運用します。
ここでいう褥瘡の状態評価は、DESIGN-R2020(日本褥瘡学会)に基づいて整理されます。院内で「同じ言葉」で話せるように、用語と点の扱いだけ先に揃えておくと、記録が一気にラクになります。
点数と算定要件|加算 1 / 2 の違いは「暦月 3 月」と「直近 2 月の実績点」
加算の要点は次のとおりです。
| 区分 | 点数( 1 日) | 算定の考え方(要点) | 現場で見るもの |
|---|---|---|---|
| 褥瘡対策加算 1 | 15 点 | 入院後(または評価開始後)暦月で 3 月を超えない間、または加算 2 を算定する日以外に算定 | 入院月カウント/当日が「加算 2 の日」かどうか |
| 褥瘡対策加算 2 | 5 点 | 直近 2 月の実績点が 2 月連続で前月を上回り、かつ当月に前月の実績点より上回った日に算定 | 前月・前々月の実績点/当月の上回り日 |
重要なのは、「加算 2 は毎日ではない」ことです。当月のうち、前月の実績点より上回った日だけが加算 2 の対象になります。逆に、それ以外の日は加算 1 で運用するのが基本になります(暦月 3 月の扱いも含む)。
運用フロー|“様式 46 → 実績点 → 判定”を毎月同じ手順にする
褥瘡対策加算がブレる原因は、「毎日の評価」「実績点」「加算 2 の日」の 3 つが混線することです。下のフローで、確認順を固定してください。
| タイミング | やること | 帳票・記録先 | ミスが出やすい点 |
|---|---|---|---|
| 毎日 | 別紙様式 46 の「褥瘡対策に関する評価」で状態を確認し、治療・ケア内容を踏まえて評価 | 別紙様式 46 /(必要時)計画見直しは診療録等 | 評価が「週 1」になってしまう/評価者が固定されていない |
| 月内(随時) | 当月の DESIGN-R2020 合計点を追跡し、月内で最も低い点を「実績点」として把握 | 実績点の控え(院内の集計表で OK ) | 実績点を「平均」や「月末の点」で扱ってしまう |
| 月初 | 前月・前々月の実績点を並べ、直近 2 月が 2 月連続で上回っているかを確認 | 前月実績点メモ( 2 行で足りる) | 「 2 月連続」の解釈違い |
| 当月の算定日判定 | 当月に前月実績点より上回った日があれば、その日だけ「加算 2 」 | 算定日(カレンダー化すると強い) | 「上回った日」を見落とす/逆に広げすぎる |
関連:褥瘡対策の施設基準と全体フローから整理したい場合は、先に 褥瘡対策の基準~フロー(親ページ) を見ておくと迷いが減ります。
DESIGN-R2020 と「実績点」|合計点は“深さ”を足さない
通知では、別紙様式 46 の評価項目のうち、「深さ」の点数は合計に加えない扱いになっています。さらに、暦月内で DESIGN-R2020 の合計点が最も低かった日の点数が、その月の実績点です。
ここがズレると、加算 2 の判定が崩れます。「深さを足してしまう」「月末の点を実績点にしてしまう」は、現場で最も起きやすい落とし穴なので、院内ルールとして明文化しておくのがおすすめです。
PT が押さえる役割|“荷重・体位・座位”を「評価→介入→記録」でつなぐ
褥瘡対策は看護主導になりやすい一方、PT が関与できる領域(体位変換の実効性、座位の圧分散、動作時のずれ・摩擦、離床量の設計)が多くあります。ポイントは、介入だけで終わらせず「記録に残る形」へ落とすことです。
- 体位:頻度の提案ではなく「根拠(皮膚所見・疼痛・循環・耐久性)」を 1 行で残す
- 座位:シーティング(座位保持・ずれ)を評価し、クッション・フットサポート調整の要点を残す
- 離床:離床が増えると皮膚は良くなるとは限らないため、リスク(ずれ・失禁・栄養)をセットで見る
現場の詰まりどころ/よくある失敗|「監査で落ちる」ズレを先に潰す
褥瘡対策加算は、やっているつもりでも“記録の形”が揃っていないと落ちます。特に「毎日評価」「実績点」「計画見直しの記載先」は、ズレが出やすい 3 点です。
| よくある失敗 | なぜ起きる? | 対策(最小) | 記録ポイント |
|---|---|---|---|
| 「週 1 評価」になっている | 担当が固定されず、業務に埋もれる | 評価担当を“当番制”にし、実施チェックを 1 つ作る | 様式 46 の評価日が空かないこと |
| 実績点を「月末の点」で扱う | 実績点の定義が共有されていない | 「月内の最小点=実績点」を院内ルールにする | 実績点は 1 行で控える(前月・前々月) |
| 合計点に「深さ」を足してしまう | DESIGN-R の合計の扱いが曖昧 | 深さは合計に入れない、と明記 | 点の算出手順を 1 行で残す |
| 計画を見直したのに診療録に残っていない | カンファで決めて終わる | 見直しの要点だけ「診療録等」に 2 行で残す | “いつ・何を・なぜ”の最小セット |
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1. 褥瘡対策加算 2 は「毎日」算定できますか?
基本はできません。加算 2 は、直近 2 月の実績点条件を満たしたうえで、当月に「前月の実績点より上回った日」に算定します。つまり、当月のうち“該当する日だけ”が対象です。
Q2. 入院してすぐは、加算 2 の条件を満たしていても加算 1 ですか?
通知上、入院後(または評価開始後)暦月で 3 月を超えない間は、加算 1 を算定する扱いになります。まずは月カウントを確認し、そのうえで加算 2 の日を判定してください。
Q3. 実績点は「平均」や「月末の点」ではダメですか?
実績点は、暦月内で DESIGN-R2020 の合計点が最も低かった日の点数です。平均や月末の点で置き換えると、加算 2 の判定が崩れるため、月内の最小点で管理するのが安全です。
Q4. 合計点に深さ( Depth )を足してよいですか?
通知上、別紙様式 46 の評価項目のうち「深さ」の点数は合計点に加えない取扱いです。院内で同じ計算ルールに統一してください。
Q5. PT はどこまで関与すべきですか?
PT は、体位・離床・座位の「ずれ・摩擦・圧分散」に関する評価と調整を、ケア計画や診療録へ“要点だけ”残すところまで関与できると、運用が強くなります。
次の一手|院内で「迷わない型」を完成させる
褥瘡対策加算は、要件そのものより「運用(誰が・いつ・どこに・どう残すか)」が揃っているかで安定します。最後に、院内で整える順番だけ決めておきます。
- 運用を整える:まずは褥瘡対策の全体像(施設基準・役割・月次の流れ)を 1 ページで揃えます。
褥瘡対策の基準~フロー(親) - 共有の型を作る:様式 46 の評価・実績点・算定日の判断を、チームで同じ言葉で共有できるようにします。
褥瘡ケア計画の作り方 - 環境の詰まりも点検する:人員・教育体制・記録文化・標準化のどこで止まっているかを、無料のチェックシートで棚卸しします。
無料チェックシートで「運用の詰まり」を点検する
参考文献
- 厚生労働省. 第 2 部 入院料等 通則(療養病棟入院基本料・褥瘡対策加算の点数を含む).
- 厚生労働省. 別添 1 医科診療報酬点数表に関する事項(療養病棟入院基本料:褥瘡対策加算の留意事項・算定要件).
- 日本褥瘡学会. DESIGN-R2020(褥瘡状態評価の枠組み).
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下