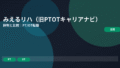運動失調の評価とリハビリの進め方(PT 目線の総論)
運動失調(協調運動障害、 ataxia )は、目的動作のために必要な関節・筋活動の時間的・空間的協調が破綻した状態を指します。小脳性失調だけでなく、感覚性・前庭性・大脳性の失調を含み、歩行・巧緻性・構音・嚥下など多くの機能に波及するため、理学療法評価とリハビリテーションの進め方を体系的に押さえておく必要があります。
本稿では、運動失調の「鑑別 → 評価スケール → 機能評価 → 環境・転倒リスク → リハ戦略」という流れを、 PT 目線で 1 本に整理します。急性発症での赤旗(脳卒中など)や、ビタミン欠乏・薬剤・アルコール・遺伝性疾患といった背景も含めて評価し、運動失調リハビリの具体的な進め方にどう落とし込むかを解説します。
運動失調の 4 分類と鑑別(小脳性・感覚性・前庭性・大脳性)
臨床で最初に行うのは「小脳性/感覚性/前庭性/大脳性」の四分類による当たり付けです。以下の表は、主要所見・キー検査・代償や悪化の特徴を並べ、運動失調の初期鑑別の迷いを減らす目的で作成しています。
視覚遮断での悪化、眼球運動の破綻、回転性めまいの有無、体幹失調の強さなど、現場で拾えるサインを軸に判断します。赤旗があれば直ちに医師へエスカレーションし、 PT 単独で対応しないことが重要です。
| 分類 | 主要所見(キーワード) | キー検査 | 代償 / 悪化の特徴 | 代表疾患 |
|---|---|---|---|---|
| 小脳性 | 測定過大・分解運動・反復拮抗運動の拙劣、眼球運動異常、構音障害 | 指鼻・踵膝、急速交互運動、サッケード / 追従 | 視覚があっても改善は限定的。体幹不安定が目立つ | 脳卒中、 SCD 、 MSA 、薬物 / アルコール、中毒 |
| 感覚性(脊髄性) | 閉眼で著明化、偽性アテトーシス、方向がランダム | ロンベルグ、振動覚・位置覚、開眼 / 閉眼での指鼻・踵膝 | 視覚で改善。暗所・閉眼で悪化 | 末梢ニューロパチー、後索障害、ビタミン B12 欠乏、糖尿病 |
| 前庭性 | 回転性めまい、頭位依存、四肢の協調は概ね保たれる | 頭位 / 頭振り試験、 VOR 、 Dix–Hallpike 、 HINTS | 慢性期は代償可。不安定面や視覚依存で変動 | 前庭神経炎、 BPPV 、メニエール、脳幹小脳卒中 |
| 大脳性 | 前頭葉性の歩行失行様、方向転換困難、デュアルで悪化 | 高次運動検査、行進 / 方向転換、デュアルタスク | 外的キューで改善する場合あり(概念は未確立) | 前頭葉病変、正常圧水頭症、血管性変化 |
※ 突然のふらつき・複視・激しいめまい・構音障害などの急性発症は、まず脳卒中などの脳血管障害を除外します。
運動失調の評価アルゴリズム( PT 版 )
運動失調の評価は「病歴・赤旗 → 神経診察 → 尺度 → 機能評価 → 危険因子・環境」の順に整理すると、 PT としての役割が明確になります。初回で仮説を立て、 1 〜 2 週で再評価し、反応に応じて課題特異的練習をチューニングします。家族・介護者への教育も同時並行で進めます。
神経診察では、眼球運動(サッケード・追従)、指鼻・踵膝、急速交互運動、ロンベルグ、頭位・頭振り試験を最低限のコアに据えます。栄養(ビタミン B 群)・薬剤歴・アルコール・家族歴も見逃さないようにし、必要に応じて主治医と共有します。協調運動検査そのものの手順や観察ポイントの詳細は、協調運動機能評価(指鼻・膝打ち・踵膝試験など)のまとめも合わせて参照してください。
- 病歴・赤旗:発症様式、嘔気・複視・構音障害、薬剤・アルコール、栄養、家族歴。
- 神経診察:眼球運動、指鼻・踵膝、急速交互運動、ロンベルグ、頭位 / 頭振り。
- 尺度: SARA 、 ICARS 。
- 機能: BBS 、 TUG 、歩行速度、 9 HPT 、構音・嚥下の観察。
- 補助評価:転倒歴、補助具適合、居住環境、介助者教育。
関連記事:脊髄小脳変性症の理学療法評価
運動失調に用いる評価尺度の使い分け(目的・所要時間・一次情報)
運動失調の重症度モニタには、臨床で扱いやすい合計 40 点の SARA を主軸に、詳細を詰めたい場面で ICARS を補完します。上肢巧緻なら 9 HPT 、バランスなら BBS 、移動なら TUG と、機能スケールを並走させることで、リハビリ介入に対する反応を多面的に把握できます。
評価尺度は「誰が・どの場面で・どれだけの時間で」実施できるかが肝心です。急性期〜生活期、外来・在宅など自施設の流れの中で、運動失調評価の標準セットをチーム内で共有しておくと、記録のブレが減り、経時的な比較も容易になります。
| 尺度 | 何をみるか | 推奨場面 | 範囲 / 目安 | 一次情報 |
|---|---|---|---|---|
| SARA | 失調重症度(歩行・体幹・四肢・構音) | SCD などのフォロー、介入前後の変化 | 0–40(高いほど重い) | DOI |
| ICARS | 姿勢・歩行、四肢運動、言語、眼球運動 | 詳細評価や研究、 SARA 併用 | 0–100(高いほど重い) | PubMed |
| BBS | 静的〜動的バランス | 転倒リスク層別、在宅退院判断の一助 | 0–56(カットオフは対象で変動) | — |
| TUG | 機能的移動能力(立ち上がり〜歩行) | 迅速スクリーニング、介入効果の把握 | 秒(目安 13.5 s 前後※) | — |
| 9 HPT | 手指巧緻性(上肢) | 上肢協調の変化検出、 SARA 補完 | 秒(左右別に記録) | — |
※ 目安値は対象や文献で変動します(自施設の基準で運用基準を明確化)。
運動失調リハビリの戦略:協調訓練とバランス再学習
運動失調リハビリのコアは「誤ったタイミングと力配分の再学習」です。課題特異的・反復・段階的負荷で運動協調を再学習していきます。到達・把持、指先操作、体幹・骨盤コントロール、ステップや方向転換、歩行のサブタスクに分解し、患者さんごとの主要な制限因子に合わせて組み立てます。
バランス訓練では、多感覚リウェイティング(固い床 → フォーム → 不安定面)、支持基底面の変化、デュアルタスクなどを段階的に導入します。前庭性失調には注視安定・頭部運動、感覚性失調には視覚代償や下肢装具・杖などの補装具を組み合わせ、全体に疲労管理・栄養・転倒予防教育を並走させることが大切です。
運動失調リハビリの OK / NG 比較表(現場の判断の目安)
「何を増やし、何を減らすか」を一目で共有できるよう OK / NG を対比しました。安全性と学習効率の両立がねらいです。危険兆候(症状急変、強いめまい・嘔気、神経徴候の新規出現)があれば即中止し、再評価と主治医への報告を優先します。
補助具・環境調整は代償の固定化を避けつつ、転倒予防とのバランスで最適化します。フィードバックは外部フォーカスを基本に、必要に応じて内的フォーカスを補助的に用いることで、力みや同時収縮の固定化を防ぎます。
| OK(推奨) | NG / 慎重(推奨しない・状況次第) |
|---|---|
| 課題特異的な協調訓練(到達・把持・歩行サブタスク) | 漫然とした重錘負荷の常用(動作をさらに粗雑化) |
| 外部フォーカス指示・視覚 / 触覚フィードバック | 内的フォーカスのみで反復(力み・同時収縮の固定化) |
| 体幹安定化+多感覚リウェイティング(床条件の段階付け) | 危険な不安定面での過負荷練習(転倒リスク増) |
| 前庭リハ(前庭性には注視安定・頭部運動) | めまい急性期の強行負荷(悪化リスク) |
| 補助具・環境調整(杖・手すり・滑り止め等) | 補助具の不適合放置(代償の固定化・転倒) |
まとめ
運動失調は原因が多彩でも、評価は「鑑別 → 評価スケール → 機能評価 → 環境」の順で整理できます。 SARA / ICARS による失調重症度の見える化と、 BBS ・ TUG ・ 9 HPT などの機能評価を組み合わせることで、運動失調リハビリの進め方を論理的に説明しやすくなります。
赤旗(急性発症など)を逃さず、栄養・疲労・転倒予防・補助具適合まで含めた包括介入を計画しましょう。 1 〜 2 週ごとに再評価し、運動失調の経過とリハビリ効果をチームで共有していくことで、本人・家族の納得感も高まりやすくなります。
おわりに
実地では「鑑別 → 評価スケール → 機能訓練 → 環境調整 → 再評価」というリズムで、運動失調のリハビリを回していくことが大切です。患者さんごとに失調のタイプと生活背景が異なるため、検査結果をチームで共有しながら、転倒リスクや疲労度に応じて負荷や課題設定を微調整していきましょう。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に、見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック( A4 ・ 5 分)と職場評価シート( A4 )を無料公開しています。印刷してそのまま使えます。ダウンロードページを見る。
参考文献
- Schmitz-Hübsch T, et al. Scale for the Assessment and Rating of Ataxia ( SARA ). Neurology. 2006;66(11):1717-1720. DOI
- Trouillas P, et al. International Cooperative Ataxia Rating Scale ( ICARS ). J Neurol Sci. 1997;145(2):205-211. PubMed
- Chien HF, et al. Rehabilitation in patients with cerebellar ataxias. Brain Circ. 2022;8(4):218-227. PMC
- Milne SC, et al. Rehabilitation for ataxia: systematic review. Neurorehabil Neural Repair. 2017;31(8):735-742. DOI
- Radmard S, et al. Evaluation of cerebellar ataxic patients. Iran J Neurol. 2022. PMC
- Waterston J. Distinguishing sensory from cerebellar ataxia. Pract Neurol. 2014;14(4):242-251. Link
- Pedroso JL, et al. Acute cerebellar ataxia: review. Arq Neuropsiquiatr. 2019;77(1):60-69. PDF
関連記事:
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下