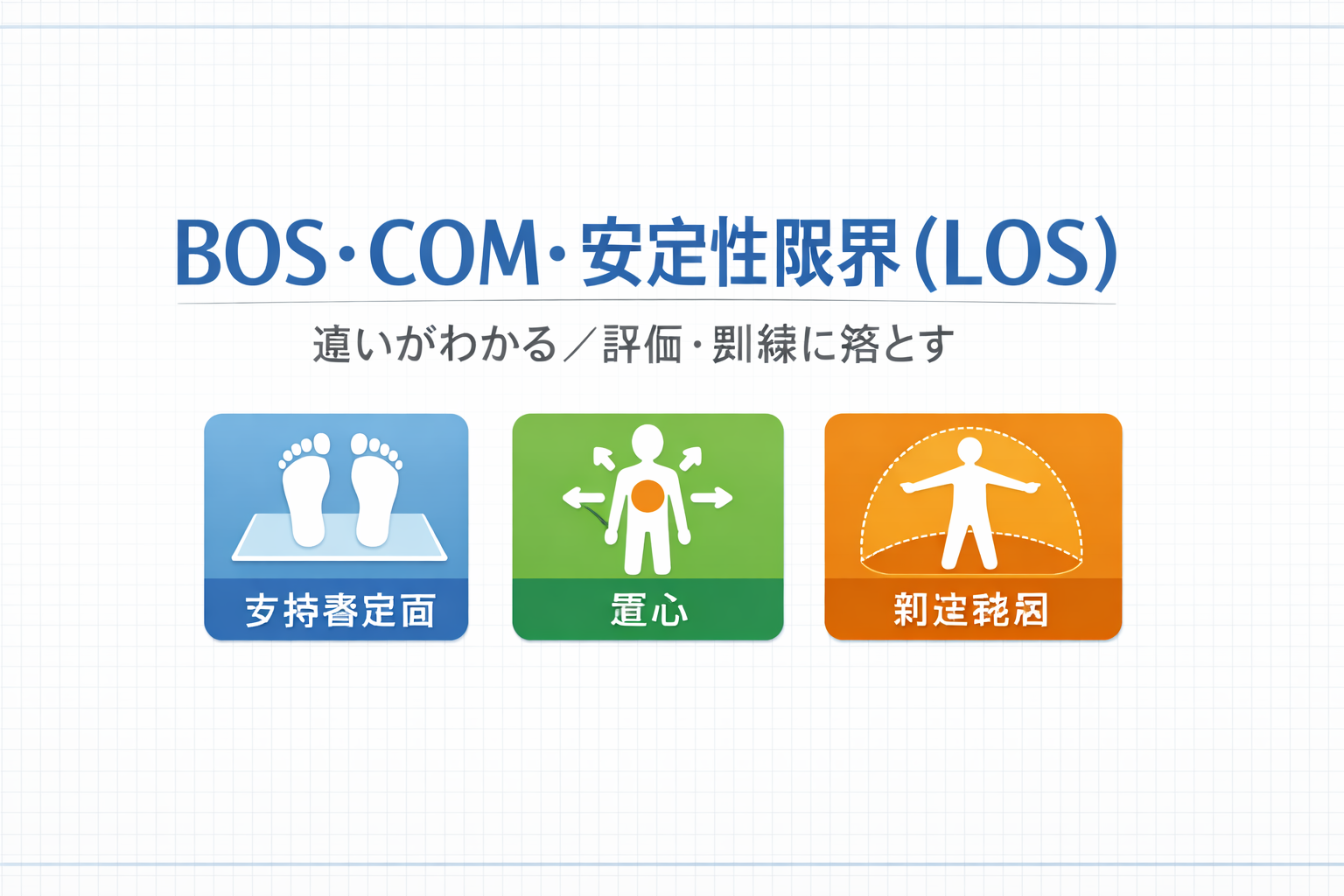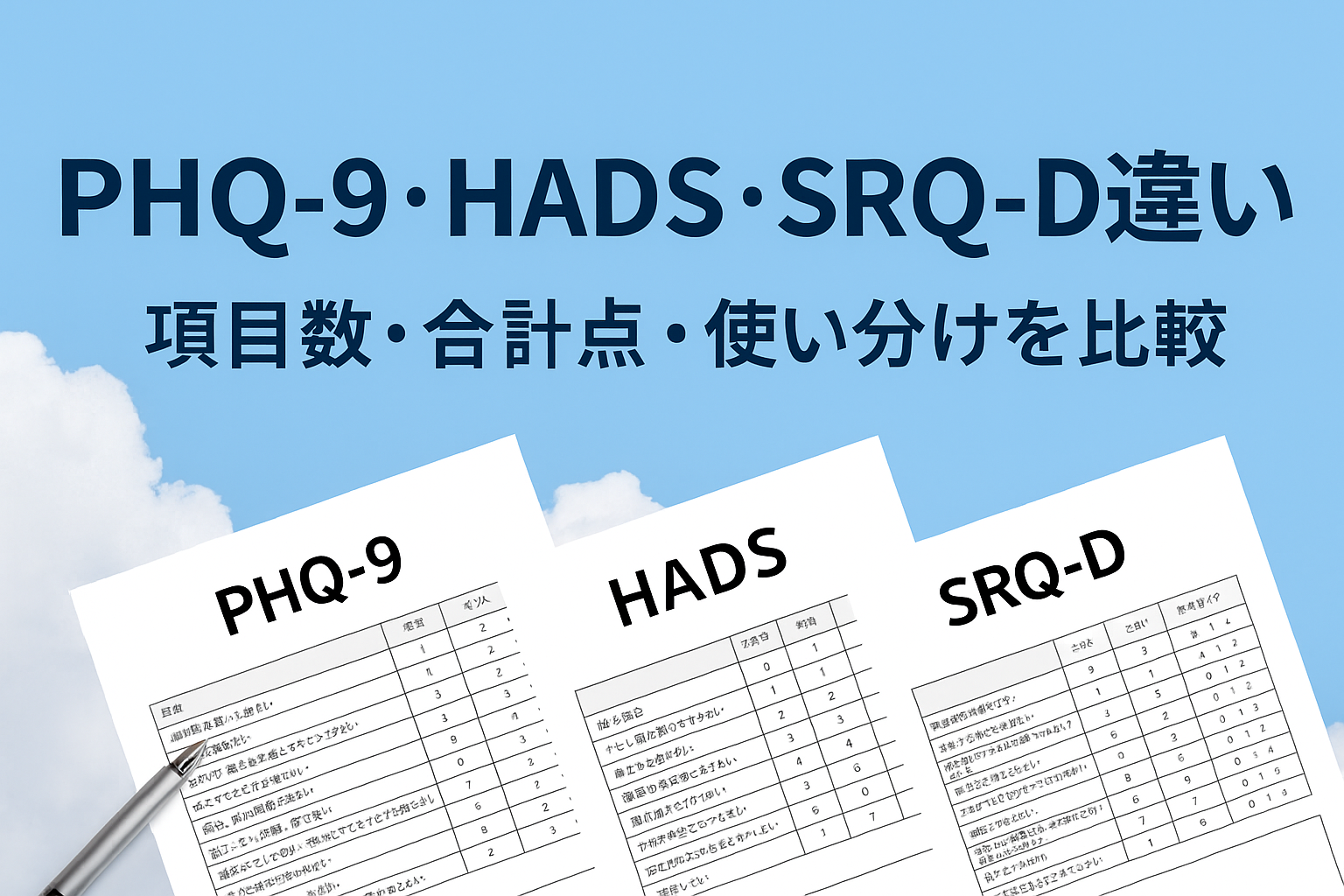BOS・COM・安定性限界( LOS )の違い(1 分でわかる)
BOS(支持基底面)は「身体を支える面(足底で作る範囲)」、COM(重心)は「身体の重さの中心(その投影位置)」、安定性限界( limits of stability:LOS)は「転ばずに COM を BOS 内でどこまで動かせるか」の到達範囲です。
臨床の “バランス不良” は、① COM を狙いどおり動かせない(スピード/方向/協調)、② 安定性限界が狭い(疼痛・拘縮・不良姿勢・恐怖などで “行ける範囲” が小さい)、③ 感覚統合の偏り(視覚/体性感覚/前庭の重みづけ不適切)のどれか(または複合)として整理できます。本記事では、この 3 つを「評価の選び方」と「訓練パラメータ」に落とします。
安定性限界( LOS )をどう測る?(機器あり / なし)
安定性限界は「前後左右にどこまで行けるか」だけでなく、どれだけ速く・まっすぐ・最初の一発で到達できるかまで含めて評価すると、介入の焦点が明確になります。機器(重心移動を可視化するシステム)がある場合は LOS テストが代表で、反応時間・移動速度・到達の質を 1 セットで把握できます。
LOS 指標(RT / MVL / EPE / MXE / DCL)の “臨床語” 翻訳
LOS テストでよく使われる 5 指標は、読み替えると現場での “詰まり” が見えます(機器がなくても観察観点として転用できます)。
| 指標 | ざっくり意味 | 臨床での読み替え | 介入の当たり |
|---|---|---|---|
| RT | 合図 → 動き出しまで | 「切り替えが遅い」「怖くて出だしが固い」 | 予告 → 合図 → 小さく開始、成功体験の反復 |
| MVL | 目標へ向かう平均速度 | 「ゆっくりしか動けない」「加速が出ない」 | 距離を短くして速度課題、反復で “速さの許可” |
| EPE | 最初の一発でどこまで届くか | 「一回目が浅い=自信がない/探索が多い」 | 到達目標を段階化、最初の一発を “当てる” 練習 |
| MXE | その試行での最大到達 | 「最終的には行けるが、時間がかかる」 | 反復で範囲拡大、保持を短くして探索コストを減らす |
| DCL | 目標方向にどれだけまっすぐ行けたか | 「蛇行する」「余計な揺れが多い」 | 支持面/足幅で難度調整、視覚フィードバックの併用 |
機器がない場合の “代替プロトコル”(前後左右の到達 → 保持)
機器がない現場でも、安定性限界は “再現性ある型” に落とせます。ポイントは 到達(どこまで)と保持(止められるか)をセットで見ることです。
- 開始条件を固定(足幅・足先角度・視線・支持物なし/ありを決め、毎回同じにする)
- 前・後・右・左の順に、COM を「ゆっくり移動」→「 2 秒止める」
- 記録は 3 点セット(到達の深さ / ふらつき方向 / 代償:股関節戦略・足趾把持・体幹回旋など)
- 難度調整は 1 つだけ変える(足幅、支持面、視覚、タスクのいずれか 1 つ)
評価での使い方(どの尺度と結ぶ?)
BOS・COM・安定性限界を “評価として回す” には、どの要因を見たいかで尺度を選び、訓練パラメータ(足幅・支持面・視覚・外乱・タスク特異性)に接続します。
※この表は横にスクロールできます。
| パラメータ | 易 → 難 | 狙い | 関連評価 | 安全管理 |
|---|---|---|---|---|
| BOS(足幅・支持様式) | 広 → 狭/タンデム/片脚 | 安定性限界の操作・方略切替 | mCTSIB、Mini-BESTest | 介助者配置・転倒方向の予測 |
| 支持面の硬さ | 硬 → 柔(フォーム等) | 体性感覚の信頼性低下への適応 | mCTSIB | 足関節内外反・膝折れの保護 |
| 視覚情報 | 開眼 → 視覚制限 → 閉眼 | リウェイティングの促通 | mCTSIB | 閉眼は常時介助・周囲クリアランス確保 |
| 外乱(大きさ / 方向) | 小 → 中 → 大/単方向 → 多方向 | 反応的バランスの強化 | Mini-BESTest | 後方介助・ハーネス/手すりの段階づけ |
| タスク特異性 | 静的 → 動的 → 歩行中 | 目標 ADL への汎化 | FGA、BBS・TUG | 床面・障害物・転回スペース確保 |
| ステップ方略 | 規則的 → 方向切替 → 二重課題 | 「行き過ぎた」後の回収能力 | FSST | 転倒方向の想定、介助位置の固定 |
処方の組み立て(順序とチェック)
おすすめの順序は、土台(感覚統合)→ 安定性限界( LOS )の再学習 → 反応 / 予測の統合です。最初に「どの感覚に頼りすぎ、どの感覚が弱いか」を押さえ、BOS・支持面・視覚の組み合わせで負荷を 1 つずつ調整します。
次に、安定性限界を「到達」だけで終わらせず、到達 → 保持 → 戻すまでを 1 セットとして反復します。最後に外乱や歩行課題へ統合し、方向転換・速度変化・頭部運動など “崩れやすい場面” をタスク特異的に再現します。
チェックリスト(観察 → 数値 → 次の一手)
- どの方向が狭いか(前方だけ / 後方だけ / 左右差)
- 狭い原因がどれか(疼痛・可動域・恐怖・感覚依存・筋出力)
- 到達の質(最初の一発が浅い / 蛇行する / 止められない)
- パラメータで 1 つだけ変える(足幅 or 支持面 or 視覚 or 外乱 or タスク)
現場の詰まりどころ(よくある失敗と修正)
ここは “ありがちな NG” を先に潰すと、介入が速くなります。チーム内の言葉をそろえる目的で、OK/NG 早見にしました。
※この表は横にスクロールできます。
| 詰まりどころ | NG(起こりがち) | OK(修正の方向性) | 記録の一言 |
|---|---|---|---|
| BOS を “広げるだけ” で終わる | 足幅を広げて安定した時点で満足し、到達範囲が伸びない | 「前後左右の到達 → 2 秒保持 → 戻す」をセット化して LOS を拡げる | 「足幅は維持、前方到達の停止が改善」 |
| 静的評価だけで動的を語る | 立位保持が良い=安心、として方向転換や二重課題を見落とす | 歩行・転回の “崩れる場面” を評価(FGA / Mini-BESTest など) | 「静的は安定、転回で左へ崩れる」 |
| 感覚統合を後回しにする | 足幅と重心位置ばかり調整し、視覚依存や足底感覚低下を見落とす | 視覚・支持面を 1 つずつ操作し、条件ごとの安定性を確認して処方へ | 「閉眼で後方へ、フォームで右へ」 |
| 安全管理が曖昧なまま外乱へ進む | 介助位置・転倒方向・環境整理が曖昧で、課題が “怖さ” で止まる | 介助者位置を固定し、難度は 1 つだけ上げる(外乱の方向→大きさ等) | 「後方介助で実施、外乱は前→左右へ」 |
なお、こうした “詰まり” を減らすには、見学・教育・振り返りの土台も大事です。配属先の評価表や面談準備のチェックが必要なときは、面談準備チェックと職場評価シート(無料)を先に用意しておくと、学びの優先順位が整理しやすくなります。
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
BOS を広げれば、常に安全ですか?
静的には安定しやすい一方で、動的課題では歩幅や方向転換の自由度を落とし、代償(股関節戦略の固定、すり足、速度低下)を増やすことがあります。目標タスクに合わせて「どこまで広げるか」を決め、安定性限界( LOS )の到達と停止が作れたら、段階的に狭めていくほうが実用的です。
閉眼訓練はいつから導入すべきですか?
まずは開眼で姿勢戦略を学び、体性感覚の信頼性を確認した後に、視覚制限 → 閉眼へ段階づけます。閉眼は常時介助と環境管理が前提です。「どの条件なら崩れるか」を先に押さえると安全に処方できます。
重心( COM )を患者さんにどう説明すればよいですか?
解剖学的な定義より、「おへそ付近の重りを前後左右にゆっくり動かすイメージ」で伝えると通じやすいです。鏡や目印を使い、「今の COM が足のどの位置にあるか」を一緒に確認すると共有が速くなります。
安定性限界が狭い原因は、どう見分けますか?
まず “方向” を決めます(前方だけ狭い、後方だけ怖い、左右差が強い等)。次に、疼痛・可動域・恐怖・感覚依存・筋出力のどれが主因かを、パラメータを 1 つだけ変えて反応で見ます。例:足幅を変えて改善するなら BOS 要因、支持面や視覚で大きく変わるなら感覚要因の比重が上がります。
次の一手(関連:全体像 → 兄弟記事)
参考文献
- Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor Control: Translating Research into Clinical Practice. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2011.(出版社)
- Horak FB. Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to prevent falls? Age Ageing. 2006;35(Suppl 2):ii7–ii11. doi:10.1093/ageing/afl077(PubMed)
- Franchignoni F, Horak F, Godi M, Nardone A, Giordano A. Using psychometric techniques to improve the Balance Evaluation Systems Test: the mini-BESTest. J Rehabil Med. 2010;42(4):323–331. doi:10.2340/16501977-0537(PubMed)
- Wrisley DM, Marchetti GF, Kuharsky DK, Whitney SL. Reliability, internal consistency, and validity of data obtained with the Functional Gait Assessment. Phys Ther. 2004;84(10):906–918.(PubMed)
- Clark S, Rose DJ, Fujimoto K. Generalizability of the limits of stability test in older adults. Arch Phys Med Rehabil. 1997;78(10):1078–1084. doi:10.1016/S0003-9993(97)90027-5(PubMed)
- Juras G, Słomka K, Fredyk A, Sobota G, Bacik B. Evaluation of the Limits of Stability (LOS) Balance Test. J Hum Kinet. 2008;19:39–52. doi:10.2478/v10078-008-0003-0(DOI)
- Lininger MR, Leahy TE. Test-retest reliability of the Limits of Stability test performed by young adults using NeuroCom® VSR Sport. Int J Sports Phys Ther. 2018;13(6):1000–1011. PMID:30276012(PubMed)
- 大高恵莉ほか.日本語版 Mini-Balance Evaluation Systems Test(Mini-BESTest)の作成と妥当性の検討.リハビリテーション医学. 2014;51(10):673–681.(J-STAGE)
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下