 評価
評価 Trendelenburg 歩行|原因仮説と確認テスト(骨盤下制・体幹側屈)
Trendelenburg(骨盤下制・体幹側屈)は「中殿筋だけ」と決め打ちすると外しやすい所見。疼痛回避/体幹戦略/脚長差などを含めて 3 本柱で絞り、最小の確認テストと 1 行記録で運用を固定します。
 評価
評価 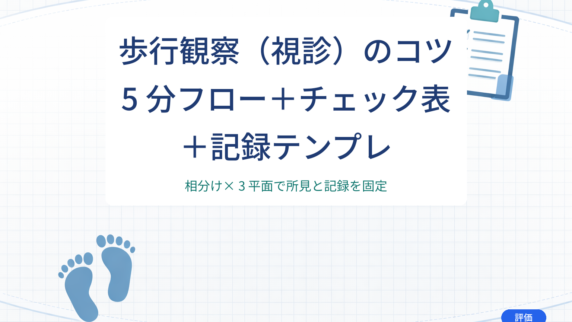 評価
評価 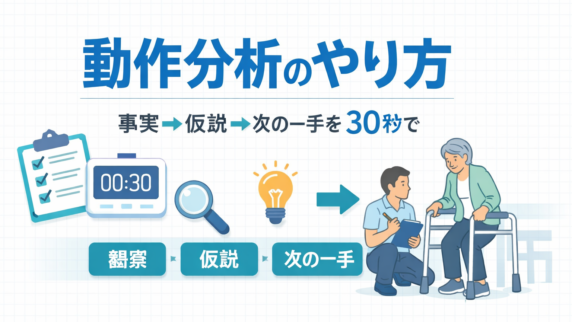 評価
評価 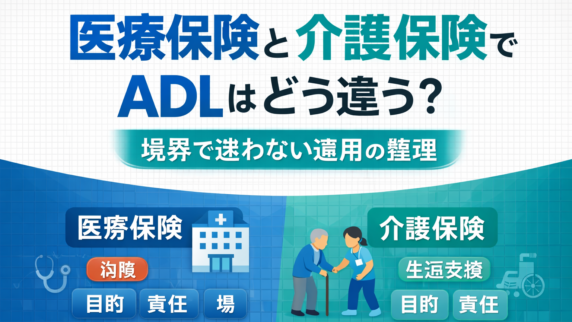 評価
評価  評価
評価  評価
評価 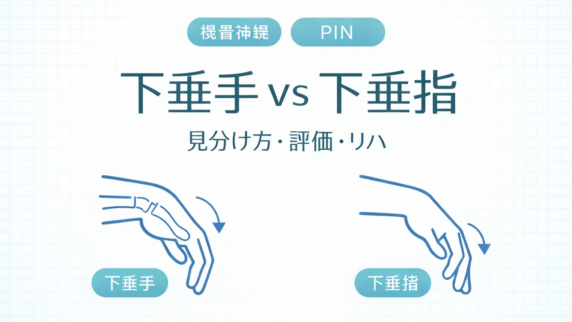 評価
評価  評価
評価  評価
評価  評価
評価