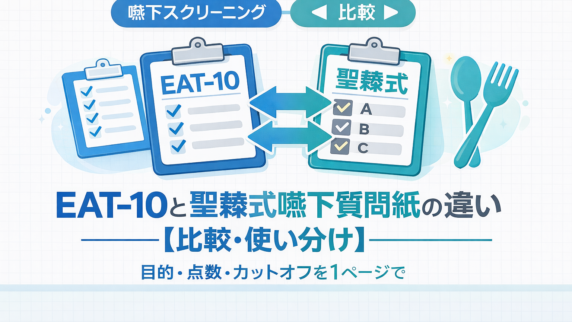 栄養・嚥下
栄養・嚥下 EAT-10 と 聖隷式嚥下質問紙の違い【比較・使い分け】
EAT-10 と 聖隷式嚥下質問紙を「拾い上げ」と「経時変化」で比較。判定固定のコツ、陽性後フロー、現場で迷わない使い分けを整理します。
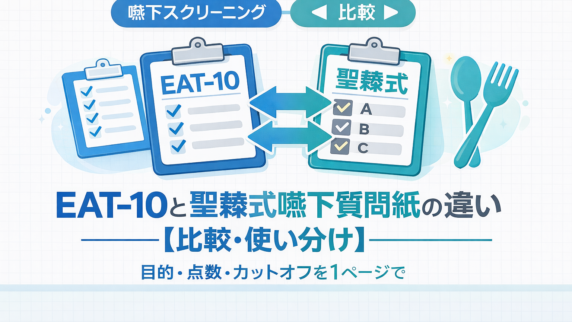 栄養・嚥下
栄養・嚥下  栄養・嚥下
栄養・嚥下 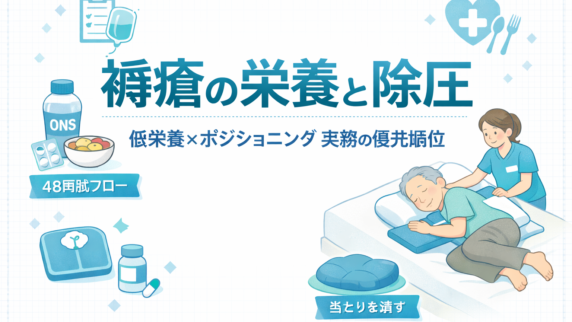 栄養・嚥下
栄養・嚥下 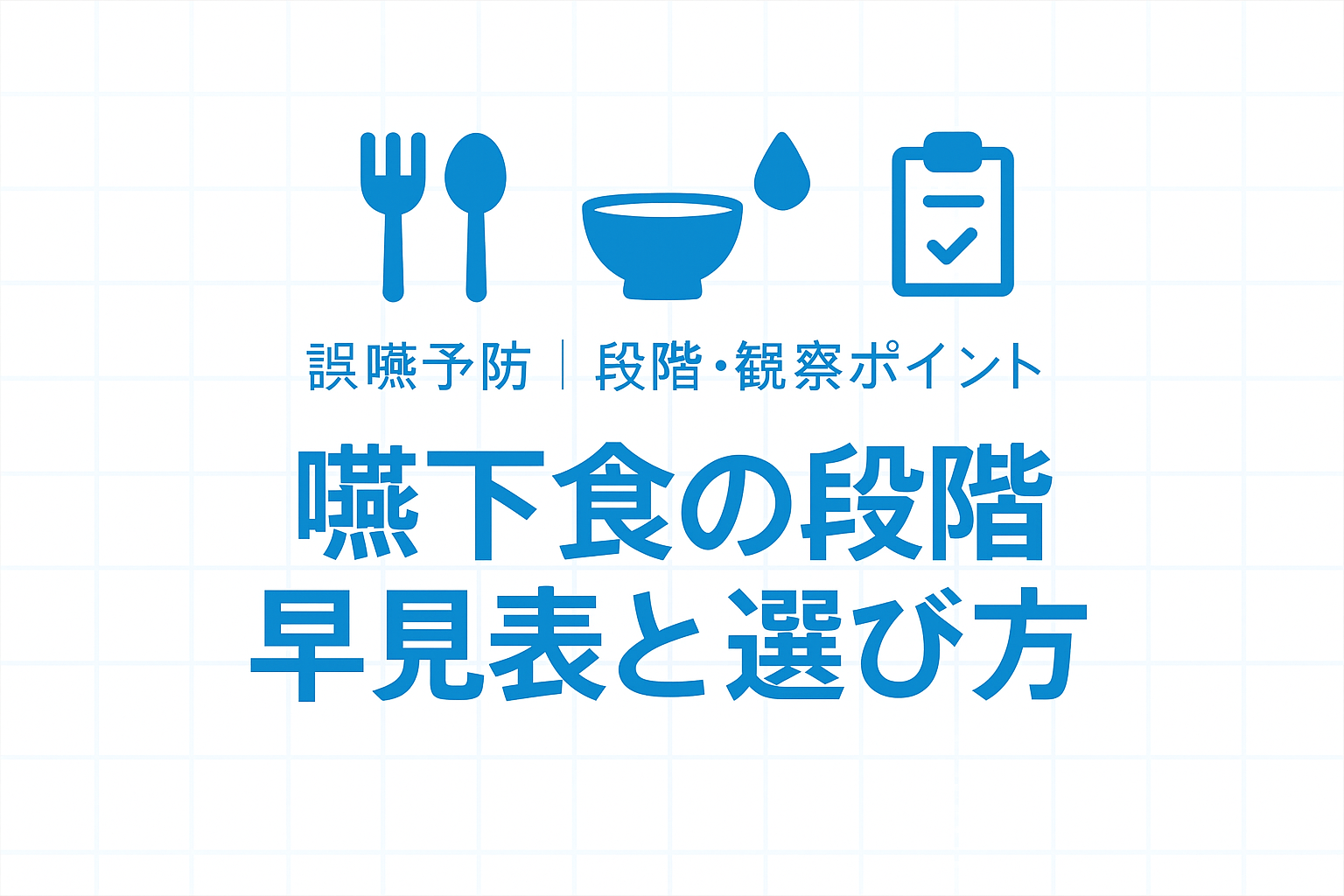 栄養・嚥下
栄養・嚥下 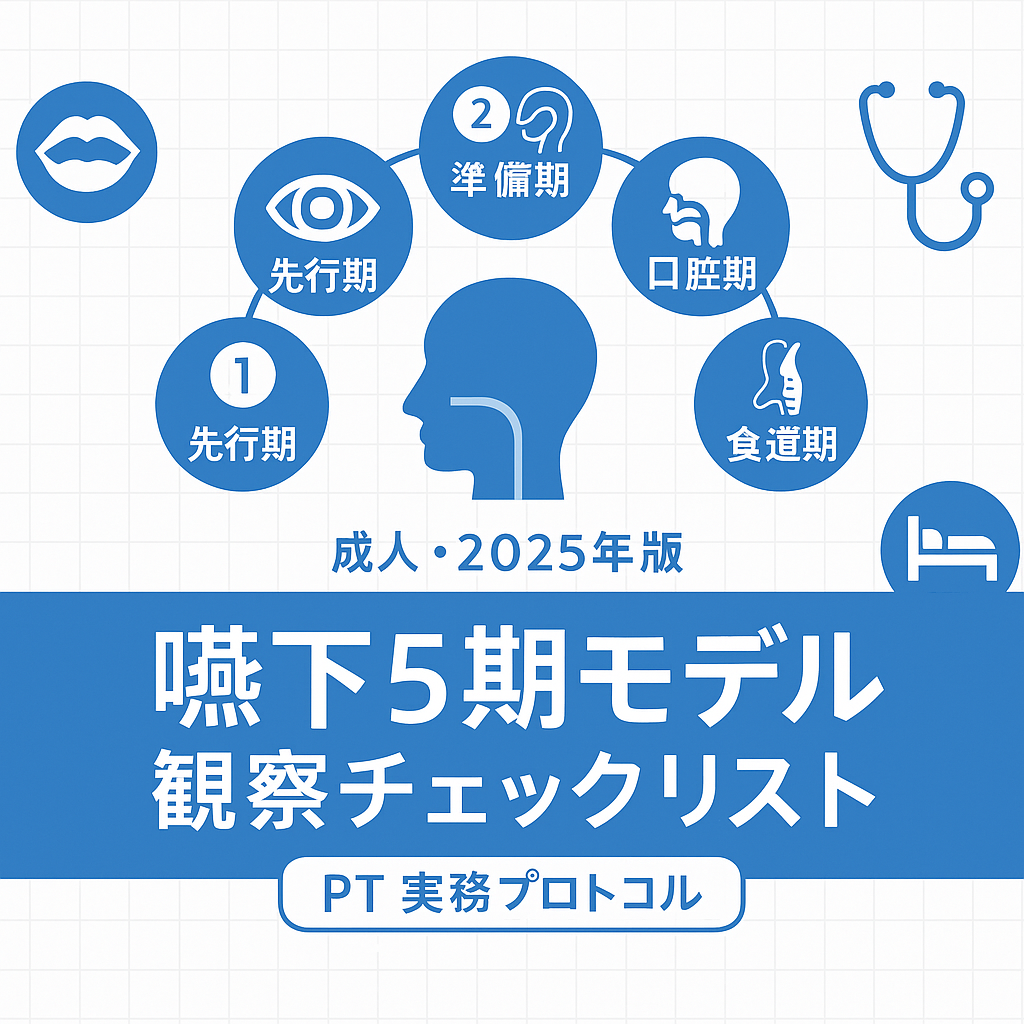 栄養・嚥下
栄養・嚥下  栄養・嚥下
栄養・嚥下  栄養・嚥下
栄養・嚥下  栄養・嚥下
栄養・嚥下 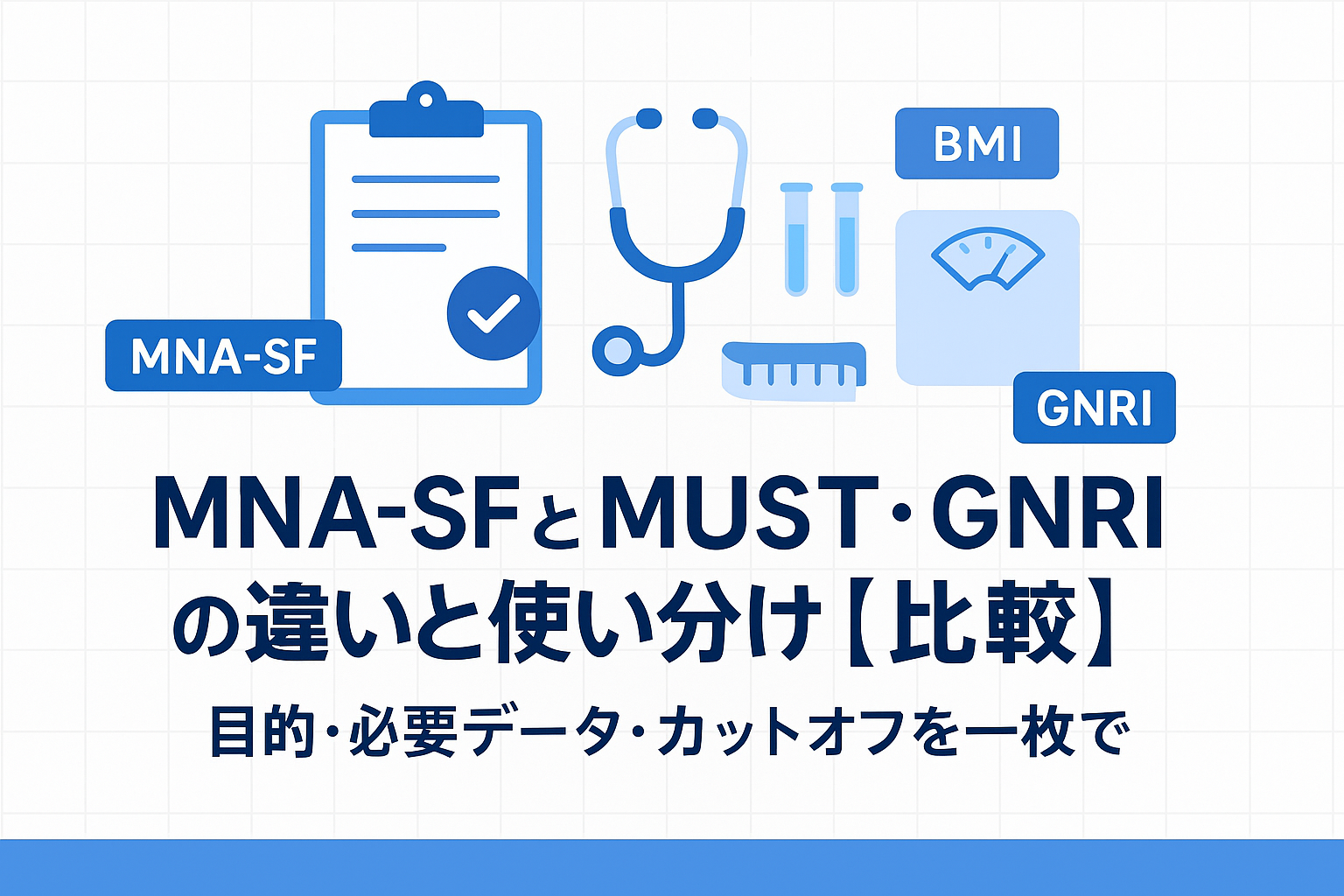 栄養・嚥下
栄養・嚥下 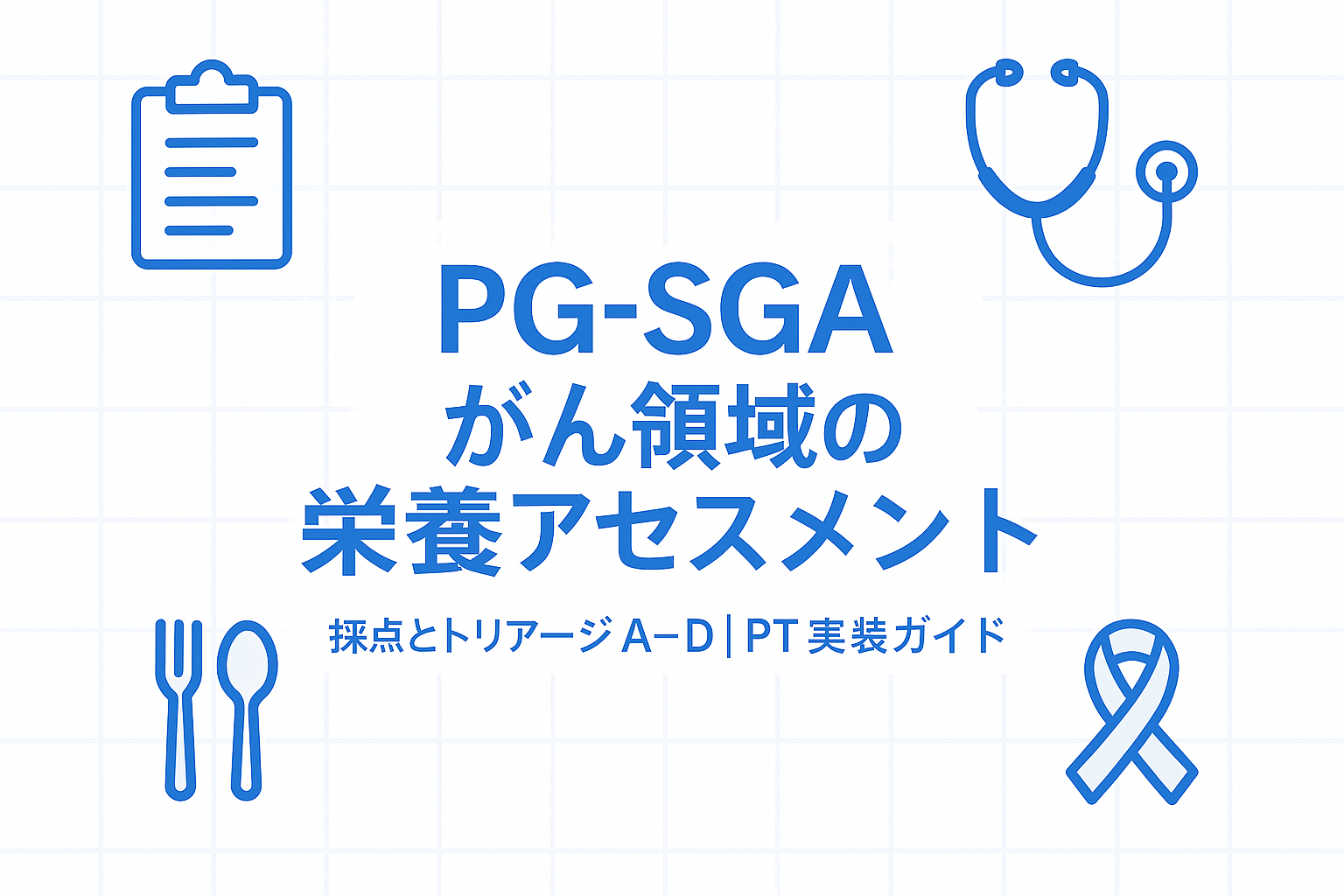 栄養・嚥下
栄養・嚥下