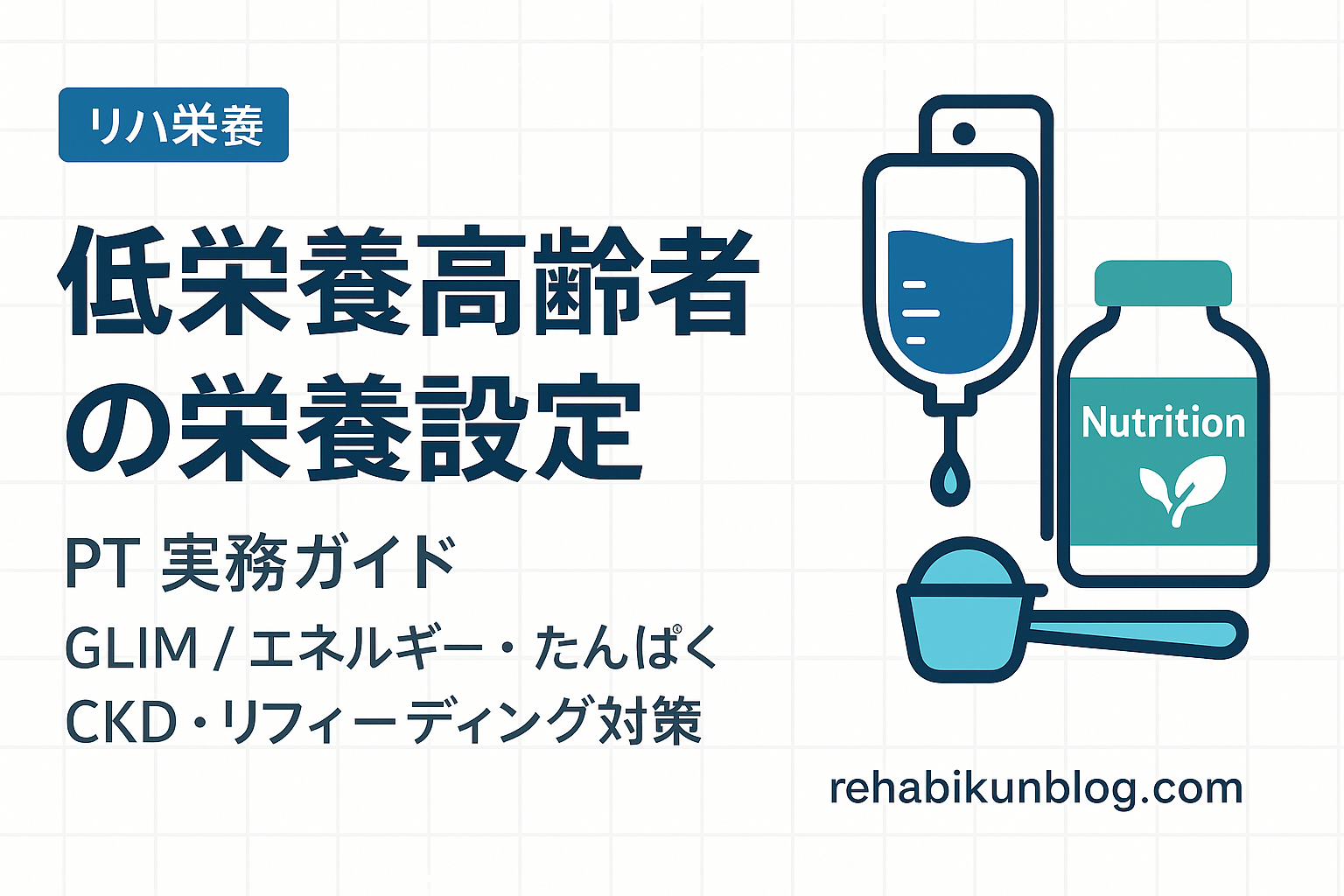結論:PT は「栄養 × 機能」を同時に設計する
低栄養は ADL 低下や入院長期化に直結します。PT は GLIM の前提(表現型+病因の少なくとも各 1 つ)をチームで共有し、体重・筋量( proxy )・筋力・摂取量・炎症を最初の 1 週間で押さえます。以降は週 1 回のミニ再評価と月 1 回の KPI 再設定で、食事・ ONS ・運動を “同じ表” で回すのが実装しやすい型です。
栄養の「設定」は エネルギー( kcal )× たんぱく( g/kg/日 )が軸です。食塩・水分・微量栄養素は原疾患の指示が最優先で、未指示なら公的基準に準拠しつつ、摂取量低下を招く過度な制限は避けます。
実務フロー(初回 1 週間)
Day 0–2: GLIM の項目収集(体重変化・ BMI ・筋量 proxy・摂取量・炎症)、 GNRI 、食事聞き取り、嚥下・咀嚼、併存症を確認。機能は握力・ 5 回椅子立ち上がり・歩行速度でベースライン化します。
Day 3–7: 目標設定(体重・歩行・ ADL )、エネルギー・たんぱくを暫定処方。食事/ ONS /食形態・間食・運動(レジスタンス+歩行)を組み合わせ、摂取実績と体重で調整します。
エネルギーとたんぱくの設定
エネルギー:原則は間接熱量測定が最適です。機器が無ければ推定式で BEE を算出し、TEE = BEE × 活動係数 × ストレス係数で見積もります。体重増加を狙う場合は、エネルギー蓄積量(成人で概ね 7,500 kcal/kg 目安)を参考に、現場では 1 日あたり 200 ~ 750 kcal程度の上乗せから開始し、浮腫・摂取実績・体重推移で微調整します。
たんぱく:高齢者は 1.0 ~ 1.2 g/kg/日、疾患時は 1.2 ~ 1.5 g/kg/日、重症や著明な低栄養では最大 2.0 g/kg/日までを文献範囲で検討します。エネルギー不足があると筋同化が進みにくいため、まずエネルギー不足を是正しつつ、運動療法(特にレジスタンス)と併用します。
参考の根拠(要点)
- 間接熱量測定がゴールドスタンダード。推定式は過小・過大推定のリスクがあります。
- ONS は少なくとも 400 kcal/日・たんぱく 30 g/日を目安に継続( ≥ 1 か月)し、体重・食欲・機能で再評価します。
- 体重増加のエネルギーコストは成人で概ね 7,500 kcal/kg が目安ですが、高齢者では幅が大きい報告があるため、経過で補正します。
CKD 併存時の注意(非透析)
CKD では一律のたんぱく制限は推奨されず、重症度・サルコペニア・ PEW の有無をふまえ個別化します。KDOQI 2020 では、代謝安定時の CKD G3–G5(非透析)で 0.6–0.8 g/kg/日が選択肢ですが、筋量・機能低下がある場合は優先課題が “栄養不良の是正”になりやすい点に注意が必要です。腎専門医・管理栄養士と協働し、十分なエネルギー確保(例: 25–35 kcal/kg/日 目安)を前提に調整します。
食塩・カリウム・リンは腎指示に従います。PT はむくみ・起立性低血圧・運動時の不整脈リスクなど所見の変化を日々共有し、運動処方を微調整します。
リフィーディング症候群の回避
長期低栄養の方は、開始直後の急速な増量で低 P /低 K /低 Mg 、心不整脈、浮腫などのリスクがあります。初期は 10–20 kcal/kg/日程度から開始し、 1–2 日ごとに段階的に増量、電解質を連日チェックし、ビタミン(特にチアミン)補充を検討します。
高リスク(著明な体重減少、長期の摂取不良、電解質低値など)では NST と連携し、運動負荷の上げ幅も緩やかにします。
ONS・経腸栄養の使い方(要点)
ONS: 400 kcal/日以上でたんぱく 30 g/日相当を 1 か月以上継続し、月 1 回は体重・食欲・機能を再評価します。嚥下障害にはテクスチャ調整品を選択し、嗜好に合わせて味・形態をローテーションします。
経腸:経口が見込み薄で 3 日超不可能、または 1 週間で必要量の 1/2 未満が続く場合に適応を検討します。予後とリスク・ベネフィットを個別に見極めます。
KPI(毎月)と目安
| 領域 | 指標 | 目安・カットオフ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 栄養 | 体重・体重変化 | 月 +0.5 ~ +2.0 kg | むくみ・脱水を併記 |
| 栄養 | GNRI | > 98 低リスク/ 92–98 軽度/ 82–<92 中等度/ < 82 高度 | Alb と体重から算出 |
| 機能 | 握力 | AWGS 2019:男 < 28 kg、女 < 18 kg で低下 | ハンドグリップ |
| 機能 | 5 回立ち上がり | ≥ 12 秒で低下目安 | SPPB の一部 |
| 持久 | 6 MWT | 前月比 +30 m を目安 | コース・声かけ・中止基準の固定 |
| ADL | BI / FIM | 月 +10 点を目安 | 施設運用に合わせて統一 |
現場の詰まりどころ:よくある NG と OK(落とし穴)
| NG | なぜ問題? | OK | PT の具体策 |
|---|---|---|---|
| 極端な減塩で食下がり | 総摂取エネルギーが落ちて逆効果 | 段階的減塩+うま味活用 | 味覚確認・食札メモを病棟で共有 |
| たんぱくだけ先に増やす | エネルギー不足だと筋同化しにくい | まずエネルギー確保 → たんぱく増量 | 間食・ ONS の “時間割” を一緒に設計 |
| CKD に一律制限 | サルコペニア進行のリスク | 個別化(腎 × 栄養 × 機能で判断) | 腎・栄養と週次カンファを “定例化” |
| 初日から全量投与 | リフィーディング症候群の危険 | 10–20 kcal/kg/日で開始し漸増 | 電解質・バイタルを日次で追う |
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に。見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック( A4 ・ 5 分)と職場評価シート( A4 )を無料公開しています。印刷してそのまま使えます。ダウンロードページを見る。
次の一手(関連)
参考文献
- Cederholm T, et al. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9. doi: 10.1016/j.clnu.2018.08.002. PubMed / DOI / PDF
- Volkert D, et al. Clin Nutr. 2022;41(4):958-989. doi: 10.1016/j.clnu.2022.01.024. PubMed / DOI / PDF
- 日本リハビリテーション栄養学会. 「攻めの栄養療法」提言( 2016 ). J-STAGE
- Ikizler TA, et al. Am J Kidney Dis. 2020;76(3 Suppl 1):S1-S107. doi: 10.1053/j.ajkd.2020.05.006. PubMed / DOI
- NICE. Nutrition support for adults (CG32). PDF
- 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準( 2025 年版 ). PDF
- Mifflin MD, et al. Am J Clin Nutr. 1990;51:241-247. PubMed
- Bouillanne O, et al. Am J Clin Nutr. 2005;82(4):777-783. doi: 10.1093/ajcn/82.4.777. PubMed / DOI
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下