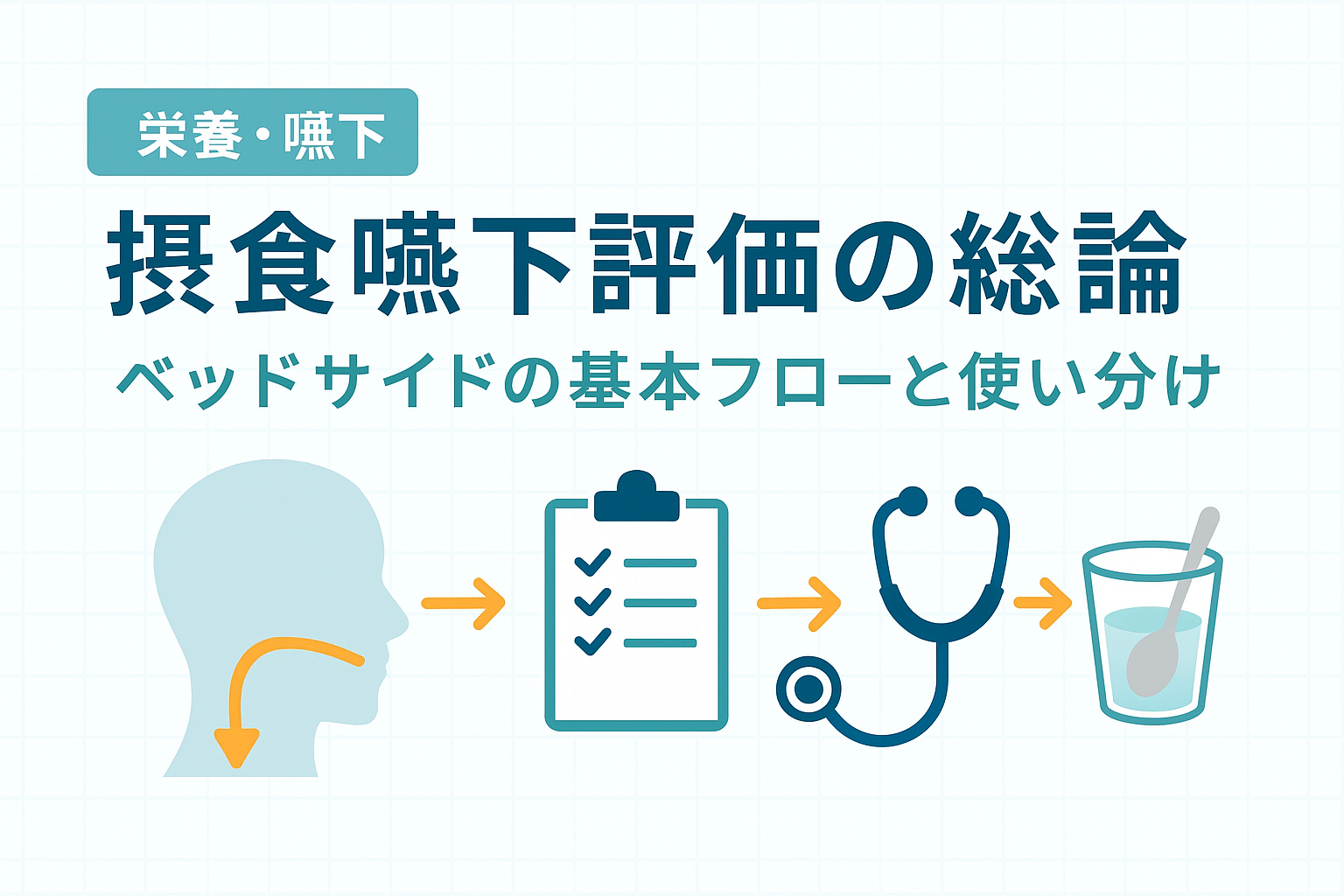摂食嚥下評価(総論):ベッドサイドの基本フローと使い分け
結論:ベッドサイド嚥下評価は「安全確認 → 観察 → RSST/ MWST /フードテスト/咳テスト/頚部聴診( CA )→ 申し送り」で 5 分で仮方針まで決めます。
本記事は「嚥下スクリーニングで迷わない選び分け」と「記録の型」を、総論としてコンパクトに整理します。
対象:病棟・在宅の初期評価で「どの検査を、どの順番で、どこまでやるか」に迷いやすい PT ・ OT ・ ST /看護師の方向けです( VF / VE の適応判断は最終的に医師・ ST と連携して決定します)。
注意:強いむせ、吸気性喘鳴、 SpO₂ の顕著な低下などが出現した場合は評価を中止し、施設の指針に従って対応してください。
嚥下評価を“手順で学ぶ”| ST キャリアガイド( #flow )
この記事は「総論(全体像)」です。評価の流れ・観察の視点・主要ツールの使い分けを整理します。
関連:栄養・嚥下の全体像(スクリーニング → 介入 → 安全管理)は 栄養・嚥下ハブ にまとめています。
評価の基本フロー( 5 ステップ )
- 情報収集:既往・服薬・嚥下歴・栄養状態・現行の食形態/一口量・補助具。
- 体位づくり・安全確認:座位または側臥位の選択、呼吸状態・バイタル・意識/認知のチェック。
- 観察・触診:口唇・舌の可動、嚥下反射兆候、声質(湿性嗄声)、咳/むせ、喉頭の挙上感。
- ベッドサイド検査(嚥下スクリーニング):目的に応じて RSST / MWST /フードテスト/咳テスト/頚部聴診法( CA )を選択。
- 総合判定・記録・共有:所見+条件(体位・一口量・介助量)を記録し、多職種で共有。
現場の詰まりどころ(迷いを減らす 4 つの型)
| 詰まりどころ | なぜ起きる? | 解決(型) |
|---|---|---|
| むせがない=安全? | 不顕性誤嚥や咳反射低下で「むせ」が出ないことがある | むせの有無だけで決めない。声・呼吸・痰・ SpO₂ 変化をセットで判定する |
| 検査を増やしすぎる | 「不安だから追加」で負荷が上がり、所見が混ざる | 目的を 1 つに絞って選ぶ(例:反射= RSST 、液体= MWST )→異常なら段階を戻す |
| 条件が揃っていない | 体位・一口量・介助量が毎回違い、比較できない | 体位と一口量( mL )を記録し、再評価条件を固定する |
| 申し送りが抽象的 | 「むせあり/なし」だけだと、次の職種が再現できない | 条件+所見+次アクション(体位・形態・精査)を最小セットで伝える |
観察と触診のポイント(チェックリスト)
| 領域 | 見る/触るポイント | 注意( NG 例 ) |
|---|---|---|
| 姿勢・体位 | 骨盤中間位、体幹正中、頸部は中間〜軽屈曲 | 過伸展で喉頭が低く見える “見かけ” の変化 |
| 口腔機能 | 口唇閉鎖、舌先挙上・側方運動、頬の保持 | 乾燥・義歯不適合・食渣残留(口腔ケア不足) |
| 嚥下兆候 | 嚥下誘発・喉頭挙上の滑らかさ、嚥下後の声質 | 湿性嗄声/再呼吸不良/嚥下の遷延 |
| 呼吸 | 呼吸数・ SpO₂ ・咳の質(指示咳の強さ/持続) | 努力性呼吸/ SpO₂ 低下(目安 3% 以上 ) |
主要ツールの使い分け(比較表)
| 目的 | 推奨ツール | 所要 | 判定の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 迅速スクリーニング | RSST(反復唾液嚥下テスト) | 30 秒 | 3 回未満は機能低下の示唆 | 体位・頸部角度・口腔乾燥の影響に注意 |
| 液体での安全確認 | MWST(改訂水飲みテスト) | 1–2 分 | むせ・咳・湿性嗄声・再呼吸の変化 | 一口量の記録・段階調整(氷→水→とろみ等) |
| 固形物の移送確認 | フードテスト | 2–3 分 | 咀嚼〜咽頭移送の円滑性・残留兆候 | 安全な試験食(ゲル/プリン状など)で開始 |
| 咳反射・喀出力の目安 | 咳テスト | 1–2 分 | 指示咳の質/反射咳の誘発 | 禁忌:重度気道過敏・重症 COPD 他 |
| 動態の補助情報 | 頚部聴診法( CA ) | 1–2 分 | 嚥下音パターン/後嚥下の湿性化 | 単独判定不可。経時変化の追跡に有用 |
RSST(反復唾液嚥下テスト)の要点
- 目的:唾液嚥下の誘発性・遂行性を簡便に評価。
- 方法:30 秒で嚥下回数を数える(顎下触診+喉頭挙上の観察)。
- 判定の目安:成人で 3 回未満は機能低下を示唆。むせ・湿性嗄声を併記。
- 注意:口腔乾燥・認知/理解度の影響。一口量提示は行わないスクリーニング。
MWST(改訂水飲みテスト)の要点
- 目的:液体摂取時の安全性(むせ・湿性嗄声・再呼吸)を短時間で確認。
- 方法:成人では 3 mL を用いることが多いです。体位・一口量を固定し、嚥下直後〜後嚥下 5–10 秒の変化(咳・声質・呼吸)を観察します。
- 記録のコツ:体位(座位/側臥位)、頸部角度、一口量、介助量、嚥下回数( 1 回で入るか)を必ず併記します。
| スコア | 観察ポイント(要約) | 解釈の目安 | 次アクション例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嚥下が起こらない/明らかな呼吸苦や強いむせ | 高リスク | 中止。体位・覚醒・口腔環境を整え、別日に再評価 |
| 2 | 嚥下は起こるが、むせ・呼吸状態の悪化が出る | 高リスク | 一口量を増やさない。とろみ・代償法の検討、専門評価へ |
| 3 | 嚥下は起こり、むせは目立たないが、湿性嗄声など “湿り” が残る | 注意が必要 | 咳払い/嚥下再試行で変化を確認。条件固定で再現性をみる |
| 4 | 嚥下が起こり、むせ・湿性嗄声・呼吸悪化が目立たない | 比較的良好 | 同条件で再現性確認。食形態・一口量の段階付けを検討 |
| 5 | スコア 4 の条件に加え、短時間内に追加の嚥下を安定して行える | より良好 | 次段階(食形態・課題)へ。所見と条件を申し送りに落とす |
フードテストの要点
- 目的:咀嚼〜送り込み〜咽頭移送の確認(固形成分)。
- 方法:安全な試験食(プリン/ゲル状など)を 少量で開始し、残留・咳・湿性嗄声を確認。
- 判定の目安:咀嚼遷延・咽頭残留兆候・後嚥下の湿性化があれば段階を戻す。
- 注意:義歯・舌運動・口腔ケアの影響を併記。
咳テストの要点
- 目的:防御反射(反射咳)と指示咳の質・喀出力の目安。
- 方法:指示咳(咳の強さ・持続・連発)を観察し、必要に応じて安全域で反射咳を評価。
- 判定の目安:力弱い・単発のみ・湿性化の改善が乏しい場合はリスクが上がる。
- 注意:重度気道過敏・未治療の気胸/血痰は禁忌。 SpO₂ 監視下で。
頚部聴診法( Cervical Auscultation : CA )の位置づけと手順
CA は、嚥下関連音(前嚥下音・嚥下音・後嚥下音)や気道内分泌の変化を聴取して、嚥下の誘発・完了・残留/誤嚥の示唆所見を把握する方法です。単独で診断はせず、スクリーニングや経時変化の把握に用います。
基本手順
- 体位:骨盤中間位・体幹正中・頸部中間〜軽屈曲。 SpO₂ ・呼吸状態を事前確認。
- 聴診位置:甲状軟骨横〜やや側方/喉頭隆起の上外側。
必要に応じて第 6 頸椎棘突起周囲の気道音も併聴。 - タイミング:安静呼吸 → 一口量提示 → 嚥下誘発〜完了 → 後嚥下 5–10 秒。
- 対象音:①前嚥下音(唾液移送)②嚥下音(ピーク)③後嚥下音(再呼吸・残留音)④付随音(吸気性喘鳴・湿性嗄声)
判定の考え方(例)
| 所見 | 示唆・次アクション |
|---|---|
| 嚥下音が遷延・二峰性 | 嚥下動態の不整/残留疑い → 一口量縮小・食形態再検討 |
| 後嚥下で湿性ラ音が持続 | 咽喉頭残留・微小誤嚥の示唆 → 咳払い・嚥下再試行で変化を再評価 |
| 吸気性喘鳴 | 気道狭窄・誤嚥後の気道反応を示唆 → 直ちに中止・体位再設定 |
| 咳で音がクリアになる | 分泌物除去の反応良好 → 咳トレーニング・口腔ケア併用 |
※ 機器(聴診器/電子聴診器)や記録環境で聴取特性が変わります。 CA の解釈は訓練と症例学習を要し、単独判定を避けるのが原則です。
多職種連携・申し送り(最小セット)
- 条件:体位・一口量・食形態・介助量・補助具。
- 所見:むせ/湿性嗄声・再呼吸・咳の質・窒息兆候。
- 数値:RSST 回数、 MWST スコア、 CA 所見(前/主/後嚥下音)など。
- 方針:姿勢調整・食形態調整・訓練の可否と注意点。
安全配慮・中止基準
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 強い頸部痛・めまい・嚥下時痛 | 即時中止。疼痛評価・医師へ共有。 |
| SpO₂ 低下(目安 3% 以上 )・チアノーゼ | 休止し体位再設定。必要時は吸引・連絡。 |
| 強いむせ・吸気性喘鳴・湿性嗄声の持続 | 同条件での再試行は避け、段階を戻す/別日に再評価。 |
この後に読む(子記事:手順特化)
- RSST(反復唾液嚥下テスト):手順・カットオフ・記録テンプレ
- MWST(改訂水飲みテスト):手順・評価/WSTとの違い
- 咳テスト(CRT):サイレント誤嚥を見逃さない視点
- 不顕性誤嚥:スクリーニング手順(PTプロトコル)
- サイレント誤嚥:5点セットでの運用(現場向け)
- RLP/GS:嚥下筋の評価手順(測定のコツ)
- 嚥下食レベル/嚥下調整食2013:食形態の整理
- 摂食嚥下の5期モデル:ベッドサイド観察の軸
おわりに
ベッドサイドの摂食嚥下評価は、安全の確保 → 条件を固定 → 段階的に刺激 → 所見を記録 → 再評価のリズムを揃えるほど、判断と申し送りが安定します。見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック( A4 ・ 5 分)と職場評価シート( A4 )を無料公開しています。印刷してそのまま使えます。配布物は /mynavi-medical/#download にまとめています。
よくある質問( FAQ )
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
RSST のカットオフは?
成人では 30 秒で 3 回未満が機能低下の目安です。体位や口腔乾燥、理解度の影響を併記して解釈します。
頚部聴診法( CA )は単独で診断できますか?
できません。 CA は嚥下音の補助所見として有用ですが単独判定は避け、 RSST ・ MWST ・フードテスト・咳テストなどと統合して評価します。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:嚥下・栄養(リハ栄養)、脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、シーティング、摂食・嚥下
参考文献
- Belafsky PC, et al. Validation of the EAT-10: A symptom severity questionnaire for dysphagia. Dysphagia. 2008;23(3):289–295. PubMed / DOI.
- Oguchi K, et al. The Repetitive Saliva Swallowing Test ( RSST ) as a screening test of functional dysphagia. Jpn J Rehabil Med. 2000;37(6):383–388. J-STAGE.
- Yoshimatsu Y, et al. Predictive roles of the RSST for aspiration pneumonia. Healthcare (Basel). 2020;8(3):245. PMC.
- Smith AC, et al. Cervical auscultation in dysphagia: A scoping review. Dysphagia. 2021;36:1030–1048. DOI.
- Logemann JA. Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders. 2nd ed. Pro-Ed; 1998.
- Japanese Clinical Practice Guidelines for aspiration and pharyngeal residue assessment during eating and swallowing for nursing care. Jpn Acad Nurs Sci. 2022. J-STAGE.