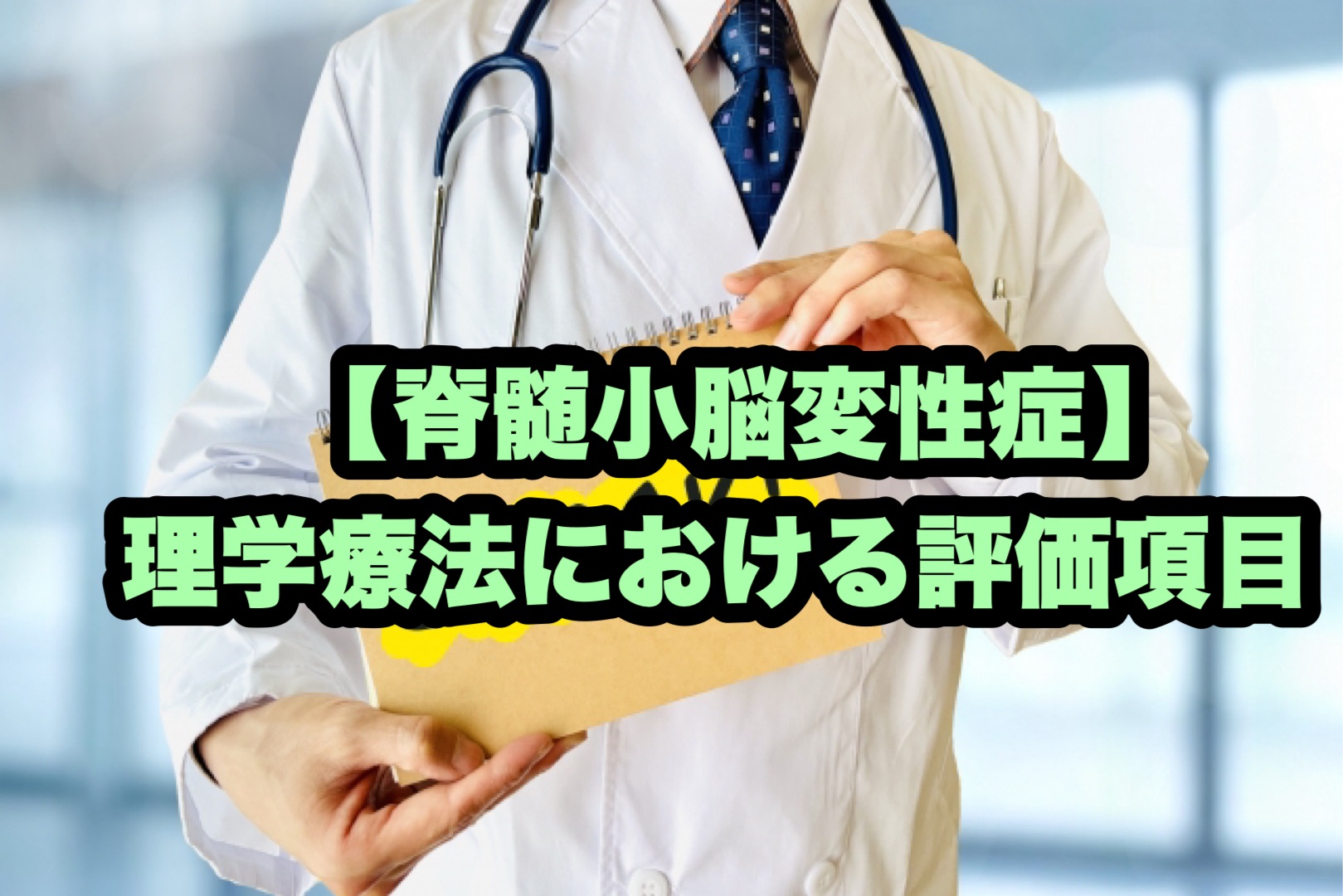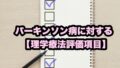脊髄小脳変性症( SCD )の理学療法評価|チェックリスト&使い分け
SCD の評価は「入口 → カテゴリ選択 → 条件固定」で迷いが減ります。 評価 → 介入 → 再評価の型をまとめて確認する( PT キャリアガイド ) ※臨床の「進め方」を固定すると、スケールの使い分けが一気にラクになります。
本ページは SCD の臨床で迷いがちな「入口の確認 → カテゴリ選択 → 再評価固定」を、チェックリストと段階フローで統一します。評価は「数値」だけでなく、崩れ方(方向・タイミング・反復で悪化)まで短文で残すと、介入の当たりが付きやすくなります。運動失調の全体設計(鑑別 → 評価 → リハ戦略)は、総論に整理しました:運動失調の評価とリハビリの進め方( PT 向け総論 )。
最短フロー(安全 → 静的 → 動的 → 歩行)
矢印は左から右(負荷が上がる)で正しい並びです。初回はスクリーン中心、精査は別日に分けても構いません。
評価チェックリスト(入口 → カテゴリ → 再評価固定)
- 入口の確認:主訴/転倒歴/補助具・装具/既往(脳梗塞・末梢神経障害など)/睡眠・疲労/起立性低血圧の有無。
- カテゴリ選択(必要に応じて追加)
- 総合重症度:SARA(基軸)/ ICARS(精査)
- バランス:ロムベルグ/ mCTSIB → FRT・四方向リーチ → Mini-BESTest(精査)
- 歩行: 10 m ・ TUG(装具/補助具・介助量も固定)
- 協調:指鼻・膝打ち・踵膝・回内外反復(速度 × 正確性)
- 眼球運動:滑動追従・サッケード・注視眼振(所見の方向と誘発条件)
- 体幹・姿勢:座位保持・立ち上がり・方向転換の安定性
- 構音・嚥下:発話明瞭度/ EAT-10 ・ RSST(必要に応じ VF / VE )
- ADL / IADL : FIM(している ADL )/ Lawton IADL(買い物・金銭・服薬など)
- 自律神経:起立試験(血圧・心拍)/便秘・排尿障害の聴取
- 再評価を固定:同時間帯・同環境・同設定(床面/靴/足位/補助具/開始姿勢)で実施し、内服タイミングと疲労度を必ず併記。
代表指標の使い分け(要点早見)
※表は横スクロールできます。現場では「同条件の再現性」と「崩れ方の言語化」が差になります。
| 領域 | 代表指標 | 目的 | 要点( SCD でのコツ ) | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 総合重症度 | □ SARA / ◆ ICARS | 運動失調の重症度と経時変化 | 順路固定・説明は簡潔。疲労の影響に留意。 | 同条件で再評価。動画記録が有用。 |
| 静的バランス | □ ロムベルグ/ □ mCTSIB | 入力依存(視覚・前庭・体性感覚) | 床面・足位・靴を固定。最大保持秒で記録。 | 高リスクでは近接監視・支持者配置。 |
| 動的バランス | □ FRT / □ 四方向リーチ/ ◆ Mini-BESTest | 姿勢変換・リーチ時の安定性 | 身長・腕長を併記(比較補正)。代償動作を言語化。 | 踏み換えの有無を所見で残す。 |
| 歩行 | □ 10 m / □ TUG | 速度と機能的移動能力 | 助走 2 m +計測 10 m +余裕 2 m。介助量・補助具を固定。 | 小脳性失調歩行の特徴(歩隔・測定変動)を併記。 |
| 協調 | □ 指鼻・膝打ち・踵膝 | dysmetria / dysdiadochokinesia の把握 | 速度 × 正確性で採点。崩れ方(過小過大・反復で悪化)を書く。 | 疼痛・ ROM 制限の影響を除外。 |
| 眼球運動 | □ 追従/サッケード/注視眼振 | 小脳・脳幹所見のスクリーニング | 方向・誘発条件(側方注視など)を固定語彙で記録。 | 複視・めまい強いときは中止・安静。 |
| 構音・嚥下 | □ 明瞭度/ □ EAT-10 ・ RSST( VF / VE 連携 ) | 窒息・誤嚥リスクと介入要否 | 体位と食形態を揃える。薬剤性口渇に注意。 | スクリーニングの限界を説明し ST と連携。 |
| ADL / IADL | □ FIM(している ADL )/ □ Lawton IADL | 支援設計・家族教育 | 介助様式・時間・環境条件を具体化。 | 介護者負担感も評価。 |
現場の詰まりどころ(よくあるミス → 直し方)
| 場面 | NG(起きがち) | OK(直し方) | 記録に残す一言 |
|---|---|---|---|
| 初回評価 | 全部の指標を同日に実施して疲労で崩れる | スクリーン(静的→動的→歩行)だけ先に固定し、精査は別日に分ける | 「疲労( 0–10 )/休憩回数」 |
| 歩行評価 | 装具・補助具・介助量が毎回変わる | 補助具・装具・介助量を「固定条件」として先に宣言してから測る | 「補助具:__/介助:__」 |
| バランス評価 | 床面・足位・靴が毎回違い比較できない | 床面(フォーム等)・足位・靴をテンプレで固定し、保持秒とふらつき方向をセットで書く | 「足位:__/床:__/方向:__」 |
| 所見の共有 | 数値だけで「どこが崩れたか」が伝わらない | 数値+崩れ方(方向・タイミング・反復で悪化)を短文で足す | 「反復で増悪/左右差/方向」 |
記録テンプレ(同条件で再評価)
| 項目 | 設定・条件 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ロムベルグ/ mCTSIB | 足位/靴/床面(フォーム)/視覚 | 保持 s(最長 30–60 ) | ふらつき方向・支持物の有無 |
| FRT /四方向リーチ | 腕長 cm /開始姿勢/方向 | 到達 cm( 3 回平均 ) | 体幹屈曲・踏み換え |
| 10 m 歩行 | 助走 2 m +計測 10 m +余裕 2 m /補助具・装具 | m/s( 3 回平均 ) | 歩隔・左右差・ふらつき |
| TUG | 椅子高/靴/介助量 | 秒( × 3 回 ) | 立ち上がり・方向転換の安定性 |
| SARA | 順路固定/説明簡潔 | 合計 / 40 | 崩れ方(協調低下の特徴) |
よくある質問( FAQ )
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
SARA と ICARS はどちらを使うといいですか?
経時変化の追跡は SARA を基軸にし、所見の解像度を上げたい(協調・体幹・眼球運動などを丁寧に拾いたい)ときに ICARS を追加すると運用が安定します。どちらも「順路」と「説明」を固定し、疲労の影響(休憩回数・主観疲労)を併記すると比較がしやすくなります。
評価はどれくらいの頻度で再評価しますか?
外来・訪問・通所では、介入量と生活状況により幅がありますが、目安は 4〜8 週で「同条件の再評価」を 1 回入れる運用が現実的です。急に崩れた場合(転倒増加・嚥下悪化・起立性低血圧の増悪など)は、週単位でスクリーンを短縮して様子を見るのが安全です。
疲労や日内変動が強いとき、何を固定すべきですか?
最優先は 時間帯・休憩ルール・補助具(装具)・床面です。これに加えて、主観疲労( 0–10 )と休憩回数を固定の記録欄に入れると、「本当に改善したのか/疲労が減っただけか」を切り分けやすくなります。
転倒リスクの最小セット(最短で見たい)を教えてください
まずは 静的(ロムベルグ or mCTSIB )→ 動的( FRT )→ 歩行( 10 m or TUG )の 3 本で十分に見立てが作れます。ここに転倒歴・歩隔・ふらつき方向(左右・前後)を添えると、環境調整と介助設計につながります。
実務のコツ(再評価が強くなる)
- 一度に全部やらない:疲労で成績が崩れます。スクリーン → 精査で段階化。
- “崩れ方”を言語化:数値+代償(方向・タイミング・反復で悪化)を短文で残す。
- 起立性低血圧はセットで扱う:起立前の水分・弾性ストッキング・腹帯など「介入」と「再評価」を同日に束ねると、生活指導の質が上がります。
次の一手(行動 → 関連リンク)
- 今日の実務:静的(ロムベルグ/ mCTSIB )→動的( FRT )→歩行( 10 m / TUG )の順番を固定し、同条件で再評価して「変化」を残す。
- 関連(索引):運動失調ハブ
- 親記事(全体設計):運動失調の評価とリハビリの進め方( PT 向け総論 )
- 兄弟記事(疾患別):多系統萎縮症( MSA )の理学療法評価
参考文献( DOI / PubMed )
- Schmitz-Hübsch T, et al. Scale for the Assessment and Rating of Ataxia ( SARA ). Neurology. 2006. PMCID:PMC6927357
- Trouillas P, et al. International Cooperative Ataxia Rating Scale ( ICARS ). J Neurol Sci. 1997;145:205-211. PubMed:9149072
- Franchignoni F, et al. Mini-BESTest: a new balance test for patients with neurological disorders. J Rehabil Med. 2010;42:323-331. PubMed:20461334
- Duncan PW, et al. Functional Reach: a new clinical measure of balance. J Gerontol. 1990;45(6):M192-M197. DOI:10.1093/geronj/45.6.M192
- Dite W, Temple VA. A clinical test of stepping and change of direction to identify multiple falling older adults. Arch Phys Med Rehabil. 2002;83(11):1566-1571. DOI:10.1053/apmr.2002.35469
- Podsiadlo D, Richardson S. The Timed “Up & Go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991;39(2):142-148. DOI:10.1111/j.1532-5415.1991.tb01616.x
- Belafsky PC, et al. Validity and reliability of the Eating Assessment Tool ( EAT-10 ). Ann Otol Rhinol Laryngol. 2008;117:919-924. PubMed:19140539
- Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist. 1969;9(3):179-186. PubMed:5349366
- 日本神経学会(監修). 脊髄小脳変性症・多系統萎縮症診療ガイドライン 2018( PDF ):neurology-jp.org
- 宮井一郎. 脊髄小脳変性症のリハビリテーションの実際. 臨床神経. 2013;53:931-933( PDF ):neurology-jp.org
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下