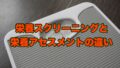ハリス・ベネディクトの式の使い方( 3 ステップで結論 )
結論:ハリス・ベネディクトの式( Harris–Benedict equation / HB )は、体重・身長・年齢・性別から BMR(基礎代謝量) を推定し、活動係数( PAL ) と必要に応じて ストレス係数( SF ) を掛けて、1 日の 必要エネルギー量( TEE )の “目安レンジ” を作るためのツールです。
使い方はシンプルで、現場では次の 3 ステップに落とすと迷いません(数値は「固定」ではなく、2〜4 週で体重・摂取量・浮腫・創傷治癒・ ADL の推移を見て微調整します)。
- BMR を算出(改訂 HB または MSJ、あるいは日本人の基礎代謝基準値 × 体重)
- PAL を決める(生活像とリハ量から「低い/ふつう/高い」を選ぶ)
- TEE を計算( TEE=BMR×PAL )→ 周術期・感染などが強いときだけ ×SF
なお、必要エネルギー量を「どう決めて、どう見直すか」の全体像は、総論の 必要エネルギー量の決め方( BMR/PAL/ SF から再評価まで ) にまとめています。
ハリス・ベネディクトの式とは(役割と限界)
ハリス・ベネディクトの式は古典的な回帰式で、現在は 1984 年の 改訂ハリス・ベネディクト と、1990 年の MSJ( Mifflin–St Jeor ) が臨床で使われる代表です。推定した BMR を起点に、PAL(必要なら SF )を掛けて必要量を推定します。
ただし、ハリス・ベネディクトの式は欧米人データがベースで、日本人や高齢者にそのまま当てはめると誤差が大きくなる 場面があります。サルコペニア、低栄養、高度肥満、浮腫、切断など体組成が偏る症例では特に注意が必要で、本来は 間接熱量測定 が優先です。現場では「目安レンジ」を共有し、体重推移や摂取量、浮腫、創傷治癒、 ADL の変化で補正していく運用が現実的です。
式と計算手順(改訂 HB/MSJ/日本人の基準値)
成人では、改訂ハリス・ベネディクトの式、MSJ、そして 日本人向けの基礎代謝基準値 の 3 ルートを押さえておけば実務上は十分です。式はメートル法(体重= kg・身長= cm・年齢= 歳)で、W=体重・H=身長・A=年齢 とします。まず BMR を求め、次に TEE(必要エネルギー量)≒ BMR × PAL を基本形として、必要に応じて SF を乗じます。
| 区分 | 男性 | 女性 | メモ |
|---|---|---|---|
| 改訂 HB( 1984 ) | BMR = 13.397 × W + 4.799 × H − 5.677 × A + 88.362 |
BMR = 9.247 × W + 3.098 × H − 4.330 × A + 447.593 |
いわゆる「ハリス・ベネディクトの式」。標準体格では妥当だが、肥満・るいそう・浮腫では誤差が増えやすい。Roza & Shizgal 1984 |
| MSJ( 1990 ) | BMR = 10 × W + 6.25 × H − 5 × A + 5 |
BMR = 10 × W + 6.25 × H − 5 × A − 161 |
外来成人(肥満含む)で実測値とのずれが比較的小さいとの報告が多く、 HB の代替として広く使われる。Mifflin 1990 |
| 基礎代謝基準値(日本人) | BMR ≒ 基礎代謝基準値( kcal/kg/日 ) × 体重( kg ) |
日本人データに基づく枠組み。年齢・性別で基準値が異なり、栄養指導や制度面との整合性を取りやすい。食事摂取基準 2025( PDF ) | |
臨床の簡易推定としては、BMR の計算を省略して 体重 × 係数( kcal/kg/日 ) でざっくり見積もる方法も使われます。ただし、これは「便利な近道」であり、体重・摂取量・浮腫・活動量の変化を必ずセットで確認して補正する前提です。
まず詰まりやすい:どの体重( BW )を代入する?(早見表)
「ハリス・ベネディクトの式 使い方」で迷いやすいのが、式に入れる体重( BW )の扱いです。ここを曖昧にすると、推定値が一気にブレます。
| 状況 | 代入の考え方 | 理由 | 次の一手 |
|---|---|---|---|
| 標準体格(浮腫なし) | 実測体重( BW ) | 体組成の偏りが小さく、推定式の前提に近い | 2〜4 週で体重と摂取量を見て微調整 |
| 明らかな浮腫・体液貯留 | 「乾燥体重」を推定して代入(または保守的に低めから) | 水分で見かけの体重が増え、必要量を過大にしやすい | 利尿・体液変動を踏まえ、週単位で見直す |
| 高度肥満 | MSJ を優先し、過大推定に注意(施設プロトコル優先) | 脂肪量が多いほど、式の推定誤差が問題になりやすい | 減量目的か維持かを明確にし、目標設定を共有 |
| るいそう・サルコペニア | 日本人の基準値でレンジ確認 → HB/MSJ は妥当性チェックに | 筋量が少ないと、推定が高めに出るリスクがある | 筋力・ ADL・創傷治癒とセットで評価 |
| 切断・重い拘縮など | 推定式だけで決めない(チームで補正前提) | 体重と体組成の関係が大きく崩れ、誤差が増える | 経過(体重・摂取・臨床所見)で小刻みに補正 |
計算例(高齢者: 65 歳・女性・ 155 cm・ 50 kg )
高齢者を想定した症例で、改訂 HB、MSJ、日本人の基礎代謝基準値を比較します(四捨五入は ± 1 kcal 程度)。
- 改訂 HB:約 1,109 kcal/日( 9.247 × 50 + 3.098 × 155 − 4.330 × 65 + 447.593 )
- MSJ:約 983 kcal/日( 10 × 50 + 6.25 × 155 − 5 × 65 − 161 )
- 基準値 × 体重:約 1,035 kcal/日( 65–74 歳女性 基礎代謝基準値 20.7 × 50 )
この例では、推定 BMR の差は ± 100 kcal/日 程度です。ここに PAL を掛けると、必要エネルギー量の差はさらに広がるため、PAL の選び方と再評価が重要になります。
BMR・必要エネルギー量( TEE )計算ツール
数値を入れると、改訂 HB/ MSJ/(日本人基準値×体重)で BMR を出し、PAL と SF を掛けて TEE を計算します。入力はブラウザに保存できます。
活動係数( PAL )とストレス係数( SF )の考え方
推定式を使うときの基本形は、TEE=BMR×PAL です。成人の PAL はおおよそ 低い= 1.5/ふつう= 1.75/高い= 2.0 が目安で、「ふつう」は自立 ADL に加えて一定の歩行・家事・軽運動を含んだ生活像を指します。
急性期や周術期では、炎症・発熱・創傷治癒・敗血症などに応じて SF(例:軽度 1.1〜1.2、中等度 1.2〜1.3 など)を乗じることがありますが、施設の NST や診療科ごとのプロトコルが優先 です。推定値は「レンジを掴む」ための道具と捉え、最終的な投与量は血糖・電解質・窒素バランス・体重などの経過を見ながらチームで決定しましょう。
臨床での使い分け(高齢者・日本人の実務目安)
日本の高齢者リハでは、日本人の基礎代謝基準値 × PAL を起点にしつつ、HB/MSJ を「補助的な確認」に使う運用が安全です。フレイル・サルコペニアが疑われるケースでは、見かけの体重だけでなく 筋量・浮腫・褥瘡/創傷 を合わせて評価し、「数字の正しさ」よりも 体重・筋力・ ADL の変化が改善方向に向かっているか を重視します。
一方で、肥満を伴う生活習慣病などで減量目的の設定が必要な場合は、MSJ を用いた推定値を起点に、栄養士主導の計画に沿うことが多くなります。いずれの場合も、TEE はあくまで スタート地点。体重・体組成・浮腫・創部治癒・活動量の変化を見ながら、2〜4 週サイクルで見直していくことが重要です。
よくあるミス( 5 つだけチェック )
| よくあるミス | 起きる問題 | 対策 | 記録ポイント |
|---|---|---|---|
| 単位の混在( H を m で入れる等) | BMR が大きくズレる | 入力前に「 kg/ cm/ 歳 」を声に出して確認 | 計算に使った W・H・A をそのまま残す |
| 年齢を更新せずに回し続ける | 経年的な低下を見逃す | 再評価時に年齢欄も更新する運用に | 計算日と年齢をセットで記録 |
| 生活像より高い PAL を選ぶ | TEE を過大評価しやすい | 歩数・離床時間・ ADL・リハ量から PAL を決める | 「根拠(歩行量など)」を 1 行メモ |
| 浮腫の体重をそのまま代入 | 過大推定のリスク | 乾燥体重を推定し、経過で補正 | 浮腫所見と体重変動をセットで記録 |
| 一度決めた TEE を固定する | 体重・創傷治癒・ ADL の変化に追従できない | 2〜4 週で再評価(体重・摂取量・活動量) | 「見直し日」と「変更理由」を残す |
参考文献(一次情報中心)
- Mifflin MD, et al. A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. Am J Clin Nutr. 1990;51(2):241–247. doi:10.1093/ajcn/51.2.241. PubMed
- Roza AM, Shizgal HM. The Harris Benedict equation reevaluated. Am J Clin Nutr. 1984;40(1):168–182. doi:10.1093/ajcn/40.1.168. PubMed
- Frankenfield D, et al. Comparison of predictive equations for resting metabolic rate in healthy nonobese and obese adults: a systematic review. J Am Diet Assoc. 2005;105(5):775–789. doi:10.1016/j.jada.2005.02.005.
- 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準( 2025 年版 )関連資料. PDF
- (参考)成人の身体活動レベル( PAL )の定義と代表値:総説(日本栄養・食糧学会誌)。J-STAGE
おわりに
ハリス・ベネディクトの式や MSJ は、推定 → 実際の摂取/体重推移で補正 → 再評価 という一連の流れの「入口」を整える道具です。特に高齢者や日本人では、式そのものの精度よりも、推定値を起点に 小さく試して小さく修正するサイクル を回せているかがアウトカムを分けます。「だいたいこのレンジ」という共通言語をチームで持ち、リハと栄養の連携を前に進めましょう。
働き方を見直すときの抜け漏れ防止に。見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック( A4・ 5 分 )と職場評価シート( A4 )を無料公開しています。印刷してそのまま使えます。詳しくは「マイナビコメディカル」ページの download セクション( /mynavi-medical/#download )をご参照ください。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
ハリス・ベネディクトの式の「使い方」を最短で確認するには?
まずは ① BMR を出す → ② PAL を決める → ③ TEE=BMR×PAL(必要なら ×SF ) の順です。次に、式へ代入する体重( BW )が「浮腫で増えていないか」「極端な肥満/るいそうではないか」を確認し、推定値は固定せず 2〜4 週で体重・摂取量・浮腫・ ADL の推移を見て微調整します。
HB と MSJ、どちらを優先して使えばよいですか?
外来成人(肥満を含む)では、実測とのずれが比較的小さいとされる MSJ を優先する報告が多い一方、実務では「日本人の基準値でレンジをつかむ → MSJ/ HB は妥当性チェックに使う」という形が安定します。どちらを使っても、最終的には 経過(体重・摂取量・臨床所見)で補正することが重要です。
高齢者やサルコペニア患者に推定式を使っても大丈夫ですか?
高齢者・サルコペニアでは、見かけの体重に対して筋量が少ないため、推定が高めに出るリスクがあります。式だけで判断せず、体重・筋力・歩行能力・浮腫・褥瘡/創傷の経過 をセットで観察し、2〜4 週ごとに必要エネルギー量を見直すのが安全です。
ストレス係数( SF )は理学療法士がどこまで意識すべきですか?
SF の最終判断は主治医や NST の方針が優先ですが、PT としては「どういう状態で需要が増えるか」を理解し、活動量(離床・歩行)とアウトカム(体重・筋力・ ADL )の推移をフィードバックできれば十分です。推定値を「チームの共通言語」にする意識が、連携をスムーズにします。
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下